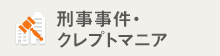民事訴訟法
- 民事訴訟審理の全体構造
-
PART1 民事訴訟審理の全体構造
第1編 申立て(審判対象―権利―の提示)
第1 申立て
1 意義
申立てとは,裁判所に対して,裁判や証拠調べなどを求める当事者の訴訟行為の総称をいう
2 訴え
訴えとは,申立てうち,原告が被告に対し一定の権利を主張し,裁判所に対してその当否について審理・判断を求める訴訟行為をいう
⇒ 『訴え』という原告の行為によって,被告及び裁判所に対して,審判対象となる権利又は法律関係が提示される
第2 訴訟上の請求と訴訟物
1 訴え,訴訟上の請求及び訴訟物の関係
(1) 訴訟上の請求とは,①「被告に対する権利主張」と②「裁判所に対する審判要求」の2点から構成されている
(2) 上記①「被告に対する権利主張」の中身を訴訟物という。訴訟物とは,実体法上の権利又は法律関係そのものである[1]
(3) 訴えによる原告の行為によって,被告及び裁判所に対して,審判対象となる権利又は法律関係が提示されるところ,これが不十分であれば,『訴え』が却下される
2 訴訟物の特定
(1) 審理開始のためのミニマム
訴訟物が何であるかが特定されていること
⇒ 「請求の趣旨」+「請求の原因」で審理の対象となる権利を特定
∵① 被告の視点からは防御の焦点が定まらない
② 裁判所の視点からは,訴訟物が特定されないと請求を基礎付ける要件事実が決まらないので審理のしようがなくなってしまう
(2) 訴訟物の選択
∴ 原告の専権
∵ 処分権主義の観点
⇒ 訴訟物の選択は,「何が合理的か」という視点から考えるのではなく,「原告が訴訟物として何を選択したのか」を解明することによって訴訟物を決める
3 訴訟物の識別
訴訟物の特定がなされたというためには,他の権利と誤認混同が生じない程度のもので足りる
⇒ 事案ごとに考えるべき相対的な問題
(1) 物権の特定識別要素
① 権利の主体(権利者)
② 権利の客体(物権の対象物)
③ 権利の内容
* 物権は,同一物に同一の物権は存在しない(トレード・オフの視点)ので特定しやすい性質がある
(2) 債権の特定識別要素
① 権利者(債権者)
② 義務者(債務者)
③ 権利の内容
④ 権利の発生原因事実
* 債権は排他性がないので同一内容の権利が両立する(トレード・オンの視点)ことがあるので,上記①から③では十分ではなく④が必要
(3) 訴訟物の特定についての基本的視座
視点 『訴訟物の特定』の要素は固定的に考えるのではなく,どこまで特定すれば他の権利と区別することができるのか,という視点が重要[2]
ア 抵当権の場合
抵当権の場合は,同一目的物の同一内容の物権が併存する
⇒ トレード・オフの視点が抵当権には妥当でいないことが分かる!!
イ 債権の場合
④の「権利の発生原因事実」を挙げても特定できないことはあるので,それ以外にも,特定要素が要求されることはある。また,債権でも離婚の訴えにおける離婚権という訴訟物であれば,トレード・オフの視点が妥当するので厳密な特定はいらない
(4) 訴訟物の特定と民事訴訟手続
ア 訴訟物が特定しない場合
① 訴状において訴訟物が特定していない場合は,裁判長は補正期間を定めて補正命令(137条1項)
② 期間内に不備を補正したいときは,訴状却下命令を出して事件を終局(137条2項)
⇒ 審判対象を特定しない無益な請求に対しては,納税者である国民全体の利益という見地から裁判所は門戸を開けない[3]
4 申立て段階における民事訴訟の基本原理(処分権主義)
(1) 処分権主義の内容
① 訴訟は,当事者の申立てをもって開始される
② 裁判所は,当事者の申立ての範囲を超えて裁判をすることはできない
* 訴訟物の同一性,求める審判の種類,形式(給付,確認,形成)の別,その種類・形式の範囲内かどうか―が考慮要素
* 原告が求めた裁判の量を超えて裁判をすることはできない(246条)
③ 当事者の意思により,裁判によらずに訴訟を終了させることができる
* 訴訟の開始段階のみ当事者の意思を尊重しても趣旨を達成できない
(2) 処分権主義の根拠
① 民事訴訟は,実体権の形成・行使・処分のプロセスでもあることから,訴訟上もこれとの連続性を確保するのが望ましい
② 133条1項・2項2号が訴訟物の設定権を原告に認め,246条は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない
(3) 処分権主義の機能
① 民事訴訟を利用するかは当事者の意思決定に委ねられている
② 利用する場合において,その判決の上限を指定する権能を当事者に与える
5 訴訟物の把握
(1) 貸金請求
(2) 建物引渡請求[4]
(3) 抹消登記手続請求
(4) 建物明渡請求
(5) 債務不存在確認請求
第2編 主張(具体的な攻撃防御対象―事実―の提出)
第1 権利の認識・把握の方法
1 事実把握の必要性
⇒ 実体法が権利の存否を認識するための手段として機能する
2 法律効果,法律要件,要件事実
⇒ 請求権の発生という法律効果の有無は,結局,その請求権が発生すると規定している実体法の法律要件に該当する事実(主要事実)の存否で決まる
3 実体法の規定と権利の現存性の判定
(1) 裁判所の判断の対象は現在の権利又は法律関係
∴ 民事訴訟による解決に資するのは,現在の権利又は法律関係であって,過去の権利又は法律関係についての訴えは,原則として不適法
∵ 過去の権利又は法律関係は,仮にその成立が認められたとしても,現在においては,すでに消滅・変更してしまっている可能性があり,現在の紛争解決には直接役立たないから
(2) 権利不変の公理
⇒ 実体法が定める法律効果を組み合わせると,権利が現在も存在するかが分かる
∴ 法は,いったん発生した権利義務は,その後に変更,消滅しない限り,そのまま存続しているものと考える
∵ 実体法は,権利の発生,変更,消滅の規定から成り立っているので,権利不変の公理を当然の前提としている
(3) 実体法の規定の仕方
① 権利根拠規定
権利根拠規定とは,権利関係が発生するという効果が生じるための要件を定めた規定をいう
② 権利消滅規定
権利消滅規定とは,いったん発生した権利関係が消滅するという効果を生じさせるための要件を定めた規定をいう
③ 権利障害規定
権利障害規定とは,権利根拠規定や権利消滅規定に基づく法律効果の発生を抑止・障害する法律効果を発生させるための必要な要件を定めた規定をいう
④ 権利阻止規定
権利阻止規定とは,発生した権利の行使の一時的阻止要件を規定するもので,同時履行の抗弁権を定めた民法533条をいう
第2 主張段階における民事訴訟の基本原理
1 事実主張の意義
(1) 事実の機能
そもそも,請求権が存在するかは,実体法の定める法律効果の論理的組み合わせによって,権利が存在するかどうかを裁判所が判定することになっている。そして,その判定の際に参照される資料が,「法律効果を定めた法規の要件に該当する具体的事実」である
(2) 当事者の事実[5]主張責任
権利の存否を判断するための基礎資料を収集して裁判所に提出する権能を有し,かつ責任を負うのも当事者
ア 原告の事実の主張責任
原告は,自分の申立ての根拠を「事実主張」という形で明らかにする
⇒ 権利の発生,変更,消滅を規定する法律の要件に該当する事実が,「審理の具体的対象」として提示
イ 被告の事実の主張責任
被告は,原告の申立てが正当でないと反論するときは,その根拠となる事実を主張することによって反論の内容を明らかにする
2 弁論主義
(1) 意義
ア 定義
弁論主義とは,判決の基礎となる資料(事実及び証拠)の提出を当事者の権能かつ責任とする建前のことをいう
イ 制度趣旨
民事訴訟の対象となっている権利関係は,通常,私人間で自由に処分できるものであるから,訴訟でその存否が問題となった場合,どのような条件下で,またどのような認定資料に基づいてその存否を決するかも当事者の自由に委ねられてよい点にある[6]
(2) 事実主張レベルにおける弁論主義
⇒ 事実主張レベルでは,第1テーゼと第2テーゼが問題
ア 弁論主義の適用範囲を画する事実
弁論主義のテーゼが適用される事実とは,法律要件に直接該当する事実,すなわち主要事実(=要件事実)のことをいう
⇒ 間接事実や補助事実には,弁論主義の適用はない
* 事実主張レベルでは,いろいろな事実が提出されるが,その訴訟法上の役割には違いがある[7][8]
イ 弁論主義の第1テーゼと主要事実
(ア) 主要事実に第1テーゼが適用される理由
① 主要事実は,法律要件に該当する具体的事実であって,裁判所の審理の具体的な目標となるし,相手方の防御の対象となる審理の骨格を作る重要な事実だから
② 当事者が主張していない事実を認定してしまうと,当事者にとって不意打ちとなってしまい,当事者の防御の利益を損なうおそれがあるから
(イ) 主要事実以外に第1テーゼの適用がない理由
① 主要事実を幹とすると間接事実は枝葉にすぎない(事実の訴訟法上の機能がまったく異なる)
② 裁判所が主要事実の存否を認定する際の大きな制約となり,当事者にとっても過度の負担となる
(ウ) 主要事実に第1テーゼが適用される効果
証拠の中に原告又は被告に有利な主要事実が現れていても,当事者の主張がなければ裁判所はこれを取り上げることができない(訴訟資料と証拠資料の峻別)
ウ 弁論主義の第2テーゼと主要事実
(ア) 主要事実に第2テーゼが適用される理由
① 当事者の意思の尊重
② 争点整理や証拠調べを削減することによって審理効率が向上する
(イ) 主要事実以外に第2テーゼの適用がない理由
① 第2テーゼが働くと,裁判所の事実認定権が実質的に制約される
② 裁判所の自由心証主義による合理的な事実認定を担保するためには,主要事実の推認や証拠の評価に関する事実については,自白の拘束力を認めるべきでない
(ウ) 自白の撤回(撤回禁止効・当事者拘束力)の要件
① 相手方の同意がある場合
② 刑事上罰すべき他人の行為によって自白した場合
③ 自白の内容が真実に反し,かつ自白が錯誤に基づいてなされた場合
* 判例は,『反真実』が証明されたときは,錯誤の存在は推定される[9]
* 『反真実』の立証が求められることで立証責任の転換がもたらされる[10]
エ 一方当事者の主張に対する相手方当事者の態度
(ア) 事実上の主張とこれに対する認否
① 認める(179条,第2テーゼ)
② 沈黙(159条1項)
③ 知らない
④ 否認する
*民事訴訟においては,争いのある限度でのみ証拠調べを行う
(イ) 法律上の主張とこれに対する認否
Ⅰ 原則的処理
∴ 当事者が法律上の主張を述べても訴訟法上は意味がない主張
∵ 裁判官は,実体法の存在及びその解釈については習熟していることが前提となっており,法規の存否及びその解釈適用は,裁判所の専権
⇒ 裁判官が事実上これを参考にするにすぎない!!
Ⅱ 例外的処理
ⅰ 要件
① 事実主張に代えて,これを簡素化する意図で具体的な権利又は法律効果を主張していること
② 相手方がこれを容認していること(権利又は法律効果の存在を認めている)[11]
ⅱ 効果
事実主張に代わるものとして訴訟法上の意味を認めてよい
ⅲ 典型例
「Aは甲建物を所有している」などという具体的な権利又は法律効果の主張など
(3) 立証レベルにおける弁論主義(第3テーゼ,職権証拠調べの禁止)
第3テーゼとは,裁判所が証拠調べをするためには,当事者の申出を必要とするとの原則をいう
*弁論主義の各テーゼの関係
当事者が主張した事実(第1テーゼ)

争いなし 争いあり
証拠調べする必要!BUT職権不可!!
判決の基礎となる(第2テーゼ)
*弁論主義は,当事者に事実認定のコントロール権を与えている
3 弁論主義違反かどうかについての若干の問題事例
(1) 代理
ア 判例の検討
① 最判昭和33年7月8日民集12巻11号1740頁
当事者間で直接に契約が成立したと主張している場合に代理人と相手方との間で契約が成立したと認定すること[適法]
② 最判昭和42年6月16日判時489号50頁
代理人との間で契約が成立したと主張している場合に本人との間で契約が成立したと認定すること[適法]
∵ いずれも法律効果において相違がない
イ 判例の評価
弁論主義の第1テーゼの目的は,当事者の自律的主体的な争点形成を促す点
↓
事実審理の核心は法律効果にあるのではなく,その発生要件に該当する事実をどのように審理に提出し攻撃防御を尽くすかという点
↓
*判例は不当というべき[12]
(2) 所有権移転経過
ア 判例の検討
① 最判昭和41年4月12日民集20巻4号548頁)
所有権に基づく返還請求や所有権確認などの所有権訴訟において,当事者の主張する所有権移転の経過と異なる事実を認定する場合[違法]
イ 判例の評価
所有権訴訟では,原告が「自己の現所有」を請求原因として主張立証しなければならないが,権利自白が成立しない場合は,原告は「自己への所有権移転経過(来歴経過)を主張立証しなければならないことになる。これを,「現在の所有」に対する間接事実と見れば,弁論主義違反とならないが,現在では,主要事実と見ることに争いはない
(3) 規範的要件(過失,正当理由)
● 評価根拠事実を主要事実と理解すべきではない
∵① 手続保障の重視の故に当事者の主張責任の負担は重くなってしまう
② 審理が硬直化するおそれ
○ 評価根拠事実は主要事実と理解すべき(司法研修所)
∵① 反対説を採ると,過失の法律要件は事実そのものではなく,認定された事実に基づく当該規範的評価が可能かどうかという法的判断が必然に介在するので,単に「過失あり」と主張しただけでは主張責任を尽くしたとはいえない[13]
② 反対説を採ると,裁判所の認定がフリーハンドになってしまい,事実主張が担うべき争点の自覚的形成を通じて手続保障を確保する機能が失われる[14]
(4) 過失相殺
ア 判例の検討
① 最判昭和43年12月24日民集22巻13号3454頁
債務者の主張がなくても裁判所が職権で過失相殺をすることができるが,債権者に過失があった事実については債務者に証明責任がある
イ 判例の評価
判例は,「過失相殺すべきである」という法律上の主張を不要としたものにとどまると読めるので,その基礎付け事実の主張なくして裁判所が職権で過失相殺できるとまで判示しているかについては疑問あり[15]
(5) 一般条項(信義則,権利濫用,公序良俗)
● 職権斟酌が可能であって当事者の主張に拘束されない
∵ 証拠調べの結果,公序良俗違反を基礎付ける事実が明らかになっているのに,当事者の主張がないため斟酌できないとするのは,裁判官の法適用の職責と相容れない
× 公益性の要請といえどもその程度は多様であるから,一般的に弁論主義が排除されるとは考えるべきではない
○ 公序良俗違反,信義則違反という抽象的表現をもってする主張は,「法律上の主張」であって,裁判所は拘束されないが,これを基礎付ける事実は,当事者の攻撃防御対象の核心部分であってその主張を要するというべき[16]
∵ 防御の機会を確保すべき
(6) 手形法16条1項
ア 判例の検討
① 最大判昭和45年6月24日民集24巻6号712頁
手形法16条1項[裏書の連続]の適用を主張するには,「連続した裏書の記載のある手形を所持し,その手形に基づき手形金の請求をしている場合には,当然にその主張があると解すべき
イ 判例の評価
被告は,原告が明示的に主張しなくても当然にこのような厳しい推定を覆すための証明責任の転換を受けることになるが,提出された手形によってそのことを容易に知り得る[17]
第3編 立証(証拠の提出と証明責任)
第1 立証
立証が必要⇒当事者間で争いのある事実
第2 主張立証責任の分配
1 自由心証主義
(1) 意義
自由心証主義とは,心証形成の方法について用いることができる証拠や経験則を特に法が制限せず,裁判官の自由な選択に委ねる法原理をいう[18]
(2) 証拠共通
証拠共通の原則とは,自由心証主義に基づいて裁判官が提出された証拠をどの程度事実認定に役立つか自由に評価できる結果,提出者の有利にも不利にも評価できるということをいう
∵① 証拠調べの結果を総合的に評価して合理的で落ち着きのよい事実認定を可能とする趣旨
② 弁論主義は,訴訟資料の収集提出に関し,裁判所の役割とするか当事者の役割とするかという作業分担の規律にすぎない[19]
2 証明責任
(1) 意義
ア 定義
ある事実が真偽不明の場合に判決においてその事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことになる一方当事者の不利益をいう
イ ノン・リケットが生じる原因
① 証拠収集は当事者の責任なので一定の限界がある(刑訴のように,原告であるからといって,権力や組織を持っているとは限らない)
② 裁判所の事実認識手段・能力にも自ずと限界[20]
ウ 主観的証明責任
⇒ 証明責任の所在を明確に理解しておくと,当事者の攻撃防御活動を理解する上でも重要[21]
(2) 証明責任の分配
ア 原則的処理
当該法律効果の発生によって利益を受ける側の当事者に帰属
∴ 公平だから
イ 例外的処理(法律要件分類説の修正要因)
* 考慮要素
① 当事者の公平・対等性の確保[22]
② 実定法秩序との整合性
③ 証拠との距離
④ 立証の難易
ウ 修正の具体例
① 帰責事由の証明責任―条文相互間の衝突
② 準消費貸借における旧債務の存在の証明責任―立証難易の考慮程度
③ 背信行為と認めるに足りない特段の事情の証明責任―条文にない事項
3 主張立証責任の所在と攻撃防御方法
(1) 請求原因
請求原因とは,原告が自己の請求(訴訟物たる権利又は法律関係)を基礎付けるために主張立証すべき事実をいう
(2) 抗弁
抗弁とは,請求原因と両立し請求原因による法律効果の全部又は一部を排斥する効果をもたらす法律要件に該当する事実で被告が主張立証責任を負っている事実をいう
* 『請求原因と両立する』の意味
トレード・オンの関係にあるかは,事実と事実を比較して検討する(法的効果で比較するのではない)
(3) 否認と抗弁の区別
事実関係がトレード・オンの関係にあるか及び証明責任の所在で決定される
第4編 攻撃防御の構造と要件事実
第1 売買契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造
第2 消費貸借契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造
第3 賃貸借契約をめぐる基本的な攻撃防御の構造
第4 所有権に基づく請求についての基本的な攻撃防御の構造
第5 訴訟物(訴訟上の請求)と請求原因との関係
1 問題の所在
実体法上の権利関係の発生原因事実と当事者適格を基礎付ける事実とが分離する場合
⇒ ① 他人の権利を行使する場合(債権者代位などの訴訟担当)
② 実体法上の権利関係が同一性を保持したまま譲渡・承継された(債権譲渡や相続など)[23]
2 訴訟物と当事者適格との関係
(1) 権利の発生原因と当事者適格が一致する場合
当事者適格とは,訴訟物たる特定の権利又は法律関係について,当事者として訴訟を追行し,本案判決を求めうる資格をいう[24]
⇒ 権利者は,法的利益の帰属主体であるので,当事者適格がある
* 典型的な紛争パターンは,権利の発生原因と帰属原因とは分離しない
⇒ 訴訟物たる権利の主張で当事者適格が十分に基礎付けられている
(2) 権利の発生原因と当事者適格が分離する場合
問題の所在 他人のもとで発生した権利をそのままの状態で行使することを認める場合がある(第三者の訴訟担当)
⇒ 要件事実を2つに分けて考察する必要!!
① 訴訟物たる権利の発生原因事実
② 原告がなぜその権利を行使することができるのか(原告適格を基礎付ける事実)
3 債権者代位訴訟
4 特定承継(債権譲渡)
第6 主張立証責任の軽減・転換,法律上の推定
1 法律上の推定と事実上の推定
2 法律上の事実推定
(1) 意義と構造
(2) 具体例
(3) 推定規定をめぐる当事者の立証活動
3 法律上の権利推定
(1) 意義と構造
(2) 具体例
4 暫定真実
(1) 意義と構造
(2) 具体例
5 意思推定・解釈規定
(1) 意義と構造
(2) 具体例
6 法定証拠法則
[1] 訴訟物とは,「実体法上の権利又は法律関係」と定義すると,たしかに,請求の趣旨においては,請求認容判決の主文に対応する文章を,法的性質を明示しないで記載することになっている。そうすると,請求の趣旨のみでは,どのような権利に基づいているかが分からないので,結局,「実体法上の権利又は法律関係」がそれのみで定まるわけではない。そこで,「実体法上の権利又は法律関係」が何かという点に光をあてて,訴訟物特定に必要な限度で「請求の原因」から,権利又は法律関係を読み取るということになる。すなわち,訴訟物=請求の趣旨,判決理由=請求原因のように割り切って考えないようにして欲しい。
[2] 藤田20の視点は示唆に富んでいると思われる。この点,藤田20の叙述を見ながら考えると,「識別ができるか」は,「両立しないか」という社会科学の一視点ですべて説明がつくであろう。そうすると,法律的に権利の成立によって機械的に決まるわけではないので,個別具体的な事情によって判断していくことが必要であり,これをドイツ的な概念法学で説明することはできないであろう。藤田20にいう「マニュアル的」思考というのは,ドイツ概念法学に対する批判に他ならないであろう。
[3] 個人的には,このような功利主義的な視点で説明することには疑問がある。むしろ,「裁判を受ける権利を行使する前提条件がそろっていない」という視点から説明した方が適切であろう。
[4] 藤田25には,新司法試験民法の問題意識が表れているといえよう。
[5] 実際には,当事者の「主張」には,事実ではなく,「法的な観点」の主張が含まれることがある
[6] すでに述べているように,弁論主義は,訴訟の審理の内容形成を誰に委ねるのかという問題であるところ,法は弁論主義を基調としつつも他方で釈明権を規定しているのであるから,その形成責任をすべて当事者主義に委ねているわけではない。もっとも,法が弁論主義を採用し,訴訟の審理の内容形成に当事者の意思を尊重しているのは,訴訟主体である当事者が積極的に活発な訴訟活動を行わせることで公正公平な裁判が可能となるし,裁判所が私人間の私的な紛争に必要以上に介入しないという19世紀的な視点からも説明することができるであろう。
[7] 訴訟上の役割分担が異なるという点を強調すれば,主要事実と間接事実の機能の違いは明確といえる。というのも,主要事実の存在が認められれば法律効果の発生が認められるのであるから,訴訟の帰趨を決する事実といえるのに対して,間接事実には主要事実ほどの重要性は認められない。そうすると,弁論主義の適用対象の議論で両事実の訴訟法上の役割に違いがあるというのは,意識されてよいであろう。
[8] 弁論主義のⅠ論拠とⅡ機能―という2つの視点から考えてみたい。
1 弁論主義の論拠について
(1) まず,弁論主義の論拠から考えると,その背景には19世紀な視点がある。このような視点からすれば,審理の内容形成についての裁判所の介入は,最小限度であることが望ましいということになると考えられる。この視点を徹底すれば,裁判所に審理の内容形成についてフリーハンドを与えるべきではないということになる。したがって,弁論主義の適用範囲は拡大するのが望ましいので,間接事実や補助事実についても弁論主義の制約を及ぼすべきであるとの主張が成り立つ。
(2) これに対して,判例・通説は弁論主義の適用範囲は主要事実に限られるとするから,弁論主義の適用範囲を限定する論拠を示す必要に迫られると考えられる。この点,対立軸は,「当事者の意思を尊重した紛争の解決」という民事訴訟制度の目的の達成に求められるということができる。すなわち,間接事実に対して,弁論主義を適用してしまう場合に生じる弊害としては,①当事者の主張がなければ判決の基礎とすることができないとすると,主要事実の認定が難しくなる,②自白の拘束力を認めると,①と同様の問題点があるし20世紀的視点からすれば,訴訟追行能力が十分でない者に対して,裁判所が釈明権を行使するということも難しくなるという弊害があると考えられる。
たしかに,民事訴訟制度の目的に照らすと,当事者は,訴訟物として示された権利又は法律関係の存否を中心に攻撃防御を展開させているのであるから,間接事実の主張がないために,当事者の主張のある主要事実が認定することができないというのは,当事者の意思を尊重しない解釈ということができる。また,主張がなければ間接事実の認定ができないことや間接事実にも自白が成立してしまうと考えると,これらは訴訟弱者にとっては,不利益になる制度として位置付けられる。そもそも,法は弁論主義を基調としていても,他方で20世紀的視点から,裁判所が釈明権を行使して審理内容の形成に一定程度干渉することを認めている。そうすると,間接事実にも弁論主義を適用させてしまうと,釈明権を規定した意義が減殺され,当事者にとって過度の負担となると説明することができる。
2 弁論主義の機能について
(1) 弁論主義の機能は,その論拠とは離れて,「訴訟上の不意打ち防止」という機能を担っている。そうすると,間接事実であれば不意打ちは考慮しなくてもよいかは疑問が生じるところである。
(2) 考え方としては,重要な間接事実とそうでない間接事実を分けてみよう。
まず,重要な間接事実について考えてみると,たしかに,実務上は,主要事実を強く推認させる「重要な間接事実」の存否をめぐって攻撃防御が集中する傾向がある。とすれば,重要な間接事実について当事者の主張がないのに裁判所がこれを認定するのは問題が大きいことは明らかである。もっとも,抽象的に重要な間接事実とは何かということを考えると,今日では要件事実論が主要事実をして扱っているものも少なくないと考えられる。そうすると,重要な間接事実は主要事実として第1テーゼの適用があると実際上は考えられるケースが多い。また,そうでないにしても裁判所に釈明義務違反があると理解することもできると考えられる。
したがって,重要な間接事実について,第1テーゼとの関係で抱える問題は少ないということができるであろう。
次に,重要でない間接事実であれば,それは証拠と同様の機能を営むのであるから,わざわざ当事者の主張を必要とするのも問題がある。特に,不親切な裁判所というイメージがつくので,20世紀的な視点から裁判所が重要でない間接事実に拘束されないようにした方が審理を弾力化できるといえる。
3 実務の運用
以上から考えてくると,実際上の運用においても判例・通説の見解を採ることについてそれほど大きな弊害があるというわけではない。ただ,不意打ちの危険は,生じうるので,実質的に不意打ち防止を図りながら実務を運用するのが望ましいとはいえよう。
[9] 反真実かつ錯誤については,撤回禁止効の根拠からすれば,禁反言を破るための要件と考えて,「錯誤」が重要な要因となるものと考えられる。錯誤とは,民法総則の錯誤とは異なり,「真実に反するにもかかわらず,真実と誤信して自白の陳述をなすこと」をいう。このような観点から,判例は,「真実に反する」という要件を満たせば,事実上,「真実と誤信して自白の陳述をなした」と推定しているものと考えられる。これは,錯誤があったことの立証は困難なことが多いので推定を認めたものと考えられる。このように考えると,「反真実は錯誤を推認する間接事実としての位置づけ」となる。これは,理論上は錯誤が上位レベルにあるが,現実の機能上は反真実の立証がメインとなり,「錯誤」が独立の要件とされる意義は乏しいものになっている。
[10] 例えば,XがYに対して貸金返還請求をしている場合において,Yが,「金銭の交付があったこと」について自白したとしよう。そうすると,Yの自白の結果,Xは証明責任の負担を免れている。ところが,Yが自白の撤回をしようとすれば,Xは再び,「金銭の交付があったこと」との要件事実について証明責任を負わなくてはならないということになるのが原則である。ところが,自白を撤回するためには,Yは,「金銭の交付がなかったこと」を主張立証しなければならなくなるので,これは事実上,主張立証責任が転換されたに等しい結果となっている。このように,反真実を要件とすることで,訴訟全体の進行については,撤回要件の立証主題が本来の立証対象と合致するように仕組まれている。その結果,全体的にみると,自白の撤回についての論点が生じても,訴訟経済は失われないという構造となっている。
[11] 権利自白である。結局,権利自白とは,一方当事者の法律上の主張について,訴訟法上の意味を与えるための要件の1つという位置付けとなる。したがって,相手方が権利自白をしない場合は,一方当事者の法律上の主張も要件を満たさず,訴訟法上の意味がないものとなってしまう。この場合は,改めて本来の主張として事実主張をすることになる。例えば,所有権について権利自白があれば,その結果,一方当事者の「私は甲建物を所有している」という主張の訴訟法上の意味が認められるということになる。これに対して,相手方が権利自白をしなかった場合,一方当事者としては,前主からの来歴経過を主張する必要に迫られるということになる。こういう視点からみると,権利自白とは,本来は事実主張をすべきであるが,「めんどくさいので」,権利又は法律効果の存在を主張する場合ということができよう。
[12] 藤田49は,現在の実務は争点整理を通じて証拠調べ前に要証事実を明らかにしているので,証拠調べが終局まで進んだ段階で,「実は代理人が介在しているのではないか」ということが明らかになることはなくなっていると指摘する。また,仮に証拠調べにおいてそのようなことが判明した場合は,審理の内容を形成するのは,弁論主義を基調とするものの,釈明権を中心に裁判所が干渉することも予定されているのであるから,裁判所は当事者に対して釈明を求めて対応することになる。
[13] これは,「主張責任」という観点から光をあてた説明といえる。弁論主義の場合,事実や証拠の提出は当事者の責任とされる。この責任という側面を強調すると,当事者は,審理の内容を形成するに足りる十分な事実を主張しなければならないということになる。ところが,原告が単に「被告には過失がある」と主張する場合,どのような過失があるかが分からず,しかも,「過失がある」というのは事実ではなく法的評価の結果を述べているものにすぎない。したがって,主張責任という観点からみると,評価根拠事実を間接事実ととらえると,原告は,「過失がある」と主張すれば一応足りるということになるが,これでは,当事者は審理の内容を形成するに足りる十分な事実を主張しておらず,責任を果たしていないのではないかという意味と考えられる。
[14] 評価根拠事実を間接事実ととらえると,通説によれば弁論主義の適用がないから,当事者の主張の有無にかかわらず,裁判所が勝手に事実を認定できる範囲が広がることになる。これは,原告の視点から見ると,何とも頼もしいといえそうであるが,被告の視点から見ると,審理に主張として現れていないものですら判決の基礎とされかねない。そうすると,弁論主義の機能からみると「不意打ちのおそれ」があると思うし,民事訴訟制度の目的に照らしても,当事者の意思から離れて裁判所が暴走するおそれがあるということになろう。それは,究極的には原告の意思にも沿わない紛争の解決になると思われる。
[15] ただし,債権者に過失があっても,おそらくは「債権者の側」が主張している事実によって,公判に事実が上がっていることが多いと予測される。そして,主張共通の原則が認められるので,過失を基礎付ける事実というのも現実には問題とならないことが多いものと考えられる。ただし,藤田51は,あくまで被告が事実主張をしないと不意打ちになると考えているようである。
[16] おそらく,突き詰めていくと,ここで問題となるのは,事実の主張の程度ではないかと思われる。少なくとも主張共通の原則が妥当するので,「当事者間でまったく公序良俗違反の評価根拠事実の主張がなされず,証拠資料から公序良俗の事実が判明する」というのは現実には多くないように思われる。後は,当事者が主張した事実が,公序良俗違反を基礎付ける事実主張として十分といえるかという視点から見ていくことになろう。
[17] なお,45年大法廷判決によると,「弁論主義の観点から主張が必要とされる場合であっても,Ⅰ当事者の合理的意思推測とⅡ相手方当事者に対する不意打ちのおそれの有無―という観点から明示的には主張がなくても弁論主義違反とならない」という命題が導かれることになるが,藤田52は,45年大法廷判決からこのような一般論を抽出するのは妥当でないとする。
[18] 「自由心証主義」という概念もブラック・ボックスに入った概念になってしまっている人がいる。そもそも,自由心証主義が妥当するのは,「争いのある事実」についてのみであるということを理解しておく必要がある。つまり,争いのない事実や当事者が主張しない事実については,そもそも判決の基礎とすることができないのであるから,自由心証主義の守備範囲ではない。繰り返すが,自由心証主義の守備範囲は,当事者間に「争いのある事実」について,当事者が証拠調べ請求をして公判廷に証拠が出てきたときに,その出てきた証拠は果たして主要事実を推認することができるのか―という作業が問題となる局面に限られている。そして,自由心証主義というのは,ある事実を認定するための証拠を制限せず,あるいは利用可能な経験則を法が定めていないということにすぎない。したがって,突き詰めていけば,ある事実を認定するのに,複数の証拠方法があり得ていずれの証拠方法が提出されても,ある事実を推認することができる限りは証拠とすることができる。他方,ある証拠から要証事実を推認する経験則の選択は裁判官に委ねられているということになる。これも,ある証拠から要証事実を推認する経験則は複数あり得るからこのような定め方になっているものと考えられる。このように考えてくると,自由心証主義の実践的意義は,「争いのある事実」について,要件事実を認定する証拠及び利用可能な経験則が複数のチョイスがある場合に,どれを選んで事実認定をするかは,裁判官にお任せします,いう一種の裁量を認めたものに限られると解されるであり,それ以上に裁判官の恣意を許せば,審理の内容形成の面で当事者にイニシアティブを与えた弁論主義の試みが水泡に帰するということになろう。言い換えれば,様々な局面で自由心証を強調するような解釈があればそれは疑った方がよいということであろう。
[19] たしかに,「証拠共通が弁論主義に抵触するか」という問題の立て方であれば,抵触しないといわざるを得ない。というのも,弁論主義とは,概念法学の影響を受けているので,中身もまた概念化されている(つまり,概念化されている以上の内容が含まれていると考えてはいけない)。そうすると,そのいずれかに抵触するかを考えていくと,まず,第1テーゼとの関係では,これは当事者が主張をすればよいという意味にすぎないので,逆にいえばその事実は有利,不利を問わず,いずれの当事者から主張されても構わないというものである。そうすると,主張自体がなされていれば,第1テーゼには反しない。また,第3テーゼは職権証拠調べを禁止するというものであるから,当事者が提出した証拠という点が守られていれば足りるので,第3テーゼにも違反しないということになる。したがって,弁論主義には反しない。しかしながら,もう少し離れて,民事訴訟の目的を「当事者の意思を尊重した紛争の解決」にあると解した場合に問題があるかを考えてみるとよいかもしれない。ただ,当事者の意思を審理の内容形成に敷衍すると,争点を自律的に形成できるということになると考えられる。そうすると,第1テーゼや第3テーゼが守られていれば一応は「当事者の意思」に即していると考えてよいであろう。とすれば,弁論主義や民訴法の目的からいっても問題はないと考えられる。以上のように見てくると,証拠共通の原則は認めて構わないであろう。
[20] たしかに,裁判官の自由心証に委ねたところで,自由心証の意義は,「証拠AとBがある場合にどちらを選ぶか」,「経験則AとBがある場合にどちらを選ぶか」という問題にすぎない。そうすると,もし審理の結果,「証拠がない」ということになれば選択の余地などないであろう。また,経験則も証拠が少ない場合に限って,特別な経験則を持ち出してよいということになると,そもそも「本当にそのような経験則が社会に存在しているか」ということ自体が疑わしくなってくるといえる。こうして見てくると,そもそも証拠資料が乏しい事件についていくら自由心証を強調しても,出来ることが限られているということが分かるであろう。勘違いしてはならないのは,自由心証は裁判官の恣意を許すものではないから,「証拠も弁論の全趣旨を総合しても確信はないけど,何となくAさんを勝たせてしまおう」というのは自由心証とはいわないということである。
[21] いわゆる主観的証明責任についても誤解ないようにしておく必要がある。そもそも,証明責任が妥当するのは,自由心証が妥当する範囲とイコールである。なぜなら,当事者が主張しない事実や争いがない事実は弁論主義の制約から処理の手順がもう定まっているからである。そうすると,証明責任とは「争いのある事実」のみに射程が及ぶだけというのが原型である。もっとも,要件事実論では,ありとあらゆる点について,証明責任の振り分けが行われている。これは,最終的に「争いのある事実」となり,ノンリケットになれば,証明責任を負う側が不利益を被るのであるから,当事者は攻撃防御の段階で,自己が証明責任を負う要件事実について積極的に立証活動を展開していかなければならないというわけである。
[22] ただし,法律要件分類説はあくまでも条文を基準とすることには変わりがない。形式的には,条文の文言のみならず,「制度趣旨」の反映も許されていると理解した方がよい。つまり,基本は実体法の解釈の問題であるという一線からはみ出してはダメであろう。例えば,債務者の債務不履行を理由に民法415条に基づいて損害賠償請求をする場合,条文の文言からは,「履行をしないとき」という事実が要件事実となると考えるのが素直であろう。もっとも,ここで悪魔の証明だからとか,債務者に証拠があるからということを正面から挙げるのは妥当でなく,まずは実体法的な見地から,「立証困難な事実を要件とすると,訴訟上これを認める余地が極めて乏しくなり,実体法の制度趣旨に反する」という説明をした方がよい。要するに,条文の文言に着目すると不当であっても,趣旨に着目すると,かえって文言に反する要件事実とした方が制度趣旨にかなうということがあるわけである。これは,行政法における「法律上保護された利益説」と「裁判上保護に値する利益説」の対立に似たものがあるといえる。つまり,条文の文言から離れて制度趣旨に合致しているかという視点から,本文の考慮要素も検討の対象に入れていくと,新堂説的な利益衡量説にかなり近くなっていくというのは,行政法の上記学説の対立と似たような現象が生じるということである。したがって,裸の利益衡量を持ち出して立証責任の所在を論じてはならないということである(新堂説を採用すれば別である)。
[23] 藤田95は,広い意味において「実体法上の権利関係の同一性を保持したまま譲渡」されるケースも他人の権利を行使する場合に含めて理解すると分かりやすいという。
[24] 藤田95は,当事者適格を当事者の権能という視点から置き換えると,「訴訟追行権」になるという。