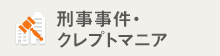憲法
- 人権総論
-
第4章 人権総論
視点 ① 人権は,いつ,どこで,いかなる観念として形成され発展したか
② 人権は,いかなる類型に区別されるのか
③ 人権は,保障される主体は誰か
1 人権の歴史
(1) 前史
人権は,人が人であるが故に有する権利との定義で歴史上初めて宣言されたのは,北米のヴァージニア権利章典(1776年)
人権は,国民が国王の権力を制約する権利との定義で歴史上初めて確立されたのは,イギリス
(2) 成立
近代的人権を最初に宣言したのは,北アメリカのヴァージニア権利章典(1776年)
フランスは,1789年に始まるフランス大革命の中で,「人及び市民の権利宣言」
(3) 普及と変容
人権思想は,アメリカとフランスの近代革命の中で成立したもの
人権思想は,自然権思想の退潮を受けて,「人の権利」から「国民の権利」へ変化
∵ ① 君主主権を基礎に置く憲法では,自然権思想は認められない
② 19世紀後半以降,法実証主義の思想が支配的に
(4) 両対戦間の動き
(ア) マルクス主義的観念が登場
マルクス主義的観念とは,近代的人権は,それを享受するための物質的基盤(要するに,お金)を欠く労働者階級にとっては,抽象的・形式的な権利にすぎないと批判した。そして,マルクス主義的観念は,人権とは天賦のものとして既に存在するものではなく,階級なき社会において初めて獲得されるものと批判
(イ) ロシア革命の成功と西欧諸国の影響
ドイツは,ワイマール憲法は,財産権を制限し社会権を保障
(ウ) 人権への挑戦
全体主義からの挑戦(全体主義は,価値の根源を全体に見て個人を前提に貢献する限りにおいてしか価値を持たないとする思想であり,個人主義を基礎にする人権の思想を否定)
(5) 第二次世界大戦後の動向
ファシズムやナチズムへの反省は,自然権思想の再生をもたらす
2 人権の観念
(1) 自然権としての人権
人権とは,人が人であるが故に当然に保持する権利をいう。当初,個々人が自然状態として有している前社会的・前国家的自然権に由来すると説明され,例えば,参政権や社会権は,「人権」の対象から外れてしまうことになる
(2) 人権の根拠
(ア) 日本国憲法の人権の根拠
現在,参政権や社会権は,人権に含めて考えられている
⇒ 日本国憲法では,人権の理解に近代的な自然権の論理(自然状態・社会契約論)は,もはやそのままでは使用されていないということ
* 人権の根拠は,「個人の尊厳」という思想に求められている。従前は,「人であること」に根拠を置いていたが,日本国憲法では,その根拠が「個人の尊厳」にシフトしている
(イ) 個人の尊厳
個人の尊厳の概念は,個人と全体(社会・集団)との関係を頭に置いた観念であり,全体を構成する個々人に価値の根源をみる思想をいう(憲法24条参照)
⇒ 個人の尊厳とは,個人を全体の犠牲にすることを禁じる思想をいう
(ウ) 個人と全体(団体・集団)との関係
問題意識 日本人は,いかなる社会集団に帰属しているかを自己のアイデンティティの要素として重視する傾向が強く,集団が個人を飲み込み個人の自律性を圧殺する同化圧力が強いことに警戒する必要
a 任意的団体
任意的団体とは,社会集団への加入・脱退が完全に自由な団体をいう(共産党)
⇒ メンバーの自由な選択により加入しているから,団体のルールによって人権が制約されているように見えても,個人の尊厳とは矛盾しない
b 非任意的団体
非任意的団体とは,社会集団への加入・脱退に何らかの制限がある団体(家族・国)
⇒ 個人は,そこに生まれ落ちるにすぎず,自分で選択して加入することができない。
すなわち,団体のルールによって人権が制約されると,それはそのまま人権侵害を意味することになる。そうすると,その団体のルールは,個人の尊厳を踏まえたものである必要がある。そこで,日本国憲法は,個人と家族や国家との関係を個人主義の原理によって構成するように命じている(憲法24条2項参照)
(エ) 個人主義の原理の真の狙い
a 個人主義の原理
個人主義の原理は,個人と社会との関係では個人の側を重視するが,これは,社会を軽視することを意味するものではない。たしかに,社会の価値は,個人の価値の集積であるから,社会を攻撃するということは,多くの個人を攻撃するのに等しい。しかしながら,社会の価値は,個人の価値の集積体であるのに対して,個人の価値は,そのすべてを社会の価値に依存しているわけではない。人間は,旧来のものを批判し新しいものを創造する能力を有している。そうすると,既存の価値(=社会)に対する反省・批判を一切許さないというのでは,伝統的価値に拘束されるだけで,新たな価値を発見・創出し,人格的自律の達成は不可能となる。個人と社会との関係で個人の側を重視するといっても,要するにバランス感覚であるが,バランスをとる場合は,個人の価値を重視
b 日本国憲法13条前段
「個人として尊重する」とは,個人が自律的に自己の生き方を選択・実践していくことを,個人のあるべき像としたうえで,個人のそのようなあり方を尊重するということ
(3) 幸福追求権(13条後段)
幸福追求権とは,個人が自律的な自己の生き方を選択・実践するために必要不可欠の権利をいう
人権の観念は,前国家的権利か否かは重要ではなく,憲法の基本的価値としての「個人の尊厳」から直接的に導かれるものであるか否かが重要
3 人権の類型
視点 人権の類型化・体系化は,どれか一つが正しいというものではなく,それぞれの体系がいかなる観点から何を明らかにするためになされているか
(1) 人権の構造的類型論(イェリネック)
人権の構造的類型論とは,国民が国家との関係でどのような地位に置かれているかにより,国民を,①行政客体としての受動的地位,②国家からの自由,③国家による自由,④国家への自由―の4つの地位に分類・分析するものをいう
ex.表現の自由の問題意識の変化を上手く説明することができる(東京都公安条例事件⇒情報公開法の制定⇒映画『靖国』問題など)
(2) 人権の内容的類型論
高橋教授は,人権を5つに分類する。
① 個人の活動の自由(精神活動の自由,経済活動の自由,人身の自由,新しい人権)
② 参政権(選挙権・被選挙権)
③ 国務請求権・受益権(裁判を受ける権利)
④ 社会権(生存権・教育を受ける権利・勤労の権利)
⑤ 適正処遇権(平等権・適正手続権)
(3) 審査基準を基礎にした分類(裁判官伊藤正己の分類論)
① 超緩やか 生存権的基本権
∵ 生存権的基本権は,裁判規範ではなく国政の指導原理にすぎない
② 緩やか 経済的自由権
∵ 現代国家においては,この権利の制約立法は合憲性の推定を受ける
③ 厳格 精神的自由権
∵ 精神活動の自由の保障であるから厳格な審査が必要であり,ただ他者の人権と衝突する可能性がある限度で制限される
④ 絶対 内面性の精神的自由権
∵ 内心の自由を保障するものであり,絶対的自由というほどに強い保障が与えられなければならない
* これ以外の人権類型については,4類型の近似性を考慮して基準を設定するという
(4) 制度保障
問題意識 人権規定の中には,個別の人権を保障する規定と並んで,人権そのものでなく特定の制度を保障するとみられる規定も存在するが,どのように理解するか
(ア) ポイント
制度的保障は,憲法上の保障であり制度が法律による侵害から保護されている
(イ) 問題点
法律により侵害されてはならない制度の本質・核心とは何かを解釈により確定する必要
(ウ) 具体例
a 政教分離
(a) 多数説の問題点
多数説は,制度保障は人権保障と異なるから制度の本質を維持する限り,法律により大幅に制限を行うことも許されるという(津地鎮祭事件判決[最大判昭和52年7月13日]のこのような論理を展開している)。
× 制度保障の観念は,制度の本質・核心さえ保持すれば法律により緩和することを意味しない
○ 制度保障を論じる場合に重要なのは,人権の保障内容を明らかにしたうえで,個別の人権が実体のみならず,手段・制度を含めてどこまで保障しているかを明らかにする点
☆ 津地鎮祭事件判決[最大判昭和52年7月13日]
そもそも,わが国においては,キリスト教諸国や回教諸国等と異なり,各種の宗教が多元的,重層的に発達,併存してきている。これらの点に照らすと,憲法は,政教分離規定を設けるにあたり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたと解される。
しかしながら,元来,政教分離規定は,いわゆる制度的保障の規定であって,国家と宗教との分離を制度として保障することにより,間接的に信教の自由の保障を確保しようとする点に趣旨がある。ところが,宗教は,多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴う。宗教は,教育,福祉,文化,民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触を有するから,国家が,社会生活に規制を加え,教育,福祉,文化などに関する助成,援助等の諸施策を実施すると宗教とのかかわり合いを生ずることを避けられない。したがって,現実の国家制度として,国家と宗教との完全な分離を実現することは,実際上不可能に近い。むしろ,政教分離原則を完全に貫こうとすれば,かえって不合理な事態を生ずることが避けられない。
これらの点に照らすと,政教分離原則は,社会的・文化的諸条件に照らし,国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としている。そのうえで,そのかかわり合いが,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で,いかなる場合にいかなる限度で許されないかが問題とされる。このような見地から考えると,わが憲法の政教分離原則は,国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが,国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないと解される。
b 大学の自治
c 私有財産の自由
4 人権の主体
問題意識 第3章「国民(?!)の権利及び義務」と規定されている
(1) 国民の範囲
(ア) 「人」としての国民
憲法10条「日本国民たる要件は,法律でこれを定める」
× 憲法の下位にある法律が国民の範囲を自由に定められるとは考えられない
○ 論理上は,国民の範囲は「社会構成員」として憲法以前に定まっているもの国籍法の規定は,ある程度立法裁量は認められるとしても,確認的意味を有するだけ
(イ) 子ども
子どもは,人権の主体であることは当然
× 子どもは,成熟した判断能力を常に有するとは限らないから,本人の利益に反する生き方を選択・実践するおそれ
○ 子どもは,本人の利益を保護したり,未熟な判断による行為が社会的に好ましくなかったりする場合は,一定の人権の行使の制限が許される
(2) 外国人[1]
(ア) 考え方
① 国家の構成員は,国籍の保持者とイコールではない
∵ 社会契約説の論理では,人権を護るために社会契約に参加した者がその構成員となるから,論理的には国籍を有しない外国人も社会契約に参加することは可能
② 日本国憲法は,国際協調主義を採用(98条2項)
∵ 外国人には人権の主体性を原則的に承認するのが日本国憲法の要請
⇒ 視点 外国人の人権享有主体性を肯定して,国民と異なる取扱いがどの限度で正当化されるかを考えるアプローチが妥当!!
考慮要素
① 人権の性質の違い
② 外国人の種類(永住者,ツーリスト)
(イ) 具体的事例総論
a 理論的な分析の手順
① 外国人に保障されない人権類型を明らかにする ⇒ ② 保障される人権に関して,外国人であることを理由にどのような制約が許されるかを検討
b 高橋説の視座
高橋説は,外国人でも一応すべての人権が保障の対象となるという前提の下,それぞれの人権についてどのような制約が可能かを検討するというアプローチを採っている。
考え方 高橋説は,外国人は,平等権を享有しているから,外国人であることを理由とする差別の合理性を検討するアプローチを採る
(ウ) 具体的事例各論
a 入国・在留・再入国の権利
入国の自由は保障されない(最大判昭和32年6月19日)
在留の権利は保障されない(マクリーン事件[最大判昭和53年10月4日])
再入国の自由は保障されない(森川キャサリーン事件[最判平成4年11月16日])
* 高橋説は,在日外国人はすでに日本に滞在しているのであるから,上記判例群の理論的前提となっている入国の自由の保障がないという32年判例の射程が及ばないと考える。そうすると,「入国の自由がないから在留の権利もない」という論理が成り立たなくなる。そこで高橋説は,在日外国人は在留の権利もあるし,再入国の自由も保障されると論じる
b 政治活動の自由
多数説 参政権は,日本の政治に重大な影響を与えるような活動の制限は許される
× ① 政治活動と参政権はイコールではない
② 外国人の発信する政治的表現は,国民の選挙権行使の資料となる
○ 表現の自由自体は,最大限に保障すべき
マクリーンの在留期間更新申請に対し法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるものとはいえないとしてこれを許可しなかったのは,マクリーンの在留期間中の無届転職と政治活動のゆえである。なかでも政治活動が重視されている。
基本的人権の保障は,権利の性質上国民のみを対象としているものを除き,在留する外国人に対しても等しく及ぶ。政治活動の自由についても,わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないものを除き同様といえる。しかしながら,外国人は,法務大臣が裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断する限り,在留期間の更新を受けられる地位を与えられているにすぎない。したがって,外国人に対する基本的人権の保障は,外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない。すなわち,在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されない保障を与えるものではない。在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも,法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとつて好ましいものとはいえないと評価し,また,右行為から将来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは,その行為が憲法の保障を受けるものであるからといって妨げられない。
* この判例は,外国人の政治活動の自由が制限されうることを示したものという読み方も可能であるが,在留外国人の基本的人権は出入国システムの枠内で保障されるという出入国システム優位説を採用したと考えるのが素直
c 社会権
国際人権規約を批准したため,社会保障関係法に存在した国籍要件は撤廃
d 参政権
多数説 参政権は,性質上,外国人には認められない
∵ 参政権は主権の行使の意味を持つから,国民主権の原理から不可能
× 仮に国民主権にいう国民が国籍保有者を指すとしても,外国人に参政権を認めることが国民主権の原理に反するとまで言えない
○ 主権者国民が外国人に参政権を与える決定を法律により行うことを憲法は禁止し
ていない(最判平成7年2月28日[地方参政権について])
e 公務就任権
(a) 公務就任権の中身
多数説 公務就任権を人権の構造的類型論に照らして,同一の構造を採る参政権とパラレルに理解しようとして,参政権がないのと同様に認められないと論じる
× ①政治的な政策決定を行う公務員と②単に公務を執行するにすぎない公務員を同一視することはできない
○ 高橋説の視座
① 政治的な政策決定を行う公務員 ⇒ 公務就任権は,参政権の問題
* ①については,たしかに,主権原理は,国家の自律的統治を困難にするような事態の作出を禁止しているが,一般職の公務に関しては,外国人が就任すると自律的と内が困難となることはない(主任の大臣など上位者のコントロールを受ける)。
② 単なる公務執行公務員 ⇒ 公務就任権は,職業選択の自由(22条1項)の問題
* ②は,平等権・職業選択の自由の侵害とならないかを考えるべき
(b) 昇格差別(公務就任が原則的に許されることを前提にした議論)
○ 昇格差別は,公務の階層性が上部に位置し裁量権が増すのに比例して合理性が認められることが多くなる
(c) 管理職試験の受験資格制度の採用
問題意識 国・地方公共団体の管理職の要件として,管理職試験の合格を要求し,外国人には受験資格を認めない制度を採用することはできるか。
× 管理職ポストのすべてが外国人に否定してもよい性格のものであれば問題はない
が,外国人に拒否することの合理性が認められない性格のものが含まれている
○ 在日外国人は,可能な限り日本人と同様に扱うべきであり,そのような制度設計が困難であるという事情があるかを審査すべき
*東京都管理職登用事件(最大判平成17年1月26日)[2][3]
公権力行使等地方公務員の職務の遂行は,住民の権利義務や法的地位の内容を定め,あるいはこれらに事実上大きな影響を及ぼすなど,住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有する。それゆえ,国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきであること(憲法1条,15条1項参照)に照らし,外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではない。
また,普通地方公共団体が,公務員制度を構築するに当たって,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ることも,その判断により行うことができる。そうすると,普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものである。この理は,前記の特別永住者についても異なるものではない。
f 人格権
人格権・自己情報コントロール権・自己決定権は,外国人につき制限する合理性なし
Cf. 指紋押捺制度
判例(最判平成7年12月15日)は,合憲説
× LRAの基準に照らすと,人物特定の手段として他の方法がある(署名と写真)
* 外国人の人権であっても,そもそも問題とされている権利・自由が具体的にいかなる個人的・社会的権利の中に位置付けられており,憲法上どの程度保護されるかが真の問題点であり,定住外国人についてはその保障の範囲・程度を手厚くすべきとする視点も加味しながら思考することが重要
(3) 法人・団体
(ア) 基本的な考え方
⇒ 団体には,固有の人権主体性はなく,構成員の人権を代表して主張できるにすぎない
*ポイント
① 法人が享有するのは,人権ではなく「憲法上の権利」である
② 憲法上の権利を法人が享有するのか,あるいは代位主張するのみかという問題あり
③ 憲法上の理由がある限り,その団体が法人格を有するか否かに関わらず,団体に憲法上の権利の保護が認められる
⇒ 要するに,団体に憲法上の権利が認められるかは,抽象的に権利の性質から決まるのではなく,むしろ,憲法上の権利とその団体の意義(例えば,宗教団体の場合は信者の信教の自由の保障との関連),構成員と団体との関係を考慮して決定されるべき
* 外国人と比べて団体は一定の目的のための個人の結合であるから,団体毎の昨日に応じた具体的な議論が求められる
(イ) 判例
① 団体が外部との関係で人権を援用する場合
ⅰ 国家と対抗する場合
博多駅フィルム事件(最大決昭和44年11月26日)
ⅱ 私人と対抗する場合
サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)
* 団体が構成員のもつ人権を代位主張したとみてスタンディングは認められる
② 団体が自己の構成員との関係で人権を援用する場合
高橋説は,②のケースは,団体は人権を援用しうる立場にはない。そうすると,高橋説では,理論的に②のケースでのみ法人の人権享有主体性を検討する意味があることに
∵ 高橋説は,人権は対国家防御権であることを重視しているから,「結社の自由は,国家に対する権利であり,構成員に対する紀律権の根拠」とならないとする。なお,高橋説は,団体が構成員の間で構成員に対して主張できるのは人権ではなく,団体の紀律権であるとする。
Ex.八幡製鐵政治献金事件,南九州税理士会事件
[1] なぜ,外国人の人権問題というものが論じられるのか,その理論的根拠を押さえておく必要がある。社会契約論からすれば,国家は個々人の自然権を保障するために創られたものである。とすれば,国家が人権を保障する義務を負うのは,社会契約に参加している者のみという論理になる。このような観点が日本人と外国人を区別する1つの理論的根拠となる。しかしながら,では憲法は,社会契約に参加しなかった者の人権を保障しなくてもよいと考えているかについては,憲法解釈の余地が生じてくるわけである。この点に関しては,定石を流して原則として性質上可能な限り外国人にも人権が保障されているという論理となる。しかし,逆に言えば,性質上可能な限りの性質というのは,いわば社会契約に参加しているか否かが問われないという趣旨に理解することができるであろう。このような基本的視座から外国人に対する差別が正当化することができるかということを検討することが求められるものと考える。
[2](泉裁判官の反対意見)1 人権制限の正当化根拠
地方公共団体が,特別永住者について地方公務員となることを,一定の範囲で制限することが許されるかどうかを検討する。
(1) ・・・国民は,この国民主権の下で,憲法15条1項により,公務員を選定し,及びこれを罷免することを,国民固有の権利として保障されている。国民主権は,国家権力である立法権・行政権・司法権を包含する統治権の行使の主体が国民,すなわち,統治権を行使する主体が,統治権の行使の客体である国民と同じ自国民であること(以下,「自己統治の原理」)を,内容として含んでいる。
(2) 自己統治の原理に基づき自治事務を処理・執行する目的からの制限(正当化根拠①)地方公共団体における自治事務の処理・執行は,法律の範囲内において自己統治の原理が,自治事務の処理・執行についても及ぼされる。自己統治の原理は,憲法の定める国民主権から導かれるから,地方公共団体が,自己統治の原理に従い自治事務を処理・執行するという目的のため,特別永住者が一定範囲の地方公務員となることを制限することは,正当な目的といえる。したがって,その制限が目的達成のため必要かつ合理的な範囲にとどまる限り,上記制限の合憲性を肯定できると解される。
しかしながら,国は,法律により特別永住者に対し永住権を認め,その活動を制限していない。また地方公共団体は,特別永住者の活動を自由に制限する権限を有しないし,地方公共団体は法律の範囲内で自治事務を処理・執行する立場にある。そこで,地方公共団体が,自己統治の原理から特別永住者の就任を制限できるのは,自己統治の過程に密接に関係する職員,換言すれば,広範な公共政策の形成・執行・審査に直接関与し自己統治の核心に触れる機能を遂行する職員,及び警察官や消防職員のように住民に対し直接公権力を行使する職員への就任の制限に限られる。自己統治の過程に密接に関係しない職員への就任の制限を,自己統治の原理でもって合理化することはできない。
(3) 自治事務を適正に処理・執行するという目的からの制限(正当化根拠②)たしかに,地方公共団体は,自治事務を適正に処理・執行するという目的のために,特別永住者が一定範囲の地方公務員となることを制限する必要がある場合,当該地方公務員が自己統治の過程に密接に関係しない職員でも,合理的な制限として許される場合もあり得る。
しかしながら,特別永住者は,本来,憲法が保障する法の下の平等原則及び職業選択の自由を享受し,かつ,地方公務員となることを法律で制限されていない。また,職業選択の自由は,職業を通じて自己の能力を発揮し,自己実現を図るという人格権的側面を有している。しかも,特別永住者は,その住所を有する地方公共団体の自治の担い手の一人である。特別永住者は,当該地方公共団体との結び付きという点では,他の外国人と比べて,はるかに強いものを持っているし,特別永住者が通常は生涯にわたり所属することとなる共同社会の中で自己実現の機会を求めたいとする意思は十分に尊重される必要がある。そこで,特別永住者の権利を制限するについては,より厳格な合理性が要求される。
具体的には,自治事務を適正に処理・執行するという目的のために,特別永住者が自己統治の過程に密接に関係しない職員となることを制限する場合には,その制限に厳格な合理性が要求される。換言すると,具体的に採用される制限の目的が自治事務の処理・執行の上で重要なものであり,かつ,この目的と手段たる当該制限との間に実質的な関連性が存することが要求され,その存在を地方公共団体の方で論証したときに限り,当該制限の合理性を肯定すべきである。
2 具体的検討以上の観点から,東京都人事委員会が特別永住者であるXに対し本件管理職選考の受験を拒否した行為が許容されるものかどうかを検討する。
(1) 正当化根拠①からの検討本件管理職選考は,「課長級の職」への第一次選考である。課長級の職には,自己統治の過程に密接に関係する職員が含まれるから,自己統治の原理に従い自治事務を処理・執行するという目的の下に,特別永住者が上記職員となることを制限しても,合理的制限として許容される。
しかしながら,本件管理職選考は,知事などに任命権がある職員の課長級の職への第一次選考にすぎない。これは,選考対象の範囲が極めて広く,「課長級の職」がすべて自己統治の過程に密接に関係する職員とは評価できない。公の意思の形成といっても,その内容・性質は各種・各様であって,地方公共団体の課長級の職員が行う行為すべてが,広範な公共政策の形成・執行・審査に直接関与し自己統治の核心に触れる機能を遂行するとは評価できないからである。このように,課長級の職には,自己統治の過程に密接に関係しない職員が相当数含まれている。そうすると,自己統治の原理に従い自治事務を処理・執行するという目的を達成する手段として,特別永住者に対し「課長級の職」への第一次選考である本件管理職選考の受験を拒否することは,上記目的達成のための必要かつ合理的範囲を超えるもので,過度に広範な制限といわざるを得ず,その合理性を否定せざるを得ない(正当化根拠①からは正当化できない)。
(2) 正当化根拠②からの検討ア Y団体は,Y団体の人事管理の下では,本件管理職選考に合格した者はいずれ自己統治の過程に密接に関係する職に就かせることになるので,人事管理政策の遂行のため,特別永住者の受験そのものを拒否し,「課長級の職」の中で自己統治の過程に密接に関係しない職員となることも制限が許されるべきと主張している。
イ かかる制限を正当化には,具体的に採用される制限の目的,すなわち,Y団体の人事管理政策を実施することが自治事務を処理・執行する上において重要といえる必要がある。また,目的と手段たる当該制限,すなわち,特別永住者に対し本件管理職選考の受験を拒否し,「課長級の職」の中の自己統治の過程に密接に関係しない職員となることを制限すること―との間に実質的な関連性が存することが必要である。
ウ たしかに,Y団体の人事管理政策を実施するという目的は,自治事務を適正に処理・執行する上において合理性を有するものであって,一応の正当性を肯定することができる。しかしながら,特別永住者に対し法の下の平等取扱い及び職業選択の自由の面で不利益を与えることを正当化するほど,自治事務を処理・執行する上で重要性を有する目的とはいい難い。
エ また,4級の職員が第一次選考である本件管理職選考に合格しても,直ちに課長級の職に就くわけではなく,更に選考を経て5級及び6級の職をそれぞれ数年間は経験する必要があるし,Y団体では,多数の課長級の職を設けられている。このことに照らすと,Y団体が,特別永住者に本件管理職選考の受験を認め,将来において課長級の職に昇任させた上,自己統治の過程に密接に関係しない職員に任用しても,Y団体の人事管理政策の実施に支障が生ずるものとは考えられない。以上より,Y団体が特別永住者に対し本件管理職選考の受験自体を拒否し,自己統治の過程に密接に関係しない職員になることを制限するという手段は,Y団体の人事管理政策の実施という目的と実質的な関連性を有するとはいい難い。したがって,上記の制限をもって合理的なものということはできない。[3] この判旨は,外国人を差別しない任用制度の可能性を十分に議論しないで,「一体的な任用制度」も許されるという判断を先行させ,そこから差別の合理性を導くという思考過程をたどっている点が特徴である。要するに,制度を人権に優先させている(芦部92)