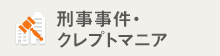交通事故
- 事故により脳脊髄液減少症及び胸郭出口症候群を発症したと認めた事例
-
平成29年6月1日名古屋高裁判決
控訴人は本件事故直後,明確に頭痛を訴えることはなかったものの,同ウのとおり,本件事故から10日余り後には,医師に対して強く頭痛を訴えていることが診療記録上も認められる。また,控訴人は,本件事故により,頚部や腰部など,身体の他の箇所にも強い痛みや痺れを訴えており,特に,目眩,耳鳴り,光過敏等,脳脊髄液減少症に伴って生じる症状が事故直後から存在していたことは診療記録上も明らかである。これらからすると,控訴人は,事故直後には頭部痛を明確に意識し得なかったが,その後の身体症状の変化に伴って頭痛を意識できるようになり,その結果,本件事故の10日余り後になってから,医師に対して頭痛を強く訴え始めたとも考えられるところである。そして,このような事情を踏まえると,事故直後の諸状況につき他の客観的証拠に合致しておらず,全般に信用性の低いといわざるを得ない控訴人本人の供述(甲77の陳述書による陳述も含む。以下同様。)についても,事故後の早い時点以後には頭痛が生じていることを意識し始めたという限度において,その信用性を否定することは困難であるということができる。そして,それら初期の頭痛が,当時から確実に起立性の頭痛として意識されていたことを認めるに足りる明確な証拠はないものの,本件事故から数か月後の平成18年4月以降には起立性頭痛と認められる症状を控訴人がはっきり訴えていることからすると,むしろ初期の頭痛だけが起立性の頭痛ではなかったとは断じ難いところである。
なお,控訴人は,平成18年2月9日にブラッドパッチ治療を受けた後,急激に体調が悪化し,起立性頭痛が生じたかのように訴えているが,それこそ控訴人の愁訴によるものにすぎず(乙24の97頁),上記ブラッドパッチ治療に医療過誤があったために起立性頭痛が発症したとは認められない以上,起立性頭痛の原因は本件事故以外には考えられないというべきであるから,当初に起立性頭痛の明確な愁訴がなく,遅くなってからそれを強く訴えるようになったからといって,当初からの起立性頭痛の存在が否定されるものではない。
以上からすると,控訴人は,本件事故後の早い時期に頭痛を訴えていたことが認められ,それは起立性のものであったと推認することができる。
仮に,控訴人の頭痛が起立性のものでなかったとしても,国際頭痛分類第3版β版の基準では,頭痛が起立性であることが必須である旨の記載は認められないところであるから(乙56),控訴人の症状が直ちに前記各基準を満たさないものとはいえない。
ウ 画像所見について
前記1(2)カのとおり,名古屋市立大学病院で平成18年2月8日に実施されたRI脳槽シンチグラフィーのRI注入6時間後の画像の腰椎レベルについて,E医師は,腰椎左側に明らかな髄液漏出所見を認めるとしている。
これに対し,K医師は,同画像所見として左側に3か所,右側に1か所(少量),腰椎レベルに髄液漏出所見が認められるとした上で,RIを脊髄に注入する際にできた針孔からRIが流出したものであるにすぎない可能性を示唆する。
しかしながら,上記RI脳槽シンチグラフィーにおいて用いられた針は,K医師が依拠する文献が想定するものとは異なり,25Gデシベルポイント針であると認められ(乙14の21,22頁),これによりRIを脊髄に注入する際にできた針孔からRIが流出する可能性は著しく減少しているものと考えられるから(甲102),1970年代の古い文献等に基づいて,上記可能性を示唆するK医師の意見に強い説得力があるとは解されない。
また,E医師は,同日に実施された控訴人の頭部MRIの画像により硬膜下腔の開大があると判断している箇所につき,K医師は,硬膜下腔かくも膜下腔かを区別する必要がある空間であるところ,血管が走行していることからくも膜下腔だとわかり,くも膜下腔が拡大している場合,くも膜下腔にあるのは髄液であるため,髄液が増加していることになり,脳脊髄液減少症という概念と矛盾するとの見解を示している。これに対し,同病院のL医師(以下「L医師」という。)は,硬膜下腔かくも膜下腔かはっきりしない部位もあるが,くも膜下腔の開大であったとしても,頭蓋内圧が低下したことにより開大する可能性は考えられ,積極的に両者を分ける意義は見いだせないとの意見を述べているところであって(甲70(枝番を含む。以下同様。),71),双方の意見を比較した場合,E医師の上記判断が誤りであるとは断じ得ない。また,上記頭部MRI画像において,E医師やL医師がガドリニウム造影剤による著明な硬膜増強効果があると判断している部分(甲70,71)につき,K医師は,単に頭蓋骨の脂肪であって,特段の硬膜造影効果は認められない旨述べるが,E医師らの臨床経験に基づく総合的判断に対し,画像判断のみに留まるK医師の見解が確実に正しいものとはいい切れない。
以上のとおり,臨床の現場で実際に診療活動を行っている専門医らにより,RI脳槽シンチグラフィー及び頭部MRIによって脳脊髄液減少症の発症を十分に認め得るとされる画像が存在し,それが誤りであるとはいえない上,E医師は,平成18年4月20日に施行されたMRミエログラフィーにおいても,腰椎レベルでの髄液漏出の可能性を判断しており,同年8月23日に明舞中央病院におけるRI検査においても3時間後に軽度のRI膀胱集積が認められていることをも考慮すると,本件において,脳脊髄液減少症を示す画像所見の存在一切を否定し去ることは困難というべきである。
もっとも,以上述べた画像所見を個別的に見ると,前記の厚生労働省研究班画像診断基準を満たすものではないが,同基準は本件事故後に作成されたものであり,かつ,今後の変更の余地がないとはいえないところであるから,現時点において,これら個々の画像が同基準に必ずしも合致しないからといって,その画像の臨床的な価値を全て否定する方向で同基準を用いることは相当ではない。
エ 以上のアないしウを総合すると,控訴人には事故当初からの起立性頭痛が認められ,脳脊髄液の漏出を裏付ける画像所見が認められ,ブラッドパッチ治療により症状の改善が認められるといえるから,前記した諸基準を総合判断すると,前記アの冒頭に記載の3病院における臨床診断は十分に信頼性があり,これらに基づき,控訴人は,本件事故により脳脊髄液減少症を発症したものと認められる。」
(10) 原判決39頁14行目冒頭から40頁10行目末尾までを次のとおり改める。
「 控訴人には,本件事故後,左上肢から手指にかけての痛み,脱力,しびれがあったものと認められるところ,前記1(2)ケのとおり,B医師は,控訴人において,握力低下とモーレーテストでの左上肢陽性の所見があったことから,左前斜角筋離断神経剥離術を実施したこと,B医師は,この手術中,前斜角筋の癒着を直接確認したと陳述しており(甲102),その信用性を否定すべき事情は存しないこと,本件事故後約2年半を経過した後に実施された手術であるとはいえ,左前斜角筋の癒着の原因は本件事故以外に考え難いこと,脳脊髄液減少症には胸郭出口症候群が併発する例があるといえるところ,前記のとおり控訴人に脳脊髄液減少症が認められることにも合致すること,実際,上記手術後に不定愁訴が増え完治はしなかったとはいえ,最終的に前記のような症状の軽減または改善が6割程度認められたといえること,前記1(2)キのとおり,A医師が諸検査を実施したが胸郭出口症候群との確定診断をしなかったとはいえ,A医師が腕神経叢造影検査等において,肋鎖間隙で狭窄所見を認めたことにもむしろ整合し,少なくとも矛盾はしないこと等からすると,控訴人は,本件事故により胸郭出口症候群を発症したものと認められ,これを覆すに足りる十分な証拠はない