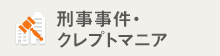名古屋の弁護士による窃盗など財産罪
第4編 財産に対する罪
第1 総説
第2 窃盗罪
1 占有の意義
(1) 占有の有無(遺失物横領との区別)
『窃取』(235条)とは,他人が占有している財物を取ること,すなわち,他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移すことをいう
刑法上の占有があるというためには,『事実上の支配』が必要である。
ア 客観的要素
事実上の支配が認められるためには,事実上の支配関係,すなわち,社会通念上占有者の支配力の及ぶ場所に存在することが必要
イ 主観的要素
財物に対する支配を行おうとする意思,すなわち,自己の支配する場所内に存在する物一般に対する概括的な意思をいう[1]
ウ 『事実上の支配』の判断の仕方
どの範囲まで,『事実上の支配』に含まれるか明確な基準はなく,具体的事実ごとに,①物の形状,②性質,③存在する場所,④時間的関係―を総合的に考慮して通常人であれば首肯することができるという社会通念によって決する[2]
エ 第三者の事実支配
被害者の事実支配を離れた物について,窃盗罪の成立が認められる可能性
区別の基準 占有者の包括的支配力が完全であるかという点が目安になる
| 包括的支配が完全ではないケース | 包括的支配が完全なケース |
| 多数の人が自由に出入りすることができる場所の場合は,直ちに管理者が占有を取得するとはいえない | 旅館のトイレで遺失した財布について旅館主の事実上の支配が及ぶとされたケースがある[3] |
(2) 占有の帰属(横領との区別)
財物の占有が行為者に帰属すれば,横領罪が成立することはあっても窃盗罪は成立しない
ア 共同占有
共同占有とは,数人が相互平等の関係で財物を占有している場合をいう
⇒ 他の者の同意を得ないで自己単独の占有に移すと窃盗罪
イ 上下主従間の占有関係
上下主従間の占有関係とは,雇用関係に基づいて下位・従属の地位にある者が財物に対して事実上共同支配の状態にあることをいう
⇒ 通常上位者に占有があり下位者は占有補助者にすぎないから,窃盗罪
ウ 委託された包装物の占有関係
封緘によって容易には開封することができない状態にされた包装物について運搬を依頼した場合において,その在中物の占有は受託者にあるかという問題
(ア) 判例の考え方
① 包括物全体
受託者に占有あり
⇒ 全体を盗めば横領罪
② 在中物
委託者に占有あり
∵ 受託者は,包装物を事実上支配しているが,その中身については自由に支配しうる,つまり,中身を開けて精査したりすることはできない状態にあるから
⇒ 中身のみ抜き取れば窃盗罪
(イ) 在中物を盗むために包括物全体を盗んだ場合の処理
○ 受託者が包装のまま領得する行為は原則として横領罪にあたる
しかしながら,開封して中身を抜き取る目的で封ごと領得する行為は,その段階で窃盗の手段としての実行行為があると解される。したがって,中身を抜き取る目的がある場合は例外的に窃盗罪が成立すると解すべき
∵ ① 行為者の目的が在中物の領得にある点が重要
② 開封の有無という形式的事実にこだわりすぎるのは妥当でない[4]
(3) 死者の占有
ア 『死者の占有』の議論の射程距離
『死者の占有』の議論は,行為者が被害者を殺害してから初めて財物領得の意思が生じた場合について,被害者が死亡しているからといって遺失物横領でよいのかという問題意識に基づいているから,死者にも占有を広く認めることや第三者による財産の取得はもともと予定されていない議論といえる
イ 『死者の占有』の検討
● 死者の占有を広く認めるべき
× 死者には財物に対する事実上の支配がない
○ 被害者を死亡させた後,領得の意思を生じて被害者が所持していたものを領得した場合は,全体的に考察して被害者が生前持っていた占有を殺害・盗取の一連の行為によって侵害し自己の占有に移したものとして窃盗を認めるべき
∵ 犯人に対する関係では,死亡と時間的場所的に近接している範囲内にある限り,死後もこれを保護しようとするものであり,社会的現実・実情に合う
ウ 一連の行為を認定する基準[5]
占有が保護されるのは,『殺害と同時』と評価しうる範囲内であり,それは,①時間的乖離の程度,②殺害場所の態様―を実質的に考慮して決める。一つのメルクマールになるのは,死亡直後の生々しい死体から奪うのであれば,『殺害と同時』と規範的には評価することができる
| 殺害と同時と規範的に評価したケース | 殺害と同時ではないと評価したケース |
| ①人を殺した直後にその現場で奪取 | ①殺害後51時間経過後の持ち出し[6] |
2 不法領得の意思
(1) 要否
窃盗罪が成立するには,通常の故意以外に主観的要件として不法領得の意思が必要とされる
∵ ① 毀棄・隠匿との区別
② 使用窃盗の除外
(2) 定義
不法領得の意思は,排除意思と利用意思の双方が必要[7]
(3) 一時使用と不法領得の意思との関係
一時使用とは,他人の財物を一時使用した後に返還する意思でその占有を侵害することをいう
視点 権利者の利用が実際,どれだけ侵害されているか,すなわち,処罰に値する程度の占有侵害があったかという観点から判断する。具体的には,①乗り捨てのように返還する意思がない場合,②長時間・長距離に及ぶ場合(このような場合,占有者の占有を失わせるものといえる),③長期の継続的な利用,④価値の消費を伴うような場合―を考慮するものと考えられる
⇒ 判例の検討で重要なのは,元に戻す意思があればそれだけで不法領得の意思が否定されるものとは考えていないという点にある
3 窃取
(1) 窃取の意義
『窃取』とは,占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し,目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいう
Cf. 詐欺罪との区別
『窃取』にあたって欺罔行為が行われた場合には窃盗罪が成立するか詐欺罪が成立するかが問題となる。
視点 欺罔行為とみられる行為があっても,それが相手の処分行為を導くようなものでない限り,詐欺罪は構成しない
(2) 着手時期
判例は,窃盗罪の着手時期について,他人の財物に対する事実上の支配を侵すについて密接なる行為をなしたときが窃盗罪の着手時期となるとする
視点 財物の占有侵害の危険が希薄な段階では処罰の必要性はない
① 侵入窃盗のケース
この点,住宅や事務所内に侵入すれば,盗みの犯意は外部的に明らかになったとはいえるが,占有侵害の危険が生じていないので窃盗の着手は認められない。
⇒ 金品の物色のためにタンスに近寄るなどの物色行為を始めたときに実行の着手が認められることが多い
② 倉庫のケース[8]
倉庫などは,通常財物しか置かれていないから,そこに侵入すれば中の財物の占有が侵害される危険が生じたと評価することができる
⇒ 倉庫に侵入を開始すれば窃盗の着手が認められる
(3) 既遂時期
窃盗の既遂時期は,自己の事実的支配下に移した時点で既遂に達する。そして,行為者が占有の取得をしているか問題となるケースは,被害者が占有を失ったか疑わしいケースといえる。
視点 占有の取得があるかは,①財物の性質,形状,②財物に対する占有状態,③窃取行為の態様―を考慮して,被害者の支配状態を脱却させることをほぼ確実なものにしたかを判断すべき
*具体的な検討
| ①との関係 | ②との関係 | ③との関係 |
| 自販機のコイン・ホルダーを取り外したケースでは,比較的小型であることを理由に手中に収めた時点で既遂に達する | レジ脇からレジ外側に持ち出すと,一般の買物客と区別できなくなるから,被害者が占有を失ったといいやすくなる | 指輪を浴室の隙間に隠す態様であったとしても,よほど見つけにくいところであれば,被害者は占有を失ったといえる |
4 不動産侵奪罪
5 親族相盗例
第3 強盗罪
1 強盗罪
(1) 客体と行為
『強取』とは,暴行・脅迫により,相手方の犯行を抑圧しその意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すことをいう
(2) 暴行・脅迫の意義
ア 暴行・脅迫の程度
暴行・脅迫は,相手の反抗を抑圧する程度に強度なものに限られる
⇒ これに至らない場合は,恐喝罪が成立するにすぎない
視点 反抗を抑圧されたかは,①被害者の性別,年齢,②犯行の場所,時間,③犯人の態度,④凶器使用の有無―など具体的事情を考慮し,社会通念上,一般に被害者の犯行を抑圧するに足りる程度のものといえるか[9]
イ ひったくりのケース
視点 ひったくりは,交付行為がないので恐喝罪が成立する余地がないという異色の行為態様であるので窃盗罪か強盗罪かが問題となる
*ひったくりの罪名
視点 暴行・脅迫が『財物奪取』の際に行われただけでは,程度が強度でも強盗になるか微妙であり,財物奪取の手段と評価することができる必要がある[10]
| 窃盗にとどまるケース | 強盗になるケース |
| 後方から追い越しざまにバッグを盗むような態様 | 女性を自転車もろとも転倒させ顔面を殴りバッグを奪った態様 |
| 窃盗罪 | 強盗罪 |
(3) 暴行・脅迫と財物奪取との因果関係
ア 判例は,「反抗抑圧に足りる暴行・脅迫⇒財物・利益の移転」という関係があれば強盗既遂を認めており,被害者が畏怖したにとどまる場合でも異ならないとする。これに対して,通説は,「反抗抑圧に足りる暴行・脅迫⇒反抗抑圧という結果⇒財物・利益の移転」という因果経過を必要とする。
イ この点,国井176,前田233は,いずれも判例の立場を支持している[11]
ウ 結局,前田説的に理解すると強盗罪の強取とは,①反抗抑圧に足りる暴行・脅迫により,②その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移させ,③暴行・脅迫と財物奪取との間に類型的な因果性が存在することが必要―ということになろう[12]
(4) 暴行・脅迫後の領得意思
ア 設例
強姦の目的で被害者を脅迫しその反抗を抑圧しつつ全裸にしたところ,男性であることに気付いただめに,この際,この機会を利用して金品を奪おうと考え実行したケース
イ 考え方
(ア) 原則的処理
強盗罪は,故意犯であるから,当初から財物奪取の意思で暴行・脅迫を加えて強取することにより成立する[13]
∵ 強盗罪の故意の成立は,暴行・脅迫を手段として財物奪取をするという意思が必要
(イ) 例外的処理
犯人が財物奪取の意思を生じた後に被害者の拒否を不能ならしめる新たな暴行・脅迫に値する行為がある場合は,強盗罪となる(特に,犯人が現場にとどまっているだけでも被害者にとって脅迫と評価できるケースもあるので十分証拠を収集して処分を検討すべき)[14][15]
(5) 着手時期と既遂時期
強盗罪の着手時期は,手段である暴行・脅迫を始めた時点である
既遂時期は,財物の占有を取得した時点である
2 利益強盗罪
(1) 処分行為の要否
判例は,不要説(最判昭和32年9月13日刑集11巻9号2263頁)[16]
● 処分行為必要説
× 強取とは,被害者の意思によらずして財物の占有を移転するのが本質であるから,これと本質が同じ2項強盗において,財産上の利益の移転が被害者の強制された処分行為を要するものと制限する理由はない
○ 不要説
ただし,「利益」の移転時期,すなわち,既遂時期を明確化することは必要
⇒ 2項強盗の財産上の利益の移転は,1項強盗の財物取得に対応する程度の現実性をもつ必要
*利益の移転時期
| 債権者殺害のケース | 両親の殺害と相続 | |
| 肯定例 | 債権の行使を当分の間不可能ならしめて,支払い猶予を得たのと同視しうる場合(なお,さらに故意で限定される) | 前田説は,相続上の利益も「財産上の利益」にあたることを前提に,「取得」にあたるかを検討する |
| 否定例 | 契約書があるため相続人が債権を行使する可能性があり,しかも一時的に支払いが延びたにすぎない場合 | 判例(東京高判平成元年2月27日)は,「任意の処分の観念を入れる余地がない」として「財産上の利益」にあたらないとしている[17] |
3 事後強盗罪
(1) 目的犯
| 類型 | 窃盗の状態 |
| ①財物の取り返し防止目的 | 窃盗既遂に限られる |
| ②逮捕免脱目的 | 窃盗の着手があればよい |
| ③罪跡隠滅目的 | 窃盗の着手があればよい |
(2) 主体
窃盗犯人
*したがって,窃盗の目的を達していない者が逮捕免脱目的で暴行・脅迫を加えた場合は,窃盗の着手があるかで事後強盗になるか否かが決定される。(なお,稀なケースであるが,窃盗犯人が財物を奪って現場を離れて30分後に再び窃盗の意思で同じ家に侵入して家人に発見された場合[18])
(3) 暴行・脅迫の程度
ア 定義
強盗として評価される以上,手段としての暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要がある
イ 限定解釈の合理性?
前田説は限定解釈を否定している[19]
だが,「反抗抑圧に足りる程度の暴行」かは,強盗罪と同様に行うべきで緩和する理由はないと考える
(4) 暴行・脅迫の時期
事後強盗が成立するには,Ⅰ暴行・脅迫とⅡ窃盗行為の間に密接な関連性がある必要がある。密接な関連性があるというためには,①窃盗の現場の継続的延長とみられる場所又は②その機会の継続中である必要がある。
∵ 通常の強盗罪と同様の実質があることが要求されるからである
視点 基本的には,窃盗行為と暴行・脅迫との時間的場所的距離の大小及び窃盗犯人に対する追及が継続しているか―によって決定される[20]
*「機会の継続性」判断
| ①逃走追跡型 | ②現場舞戻型 | ③現場滞留型 | |
| ケース | 犯人が現場から継続して追跡されている場合 | 犯人が現場に舞い戻っている場合 | 犯人が現場に滞留していた場合 |
| 判例 | 最判H16・12・10
窃盗の後に発見追跡されておらず,すでに安全圏へ脱出し,窃盗の機会は断絶と評価 |
最決H14・2・14 |
4 強盗致死傷罪
(1) 主体
強盗犯人(強盗に着手していればよい)
(2) 負傷させた
ア 傷害の程度
西田172も「本条の法定刑の重さを考慮すれば,軽微な傷害は除くべきであると解されてきたが,平成16年改正により・・・問題はほぼ解消されたといえよう」とする。もっとも,前田249も,「まさに強盗手段としての暴行に評価し尽くされる軽微な傷害」は,240条の「負傷させた」にあたらないとするのであるから,少なくとも社会通念上看過し得ない,一般に医師の治療処置を受ける必要の認められる程度の傷害のみが『負傷』にあたるという解釈を維持することは不可能ではないように思われる。
イ 暴行脅迫と負傷の関連性
● 手段説(死傷の結果は,強盗の手段としての暴行から生じたものに限る)
× ① 240条の「強盗」には事後強盗も含む
② 240条は,「人を負傷させたとき」と規定されているにすぎない
③ 実質的にも成立範囲が狭すぎて不当
○ 機会説(強盗の機会になされたもので足りる)[21]
↓
もっとも,『強盗の機会』というだけでは,たとえば,強盗犯人が逃走中,以前から殺したいと思っていた者に偶然出合ったので殺害したという場合まで含まれかねない。
↓
強盗行為と密接な関連性を有する行為により生じた結果に限る(もっとも,脚注で述べているように,機会説の実質的論拠は,事後強盗的強盗の処罰にあるから,判例の『強盗の機会』の判断枠組みは,『窃盗の機会の継続中』と同様の判断枠組みをとっている。その結果として,十分な限定になっていないという側面もあると思われる)。なお,前田254もこの問題意識を示しており,「死の結果がその機会に発生しただけでは足りず,強盗犯人の行為から生じたものでなければならない」として,因果関係は必要とする見解のように思われる。
(3) 死亡させた
ア 奪取前の死亡
強盗致死は,財物奪取の前に死亡させる場合も含む
ただし,殺害行為時に強盗の故意があることが必要であるから,この点の吟味は欠かせない
イ 強盗の機会の殺害
| 強盗傷人の場合 | 強盗殺人の場合 |
| 逮捕免脱目的が多い
⇒ 強盗の機会の範囲は狭くなる |
犯跡隠蔽目的が多い
⇒ 強盗の機会の範囲は広くなる |
第4 詐欺罪
1 欺罔行為と着手時期
詐欺とは,人を欺いて財物を交付させ,その占有を取得し,ないしは財産上の利益を得る行為をいう
(1) 欺罔行為
ア 定義
欺罔行為とは,財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れる行為をいう
| 欺罔行為の態様 | 交付行為に向けられた欺罔がない |
| ① 言語による欺罔
② 挙動による欺罔 ③ 不作為による欺罔 |
錯誤に陥れるものである必要があるから,駅員の隙をついて切符なしで乗車するという場合は『欺罔行為』がないと解される |
*欺罔行為は,何らかの意味で『人を錯誤に陥れる行為』というのでは不十分であり,処分を導くものである必要がある
イ 不作為による詐欺
① 不作為による詐欺
Ex. 既往症を隠して生命保険契約を結ぶ行為
② 挙動による詐欺[22]
Ex. 代金支払いの意思のないことを隠して飲食・宿泊する行為
ウ 誤振込みについての検討
● 遺失物横領罪
∵ 釣銭詐欺で,受け取ってからしばらくして多いことに気付いてそのままネコババするケースに似ているから
× 誤振込みの状態で預金が名義人の占有下にあるとはいえないから,釣銭詐欺の「受け取っ」たことを前提とする議論とパラレルには考えられない
○ 銀行の占有する金銭を騙取するものとして1項詐欺罪が成立する
∵ 誤って振り込まれただけでは預金が成立せず,行為者に払戻し請求権がないのに,請求権があるように装って引き出す行為を挙動による欺罔と構成し,銀行の積極的な払戻し行為を処分行為と構成すべき[23]
エ 成り行き詐欺[24]
成り行き詐欺とは,当初は善良経営だが,会社の経営危機になって支払能力・意思を欠いてからの取引が詐欺と擬律されるケースをいう(欺罔行為があるかの判断が微妙)
(2) 被欺罔者が交付権限を持っていること
ア 処分者の交付権限
被欺罔者は,財物について事実上又は法律上の財産的交付行為(処分行為)をすることができる地位又は権限を有する者である必要がある
∵ 詐欺罪は,他人の瑕疵ある意思に基づいて財産を不法に取得するものである。とすれば,詐欺罪は,他人の瑕疵ある意思に基づいて財産を不法に取得するものであるから,交付権者の意思に基づいて財物を取得するという事実が必要だからである。
イ 交付権者の錯誤
処分に向けられた欺罔行為は存在したが交付権者がそれを見抜いて錯誤には陥らなかった場合は,未遂罪
Cf. 機械と錯誤[25]
2 処分行為
(1) 処分行為の定義
処分行為とは,被欺罔者が瑕疵ある意思に基づいて財物ないし財産上の利益の占有を終局的に移転させる事実行為をいう。交付行為というには,交付権者が財物の占有ないし利益の移転とその結果を認識している必要がある
∵ ① 詐欺罪は,被欺罔者の意思に基づいて財産が移転する点が本質
② 無意識的処分行為で足りるとすると,立法者が明確に不可罰としている利益窃盗を事実上広く処罰することになってしまうから,このような解釈態度は罪刑法定主義からいって問題である
(2) 処分意思の内容
そもそも,詐欺罪は『交付』が要求されている以上,財産の移転は被欺罔者の意思に基づいていなくてはならないという点については,意識的処分行為説も無意識的処分行為説も異なる点はない
⇒ 問題の本質は,被欺罔者にどの程度の意思的関与を要するかの問題[26]
| 類型 | 具体例 | 結論 |
| ① 財産移転についておよそ意識を持っていない場合 | 訪問販売人が訪問の記念のサインだと偽って契約書にサインをさせた場合 | 被欺罔者はおよそ財産移転について意思決定する意識がない |
| ② 被欺罔者に財産移転の認識はあるが所有権を移転させる認識はない場合 | XがAに対して返却する意思がないのに,「貸して」と偽ってそのままネコババした場合 | 自己の財物の占有を移転する意思があるので所有権を移転する意思はないが処分意思としては十分 |
| ③ 処分意思として個別具体的な法律効果を目指して財産的処分行為をする意識がなければならないのか | 東京・横浜間の定期券を持っているXは,新大阪から新大阪・京都間の切符を購入し,東京で定期券を示し出場した | 東京駅の駅員は,JRがXに対して京都・新横浜間の差額請求権があることを認識していないから処分意思があるのは無理 |
3 財産上の損害の要否
(1) 定義
詐欺罪の損害は,財物に対する事実上の支配状態,すなわち財物を使用,収益,処分する利益そのものの喪失をいう
∵ 詐欺罪は,個別財産を対象とするものであるから,被害の算定は,騙取の対象となった財物それ自体について行うべき
⇒ ただし,被害者の錯誤が財産と実質的に関係のないものは除かれるべき
∵ 詐欺罪を財産罪と解する以上,財産との関連性が必要で本当のことを知ったら売らなかったであろうという関係があるすべてを財産犯とするのは,財産犯としての性格を逸脱している(16歳にH本を売る場合の本屋など)。
(2) クレジットカード詐欺
| 他人名義のカードの不正使用 | カード名義人自身による不正使用 |
| 当然詐欺 | 解釈論上,特に問題とされる |
ア 問題の所在[27]
① 加盟店は,信販会社からの支払いを受けられるので財産上の損害がない
② 欺罔者の加盟店に対する欺罔行為は存在せず,錯誤に基づく処分行為もないのではないか
イ 思考の手順[28]
○ XがA店に対して所定の支払方法により代金を支払う意思がないのに,あるように装ってカードを提示して物品の購入申込みをすることが欺罔行為にあたる。また,A店の商品の交付が処分行為にあたると解される
∵ A店としては,その情を知っているならば,物品交付をしなかったはずである。しかるに,Aはその情を知らなかったためにXについて代金支払い意思のある正常な申込みと誤信し,その誤信に基づいて商品を交付しているからである
4 着手時期・既遂時期
(1) 着手時期
着手時期とは,欺罔行為を開始した時点をいう
(2) 既遂時期
| 1項詐欺 | 2項詐欺 |
| 物品や現金などの占有が現実に移転する必要がある | 財産上の利益を犯人が取得したときに既遂に達する |
(3) 既遂か否か
事例 Xは,Yに対して『振り込め詐欺』をして,Yは騙されXの口座に500万円入金したものの,銀行がXの口座を凍結したためにXは現金の引き出しができなかった
● 1項詐欺未遂説
∵ 入手された金員はXが自由に入手できる状況にはなく,入金相当額の現金について支配を取得したとはいえない
× 出金禁止措置は銀行による事実上の措置にすぎず,あくまでも預金口座に対して入金がなされた後の事後的な事情にすぎない。そうすると,いったん入金がなされた後で出金禁止措置があるか否かで未遂か既遂が区別されるのは不合理というべき
○ 1項詐欺既遂説[29]
∵① 出金禁止措置があっても措置前に入金自体はなされている
② 窓口担当者の見落としにより払い戻される可能性もある
③ Xは口座に対して事実上の支配を及ぼしている
5 財物・財産上の利益の移転
(1) 1項詐欺と2項詐欺との区別
設例 振り込め詐欺は1項詐欺か2項詐欺か
● 2項詐欺説
∵ 被害者が振り込んだ金銭は銀行所有の不特定の金銭の中に埋没し,結局犯人が得るのは銀行に対する一定額の預金債権にとどまる点では理論的に明快
× 犯人の口座への入金は,犯人の手持ち現金の増加にすぎず,銀行の資産の増加と考えるのは社会通念に反する
○ 1項詐欺説
∴ 犯人の口座への入金は,犯人の手持ち資金の増加という理解を前提に,犯人の口座に入金記帳があった時点で金銭の現実の移転があったと評価すべき
∵ ① 第三者に対し金銭を交付させた場合でも詐欺罪は成立する[30]
② 銀行という第三者を介して被害者から金銭を受領したという構成可
(2) 不法原因給付と詐欺罪
● 詐欺罪否定説
∵ 財産上の損害は法の保護を受けない
○ 詐欺罪肯定説
∴ 欺罔がなければ財物を交付せず,保護されるべき財産状態が侵害されなかったであろう関係があれば足りる(これは所持説を全面に出している)
⇒ 相手方である交付権者がいかなる動機に基づいて財物を交付したかを問わない
∵ 詐欺罪は欺罔手段によって財物を騙取することが本質
*類型的な検討[31]
| ① 麻薬を買ってやると代金を騙取 | ② 援助交際でヤリ逃げした場合 |
| 2項詐欺罪は肯定 | 2項詐欺罪は否定 |
| 代金の交付という1項詐欺 | 売淫料の支払猶予という2項詐欺 |
| 本権説から問題を抱える | 所持説から問題を抱える |
まず,XY間の契約が公序良俗に反し不法原因給付にあたることを認定
①について
● 本権説を徹底すると否定
∵ 民法上返還請求権が認められないならば,民法上保護されるべき財産上の損害は発生していない(翻って,損害の発生を目的とした欺罔行為そのものも否定される可能性
○ 所持説によると肯定
∵ 欺罔行為に基づく占有侵害があれば,Yに代金の返還請求があると否とにかかわらず詐欺罪が成立する
○ 判例・通説によると構成
∵ ① Xの欺罔行為によりYの不法原因給付がなされていることが重要[32]
② 返還請求権が否定されるにしても,それは民事上保護される適法な利益が侵害された後に事後的に生じる事情にすぎず,占有移転後の財物の返還を問題とする民法708条とは矛盾しない
②について
● 詐欺罪成立
∵ 詐欺罪の保護法益である財産は,必ずしも民法で保護される必要はない(詐欺罪肯定説は,刑法の独自性の視点から売淫料の民事上の効果をスルーする)
○ 詐欺罪否定
∵ ① 売淫債権は公序良俗に違反し民法上対価請求権がない
② 明らかに公序良俗に反する以上,刑法独自の視点からも保護できない
第5 恐喝罪
1 恐喝罪の構造
①犯人が恐喝行為をして ⇒ ②その恐喝行為の結果,被害者が畏怖・困惑し ⇒ ③その畏怖・困惑の結果,被害者が交付行為をする ⇒ ④交付行為の結果,犯人が財物を取得し又は利益を得たという因果的連鎖が必要
2 恐喝行為と処分
(1) 恐喝行為
ア 定義
恐喝行為とは,財物・利益を交付移転させることを目的として行われる暴行・脅迫であり,相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものをいう
*反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫に達したときは,交付行為の介入する余地がなくなるから,『強盗罪』となる
*恐喝と強盗の区別
| 積極事情 | 消極事情 |
| ①拳銃や刃物など殺傷能力の高い凶器
②被害者の頸部,胸部など身体枢要部 ③夜間であるか,犯行における人数 ④犯人が男性・青年・体格頑丈・屈強 ⑤被害者が女性,カップル(男性も,女性に配慮し攻撃に出ない) ⑥屋内であるか |
①凶器を用いなかった場合
②刃物を積極的に使用しない場合 ③刃物が体にはあたってない場合 ④犯人が女性・老人・体格が貧弱 ⑤被害者と犯人との間に面識がある ⑥被害者が逃げ出し助けを求めることができる場合(精神的余裕あり) |
*基本は,暴行・脅迫の態様であり,それが強度であればもはや細かい事実認定は不要
*脅迫とは,畏怖させるに足りる程度であることが必要であり,困惑や不安といった程度で足りる
イ 虚偽の事実を告知して脅迫した場合
① 相手方が財物を交付するに至った原因を重視し,錯誤と畏怖とが同程度に働いて財物が交付するにいたったときは,観念的競合となる
② 錯誤はあるが交付するに至った相手方の決意が畏怖に基づいているときは,恐喝罪のみが成立する
3 権利行使と恐喝
(1) 学説の整理
① 脅迫罪説
② 恐喝罪説
* 権利行使の範囲を超えればそれは権利の濫用であるから恐喝罪が成立することには争いがなく,その限りでは大きな違いがあるわけではない
(2) 考え方
ア 構成要件該当性
問題の所在 権利行使と恐喝の場合,客観的には債務の弁済をしたということになるから,債務者は債務から免れるということになるから,損害に欠けるのではないかという点が問題とされる
● 全体財産の減少はない
× 恐喝罪は個別財産に対する罪
○ 恐喝罪の構成要件は否定されない
∵ 脅されなければ渡さなかった物を交付し財産上の利益を処分している[33]
イ 違法性判断
問題の所在 債権を有している場合は,可罰性が低いはずで違法性阻却の余地
(ア) 正当化の要件
① 権利の範囲内であること(権利行使の意図があるという主観的要件と解される⇒実質的違法性判断の目的の正当性判断に置き換えられる。要するに,『防衛の意思』のようなもんですな)[34]
② 権利行使の方法が社会的に一般に受忍すべき程度を超えていること
* 目的と手段,犯人と被害者との債権・債務関係の内容・性質,従来の交渉状況を総合的に考慮する[35]
![]() Ⅰ犯人の権利が明確 言動・手段が不穏当でも正当
Ⅰ犯人の権利が明確 言動・手段が不穏当でも正当
Ⅱ被害者の非難が高い
(イ) 要件を満たさない場合の効果
恐喝罪が成立する
4 恐喝利得罪
⇒ 利益窃盗との区別に注意すること。判例は,恐喝利得の処分行為について詐欺利得罪よりも緩やかに解している。たしかに,2項恐喝の場合,被害者は現実に脅されているのであるから,利益が移転するという認識に欠けることはないから,無意識的処分行為というわけではないから,詐欺利得罪と比較すれば問題を抱えることはないということもできるのである。しかし,そうすると,利益窃盗との区別が曖昧になり罪刑法定主義からいって問題となる場面もあろう。
第6 横領罪
1 自己が占有していること
占有とは,窃盗罪の場合と異なり事実的支配のみならず法的支配も含まれる
∵ 占有の排他性に着目したものではなく,濫用のおそれのある支配力に着目
*横領罪の占有概念
問題 会社の金銭を預金という形で保管している者が振替送金(現金を引き出さないということ)する行為は横領罪か
● Xは,100万円の預金債権を有しているにすぎず,A銀行にある100万円の現金の占有はないとする見解(松宮261)
∵ 横領を認めると,『占有』概念だけでなく,『財物』の概念を拡張して『債権』を含めることになってしまい不可罰の2項横領を処罰することになる
⇒ Xが100万円を引き出したとしても,Xに『100万円という現金自体』に対する占有がない以上,振替行為は横領とはならない
× 会社から金銭の保管を委託された者がネコババすれば業務上横領となるのに,預金の管理を任された場合は背任となるのは不合理
○ 預金に基づいて100万円と言う現金に対する占有を認めるべき
⇒ 預金の引出行為+現金化しない振替の方法での処分も横領罪[36]
∵ 占有は法律的支配を含むところ,預金債権は通常の債権と比較して履行される可能性が極めて高いので預金者はいつでも払い戻すことができるから,預金に基づく現金に対する自由な処分が可能である。そこで,預金をいつでも引き出せる地位にあるXは,銀行が事実上支配する不特定物たる金銭について預金額の限度で横領罪に必要な法律的支配を有すると解すべき
*委託物横領については預金による金銭の占有(預金の占有ではない)を認めるのが妥当(西田214)
2 他人の物であること
(1) 所有権の帰属
他人の物とは,その他人に所有権がある財物のことをいう
*判断の方法
所有権の帰属は原則として民法により解決されるものであるが,刑法上の保護の必要性という観点を考慮する必要がある(処罰範囲限定の思考)
⇒ 『他人の物』といえるためには,単に私法上行為者に所有権がないと言うだけでは足りず,それを領得することが所有者に一定程度の事実的・経済的マイナスを与えるものでなければならない
(2) 不法原因給付と横領罪
問題 XがAからBに対して賄賂として渡すように頼まれて預かった金銭をXがネコババした場合
○ 民法708条の『給付』とは,受給者に終局的利益を与えるものである必要があるとするのが判例である。
↓
不法原因『給付』と不法原因『寄託』を分けるべき[37]
↓
不法原因『寄託』の場合は,反射的効果としての所有権の移転は認められず
*脚注で述べたが,本来民法学に照らすと,賄賂の資金は不法原因給付となってしまうので,「あげるつもりはないから給付が終局的でない」と嘘をつく!!
↓
『他人の物』にあたると解すべき
↓
もっとも,被害者Aは,自ら不法な行為を他人に唆しておきながら,その委託関係が法的に保護されるというのはクリーン・ハンズの原則に反する
↓
よって,委託信任関係は保護の余地はないので,所有権侵害のみをとらえて遺失物横領罪が成立する[38]
3 委託信任関係[39]
横領罪の占有は,物の所有者と行為者との委託関係に基づくことを要する
∵ 横領罪がその行為が財物の委託に基づく委託者・受託者間の信頼関係を破って行われることを本質とする
4 横領行為
(1) 定義
横領とは,不法領得の意思を実現する一切の行為をいう[40]
⇒ 不法領得の意思が必要。なお,領得行為説からは,毀棄・隠匿は,横領罪は成立しないとする結論となりやすいが,判例は,不法領得の意思を「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物について権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思」と定義する。そのため,判例は,領得行為説に立ちつつも,毀棄・隠匿行為についても横領罪の成立を認めている。その結果,越権行為説との違いがなくなり相対化されていると評価することができる。
*領得の判別は,「所有権者でなければできない処分」という概念といえる
| 越権行為説(20世紀的な思考) | 領得行為説(19世紀的な思考) | 権利者を排除する意思を必要とする | |
| ①委託物を一時的に無断使用するケース | 成立 | 不法領得の意思なし | 不法領得の意思なし |
| ②委託物を毀棄・隠匿するケース | 成立 | 不法領得の意思なし | 成立 |
| ③委託者本人のために権限を越えて処分する場合 | 成立 | 不法領得の意思なし | 不法領得の意思なし |
(2) 所有者でなければできない処分
① 本人の利益を図る目的がある場合
⇒ 不可罰
② 自己の利益を図ることが明らかである場合
⇒ 横領罪
③ 本人の名義・計算か,自己の名義・計算か
第7 背任罪
1 背任罪の本質
● 代理権を有する者が本人から与えられた権限を濫用して本人に財産上の損害を加えるところに背任罪の本質がある(権限濫用説)[41]
∵ 背任と横領の区別を明確にし,かつ,不明確になりやすい背任の処罰範囲を明確にすることができる
× 可罰性の高い事実行為による財産侵害を不可罰とする点に問題があり法益保護の要請に十分応えられていない
○ 財産の処理を委託された者が,その任務に違背して本人に財産上の損害を加える点に本質がある(背信説)
⇒ 背信説に立つと,「罪刑法定主義からいって問題である」という批判を受けるので,背信説に立った上で処罰範囲の限定の要請があることを押さえる
2 背信罪と横領罪の区別
(1) 判例の区別の基準
判例は,処分行為が犯人の名義・計算によって行われたときは横領罪,本人の名義・計算によって行われるときは背任罪とする
(2) 名義による区別(形式的基準・客観的な基準)
名義とは,処分行為の外観のことをいう。つまり,処分行為を客観的に考察してみると,誰のためになされているかという観点と解される。具体的には,①貸付が帳簿に記載されているか,②天引きした利息は本人に入金されているか―などが考慮される。
(3) 計算による区別(実質的基準・主観的な基準)
計算とは,処分行為の法律効果や経済的効果(利益とか損失)が誰に帰属するかという観点である。具体的には,自分の利益を図るような行為がみられるかという観点が考慮される。
(4) 実践的な区別
① 『財産上の利益』が客体の場合
⇒ 2項横領は不可罰であるので,背任のみを検討する
② 『占有』がない場合
⇒ 横領罪が成立しないので,背任のみを検討する
③ 処分権限があるかを確認する
⇒ 処分権限がないと背任罪にいう任務が存在しないから,いかなる名義で処分行為をしたとしても犯人の計算ということになるから横領罪成立
④ 犯人の計算の場合は横領罪,本人の名義・計算の場合は背任罪となる[42]
3 他人の事務処理者
(1) 定義
『他人の』事務処理者というには,他人の事務を信任関係に基づいて誠実に処理すべき義務がある者をいい,自己の事務を他人のために処理する場合は含まれない。ここにいう事務は財産上の事務に限られる。
| 背任罪の成立範囲が本人との関係が対内的である場合に限定される理由 | 対向的関係を処罰範囲から除外する理由 |
| 資本主義市場経済が発達すると会社組織や代理機関を利用して他人を自己の手段として取引機会の増大を図る。他方,代理機関などが信頼に反して不正行為を行い,かえって財産的損害を被るおそれもある。そこで,このような行為を刑法で処罰し,財産の保護を図るために規定されたのが背任罪である | 取引社会において対等の当事者間には,自由競争の原理及び自己責任の原理が妥当するので詐欺などの不正の手段が使われない限り刑罰権を行使すべきでない。売主の目的物引渡債務は,自己の事務といえるので,かかる義務違反は単なる債務不履行にすぎず,「他人の事務」にあたらないと解すべき |
(2) 二重抵当[43]
問題 Xは,Yから800万円を借りて一番抵当を設定する約束をしたがYがすぐに登記をしなかったので,その後,Aからも500万円借りて,Aに対して1番抵当を設定した。
● 登記協力義務は,Yの自己の事務としての側面があるから,これを怠っても単なる債務不履行であり,背任罪は成立しない
○ 判例は,主としてXのための事務として背任罪を肯定[44]
⇒ 判例の事案では,XがYに対して抵当権の設定に必要な書類を交付しているという事情があった。そうすると,Yとしては,Xが独断で1番抵当権を設定することはできないと信頼していたといえる。これは,一段と高度の特別の信任関係を有しているといえる
*国井230は,判例は,抵当権を設定するというだけで直ちに背任罪と解すべきではなく,抵当権設定に必要な書類を渡すなどの高度の信任関係の生じたとみられる特段の事情が必要とする[45]
4 図利・加害目的
図利・加害目的の機能は,財産上の損害を加えることを認識している(したがって,背任罪の故意がある)場合にあえて任務違背行為に及ぶ場合に,本人の利益を意図した場合は処罰の対象とはしないとする点にあると解される。
*背任罪の故意は,Ⅰ任務違背の認識・認容とⅡ財産上の損害の発生の認識・認容が必要
① 図利目的
② 加害目的
視点 図利・加害目的の機能に照らすと,その真意は図利・加害目的の裏側,すなわち,主として本人の利益のための目的かという観点から判断される[46]
⇒ 図利・加害目的の本質は裏側にあるので,問題は,『本人のためか否か』の事実認定をどのように行うべきかという問題にシフトする[47]
考慮要素 間接事実からの推認型の場合,一番認定に苦しむのが本人図利と自己図利目的が併存している場合である。この点,①損害の発生の確率,②得られる利益の大きさ,③冒険取引の必要性―の3点を踏まえたうえで,『本人のためか否か』を間接事実から推認することになる
5 任務違背行為[48]
任務違背行為とは,委託の趣旨に反する行為のことをいい,より具体的には,本人の財産に損害を与える可能性が高く,許されない程度に危険な行為をすることをいう
視点 会社の代表者が主体となることが多く,しかも裁量権が認められることが多いので,背任罪の成否は裁量権の範囲内か否かにより判断される
考慮要素 与えられている権限を基礎に,会社の内規や取引のマニュアル,その業界の慣行などを考慮し,本人の財産に損害を与える可能性が高く,許されない程度に危険な行為をするか―を具体的に判定する
6 財産上の損害
(1) 定義
背任罪の財産は全体財産のことを意味し,全体財産の減少が要件となる
(2) 背任罪の既遂時期
問題 Xは,A銀行の貸付課長をしていたが任務に違背して無担保で業績が悪化しているY社に1000万円を貸し付けた。返済期日は,10年後であり,Y社は3年後に倒産した。貸付から1年経過時点で事態が発覚したとすれば,Xは背任の既遂か未遂か
● 法的財産概念を全体財産として把握する見解
⇒ 債権を得ているので損害はないということになり,Xは背任未遂となる
× 実現可能性のない債権は無価値
○ 経済的概念から損害を把握すべき
∵ 刑法によって保護されるべき財産状態は,法律上の財産権には限られない。したがって,法的財産概念は全体財産罪である背任罪の性格に合致しない
⇒ したがって,設問との関係では,Xが貸付を行った時点で直ちに既遂となる。貸付の時点において回収見込みのない債権になったのであるから,その時点で経済的価値を減少させて損害を与えたといえるからである。
[1] 『支配意思』の存在は,あくまでも,『占有者の支配力が及んでいるか』という観点の間接事実的な用いられ方をするだけであるという点には注意が必要といえる。『支配意思』は,占有者が支配しようという意思を現実に持っていたかという観点が重要ではなく,むしろ,行為者の見地から,一般人の立場なら占有者の支配の意思を認識することができる場合には,『占有者の支配力が及んでいる』と判断されるのにすぎない。つまり,占有者が内心で占有の意思を持っていたとしても,そのことが『占有者の支配力が及んでいるか』という点を補強するのではない。例えば,注釈2で述べるように,『事実上の支配』の難易度は,物の形状に左右されるところ,財布であれば比較的容易に支配力が失われやすいということはできる。しかしながら,例えば,極端な例を出せば,置手紙のうえに,財布が置いてあり,置手紙に「ちょっとトイレに行っています。」と書かれていたとすれば,物の性状に照らすと,もはや支配力は失われたと評価できるものの,一般人の見地からすれば,この財布は,占有者が意識的に置いたものであり,すぐ後で取りにくることが当然に予定されているというが分かる場合は,占有者の支配意思を読み取ることができる。この結果,その財布には未だ占有者の支配力が及んでいるといえると考えられる。
[2] 『事実上の支配』の難易度は,財物の形状に大きく左右されるという点に注意しなければならない。すなわち,小物や貴重品は身に付けて所持するのが通常と解されるから,通常人の立場からすれば,意識的な一時離席であるとは評価しにくいものと考えられる。したがって,カメラや財布は,比較的『事実上の支配』が及ぼしにくい結果占有が失われていると評価されることが多くなるものと解される。これに対して,空港でスーツケースが席に置かれているというような場合,通常人であれば,「重いから一時的に置いてある」と考えるから,意識的な一時離席と評価されやすいということができる。そうすると,社会通念上占有者の支配力が及んでいると解することもできやすい。
[3] この点についての判例を精査してみるのに疑問を持たれる判例が少なくない。例えば,本文で述べた旅館のトイレで遺失した財布に旅館の管理者に占有が認められるという点にももとより疑問がある。すなわち,旅館は,一般的に規模にもよるが,ロビーに関しては,不特定の者の自由に出入りを認めているように思われるから,占有が否定される典型例である列車の網棚の荷物について鉄道会社の支配力が及んでいないと解するのであれば旅館のトイレも同様に解すべきと思われる。もし,この点の判例が整合しているのであれば,『包括的支配が完全か』というメルクマールは,極めて多くの人が出入りしており,その場所の管理体制も現実には放任に近いような場合をいうものと解することになると思われる。そうだとすれば,少なくとも旅館の場合は,常時クラークの目が行き届いているし,トイレの清掃も頻繁に行われると解されるから,包括的支配が完全であったといえないこともないように思われる。しかしながら,もしそうすると,デパートに財布を置き忘れた場合にも,デパート店員の目が行き届いていると解する余地もあるわけであるが,通常,デパートの占有を認めるという議論をしないことからみて,デパートと旅館の違いも考える必要が出てこよう。そうすると,やはり旅館は,デパートと比較して閉鎖性が高い,したがって,管理体制も強いので物に対する支配意思を読み取れることが多いということなのかと思われる。比喩的にいえば,デパートは通勤電車に近く,旅館のロビーは,旅館の客室のように閉鎖的な空間に近いということなのであろうか。なお,電話ボックスの中に置き忘れられた硬貨について電話局長の占有を認めた判例があるが,いかにも非常識というべきである。
[4] したがって,郵便局員が現金書留の郵便物の現金を奪う目的でネコババしたというのであれば,郵便局で書留郵便物を抜き取った時点で窃盗罪の実行の着手が認められると考えられる。すなわち,郵便局員が家に書留を持ってかえって封を開けようとする時点で窃盗の実行の着手があるわけではない点には注意が必要である。なお,前田説は判例理論を是認するものであるが,「預かった鞄をこじ開ける行為」が窃盗になると理解しているが,仮にそのように解するのであっても,実行の着手時期は,書留郵便を抜き取った時点において認めることも不可能ではなく,結論において違いはないということができよう。
[5] 国田157は,『一連の行為』かどうかを基準としている。分かりにくいが,殺害行為と財物奪取行為が社会通念上一連の行為とみられるかを検討している。これは,前田213に言わせれば,『殺害と同時か』という問題である。『殺害と同時か』は,占有の場合,人の支配が及んでいるかがメルクマールになるのであるから,広がりを持っている概念といえる。少し敷衍して考えてみたい。そもそも,ここでの問題は,被害者に占有があるのかという問題ということを忘れてはならない。そして,占有が認められるかは事実上の支配があるかによって決定される。
『死者の占有』の論点を分かりづらくさせているのは,①死亡しているから支配の主体になれないという問題と②支配の主体になれるとしてその支配力が及んでいるか―という問題が厳格に区別されず,『死者の占有』というブラック・ボックスに入れられているからと思われる。ところが,実際はこの①②は,厳密には区別しにくい側面がある。つまり,私たちは,『死者の占有』の論点を除いては自覚的に①の論点を論じることがないので,占有とは,その際,物の性状や支配意思の強弱,客観的・物理的な支配関係の強弱を総合判断して,社会通念上,占有者の支配力が及んでいるかという観点から判断する。この際,最も重視されるのは,一般人の立場から支配が及んでいると認識できるような状況にあるかという点であると思われる。そうすると,客観的には支配が及んでいなくても支配意思が明確に読み取れるのであれば,物に対する支配が認められることになる。そうしてみると,『死者の占有』の論点でも実際上重要なのは一般人が支配意思を読み取れるかという点にあると考えることができると思われる。すなわち,客観的には,殺されたばかりの生々しい死体であったとしても,一般人の認識からすれば,未だ被害者が死亡しているか確定的ではなく,蘇生可能性もまだあると認識すると思われる。このような観点からすれば,一般人の視点からすれば未だ死亡したか分からないが『ぐったりしている人』の事実的支配が及んでいると評価されることになる。つまり,『死者の占有』の論点は,本来①の論点として位置付けられているが,その解決を考えると,②の論点が跳ね返って,①の論点の帰結に影響を与えているものと解される。たしかに,死亡しているとは行為時点は言い難いのに,客観的事後的な判断で死亡していることが分かったといって遡及的に窃盗罪を遺失物横領にするというのは明らかにおかしい。そうしてみると,国田157が一連の行為かを検討するその理由はよく分からないというべきであろう。おそらく,その心は,一連一体のものとみられれば,一般人の視点からみてもその占有については支配力が及んでいると評価するということになると思われる。また,前田213の『殺害と同時』といえるかも,殺害と同時であれば一般人が,支配力があると考えるからと思われる。結局,いずれも本質論をさておいて,分かったような,分からないような基準を立てていることが問題と思われる。さらに,一連一体とみて一つの行為となることになると,規範的には,『殺して奪った』という強盗殺人の典型場面といったい何が違うのかという問題も出てくる。この点,あまりに密接であれば強盗罪と擬律する場面も出てくると思うが,①殺害行為と財物奪取が非常に密接であれば強盗罪,②同様にまあまあ密接であれば窃盗罪,③密接とは言い難いのであれば遺失物横領ということになると思われる。そうすると,一連一体という基準を全面に押し出して「窃盗」と書くと何だか不思議な感じがしてしまう。以上の議論をみると,殺害行為と財物奪取の結びつきの程度はあまりそれ自体が本質的なのではないように思われる。
[6] 注釈で述べているように,この問題を考えるにあたって本質的なのは,一般人の立場からみて,支配意思があると認識することができるのかという点にあると思われる。つまり,客観的な死亡の時点からみて何時間経過しているかは本質的なものとはいえないと考える。そのような観点から住居での殺害事例を考えると,まず,住居であるから同居者の有無も考えてみる必要があると思う。同居者がいれば,少なくとも一人の住人が死亡したから直ちに占有離脱物になるというのは非常識であろう。また,一人暮らしとしても住居の場合,従前の旅館の客室の議論と同様に閉鎖性が高いから,一般人であればなんびとかの占有意思を読み取るのが通常と思われる。まず,死亡との時間的近接性が高ければ,従前Aさんが居住していたのであるから,Aさんの支配が及んでいると一般人であれば考えるであろう。また,状況の変化がないという事情もAさんの占有を認めるのにプラスとなると考える。だが,結局は,一般人が支配を及ぼしていると考えないといけないから,Aさんの死亡からかなりの時間が経過してAさん以外の者の占有があるとみられる事情がない限り,占有を認めることはできないと思われる。
[7] 団藤説は,排除意思のみが必要と解している。これは,毀棄・隠匿が目的であっても不法領得の意思を認めるものであるが,判例は,現実には排除意思に重点を置いており,利用意思はかなり緩やかに認めているので,実態は団藤説に近いという評価もできるであろう。
[8] 判例では,車両内の金員を窃取する目的で世情された乗用車のドアガラスの開披を開始した時点で実行の着手を認めるべきとする。本文の分類でいけば,自動車は倉庫ケースにあたるという理解になると思われる。国田166は,「車の中には通常財物が置いてあるから」とするが,自動車の中に財物を置くことが通常であるとは今日では思われない。そうすると,侵入窃盗のケースにように物色行為を開始した時点で実行の着手を認めるべきとも思える。しかしながら,侵入窃盗のケースと倉庫ケースの違いをみてみると,おそらくは,侵入行為が窃取に密着している行為と評価することができるかが本質的と思われる。すなわち,倉庫の場合,侵入することに成功すれば後は窃取するのは簡単であり,そういう意味では侵入行為と窃取の間が密着であると評価できるように思われる。これに対して,侵入窃盗の場合,家の中に入ったからといって泥棒が満足するような物品が置いてあるとは限らないと思われる。そうすると,侵入してからさらに物色しないといけないと解される。敷衍すると,窃取行為の一つ手前は,倉庫ケースでは,侵入行為であるのに対して,侵入窃盗のケースでは,物色行為が一つ手前であり,侵入行為は二つ手前ということになると思われる。したがって,窃取行為との因果的な結びつきの強さをみてみると,自動車の場合,室内は狭いから物色に要する時間も金銭が置いてありそうな場所という限定でみれば,目で見える範囲に限られるであろうから10秒もかかるかということであろう。つまり,自動車への侵入窃盗は,窃取の一歩手前は,侵入行為と解するべきなのである。このような観点からすれば,国井166の叙述は措辞適切を欠くものと思われるが結論において相当である。このような観点からすれば,鍵をかけ忘れた自動車を探すために手当たり次第に自動車のドアの施錠の有無を確認する行為は窃盗の実行の着手があると思われる。
[9] 判例は,客観説を採用するので具体的事案の被害者の主観は基準にならないとはいえる。しかし,前田230は,被害者の性格も考慮の対象になるというのであり,ここまで被害者側の事情を考慮すると主観説と異ならない程度に至っているといえる。
[10] 国井174の設例1を考えてみると,甲は,乙女のバッグをひったくろうとしているが,この時点で乙女が手を離してしまえばおそらく窃盗罪にとどまると思われる。たしかに,自動車を占有の移転の手段として利用する場合は,被害者の生命・身体に一定以上の危険を及ぼすおそれがある。しかし,乙女が手を離してしまえば,単に,『財物奪取の際』の暴行・脅迫となるであろう。これに対して,設例のように,乙女が手を離さないために,「自動車を加速させながらバッグのひもを引っ張り続ける」ということになると,乙女は先行するひったくり行為ではバッグを手離さず,したがって,その後の加速行為は,まさに,『財物奪取の手段』とされていると評価することができる。ところで,ひったくりと強盗罪の論点を検討するにあたっては,「被害者に生じた危険性」のみに目を奪われている者がいる。たしかに,危険性が大きければ反抗抑圧に足りる暴行・脅迫があったとはいえる。しかし,強盗罪の定型性から暴行・脅迫は財物奪取に向けられたものでなければならず,その手段性の有無を慎重に吟味すべきであろう。
[11] 判例の枠組みは,反抗抑圧に足りる程度の暴行・脅迫があれば,反抗抑圧の結果は生じていなくとも良いというわけである。その意味では,ここにいう暴行・脅迫とは,危険犯的にとらえられていると考える。前田説の論旨を考えると,前田説は,強盗罪の結果はそもそも財物奪取のはずで反抗抑圧という『結果』を要求するのはおかしいという理解がある。ただし,判例・前田説の立場を前提にしても,類型的な因果性は必要とされる。すなわち,通常,反抗抑圧に足りる暴行がなされれば,その占有移転は反抗抑圧という結果が原因となっているはずである。そして,その中間項が反抗抑圧という結果でなくても畏怖という念から占有を移転したという場合であっても,その畏怖は暴行・脅迫が原因となっているから緩やかな因果性は認められるという意味と解される。もっとも,被害者が哀れみの感情から財物の占有を移転した場合については,このような事情が介在するのは通常異常であり,通常の因果性の枠内にあるとは解されないと思われる。つまり,通説は判例のケースの不当性を批判するために哀れみの事案を持ち出したわけであるが,判例のケースは畏怖したというものであり,哀れんで交付したのとは異なる。哀れんで交付したのであれば被害者の意思による行為が介在しているともいえるわけであり,その因果性は乏しくなるものと評価することができるであろう。
[12] 備忘のために敷衍しておくと,通説の強盗罪の要件事実は,強取とするには,反抗抑圧という結果を経由した因果経過が必要と解されている。したがって,要件事実は,①暴行・脅迫,②反抗抑圧結果,③財物の移転―となる。すなわち,哀れみのケースを想定すると,哀れみのケースでは,反抗抑圧に足りる暴行・脅迫はあったが,現実には反抗は抑圧されておらず,財物の移転の原因となっているのは,被害者の哀れみという感情なのであるから,②の要件を満たさないということになる。したがって,通説を前提とすると強盗未遂罪が成立する。これに対して,判例についてみると,判例の要件事実は,①暴行・脅迫,②財物の移転,③①と②の間に類型的な因果性があること―となる。すなわち,ここでは反抗抑圧結果が要件とはされていないのであり,その代わりに類型的な因果性があればよいとする。したがって,暴行・脅迫により畏怖したにとどまる場合も強盗既遂罪と認めてよいということになると思われる。もっとも,哀れみのケースは介在事情が異常であるから,類型的な因果性の要件を満たさないと思われる。したがって,判例を前提としても通説と同様の結論を導くことになる。この点,通説は判例を判例の要件事実の①②のみで成立を認めていると誤解している。だからこそ,哀れみのケースを問題にしているのであるが,実は判例は類型的な因果性は要求しているのであって,①②のみで成立を認めているわけではないということになる。いずれにせよ,反抗抑圧に足りる暴行・脅迫があることと,反抗抑圧されたという結果発生の問題は,異なる次元の問題であるから分けて理解するのが妥当と思われる。
[13] すなわち,強盗罪の実行の着手は,暴行を始めた時点であるが,故意とは実行の着手時点において判断される以上,暴行を始めた時点では,財物奪取の目的がないのであれば故意がないということになる。したがって,このように考えれば,設問の事案は強制わいせつ未遂(既遂かも)と窃盗罪の併合罪とすれば十分であろう。
[14] 設例のケースで『新たな暴行』がない以上は窃盗罪とするのが正しい。この点,判例では,強盗罪の成立を一般論で認めている。たしかに,236条の合理的解釈と考えれば,刑法は事後強盗(238条)の規定を置いているところ,事後強盗の暴行は財物奪取後の暴行であるから,財物奪取との関連性が比較的弱いのにもかかわらず,強盗として論じられることになっている。そうすると,強姦目的の暴行・脅迫が先行して犯意のみに変更が生じたというのであれば,事後強盗罪のそれと比較すれば,財物奪取との因果性がより密接であるということが分かると思われる。新たな暴行・脅迫がなくても強盗罪とする見解の背景にはこのような実質的考慮がある。
しかしながら,抽象的な一般論でそういうことができるとしても,問題が多い。すなわち,設例のケースでは,強姦目的の暴行・脅迫の着手があった時点では,財物奪取の故意はないのであるから,強盗罪は成立する余地はない。この点に関して,東京高判昭和57年8月6日は,錯誤論を展開して強盗を認めてしまっているが,そもそもこの時点では客観面では,強姦の着手しかないのであるから,主観面の理論でこの客観面の欠缺を埋めることはできないといわなくてはならない。他方,抗拒不能状態となった後で財物奪取の意図を生じさせたとしても,暴行・脅迫がなければ所詮窃盗罪の構成要件該当性しか認められないというべきであろう。藤木説は,「余勢をかって財物を奪った」から,この点をとらえて強盗罪の客観的構成要件該当性を認めている。昭和57年の判例よりはマシな思考とはいえるが,『余勢をかった』の中身を具体的に明らかにしなければ,何でもかんでも強盗罪にされてしまう。その結果として,新たな暴行が求められることで落ち着いている(実務も)。上記の実質論のみで強盗にするのは,さすがに罪刑法定主義(類推解釈の禁止)に反するというべきであろう。なお,強姦の際に財物を奪う行為は,特に女性に強い恐怖心を生じさせているというべきであるから,強姦犯がとどまっていること自体が強盗の積極的脅迫行為と評価することができるから,強盗の着手を認めることができる。これらの議論に照らすと,藤木説には本質的には正しいものがあるといえよう。
[15] 東京高判平成20年3月19日判タ1274号342頁は,「強制わいせつの目的による暴行・脅迫が終了した後に,新たに財物取得の意思を生じ,前記暴行・脅迫により反抗が抑圧されている状態に乗じて財物を取得した場合において,強盗罪が成立するには,新たな暴行・脅迫と評価できる行為が必要であると解される。
しかしながら,本件のように被害者が緊縛された状態にあり,実質的には暴行・脅迫が継続していると認められる場合には,新たな暴行・脅迫がなくとも,これに乗じて財物を取得すれば,強盗罪が成立すると解すべきである。すなわち,緊縛状態の継続は,それ自体は,厳密には暴行・脅迫には当たらないとしても,逮捕監禁行為には当たりうるものであって,被告人において,この緊縛状態を解消しない限り,違法な自由侵害状態に乗じた財物の取得は,強盗罪に当たるというべきなのである。緊縛された状態にある被害者は,一切の抵抗ができず,被告人のなすがままにまかせるほかないのであって,被告人の目的が最初は強制わいせつであったが,その後財物取得の意思も生じて財物を取得しても,なすすべが全くない状態に変わりはないのに,その行為が窃盗にすぎないというのは,不当な結論であるといわなければならない。例えば,緊縛状態がなく,強制わいせつの目的による当初の暴行・脅迫により反抗を抑圧された被害害に被告人が「これを寄越せ」とか「貰っておく」と言って財物を取った場合に,その言動が新たな脅迫に当たるとして強盗罪が成立するのであれば,緊縛され問答無用の状態にある被害者から財物を取った場合が強盗罪でないというのは,到底納得できるところではない」と指摘している。
[16] 必要説は,外部に利益が移転するメルクマールとしての「処分」を要求するのにすぎなかった。そうすると,必要説が求める「処分」の具体的に中身もさほど厳格なものではなかったわけである。不要説も必要説の問題意識は受け容れており,ただ,形式的に「処分」があるかではなく,個別具体的な事情を精査して「利益」の移転時期を慎重に確定するべきという個別化アプローチを採っているといえる。
[17] 判例と学説の対立がみられるところであるので,少し補足しておく。両親の殺害と相続利益の取得については,そもそも,①相続利益が,『財産上の利益』にあたるか,②当たるとして,『取得した』,すなわち,利益取得が現実的といえるか―という2点の問題意識がある。この点,前田説は,財産上の利益は不法に取得するものであれば特に限定を付さない趣旨のように思われる。しかしながら,実務では以下のように解されている。すなわち,『財産上の利益』とは,反抗を抑圧されない状態において,当該利益を被害者が任意に処分しうるものである必要がある。なぜなら,強盗罪の保護の対象は,強取がなければ被害者が任意に処分することが可能な財産と解されるから,法定相続による財産の取得は被相続人の死亡という事実に方が付与した効果(事件)にすぎず,当事者が任意に処分しうるものとはいえないからである。したがって,相続による財産は,『財産上の利益』の保護の対象とはならないと解すべきである。
[18] このケースでは,2つの観点から考察する必要があるように思われる。まず,当初の窃盗における『窃盗の機会』が終了しているかということである。当初の窃盗行為が完全に終了していれば,Xは「窃盗」という身分を持っていないことになる。そうすると,今度は,次の行為について窃盗の着手が認められるかが問題となる。この点,侵入窃盗ケースと倉庫ケースがあるのは先述のとおりであるが,本件では,侵入窃盗ケースであるから,未だ窃盗の着手がない。こうしてみると,Xには,あらゆる観点からみて,「窃盗」という身分がないということになる。
[19] この点,前田説は妥当でないと考える。そもそも,事後強盗であっても反抗抑圧に足りる程度の暴行でなければならないところ,財物奪取の場合と比較して事後強盗の暴行は,軽度の暴行で目的を達成するケースが多い。したがって,国井184の分析によると,判例は,「ある程度軽くても本罪の成立を認めている」という正反対の評価を加えている。この論旨を敷衍すれば,財物を奪い取る原因力を内包していなければならない程度の強度の暴行は事後強盗の場合,なされることが少ないのであるから,必然的に事後強盗においては,「暴行・脅迫」が否定されることが多いということであると解される。そして,法定刑において執行猶予が付されるようになったからといって,強盗の暴行との質的な差異は解消されないのであるから,改正後も「反抗抑圧に足りるか」の認定は慎重にされるべきことは変わらないと解される。例えば,逮捕免脱目的の場合は『逮捕の意思』を制圧する程度のものであるかを具体的に検討する必要がある。これは,財産奪取のための暴行とは質的に異なることからくる制約であり,そもそも,前田説は判例が「反抗抑圧に足りるか」を過度に厳密にしているという評価自体が正しくないうえに,それらの判例の意図が強盗傷人になるのを避けるためという配慮があるというが,一面そのような面があるにしてもそれのみに尽きるわけではなく,したがって,そのような実質論のみが厳格解釈の背景にあると考えるのは誤っていると解される。さらにこのように解するのであれば,『限定解釈』という言葉自体もあまり適切ではない。前田説は,強盗致傷の傷害結果を厳密に解するべきであるという議論と反抗抑圧に足りる暴行かという議論を混同しているような気もする。
[20] 特に,判例(東京高判平成17年8月16日)が,窃盗行為と殺害行為との間に時間的・場所的近接性は認められるのに,窃盗の機会の継続中であることを否定していることに照らすと,判例は,「財物を取り返され,あるいは逮捕されうる状況」の有無に光をあてて,窃取行為と暴行行為との関連性をみているように思われる。ただし,このケースでは,『誰からも追跡されずに自宅に戻った』時点でXは窃盗を完全に終了し窃盗犯人としての身分を失っているという評価もすることができると思われる。このように考えると,たとえ全体的にみると時間的場所的近接性があるとしても,事後強盗殺人の成立を否定する判断も説明することができよう。以上のように考えると,以下のように定式化できるのではないか。まず,①追及から完全に脱したという事情がある場合は,窃盗が終了しているから窃盗犯人の身分がない(この言い方が不都合であれば『窃盗の機会は終了した』といってもいいであろう),②追及は完全に脱したとはいえない場合は,窃盗行為と暴行行為の因果性の程度を見極める必要があり,この場合は時間的・場所的近接性がメルクマールになる。以上のように思われる。『窃盗の機会の継続中』という部分もややブラック・ボックスに入っているという感が否めないが,基本的には,逮捕免脱目的であれば,少なくとも,この暴行が窃盗の逮捕免脱に重要な役割を果たしているという点が本質的なのかもしれない(そうだとすれば密接な関連性は肯定できよう)。時間的場所的近接性があれば重要な役割を果たすのは,当たり前ともいえるからである。なお,若干疑問に思うのは,本件ケースではおそらく犯跡の隠蔽目的であったと思われるから,逮捕免脱目的と異なり犯跡隠滅目的であれば「窃盗の機会」は広く認められてもよいように思われる。このように考えると,前田説の批判も分からないわけではない。逆に言えば,これを説明しようとすれば,窃盗の機会が継続していないというのは苦しいからやはり窃盗犯人の身分がなくなったからやむを得ないのだという説明が適切と思われる。
[21] 機会説には,238条の主体には『強盗犯人』が含まれないことの均衡という理論的背景がある。すなわち,窃盗犯人が逮捕を免脱する目的で暴行をすれば238条で強盗とされる。これに対して,強盗犯人が逮捕免脱する目的で犯行現場から時間的・空間的に少し離れたところで暴行を加えても,刑法238条には該当する余地はない。そこで刑罰の均衡という視点からすれば,強盗犯人の場合は刑法240条の射程距離を拡張するのが望ましいということになる。つまり,機会説の実践的な意図は,「強盗犯人が逮捕免脱目的で少し現場から離れたところで暴行を加えて負傷させた」場合を240条の射程距離に入れることにあるといえるであろう。
[22] 『挙動による欺罔』を正確に擬律することができるかは重要なスキルであるといえるので若干の補足を付すこととする。まず,タクシー強盗の意思で乗り込んだが,暴行・脅迫の前に,Xが「トイレに行く」といって逃走した場合においてXはいかなる罪責を負うかを検討する。この点,強盗罪の実行の着手は,暴行・脅迫がなされた時点であるから,Xは強盗未遂罪すら成立しないということになる。そうすると,強盗予備を考えないとするとXは無罪ということになるのであろうか。この点,詐欺罪の成否を検討するべきである。受験生の答案では,「無罪。おしまい。」とするものがあるが妥当でない。そうだとすれば,まず,詐欺罪の実行の着手があるかが問題とされる。そこで,いかなる行為を詐欺罪の実行行為ととらえるかを考える必要がある。まず,Xが「トイレに行きたい」と言っている点を欺罔行為と構成することができないかについて悩みを示すべきである。この点,欺罔行為にあたると構成しつつも,Yの「料金債務の免除」という処分行為が存在しないので詐欺罪とするのは難しい。ここまで検討されていれば,まだマシな受験生といい得るが,「無罪。おしまい。」とするのは妥当ではない。そこで,「強盗の意思,逆に言えば運賃を払うつもりがないのにタクシーに乗り込んだこと」を挙動による欺罔行為ととらえることができる。この場合の処分行為は,運転役務の提供となるから,処分行為も認められるのである。したがって,「詐欺罪が成立する」というのが正解である。ところが,ここまで答案を流せる受験生は比較的少ないと思われる。挙動による欺罔の擬律の経験に乏しいからと思われる。
次に同じような例で敷衍しよう。Xは,Y旅館に宿泊し当初は宿賃を支払うつもりでいた。ところが,宿泊途中にすべてギャンブルにお金を使ってしまいスッカラカンになってしまった。そこで,3日間宿泊しつつ思案を重ねたところ,宿賃を支払わないで逃走することにした。逃走する際,Y旅館の女将Qが「どちらへ?」と聞いてきたので,Xは,「少し散歩へ」と答えた。以上のような事案である。考えてみるのに,第一に思いつくのは,「少し散歩へ」という点が言語による欺罔にあたるのではないかという思考であろう。しかしながら,女将が宿賃債務を免除する意思を表明しているわけではないのでいずれにせよ処分行為がないといわなくてはならない。したがって,「少し散歩へ」を欺罔行為と捉えても意味がない。そこで着目すべきは,挙動による欺罔行為となる。本問が少しひねってあるのは,最初の段階では支払い意思があるので欺罔行為はないということである。そこで,受験生としては,ここまで思案をめぐらせた上で,「無罪。おしまい。」とする者がいるが妥当でない。ここで着目すべきは,「3日間宿泊しつつ思案した」という部分である。ギャンブルで所持金がなくなったという重大な事情変更があれば,信義則上,直ちに事態を先方に伝える信義則上の作為義務が発生すると考えるのが通常であろう。そうすると,3日間の間にそのことを伝えなかったのが,欺罔行為にあたり,3日間の宿泊役務を得たのが処分行為と構成することができるであろう。してみると,Xはどこからどうみても詐欺罪で有罪と解すべきなのである。なお,受験生は不可解な学説を弄して処分行為に無意識的処分行為を認めるべきとする者がいるが,そのような奇説を採る必要性が本問事案において,どこにあるのかという点も自覚して論じる必要があるように思われる(要は擬律のセンスがないから問題意識を抱えて奇説に走るのである)。あれこれ思案した結果,奇説に走るのはまだ是認できるが,そうでもない者が多い。しかもあれこれ思案した結果ダメなら罪刑法定主義の観点から無罪にするのが刑法的思考の鉄則ではなかろうか。
[23] この論点については,民法の議論に引っ張られすぎているように思われる。すなわち,誤振込みを遺失物横領と構成すべきというのは,詐欺罪が成立しない結果として消極的に遺失物横領罪が成立するにすぎない。そうすると,まず,詐欺罪が成立しないかを検討してみる必要があるのであって,預金について誰に占有があるのかという視点はすぐに必要なものではない。そうすると,本文で述べた構成によって詐欺罪を構成することもできると思われる。ただし,本文の記載は前田271の叙述によるのであるが,私はむしろ以下のように解すべきと思う。すなわち,前田説は,「払戻請求権がないのにあるように装っている」ことが挙動による欺罔であると主張する。しかしながら,民法判例によれば誤振込みでも払戻請求権はあるのであるから,ここを強調しすぎると,「民法と刑法の関係」というなんとも壮大な問題意識を抱え込まざるを得なくなる。そもそも,XとY銀行は預金契約を締結しているのであるから,両者は信義則が支配する濃密な関係にあることは間違いがないのであるから,何らかの事情変更があれば信義則上の告知義務が生じるところ,かかる誤振込みはそれにあたると構成すれば十分ではなかろうか。つまり,挙動による欺罔ではなく不作為による欺罔と構成するわけである。考えてみれば,誤振込みが釣銭詐欺の途中から気付いてネコババ類型に本当に似ているのであろうか。むしろ,誤振込みというのは,自分のお金ではなく引き出しても弁償を求められるものであるから,「釣銭が多いことに気付いていながらあえて受けとる」類型にもっとも近いのではなかろうか。このように虚心坦懐に事案をみると詐欺罪が成立するのに疑いはまったく存しない事案ということができよう。しかるに,学者は,占有の有無とか民法との関係とか問題を難しく考えすぎているように思う。この問題意識を抱えるその背景は先に指摘したように「学者には擬律のセンスがない」という点に尽きるものといわなくてはならない。
[24] まず,欺もう行為が認められるかが問題となる。欺もう行為については,何が実行行為であるかを具体的に指摘する必要がある。取り込み詐欺のケースでは,作為による詐欺か不作為による詐欺が微妙なケースが多い。通常は,支払意思や能力に関しては,やはり契約の要素となっており当然の前提とされるから,「注文した行為」を欺もう行為と構成するのが通常である。これに対して,例えば,継続的契約の場合に関しては,信義則上の告知義務違反を問題とすべきケースもあると考えられる。なぜなら,商人間ではいちいち注文をしないでも,定期的に定量を仕入れるという取引形態も考えられる。かかるケースでは,上記の如く,「注文する行為」が認められないと考えられるからである。つまり,当事者間では何らかの作為が予定されていない場合は不作為を問題とするしかないと思われる。取り込み詐欺が欺もう行為が存在するかについては,たしかに,主観的には会社の好転を期待していても,客観的に支払能力も意思もないのに,代金を支払うことを約束して取引をすることは,相手方はそれにより代金を支払ってくれるものと誤信するから,詐欺の客観面は満たしているといえる。かかる場合は故意があるかの検討が必要となる。故意の対象は,被告人が①人を欺いて,②錯誤に陥らせるという認識を有していたかが問題とされる。ここでは,主観的には会社の好転を期待していたというのであり,それには相応の根拠が必要ということになろう。そこで好転策の合理性や資金調達の見込みなどの有無を精査することにより,人を欺く,あるいは錯誤に陥らせるということについての認識を有していたかを確定していく必要がある。
[25] 機械は錯誤に陥ることはないから錯誤に基づく処分に向けられた行為は,そもそも欺罔行為に当たらないと解すべきである。もっとも,機械といえるかについては実質的に判断される必要がある。例えば,消費者金融の無人貸出装置やラブホテルの機械による入室管理システムは,機械背後にいる従業員に対して向けられた挙動による欺罔と構成することができる。そして,貸出カードや宿泊サービスの提供を受ければ詐欺罪の実行の着手があるとされる(東京高判平成15年1月29日判時1838号155頁)
[26] 処分意思の内容について若干の補足的な説明を加えることとする。まず,処分行為の有無が問われ,したがって利益窃盗にすぎないのではないかという問題意識を抱えた場合は,その擬律の手順が誤っていることが多いのであり,不作為による欺罔や挙動による欺罔として構成することができないかについて,再度検討してみる必要があると思われる。次に,処分意思不要説は,不可罰となる利益窃盗との区別ができなくなり権力による恣意的な法適用を招くから罪刑法定主義からいって問題であり,このような解釈は採りえないものといわなくてはならない。もっとも,先述のように無意識的処分行為を認める見解も本当に利益の移転という事実状態が存在していれば処分行為の存在を肯定しているわけではない。なぜなら,詐欺罪は「交付」という文言が使われており,利益の移転が意思に基づかなくてはならないという点には争いがないからである。したがって,意識的処分行為説と無意識的処分行為説の対立は,実際は処分意思の内容をどの程度まで明確かつ具体的であることを求めるのかという点の争いということを自覚しておく必要がある。例えば,キセル乗車の下車駅における処分意思の存在をみれば,東京駅の駅員がXに対してどのような処分意思を有するかというと,『乗客とは一般的にキセル乗車をするおそれがあるものであるから,ひょっとしたら,Xはキセル乗車をしているかもしれないから,このまま出場させてしまうと何らかの区間の運賃債務を免れさせてしまうかもしれない』という認識となる。これは,具体的に駅員がXに対して差額請求権の有無・その額の多寡についても具体的にはまったく認識しておらず,その認識はきわめて一般的・抽象的なものにすぎず,突き詰めれば,処分意思は,駅員の『漠然とした危惧感』で足りるということになるであろう。しかしながら,処分意思の内容が『漠然とした危惧感』で足りるとすればそれは処分意思を否定するのにも等しいものと解すべきである。そうすると,利益窃盗の不可罰的な領域との区別を曖昧にさせ罪刑法定主義からいって問題といわざるを得ない。
[27] クレジットカード詐欺については,財産上の損害がないというよりかは,欺罔行為と錯誤による処分行為がないのではないかという指摘の方が本質的と思われる。というのも,XがAに対して商品購入の申込みをしてクレジットカードを示した場合,通常の取引であればAはXが代金を支払ってくれると考えると思われる。そうすると,代金を支払う意図がないにもかかわらず,商品を購入しようとすれば「挙動による欺罔」と構成することができる。しかしながら,クレジットカード取引の場合,Aは,カード会社のB社から代金を受け取るのであり,かつ,カード会社から支払いを受けられない事態というのはほとんど想定されないということになる。そうすると,Xが詐欺者であってもAはBから代金を受け取ることができるから,本来AはXの資力状態には興味がないというのが本質的といえる。とすれば,Xの資力状態に興味を持っていないAにカードを指し示すのが,『挙動による欺罔』と評価することができるのかについては疑問があると考えられる。もし,財産上の損害がないのではないかという問題の立て方であれば,『個別財産』に対する罪であるといわれればそれで終わってしまう議論といえるであろう。
[28] この点,クレジットカード詐欺には無罪説がある。無罪説の根拠は,『財産上の損害』がないからという理由ではなく,加盟店に支払い能力があるように装うことは欺罔行為にあたらないとする理解が前提といえる。かかる無罪説は,クレジットカード詐欺が発生した当初の時点では正当といえる。なぜなら,従来は加盟店による本人確認は軽視されているという社会的実態があったからである。現実に,小売店がカード会社から支払いを受けられないという確率は無視してもよい程度であった。したがって,カード利用者の財産状態は小売店側の興味の対象ではなく,錯誤もありえないというのは,社会的実態を一面では正確にとらえていた。
しかしながら,クレジットカードの取引実態が最近微妙に変化していることにも着目する必要がある。すなわち,従前はカードの利用可能な店舗を拡大するために,小売店側の支払いを受けられないかもしれないという危惧感を払拭するために,「無条件で支払う」という点が強調されていたわけである。ところが,今日では,クレジットカードの利用が定着するとともに,カードを利用する詐欺事例が増加傾向にある。そうすると,このような社会的実態にかんがみると,加盟店の本人確認の注意義務も必然的に高度なものが求められるようになる。したがって,加盟店の対応によっては,信販会社から支払いを受けられない可能性も今日では生じているわけである。そうすると,加盟店は,カード利用者の支払い意思に関心を向けざるを得なくなっている。このような社会的実態を前提とすれば,加盟店に対する欺罔行為を肯定することも認められるというわけである。
[29] この論点については,以下のように解すべきであろう。すなわち,1項詐欺罪を肯定するのであれば,基本的には交付がなされた時点で既遂に達するものと解すべきである。したがって,交付というためには,被害者が占有を失っているかが一つのメルクマールとなる。この理解からすれば,預金の出金措置がとられても,被害者が占有を失っていると考えられる。また,交付を受けるといっても,自己が支配を及ぼす第三者に交付させても既遂となるのであるから,この理屈を推し進めればその口座はXが管理しているのであるから,自己が支配する銀行に対して支払わせたということになる。さらに,たしかに,出金禁止となればXが口座を支配しているとはいえないとも思える。しかし,いったん出金禁止となっていない状態で入金がなされた時点で既遂になると解すべきである。したがって,その後に出金禁止となっても既遂が未遂に遡及的に変更されることはありえないというべきであるから1項詐欺既遂説が妥当である。この理屈を推し進めておくと,当初から凍結されている口座に振り込みがなされた場合は,Xの支配が及んでいるとはいえないから,1項詐欺未遂説が妥当と思われる。
[30] 第三者を道具として利用する場合や欺罔行為者のために受領する者などの特別の事情がある場合は,第三者に交付させても利益の移転があるとされる。
[31] 不法原因給付と詐欺罪については,理解が難しいところがあると思われるので若干補足しておきたい。まず,不法原因給付と詐欺を論じるにあたっては,2つの考え方が混在しているという点を踏まえておく必要がある。第一に,奪取罪の保護法益について本権説を中心にとらえる考え方である。このように,本権説を前提とすれば,民法上保護に値しない不法原因給付については刑法上も保護に値しないと直結することになり詐欺罪の成立を否定するという方向性となる。そもそも,財産罪の保護法益について本権を中心に考えるのは19世紀的な発想といい得ると思われる。国家の役割が国民の財産の保護にあると考えるのであれば,それが保護に値しないというのであれば,何も国家が刑罰権を発動してまであげる必要はないという発想が根底にあるといえよう。第二は,奪取罪の保護法益について所持説を中心に考える見解である。本権をまったく無視して所持のみを考えるのも今日では少数のように思われるが,これを徹底すれば占有侵害はあるわけであるから,民法上保護に値しないことと刑法上処罰しないことは別の問題であるとされやすいのであろう。これは20世紀的な発想ともいい得る。すなわち,19世紀においては,国家の市民社会への介入は最小限度であることが求められるのに対して,20世紀においては,福祉主義の理想の下,その介入の程度が強まったのである。そうすると,たとえ民法上保護に値しないとしても詐欺が蔓延すれば社会秩序が乱れるという見地から処罰するということも正当化されるのである。これが,いわゆる刑法独自の視点というわけである。したがって,不法原因給付と詐欺罪の論点は,実は所持説を前提とする限りはほとんど論点化しないものといえよう(前田282は,『不法原因給付と1項詐欺』については何も言及がない。処罰されて当然すぎるということであろう)。
このような視点から本問を眺めるとき,まず,1項詐欺については,今日では,ほとんどの見解が詐欺罪の成立を肯定している。その実質的理由を探究してみると,横領罪と不法原因給付と比較してみるとよいであろう。つまり,横領の場合,被害者とされる側に問題があるのであるから,特に,刑法上の保護も与えられるかと言う問題意識を抱えやすいであろう。しかしながら,詐欺と不法原因給付の場合,欺罔者が欺罔をすることによって,被害者が不法の給付をさせるというわけであるところ,例えば,その給付が裏口入学の裏金のように市民にとって誘惑されやすい給付ということもあるであろう。そうであるとすれば,このような場合も含めて一切刑法上の保護を与えないとするのは,刑法の法益保護機能からいって問題があると思われる。したがって,価値判断の上では肯定説が妥当という結論がもう出ているわけである。そして,所持説を前提にすれば,『処罰に値する法益侵害があるから』と説明されれば十分であろう。これに対して,本権説を前提とすると,その論証が求められることになる。この点,多くの論者は原因において不法な行為をしているのは欺罔者の方であると指摘している。つまり,民法708条ただし書が適用されるというのであれば,そもそも不法原因給付ではなくなるので論点を殺せるというわけである。たしかに,不法原因給付という言葉使いはもともとドイツの議論を参考にしているのであって,『何らかの不法がある』という程度の意味でしか使われていなかった。つまり,厳密に何が不法原因給付かを特定しないまま大上段の議論を展開していたわけである。ところが,具体的なケースを想定すると,そもそも不法原因給付といえるのか疑わしいケースもあるし,一方に不法原因が存することが多いというケースも相当含まれていることが分かったわけである。このような観点から本権説も1項詐欺と不法原因給付については,立場の変更を余儀なくされたというように理解しておけばよいであろう。たしかに,もし,オレオレ詐欺で,XがYに対して,「ボクは息子のAであるけど暴力団に誘拐されました。だから,身代金300万円を銀行に振り込んでください」というように要求された場合,Xがこれに応じて身代金をYに振り込んだ場合に,不法原因給付であるから詐欺罪は成立しないとするのは,いかにも非常識というべきである。
このように,所持説は,1項詐欺と不法原因給付という論点では後退を余儀なくされたわけであるが,2項詐欺と不法原因給付という論点では,まだ,ガンバってしまうのである。たしかに,本権説を前提にすると,民法上保護に値する利益が必要とされるところ,1項詐欺との関係では,それは不法原因の所在に大きな偏在があるから,まだ肯定できるという論法をとっていた。これに対して,2項詐欺との関係では,そうはいかないのである。売淫料が民法上の保護に値するのであろうかと問われれば,さすがに否定されるべきであろう。つまり,本権説を前提とする限り,例外的な理由付けも立たないから無罪とされざるを得ないということになる。もっとも,ある意味すっきりしているといえるであろう。これに対して,所持説には,若干の混乱が見られることになる。結局,所持説を前提とすると,「処罰に値する法益侵害があるか」という刑法独自の視点から判断されることになるが,いかにもその判断の限界は不明確といわざるを得ないであろう。ほとんど適用者の恣意的判断によってしまうのではないかとも思える。刑法独自の観点といっても,結局,「売春婦」がお気の毒と思えば肯定,そうでもなければ否定ということになるであろう。この点,前田282は,「明らかに公序良俗に反する売春契約に基づく債務の刑法上の要保護性は低いが,詐欺罪として処罰に値する法益侵害性が常に欠けるとすべきではない」とする。大塚119は,「おそらく,不法な経済的利益が法秩序によって正面から否定される利益が否かを検討する際に,売春当事者の生活状況や売春態様などを考慮」する趣旨であろうとする。つまり,所持説を徹底するのであれば,行為態様が社会通念に反するかを検討するということである。なお,肯定説の中には,「売淫料免脱の場合も・・・支払いを猶予されたことが財産上の損害」(福田242)と本権説的に説明しようとする点が矛盾であろう。まるで本権説的な理由付けをしているが,民法上保護に値しない請求権が,こと刑法の世界に変わると突然処罰されてその根拠が「処罰に値する違法性がある」とされるだけでは処罰される側も,うかばれないであろう。先述のとおり,所持説を前提として理解するのであれば,その売淫料を保護することが社会的相当性を欠くかを別途検討すれば,場合によっては保護に値するという場面もあるということになろう。例えば,生存権保護機能が強い場合や行為態様もマッサージの延長とみられないではないサービスであれば社会通念上保護しても相当性を欠くとまではいえないように思われるということになろう。いずれにせよ,1項詐欺罪と不法原因給付の論点は,本権説的な理解をするときに問題が大きく,2項詐欺罪と不法原因給付は,所持説的な理解をするときに問題が多いと考えておけばよいであろう。
[32] この理由付けは,欺罔がなされた時点のみにフォーカスをあててみると,原因において不法であったのはXのみであるから,その時点ではYは未だ無色透明であったという構成になると思われます。すなわち,不法原因給付を惹起させたのは,Xであり給付物である金銭も欺罔による交付が行われるまではYは交付を拒むという利益も有している。かかる利益は不法原因給付にあたるわけではないから民法上の保護に値するという議論となる。そうだとうすれば,欺罔によって交付される現金が損害ということになると思われる。
これは,異なる角度からいえば,次のようにも言えるであろう。すなわち,この見解は,行為者が不法の原因を作り出しているのであるから,それは結局,不法の原因が受益者について存すると解することになる。したがって,民法708条ただし書が適用されて,それゆえ,返還請求権が認められる。故に,詐欺罪が成立すると説明するものである。
[33] 実質的個別財産説とは,財産と実質的に関係のない畏怖によって財産を処分している場合については,損害の発生はないとする見解である。権利行使と恐喝の典型的なケースでは,詐欺罪のケースと異なり,実質的個別財産説によっても損害がないとされるケースは稀のように思われる。
[34] 権利行使と恐喝の論点では,権利の範囲内であるかが一つ重要な問題となるが,権利の範囲内でなかったとしても相当の資料に基づいている場合には権利行使の意図で行為をしたとみることができる(防衛の意思とパラレルの要件と忘れないこと)。
[35] 権利行使と恐喝の事案は,不法行為債権をめぐる争いが多いと考えられる。かかる債権は,不法行為時にはどの程度の額について債権が発生しているのか不明確ということができる。したがって,行為者の債権額が確定的ではなく,あるいは,相当の根拠もないにもかかわらず,金銭を要求するという場合については,そもそも,『債権の範囲内』といい得るかも分からないといえる。これに対して,債権の額が明確である場合については,行為者に有利な事情となる。もっとも,債権者であっても暴行・脅迫を加えて権利を実現する権利はないという点からすれば,正当化されるには,債権の存在が明確というのみでは足りず,被害者が誠実な対応をしないなどの事情が必要であり,さらに,手段も社会通念上相当とかろうじていえるものに限られると考えられる。
[36]少数説の問題意識は以下のとおりである。すなわち,占有に法律的支配を含むといっても,それは法律的支配の典型例とされる登記名義人や倉荷証券の所持人を説明されるものにすぎず,しかもこの典型例では,占有という概念のみが拡張されているにすぎない。ところが,そもそも,2項横領は不可罰であることから明らかにように,権利や利益は横領罪の客体とはならない。したがって,社長が会社の委託を受けた債権証書を保管中に債権を行使して債務者から金銭を取得したとしても252条にはあたらないという基本線がある(大判明治42年11月25日刑録15輯1672頁)。預金による占有を認めると,その実質は,債権の占有を認め財物概念まで修正することになるという問題意識を有しているといえる。たしかに,権利の横領がありえないとすれば,単に占有概念の拡張ではなく財物概念まで拡張しており,その結果,2項横領を処罰することになり,罪刑法定主義からいって問題である,という論旨は傾聴に値する。
[37] 林説であるが,考えてみれば,民法708条にいう終局性とは法が不法には助力しないという観点から,法による助力を要しないという程度に達することを求めるものにすぎないものである。したがって,この観点から光を当てて考えると,賄賂のためにAからXに交付があった場合,金銭の交付自体は終局的になされておりXが金銭を得るためにもはや国家の助力はいらないのであるから,したがって,給付自体に終局性が認められるという帰結になると思われる。しかるに,西田220は,「委託であって給付にあたらず・・横領罪の成立が認められる」とする。また,国井222も判例は,『所有権を移転する目的』があった場合のケースであるところ,賄賂事例は所有権を移転するものではないから,不法原因寄託にあたるとするが,いずれも疑問である。佐伯=道垣内50は,「寄託一般を民法708条にいう「給付」に該当しないという学説は民法では存在しない」として,道垣内教授は,「不法原因寄託」という用語は民法学には存在せず,しかも林説が依拠した谷口教授の見解についても,「一場面を結びつけたものにすぎない」と批判している。更に,西田220のように「委託であって給付にあたらない」という民法708条の理解について,「金銭を預ける行為が給付であることには民法学上まったく異論はありません」,「受領者の利得が終局的でないとなぜいえるのか,理解できません」という。さらに,佐伯教授は,「XがAにBの殺人を依頼して拳銃を渡した」というケースでそれが譲渡か貸与かで区別するのは意味がないと指摘している。
[38] 不法原因給付と横領について若干の補足的な説明をする。まず,不法原因給付と詐欺罪で問題となった所持説と本権説の対立は横領罪では存在していない。すなわち,横領罪は所有権の保護を目的としている点は否定しがたく本権説が妥当するからであろう。そうだとすれば,横領にあたるかについても,民法上,行為者に所有権があるのか否かという観点から光をあてて考えるべきというのが説得的になるということになろう。この点については,横領罪は成立しないという見解と不法原因給付と不法原因寄託を分ける見解の2点が議論の対象になると思われる。だが,これらの学説も基本的視座は本権説的思考に立ち,法秩序の統一性を重視させるという点では異ならない。そうすると,整理すると以下のようになろう。まず,二分説を民法学上認められていないという点をどう態度決定するかがポイントになろう。この説は民法上承認されていない説を民法上の学説という誤った前提に立っているという問題があるが,『刑法的民法解釈』をするという前提に立てば受け容れられないものではないと思われる。これに対して,あくまで民法上ありえる解釈しか採りえないというのであれば,民法708条但書に該当するかを検討することになると思われる。結局,この論争の背景には,以下のような本質があるといえよう。すなわち,二分説の試みは,給付自体の概念に限定を加えることによって,恣意的な判断がなされるおそれを防止し基準を明確化するというメリットを重視するか,もしくは,道垣内教授がいうように,給付概念を広く認めて委託者の所有権は喪失するという不成立説に近い立場を前提としつつ,民法708条但書を適用して,委託者の違法が受託者の違法を下回るような事情があれば所有権は受託者には移転しておらず,したがって,横領罪は成立するというアプローチをとるかということになると思われる。この点は,判例は肯定説をとっており,これを支持する前田説もあるが,そのメルクマールとして指摘する「不法な領得行為に対して保護に値する利益の存在」は,基準が不明確であるし,その実態はあまり民法708条但書でバランシングを採る見解と違いがない(原則有罪,例外無罪の違いはあるが)といえようが,なぜ,本権説的な思考が求められる横領罪で,『刑法独自の視点』が出てくるのか疑問もある。案じてみるのに,前田説は,横領罪の保護法益として,財産に対する侵害よりも『委託信任関係に背く』という点を重視して,後者の部分を媒介項にして,本来導入することができないと思われる横領罪の中に『刑法独自の視点』を取り入れていると解することができるように思われる。私見を述べると,林説で妥当と思われる。たしかに,民法学ではそのような解釈は通説ではないが,同じ条文であっても刑法の場合は例えば類推解釈ができないように,民法の条文の読み方が『刑法的』になってもよいと思われる。そういう観点からみれば,二分説が罪刑法定主義的見地からいっても最も問題が少ないと思われる(両者の利益を衡量してその結果有罪とするのは問題が大きいように思われる)。
[39] この点に,財産的侵害が乏しくても刑法独自の視点を導入して可罰性を確保できるという側面があると思われる。
[40] 『横領』の意義については,越権行為説と領得行為説が対立している。越権行為説は,横領とは委託に基づく信任関係を破棄して占有物に対して権限を越えた処分を行う行為をいうと定義することになる。これは,横領罪の保護法益は,所有権侵害であるというよりはむしろ,委託信任関係に背く行為にフォーカスをあてて,それによる利用権能の事実的侵害ととらえている。これは,刑法的な独自の視点を導入しやすい物の味方と評価できるであろう。
[41] 権限濫用説は,財産関係の代理権が濫用された場合に処罰の範囲を限定している。これは,本権説的な発想によっているものと解されるし,成立範囲の基準が明確であって,罪刑法定主義の要請にかなっているといえるのであろう。このように考えると,権限濫用説と背信説の対立の本質は,罪刑法定主義の要請である基準の明確性か,法益保護の要請からくる処罰範囲の妥当性をどのように調和させるかという点にある。
[42] 判例は,名義と計算という概念を使い分けているとされるが,実質的な基準として作用しているのは,「実質的には自己の計算で行為をしたのではないか」(=計算)という視点である。これは,「所有権者でなければできないほしいままの処分をしたか」という『横領』の基準を言い換えたものにすぎないと解される。そうすると,横領罪と背任罪の区別は,『領得行為』の有無によって区別されることになる。判例の問題とする『計算』は,行為者にとって主観的にいかなる考えであったかを重視する面が強く,『横領』において不法領得の意思を重視する判例にとって使いやすい基準といえる。
[43] 二重抵当の問題の本質は,以下の点にあるものと解される。すなわち,背任罪において背信説を採ると罪刑法定主義からいって問題が生じる。そこで処罰範囲を限定していく必要が生じる。その限定の一つの試みが,「対内的ではなく対向的に本人に義務を負うにすぎない者,例えば売買契約の当事者については,対向関係にあるので,「他人のために事務を処理する者」にはいえないという主張である。したがって,二重抵当の問題の本質も,「他人のために事務を処理する者」にあたるかを通して法益保護の実現と罪刑法定主義からの処罰範囲の限定と要請をどのように調和させるのかという点にあると解される。
[44] Yに対する関係で背任罪が成立するとしてもAとの関係で詐欺罪が成立するかについて問題がある。この点,国井230は,後の抵当権者にとって一番抵当権の取得が目的であり,実際にその目的を達している以上,XがAに対して,抵当権存在の事実を秘匿したことは詐欺罪でいう詐欺行為とは言いがたいとしている。前田325は,個別財産に対する罪であるが損害は実質的に考えざるを得ないとする。この点,国井説が正当であろう。要するに,本件の場合,不作為による欺罔行為が認められるかが問題となるところ,そのためには,信義則上の告知義務が生じる必要がある。もっとも,告知義務は,何らかの法益侵害・危険が発生するという状況がない限り生じないと解される。しかるところ,本件では,Aは第一抵当権の設定を受ければ何の法益侵害もないのであるから告知義務が生じると解することはできないということになる。したがって,不作為による欺罔行為の存在が否定される。
[45] 一般的な基本書では,「他人の事務」といえるかについて,「Xの協力がなければAが抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能ですから,その限度でXの登記協力義務の履行はAの抵当権保全行為の一部をなす」(大塚271)という一般論として認めるべきものとするが,国井230の見解は,特段の事情のない限りは,「対向関係にすぎず対内関係ではない」という趣旨と解される。この点について考えてみると,登記の性格は債務の履行としての側面が強いが新たな権利関係を創設するものではない。そうすると,権利者のためにされる行為としての客観的な性格が強いことはにわかに否定できないというべきであろう。しかしながら,売買をする間に他の高値を付けた第二売主に売却したという事例を想定してみると分かるがこれを認めれば登記についても即対内関係というのは疑問がある。結局,全体的にみて債務不履行にとどまるといえるかにより判断されるといわざるを得ないが,実質的にみて未だ利害が対立する事情があるかの検討が必要なように思われる。
[46] この議論は,図利・加害の事実についての確定的認識又は意欲を必要とするという見解に対する評価にも関わってくる。たしかに,背任罪は財産上の損害という結果を必要とするから,その認識は故意の要件といえる。したがって,加害の目的が未必的認識で足りるとすれば,故意があれば加害目的も肯定されることになってしまい処罰範囲を限定する意味がなくなってしまう。そこで,従前は,加害目的については,意欲まで必要とする説も主張されていたのである。ところが,香城理論が,「図利・加害の目的という要件は,本人図利目的で行われたものではないという要件を裏側から規定したものにすぎない」と指摘した。そうすると,「本人図利目的ではない」ということが重要であり,かつ,このように目的を理解すると故意と重複するわけではない。したがって,今日では,本人加害目的が認められる以上,背任罪の図利・加害目的は未必的なもので足りるという理解が支配的となっている。そうすると,図利・加害の事実についての確定的認識が必要という大谷説はその要件の真意を正解しないもので,過去のものになったと評価できよう。
[47] 『本人のため』といえる場合に不可罰となるのは,任務違背行為があっても本人に対する不利益性が否定されることにより信任関係が侵害される行為ではなくなるからと説明できる。また,たしかに,客観的には,本人の利益にはなっていないが,本人に対する利益性を認識していた場合には,本人に対する実質的不利益性の認識がなく,信任関係の侵害について故意責任が欠けるからとも説明される。
[48] 任務違背行為について,本人の財産に損害を与える可能性を問題にし許されない程に危険な行為であるかを判断しようとするのは,罪刑法定主義的見地からいって意味があるであろう。横領罪については,領得行為説と越権行為説が対立していたが,越権行為説は罪刑法定主義からいって問題があるということで領得行為説が通説であった。ところが,背任罪は,横領でいうところの越権行為説的な理解がなされているわけであるから,もとよりこの見解は罪刑法定主義からいって問題をかかえているといえるわけである。したがって,処罰範囲を限定的に理解するためには,実質的に本人の財産に損害を与える確率や許されない程度の危険を生じさせるものであるかということを任務違背にあたって考慮し,それが否定される場合は,そもそも任務違背がないという処理をするのは適切であるといえよう。この点,前田333は,処罰に値する程度の経済的危険性が必要として,経済的損害概念による処罰の拡大を防止するという視点から,かかる実質論を導入している。かかる前田説の問題意識も罪刑法定主義から来ているということはできるが,損害で検討するよりも任務違背で検討した方がすっきりするであろう。