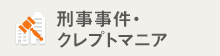被疑者の取調べ
問題が多いのは被疑者の取調べである。
なかなか身柄が拘束された極限状態の中では、自分の意思を押し通すことはできず、簡単に警察官にいなされてしまうことも少なくない。
また、余罪の取調べについて、起訴後に行われている例が増えてきており、極めて問題である。すなわち時間制限をもうけた意味がなくなってしまっている。
第7編 被疑者の取調べ
第1 総説
1 取調べの重要性
① 犯罪と犯人の結びつきを直接に示す客観的証拠はなかなか存在しない
⇒ 被疑者の供述を得て,それを他の証拠と照らし合わせる作業が不可欠
② 犯罪の主観的要素や共犯者間の役割分担は,自白がないと把握できない
⇒ 汚職,選挙違反,脱税などの密室性の強い犯罪も同様
2 被疑者取調べの法規制
刑訴法198条
第2 在宅被疑者の取調べ
1 出頭拒否・退去の自由
刑訴法198条1項ただし書き
⇒ 任意捜査として許される
* 在宅被疑者の取調べの場合は,被疑者には出頭拒否・退去の自由の保障[1]
2 任意取調べの限界
(1) 適法性判断の枠組み
ア 判例の判断枠組み
高輪グリーンマンション事件判決(最決昭和59年2月29日刑集38巻3号479頁)は,2段階のテストをする(3分説)
(ア) 判断枠組みの中身
① 強制手段によることができない
② 社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度か
* 判例の判断枠組みのイメージ
Ⅰ 強制手段を用いた違法なもの(違法な強制捜査)
Ⅱ 任意捜査として相当な限度を超え違法なもの(違法な任意捜査)
Ⅲ 任意捜査として適法なもの
(イ) 相当性の判断構造
① 事案の性質
② 嫌疑の程度
③ 取調べの必要性
④ 取調べの状況・態様
⑤ 被疑者の態度・意向などを総合
⇒ 社会通念上相当と認められる限度で許容される
(ウ) 適用上の問題
①⇒意思制圧の有無を中心に検討
* 用いられた手段・方法自体が許されないので,捜査の必要性に関わらない
②⇒①と②のテストの独立性(総合的な評価となるので,捜査の必要性の大小で許される権利制約の程度が異なる相対的な制約となる)
* 判例では,被疑者の意思に対する制約の程度が取調べの必要性と比較衡量される(だが,憲法33条にかんがみれば任意の承諾がない限り任意の取調べはできないはずであり,意思に対する制約の程度を思考するのは相当ではない)
* ②の相当性を否定したものとして大阪高判昭和63年2月17日判タ667号265頁(徹夜の取調べ)
捜査官は午後9時20分ころ,職務質問のうえ任意同行。翌日午前4時ころまで徹夜の取調べ。午前5時30分ころ緊急逮捕。嫌疑は,時価3000円相当のウィスキーの窃取[2]
(エ) 判例の3分説に対する疑問[3]
* 帰りたいといえば,逮捕状が請求ができる程度に嫌疑が高まっており,身体確保の必要な場合は逮捕できるかどうかを検討(検察)
* 任意同行の場合は捜査の必要性を具体的に考えることが大事。犯人でないなら,犯人でないことを確定しておきたいので,説得をするのはよい。ただし,どうしても帰りたいといった場合はやむを得ない。そこで,どこで合理的に線を引くかという問題である。
これは,具体的な事情で考えていくべきである。警察官の行為が限界を超えているというのはバランシングの上で主張することが大事(検察)
* 職務質問の場合
覚せい剤を所持していれば,応じるはずはない。所持品検査は任意だから「いってよい」とはいかない。逮捕の実際はそういうこと。
2 酒巻説の判断枠組み(2分説)
(1) 任意同行が実質逮捕か否かの判断構造
∵ 任意同行の際に問題となる対象者の権利・利益の内容は,憲法33条の保障する人の身体・行動の自由
⇒ 対象者の意思を制圧して侵害・制約がなされたとすれば,憲法33条に反し,違憲違法な身体拘束処分となる
(2) 認定の仕方
① 同行の方法に物理的強制力の行使がある場合
⇒ 逮捕行為そのものであり,違法逮捕と評価すべき
∵ 明示的に拒否する被疑者に対して物理的強制力を用いるに至れば,自由な意思決定を論じる余地が失われる
② 物理力・有形力行使の程度が小さい場合
典型例
外観上はあくまで任意同行ないし任意の出頭と滞留の形式が満たされているものの,実質的には出頭を拒む自由はなかった,または,いつでも退去できる自由がなかったと認められる場合
∵ 被疑者が明確な拒絶の意思表示をすることなく従っている場合でも,状況によっては,意思が制圧されていると評価すべき場合あり
● 物理的強制力の行使がなかった事実や対象者が明示的には出頭拒否の意思や退去の意思を表明していないという外形的事実を重視すべき
× 外観上の形式が明白な逮捕行為でないから,物理的強制力の有無や出頭拒否などの意思表明の手段の有無を問題にしても無意味
○ 51年判例の枠組みで判断すべき
⇒ 意思の制圧の有無と身体・行動の自由という重大な法益が実質において侵害・制約されていたかで決まる
*重要な考慮要素(法教288号71頁)
| 重要なファクター | 重要でないファクター |
| ① 出頭の拒否は困難で同行を余儀なくされたか
② 自己の意思で退去することは困難であったか(以上,意思の制圧の側面) ③ 客観的にみて,一定の時間継続した行動の自由侵害があったか(法益の側面) |
① 物理力・有形力の有無
② 明示の意思表示 |
* 被疑者の対応状況,同行及びその後の取調べの時間,場所,方法・態様,監視状況を考慮して判断すべき[4]
*酒巻の任意同行のイメージ(判例の3分説とは異なる)
 相当性
相当性
権利・利益の制約大 憲法33条のライン
![]()
承諾なし 要件を具備しない
実質逮捕 要件が具備された
⇒×違法!! 逮捕⇒○適法!!
![]() 捜査の必要性大
捜査の必要性大
相当でない任意捜査
承諾あり ⇒×違法!!
3 実質逮捕(違法な任意同行)の効果
① 法定の身体拘束期間の起算は,実質逮捕の時点から行う(205条2項参照)
② 法定期間制限を越える場合は勾留請求却下(206条,207条2項)
4 実質逮捕と勾留請求却下
(1) 基本的処理方針
| 身体拘束処分を行う実体要件がないのに実質逮捕した場合 | 任意同行は実質逮捕だが,事後的にみると逮捕の要件があった場合 | |
| 勾留請求 | 却下すべき[5] | 重大違法の存在が争点 |
| 証拠能力 | 違法収集証拠排除法則で排除[6] | 重大違法の存在が争点 |
(2) 事後的にみると逮捕の要件が揃っている場合の検討
ア 事例
① 通常逮捕の要件がある場合(199条)
② 緊急逮捕の要件がある場合(210条)
イ あり得る考え方
(ア) ①②はいずれも重大な違法ではない(渡辺咲子)
∵ 実体要件はあるから手続的な瑕疵にすぎない
(イ) ①②はいずれも重大な違法である(酒巻)
∵ 適法な手続に従わずに実質逮捕が行われたということであり,逮捕の要件の具備如何を問わず,そのような手続違背それ自体を重大な違法と解すべき
(ウ) ①は重大な違法だが,②は重大な違法ではない(下級審)
∵① 通常逮捕の要件があった場合
⇒ 本来,事前に裁判官の令状を得て身体を拘束すべきなのに,そのような手続を踏まずに実質逮捕することは重大な違法
② 緊急逮捕の要件があった場合
⇒ 緊急逮捕の実体的要件があれば,まず身体拘束することが許されているのであるから,そこで行われた実質的逮捕自体は緊急逮捕の適式な方式を執らなかった手続上の瑕疵にとどまるので直ちに重大な違法とはいえず
* その後実質逮捕から間がない時点で裁判官の審査判断が行われていれば違法は重大ではない
× 緊急逮捕手続における速やかな事後の令状請求手続は,緊急逮捕の制度が憲法上令状逮捕の一種であり,合憲性を維持するために最も重要な要素
⇒ 緊急逮捕の合憲性を支えているのは,事後の迅速適式な令状請求手続が不可欠であり,これが欠ければ令状主義違反の重大な違法というべき(法教288号74頁)
5 違法な身体拘束を利用して行われた取調べの適否と自白の証拠能力
(1) 違法収集証拠排除法則を適用する見解(酒巻)
∵① 最終目標である証拠の獲得を目的として,違法な実質逮捕状態を直接利用した取調べが行われている
② 事柄の実質が身体拘束に関する令状主義の潜脱であること
③ 違法捜査を抑止すべき政策的必要性は高いと認められる
④ 違法収集証拠排除法則の自白への適用を否定する根拠はないこと
(2) 319条の適用により任意性を否定する見解(高輪グリーン・マンション事件反対意見)
∵① 対象者の意思を制圧し,身体・行動の自由を侵害・制約するという違法な身体拘束状態の下で行われた取調べは,個別具体的事案の諸事情によっては,それによって得られた自白の任意性に疑いを生じさせる場合あり
② 任意性に疑いのある自白は319条1項の明文規定の適用により証拠能力が否定されるとする見解
× 身体拘束下の取調べにおいても,供述の任意性を直ちに失わせるわけではないから,この法的構成の場合は具体的事情によっては任意性が肯定される場合もあり
* 判例の位置づけ
|
①
*違法な強制処分ではない
|
②
*酒巻はこの②の相当性判断は
あり得ないと主張する[7]
* 捜査機関が最終目標としている被疑事実の供述証拠の獲得プロセスについて二段構えの分析検討が必要
* 最高裁は,取調べによる供述証拠の収集保全について一層厳格な規律を及ぼそうとする
第3 身体拘束中の被疑者の取調べ
1 取調べ受忍義務
(1) 問題の所在
ア 198条1項ただし書き
イ 受忍義務肯定説
ただし書きの反対解釈
(2) 受忍義務否定説の提唱(平野説)
∵① 不利益供述強要禁止(憲法38条1項)との整合性
② 198条1項ただし書きの解釈については,逮捕・勾留の効果は,被疑者の出頭拒否や退去によって失われることはない趣旨を明らかにしたもの
(3) 受忍義務否定説の展開―198条1項ただし書きの解釈論的努力をめぐって
ア 鈴木説
「私は,逮捕・勾留されている場合については明文をおかず,解釈に委ねた趣旨に解すべき」
イ 田宮説
「198条1項ただし書きは,在宅被疑者の捜査機関のもとへの出頭規定である。逮捕・勾留されている被疑者に対する出頭要求はそもそも問題となり得ない。したがって,念のために除外規定が設けられたものと解される」
(4) 松尾説の登場
「法律上の義務という点では,被疑者には,『供述をする義務』がないことはもちろん(198条2項参照),憲法38条1項が包括的な黙秘権を定めている趣旨に即して考える限り,取調べに応ずる義務も認められないというべきであろう(いわゆる取調受忍義務の否定)。身体拘束中の被疑者には,出頭拒否及び退去の自由はないので(198条1項ただし書き),求められれば取調室へは出頭することになるが,そこで取調べを拒んだ場合,捜査機関の側で翻意させるための説得を試みることは許されてもそれが長時間にわたることは許されない」[8]
2 余罪の取調べ
(1) 問題の所在
(2) 取調受忍義務を肯定する見解
ア 無制約説(渡辺咲子説)
∵① 逮捕・勾留の目的の内容には,取調べも含まれる
② 取調べはあくまで任意捜査
イ 事件単位の原則による制約を認める見解(木谷明説)
∵① 逮捕・勾留の効力により出頭滞留義務が生じる
② 取調べは取調べ受忍義務を課すのであれば強制捜査
③ 逮捕・勾留の効果で取調受忍義務が生じるから事件単位の原則で規律[9]
(3) 取調受忍義務を否定する見解
ア 事件単位の原則による制約を認める見解(鈴木説)
鈴木説:「取調受忍義務を否定し出頭拒否や退去の権利を認めたとしても,拘束中の被疑者の取調べを単純に『任意処分』として位置づけてよいかは,一つの問題である。・・・拘束中の被疑者の取調べにあたって認められるのは,強制ではなく合理的な説得にとどまる。しかし,説得といっても,適法な拘束状態にあること自体が事実上一定の強制的作用を営むことは否定できない。外界と遮断され弁護人も必ずしも事由に接触し得ない状態の下での『承諾による取調べ』は,それ自体,一種の強制処分として把握すべき一面を有するといえよう」
⇒ 拘束中の被疑者の取調べは,事件単位の原則の適用があると解すべき
イ 余罪取調べの範囲に制約はないとする見解(平野説)
ウ 逮捕・勾留の趣旨から余罪取調べにも制約が生じるとする見解(川出説)[10]
川出説:「起訴前の身体拘束期間中は,原則としてその理由とされた被疑事実についての捜査を行い,その期間をできる限り短期にとどめる必要があると解される。その前提からすれば,余罪についての取調べのために,身体拘束の理由とされた被疑事実についての取調べが中断している状況がある場合には,起訴前の身体拘束期間の趣旨から逸脱した行為により,本来の被疑事実のみの取調べを行った場合よりも,結果的に身体拘束期間が長期化するという不利益を被疑者に負わせることになる。それゆえ,そのような余罪の取調べは,たとえそれが任意に行われたものであったとしても,原則として違法になると考えられる」(刑法雑誌35巻1号)[11]
第4 被疑者の取調べの手続
1 黙秘権の告知
(1) 黙秘権の定義(憲法38条1項)
黙秘権とは,終始沈黙し,または個々の質問に対して供述を拒む権利をいう
*黙秘権についての刑訴の規定
![]() 被疑者の黙秘権 被告人の黙秘権
被疑者の黙秘権 被告人の黙秘権
直接の規定はない!! 311条1項及び291条2項に明文
⇒198条2項から推知
(2) 黙秘権の制度趣旨
ア 自己負罪拒否の観点
黙秘権は,被疑者,被告人の供述の自由を保障するために認められたものである。具体的には,たとえ真に罪を犯した者であっても,自分が有罪になる供述をなすべき義務を法律で負わせることは,人格を尊重する上から許されない。
イ 当事者主義の観点
被告人に黙秘権がなく,供述の義務があるとすれば,結局は否応なしに取調べの客体になってしまうが,現行法上,被告人は刑事訴訟の一方当事者という訴訟法上の地位が与えられているのであるから,当事者主義の観点からも黙秘権があることで,法廷において被告人に供述するべき公法上の義務を課すことはできないとすることで,当事者主義を担保するという説明もあり得る
ウ 自白強要の防止の観点
黙秘権の保障は,勢い自白を強要される危険が出てくる
* 補足意見
黙秘権の制度趣旨に関係して,若干の補足的な見解を述べておきたい。というのも,これまで黙秘権を認めるにしても,憲法38条2項の規定があるために黙秘権があるのは所与の前提とされてしまい,その制度趣旨がどのようなものであるかの解明というのは意外に十分ではなかったように思われる。例えば,争点[第3版]をみてみてもこの点については何ら取り上げられていないところである。
理論的に突き詰めて考えてみると,やはり黙秘権の論拠は38条1項にあるものと考えられる。この規定は,英米法の裁判原則がアメリカ憲法に影響を与え,これを継受したものと考えられることはもはや争いないところであろう。もっとも,すべて刑訴法上の規定を自己負罪拒否特権として説明することができるかというと問題があろう。例えば,証人についても証言拒絶権が認められている(146条)わけであるが,これと被疑者あるいは被告人の黙秘権は異なるものであろうかという問題は理論的に解明する必要があるように思われる。
そこで考えてみるのに,自己負罪拒否を黙秘権の理論的根拠に据えるということになると,被告人に対して供述義務を課すことを禁止するという命題を導くことはできない。なぜなら,証人についても自己負罪拒否特権が認められているわけであるが,それはあくまでも供述義務を前提としているものである。したがって,黙秘権の内容を自己負罪拒否特権に限るということになれば,特段,被告人は証人と異なる扱いをする必要があるということにもならず,例えば,被告人の証人適格も肯定して構わないという結論を導けるものと考えられる。
こうしてみると,黙秘権の論拠としては,自己負罪拒否の観点が中核に据えられていることは疑いがないところというべきであるが,他方,当事者主義の観点から被告人は訴訟の一方当事者としての地位があるのであるから,当事者主義,弾劾主義の下で検察官からのオフェンスに耐えうるディフェンスを行う必要がある。そうすると,証人には自己負罪があっても証言義務があるのに対して,被告人についてはこれは許されないとするのであれば,その理論的根拠は,被告人の訴訟法上の地位によって説明するほかないということになると思われる。しかしながら,その地位によってなぜ供述義務を課すことが許されないかは検討の余地があるように思われる。例えば,公判における取調べの客体となることを防止するための担保とするという見解もあり得る。たしかに,一方当事者が他方当事者あるいは裁判官の判断に対して,自白をしなくてはならないという義務があるとすれば,それは糾問主義といわざるを得ず,むしろ,職権主義の前提がなければ成り立たなくなると思われる。そうだとすれば,このようにいわば制度的に,システマティックに説明してゆくという見解は十分に傾聴に値するものと思われる。異なる視点からの説明としては,被告人の防御上のかけひきを認めるという点が考えられよう。要するに,一方当事者なのであるから,ある程度のかけひきはあって当然で黙秘権というのもかけひきの道具であり,その決定は被告人の自己決定に委ねられればよいという見解をいうものと考えられる。さらに,検察官との能力の差があるから黙っているというのは防御権の観点から当然であるという見解もあり得るものと思われる。
さて,以上の観点から被告人に証人適格が認められないという帰結を理論的に説明することができるかを考えてみるのに,なるほど,被告人に対して当事者の地位があるということであれば,その当事者を証拠と位置付けて供述義務の強制の下で取り調べるというのはおかしいということになると思われる。だが,これは理論的には,そもそも被告人に供述義務を課すことが許されないということを当然の前提とする必要があるわけであるが,憲法38条1項がそこまで要求しているとみるかには疑問がないわけではない。そうしてみると,刑訴法の規定(311条1項,291条2項)によって,「終始沈黙できる」とされて憲法上の自己負罪拒否の観点からの黙秘権が拡張されているということになると思われる。こうしてみると,「終始沈黙できる」という刑訴法の趣旨を達成するためには,供述する義務を被告人に課すことができないということとしなければ,法律レベルで矛盾が生じてしまうということになる。そこで,刑訴法の黙秘権保障の趣旨を尊重して,証人適格を認めないとするのであれば,今度は,刑訴法の黙秘権保障の趣旨が何かが問われる事態となる。
そこで考えてみるのに,刑訴法の黙秘権の趣旨は,自己負罪のみとすることは現実の運用とも合致しないのであるから,やはり不可能というべきであろう。そうだとすれば,いかなる趣旨が新たに包含されるに至ったのであろうかということであろうが,やはり供述の客体とされないことによって当事者的地位を維持させようとする点に趣旨があるものと解されよう。なお,書研によれば,自白の強要防止の趣旨もあるというが,少なくとも弁護人がいる法廷において自白が強要されるということはあり得ない。したがって,この趣旨は,被疑者段階における黙秘権の保障という観点からは格別,公判段階の黙秘権の保障の趣旨として包含されているか否やを考える必要はないと考えられる。
では,次に捜査段階の黙秘権について考えてみよう。198条2項をみれば明らかなように被疑者について黙秘権の実体法上の根拠となる規定は存在しない。そして告知の対象とされているのは,「自己の意思に反して供述をする必要がない」ことである。ところで,かかる規定は従来は,「供述を拒むことができる」とされていたものが昭和28年に改正されたものである。なるほど,改正前においては,供述を拒むことができるのであるから,これは警察の取調べにおける一切の供述と考えるのが素直なように思われる。そうだとすれば,公判段階における終始沈黙と同趣旨に出たものと解してよいはずである。したがって,同様に,取調受忍義務を課すということも認められないということになるというのが帰結であろう。ところが,改正によって文言が改められているところ,この規定は,「自己の意思に反している場合は,供述しなくてもよい」とする趣旨と考えられる。逆にいえば,「被告人の意思に反しない限りは,供述しなくてはならない」という命題を承認することは理論的には可能といえるであろう。しかしながら,だとすれば被疑者段階における黙秘権は,憲法上の自己負罪拒否のレベルとイコールであるといえるかについて考えるのに,被疑者として供述を強要されるのは基本的には罪体に関することと認めてよいはずであるから,まさに自己負罪の趣旨が妥当するということになる。
このような観点からすれば,やはり被告人に対して供述義務を課すことは許されないということになる。なぜなら,たしかに,証人には証言義務があるものの,自己負罪にからむ部分については証言義務が課されていないと解する余地がある。そうすると,自己負罪の部分については供述を強要することはできないということになる。なお,これは被疑者段階であるということで趣旨が妥当しないと解することはできない。
では,取調受忍義務と黙秘権という論点について考えてみよう。ところで,取調受忍義務については,実務サイドはその中身は「取り調べに応じなければならない義務」と定義する見解が多いのに対して,学説は「取調室に対する出頭を義務付けるもの」と定義する見解が有力のように思われるが,いずれも両立しうるのであって,それぞれ検討してみよう。まず,実務サイドの見解についてみるのに,たしかに,法の規定は,「自己の意思」に反しないのであれば,供述を求めることができるのは当然のことといい得る。したがって,被疑者の自己の意思に反しない部分の取調べをするために取り調べをするということを否定すべき理由はない。ところで,問題となるのは,被疑者が特に自己の意思に反するので取り調べ自体を拒否したいと言っている場合ではないかと思われる。理論的には,供述を拒否することができるのは当然のことであるが,進んで取調べそれ自体を拒否することができるかというと問題があるように思われる。特段,取り調べ時に自己の意思によって終始沈黙すればよいのではないかと思われるからである。したがって,取調べを受けることについての義務を課したところでこれが直ちに,自己負罪につながる部分の供述を自己の意思に反して求めるということにはならないと思われる。そうすると,実務サイドの見解も十分承認される余地があるというべきであろう。
これに対して,学説サイドの見解をみても取調室に対しての出頭を問題にしても理論的には大きく変わるものではないと思われる。だが,やはり黙秘を希望しているのにそれを不可能な状態にさせることは問題であるという問題意識に基づいて一歩踏み込んでいるものと考えられよう。その試みには賛同するところがあろう。だが,この見解をもし承認するというのであれば,翻って,被疑者段階の黙秘権の趣旨には,自白の強要防止という視点が入っていなくてはならないように思われる。自白の強要を防止するがために,法は自己の意思に反する供述させることを禁止していると解すれば,被疑者段階の黙秘権には,自白強要防止の観点も入り込むことになる。このように,黙秘権を理解すれば,例えば,もっとラディカルに推してゆけば,取調受忍義務すら否定することもあり得るだろうし,せいぜい取調室への出頭の義務にすぎずその後の取り調べに応じることまでを意味するものではないという帰結に流れやすいように思われる。
こうしてみると,実務サイドは躊躇なく取調受忍義務を認めるのであるが,理論的には,黙秘権の内容を次のように理解しているということになるであろう。すなわち,黙秘権には2つの趣旨があるところ,憲法は自己負罪拒否のみであり,これが被疑者段階にもストレートに妥当する。他方,公判段階では,当事者主義や弾劾主義の観点から被告人の地位が高められる結果,取調の客体とするには躊躇が必要であり,したがって,憲法の趣旨が高められているという理解となろう。このような視座からすれば,取調受忍義務を認めつつ,被告人には証人適格は認めないという,一見すると矛盾するような帰結もまま整合的に説明することができよう。これに対して,取調受忍義務を否定するような白取説の理解はおおむね予測してみると,おそらく「被告人については」憲法38条1項自体がもとより包括的黙秘権を保障しているという前提に立っているように思われる。これは,憲法解釈としては飛躍があるように思われるが,なるほど,まま被告人の供述というのはたいていは自己負罪に関連するのは当然というべきなのであるから,このような飛躍も感情的には理解できるものがあるといえるのであろう。もしこれを前提とすれば,憲法レベルでそのような保障があるのであるから,それが取調段階にも及んでくるということになると思われる。したがって,被疑者は終始沈黙できなくてはならず,さらによく分からないが,自白強要の防止もあるわけだし取調受忍義務なんてとんでもないという発想ではないかと考えられる。次に,東大系の考え方としては,やはり憲法の保障は自己負罪に限られつつ,公判段階では趣旨が拡張されるとみると思われる。そして,公判段階での黙秘権の趣旨と被疑者段階での黙秘権の趣旨は,弾劾主義的捜査観を強調してゆけば同じということになり,取調べの客体とすることを論難して取調受忍義務を否定するという筋があり得るのであろう。
また,被疑者段階の黙秘権は,自白強要防止を含むと解することによって,やはり否定するという方向性も考えられよう。
以上のようにみてくると,黙秘権と取調受忍義務の問題点としては,以下の点を挙げることができるのであろう。すなわち,実務の見解は,供述義務は理論的に課すことができない代わりに,取調受忍義務を持ち出して取り調べを強要することを正当化しようとするが,それは結局黙秘権保障の趣旨を没却するおのと考えられるのであり,自己負罪拒否の実効性をなくすということで憲法レベルの問題点も指摘されうるはずである。また,形式的には被疑者は訴訟の当事者にはいまだなっていないといってもいずれ訴訟の当事者となるのであるから,当事者主義の観点からは,被疑者を取り調べの客体としてしかみない「身柄」と考えるのは誤りであると考えるべきである。さらに,自白の強要があり得るということであるが,憲法ならずとも刑訴法の黙秘権保障の趣旨にも反しているという考え方になるかと思われる。
このように黙秘権についての考え方については文献も少ないところなのであるが,とりあえずは以上のように考えてゆくべきものと考える。
なお,付け加えると,たしかに,被疑者段階における黙秘権の実体的な論拠が規定上ないというは,自白の任意性の保障を与えるという趣旨に他ならないのではないかという見解も出てくるところであろう。すなわち,198条2項からすれば,自白の任意性がない場合にまで供述する必要はないという見解とも考えることができる。そうすると,なるほど,黙秘権の論拠とは実は自白の任意性のためと説明することになろう。そして,ではなぜ自白の任意性がないのかということを考えると,さすがに「黙秘権を中心とする人権擁護のため」と説明するとトートロジーになる。そこで,虚偽排除と将来の違法な取調べ抑止のためという観点からこれを基礎付けるということも理論的に可能なように思われる。つまり,黙秘権とは突き詰めれば,事実認定の誤認を防止し取り調べの適正化を担保するための自白法則の制度的保障という考え方も成り立つように思われる。
このように考えるとき,私見は次のように理解する。まず,憲法38条1項の黙秘権は自己負罪拒否特権であり,基本的には射程距離は刑事裁判に限られるように思われる。したがって,証言拒絶権や公判段階での黙秘権はこの規定の具体化として構わない。そして,後者については,刑事裁判の当事者主義と弾劾主義を担保するために,裁判所において被告人を取り調べの客体とすることのないように,要するに糾問主義に陥らないようにする担保としての趣旨も包含され,そのために供述義務を課してはならないという命題が,公判段階の黙秘権から導くことができるように思われる。
次に,憲法38条1項の保障は捜査段階には及ぶのであろうか。この点については,捜査も刑事裁判の準備であり究極的には有罪となる事項についての取調べをしているのであるから,これについて拒否することができないというのはおかしいという批判があり得るところであろう。しかしながら,捜査がそのまま刑事裁判の準備という一連の位置づけが与えられるかといえば問題のように思われるのであり,憲法38条1項の射程距離として公判段階を超えて,取調べ段階にまでその保障を及ぼしているとみるのは相当ではないというべきであろう。
では,被疑者段階の黙秘権をどのように基礎付けるべきかを考えてみるのに,まず,上記の私見の趣旨からすれば,自己負罪拒否として説明するのは止めた方がよいということになると思われる。では,なぜ黙秘権が保障されるのかということになると,条文は「自己の意思に反して」とするにすぎないのであり,自己の意思に反して行われるとは結局任意性がない場合とイコールと考えてもよいように思われる。そうすると,捜査段階での黙秘権というのは,刑訴法の319条によって保障されていると考えられる「自己の意思に反して供述を強制させることのない自由」を保障するためと考えられる。すなわち,319条で権利が保障されているから,捜査段階における黙秘権の実体規定は存在せず,それゆえ,告知が求められているのにすぎない。そして,319条の制度趣旨については,直接的には,被告人に対して,「自己の意思に反して供述を強制されない自由」を認めることによって,間接的には,虚偽を排除し捜査の適正化を担保するものと考えられよう。これは言い換えれば,新しい人権擁護説であるといえようか。従来の人権擁護説の人権と定義が不明確であるという指摘があったが,結局それは黙秘権の制度趣旨自体がはっきりせずその外延がみえにくかった点に問題があったのではないかと考えられる(私見)。ただし,超少数説となろう。
(3) 黙秘権の告知(198条2項)
ア 198条2項の要請
捜査機関は,被疑者の取調べに際して,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない
イ 黙秘権の不告知
(ア) 憲法違反か
判例は,憲法38条1項は,あらかじめ供述拒否権を告知すべき手続上の義務を定めたものではないから,黙秘権を告知しないでも違憲ではなく,供述の任意性は直ちには失われないとする
(イ) 供述の任意性
直ちに証拠能力が否定されるわけではないが,取調べ期間中,1度も黙秘権・弁護人選任権を告知せず,そのことから自白の任意性に疑いが生じる場合には,供述証拠の証拠能力が否定される(浦和地判平成3年3月25日判タ760号261頁)
* 白取171は,黙秘権の告知は憲法上の要請であるから,告知せず被疑者を取り調べた場合は供述証拠の証拠能力が失われるとする
2 調書の作成(198条3項ないし5項)
3 取調べの適正化
(1) 取調べ方法に関する具体的ルールの必要性
(2) 取調べの可視化
調書作成の現実
(3) 可視化向上のための方策
① 取調記録制度
② ビデオ・DVD録画・テープ録音
[1] 被疑者の承諾なく,警察署へ同行しあるいは取調室に滞留させ,同行・滞留が任意のものでなくなるならば,それは,実質的な逮捕にあたる身体拘束として違法であり,そのような同行後あるいは滞留中の取調べも違法となる(演習64)
[2] 同行後の取調べは,早朝から深夜まで長時間にわたっており,取調べの継続中は,常時捜査官から『滞留の働きかけ』(注・大澤は,承諾があった場合でも働きかけの異常さを考慮すると違法になる場合があるとの枠組みを示す)を受けているに等しく,それが長時間にわたって積み重なれば,意思決定の自由は損なわれやすくなる(演習65)
[3] 判例の理論的正当性に疑問を投げかける見解は,「任意同行後の取調べが任意とされるのは,被疑者が滞留して取調べを受けることを承諾しているからにほかならず,このような被疑者について,そもそも権利・利益の制約を観念することができるのか,問題だから」とする(演習66)。すなわち,比例原則を適用する場合,捜査上の必要性に比例して権利制約が許されるという関係にある。例えば,「捜索に至らない程度の所持品検査」という論点では,対象者の意思に反したプライバシーの利益に対する制約ということが考えられる。これに対して,任意同行後の取調べについては,そもそも人身の自由という重要な利益が問題とされているから,「対象者の意思に反する任意処分」というのが観念することができないという指摘である(酒巻説)。そもそも,任意取調べというのは,「被疑者が滞留して取調べを受けることを承諾している」から行うことができるわけであるからである。このように考えてくると,すでに承諾がある項目について比例原則が規律するというのも妙な話しであるので,承諾があるかという点こそが最も重要な点であるという主張となると解される。
[4] 『取調べの継続』自体から捜査官の働きかけを導き,したがって,被疑者の意思決定の自由に及ぼす影響を考慮することもできる(演習65)
[5] そもそも身体拘束する要件のない者を拘束すること自体が極めて重大な違法と考えられるので法定の拘束時間の超過の如何に関わらず,これに引き続く勾留請求は却下すべきものと解される。
[6] このような供述調書は,憲法・刑事訴訟法の要件(令状主義)に反するおよそ根拠を欠いた違法な身体拘束を直接利用して行われた違法な取調べの結果獲得されたものと考えられるので,証拠排除される。
[7] 酒巻の論旨は,要するに,実質逮捕にあたるか否かという点で違法であると評価すべきであるとする。その理由は,所持品に対するプライバシーと比較して,ここで問題とされている取調べについての法益である人身の自由や自己の意思に反して供述をする必要がないという意思決定の自由がある。これらは,いずれも憲法上の保護を受ける利益であると解される。そして,このような権利に対する比例原則に対応する制約といっても,「承諾のない人身の自由」に対する制約を認めるのは相当ではないし,意思決定の自由は,「そのような意思決定をするか否かの二者択一の問題」であるから,いずれも捜査の必要性が高ければ制約してもよいという「程度」を観念することができないと主張する。そして,もし判例を是認すると一見,二段構えの厳格な判断枠組みを採っていると思われた判例の正体は,本来は,実質逮捕+違法収集証拠排除法則の適用で処理すべき問題を,実質逮捕でなく任意取調べの限界を超えたに過ぎない⇒違法が重大ではない―という形で結局,実質逮捕の範囲を狭めて,しかも証拠排除する範囲まで狭めてしまうという危険が生じると指摘している。
[8] 松尾説は,「出頭・滞留義務」と「取調べを受けなければならない義務」を区別する。そして,198条1項ただし書き反対解釈によって,逮捕・勾留中の被疑者は,出頭・滞留義務という公法上の義務を負うと解する。これは,取調室に行かなければならない義務である。もっとも,だからといって取調べに応じなければならないわけではない。198条1項ただし書きは,出頭拒否と退去について定めたものであるから,出頭・滞留義務以上のことは定めていないわけであるから,取調べを受けなければならない義務というのは条文上「書いていない」ということになる。とすれば,そのような義務は認められないということになる。そして,被疑者には取調べを受けなければならないという義務はないから,被疑者が「もう取調べを受けたくありません」と述べれば,捜査官は取調べを中断しなくてはならないのは,黙秘権保障の見地より当然といえる。もっとも,被疑者には滞留の義務があるわけであるが,取調べができなくなる結果,滞留の義務があってもかかる義務は無意味になる。したがって,捜査官は滞留義務が無意味になる以上,被疑者を帰房させなくてはならないとする。松尾説は,渡辺咲子がいう取調受忍義務を肯定するように見えるので論旨を正解しない者が多く注意が必要である。弁護の立場からも,最大判平成11年3月24日民集53巻3号514頁が出された以上,松尾説は無視できない。
[9] この点,法教290号78頁について検討する。
まず,酒巻は,「事件単位の原則を及ぼそうとする議論は,逮捕・勾留がそれを直接利用した被疑者取調べをも目的とする法制度であることを論理的前提としなければ成り立たない」とする。たしかに,逮捕・勾留の目的として,取調べは含まれない。しかしながら,酒巻のいう「目的」とは何を指すかはよく分からない。取調受忍義務について出頭・滞留義務を課すものだとすれば,その義務を被疑者が負うのは,逮捕・勾留の「直接の効果」として負うものである。そうだとすれば,「直接の目的」かどうかという観点から事件単位の原則の導入の肯否を画するのは疑問である。むしろ,逮捕・勾留の直接の効果であるかが最も重要なポイントとなるのではないか。そうすると,逮捕・勾留の目的に取調べが含まれるかは措くとしても,逮捕・勾留の効果として,出頭・滞留義務が生じるので,事件単位の原則を導入することには疑問はないと思える。酒巻は,捜査構造論と逮捕・勾留の効果を混同している。したがって,酒巻が論理的前提と主張するものは,突き詰めると,本当に論理的前提であるのか疑問がある。
次に,酒巻は,「事件単位の原則の規律が働くのは,身体拘束処分それ自体である。取調べは,身体拘束処分とは法的に別個独立」とも主張する。たしかに,取調べを任意処分と解するのであれば,事件単位の原則を導入することはできない。しかしながら,取調べは198条1項ただし書き反対解釈により強制処分と解するのが相当であるから,逮捕・勾留という強制処分の効果の一つであるから,身体拘束処分と取調べは別個ではなく,同一ないし密接な関連性を有する。したがって,取調べを強制処分と解すると,身体拘束処分と取調べは連続性が生じるので,身体拘束処分を法的に別個独立ということにはならないのではないか。
次に,酒巻は松尾説を引用しつつ,木谷説は,「身体拘束の根拠とされた被疑事実について取調べ受忍義務を肯定することに帰着する点で全面的に支持するわけにはゆかない」とする。しかし,松尾説を前提にすれば,出頭・滞留義務と取調受忍義務は区別できるのではなかったのであろうか。取調受忍義務を否定しても,出頭・滞留義務を認め,それ故に,取調べは強制処分であり,事件単位の原則を導入できるというのが,むしろ,松尾説からの帰結となるのではないか。
さらに,私見が疑問なのは,酒巻は取調べ受忍義務では松尾説が妥当と思われる指摘をしつつも,余罪取調べになると事件単位の原則の導入を許しやすい松尾説はどこかへ飛んで行き,突然,取調受忍義務を否定する平野説が前提になる点で疑問である。
そもそも,酒巻は,取調べ受忍義務を否定するという平野説のユートピアの理想にとりつかれて,まともな取調べに対する法的規律を考えなかったわけである。その結果,違法な別件逮捕及び余罪取調べないし誤判事案が横行することになったという社会的実態がある。そうすると,酒巻の見解は,まさに現実を無視した理想論にすぎないのではないかとの疑問が生じる。結局,平野説を前提に「余罪取調べはまったく自由」というのが論理的な帰結であるというのであれば,帰結が不当と考えられる。「正しく間違えている」のではないかとの疑問を生じる。この論点では,後に触れる川出説もまともな取調べに対する規律という側面は有していない。したがって,鈴木説の示唆を受けた木谷説がもっともプラクティスに即している。この点,寺崎148は,「『事件単位の原則は身体拘束にかかわる原則だ』と制限的に解する根拠は乏しい・・・取調べ受忍義務を否定しさえすれば,捜査機関の取調を控制できるという考えは幻想である・・・刑訴法が捜査機関の取調べを禁じていないことを率直に認めたうえで,取調べができる範囲を限定しなければならない。その基準は,まさしく事件単位の原則に求めることができる」と指摘し,さらに,このことと,取調受忍義務を認めないこと及び弾劾的捜査観とは矛盾しないとも主張する。酒巻の見解は,「純理論的な観点にこだわる余り,また,理想を負うのに急な余りに,実務における・・・現実的な工夫に対し冷淡な対応しか示してこなかった・・・はなはだ遺憾な」見解と評価すべきものである(木谷明『刑事裁判の心』63頁(2004年,法律文化社))
[10] この見解は,別件逮捕・勾留の一つの見解として機能するものといえるのであり,興味深いものといえる。すなわち,身体拘束期間の制度趣旨は,被疑者の罪証隠滅や逃走のおそれを排除した状況の下で起訴・不起訴の判断に向けた捜査を行う点であると解される。とすれば,XがA罪について逮捕されているにもかかわらず,B罪の余罪取調べばかりされてしまうとA罪についての捜査は遅滞することになる。そうすると,「B罪についての余罪取調べが行われなかったとすれば,A罪についてより迅速に起訴・不起訴の判断ができる」と解される場合は,違法な身体拘束下の取調べは違法になると解する見解である。ただし,A罪についての起訴・不起訴の判断が,余罪取調べがなければより迅速に出来たと判断しうるのはどのような場合であるか分からないし,しかも,被疑事実と余罪に密接関連性があったり,迅速処理の可能性もあるというような事情からすれば,これが余罪取調べを統制する効果をどの程度有するかというのは疑問に思えるところである。ただ,川出説は,基本的には,余罪取調べではなく,別件逮捕について,本件基準説を前提とする実体喪失説で勝負するという側面が強く,ここでの議論はそこでの判断をこぼれ落ちたものを違法にするという機能にすぎないとすれば,首肯できないこともないということはできよう。演習98は,「逮捕・勾留の目的について,被疑者の取調べか,将来の公判の準備か,という問題設定に囚われ過ぎていた」として,「捜査と無関係に逃亡・罪証隠滅を防止する処分と割り切ってしまうことにも無理があった」とする。これは,捜査の進展次第では,実質的に逃亡や罪証を隠滅するおそれがなくなることがあり得るとの指摘と解される。新しい見解は,これらの点に反省を加え,従来とは異なる視点から余罪取調べの限界を導くものとして注目される。具体的には,窃盗の事実で勾留中のXを殺人罪で取り調べることができるかについて,窃盗の事案解明に資するところのない,殺人の取調べが行われることによって,窃盗の捜査が中断されるならば,窃盗の取調べだけを実施した場合よりも勾留期間を長期化させ,被疑者に無用の不利益を負わせることになる以上,原則として殺人罪の取調べの実施は許されないと考えることができる(演習102)。
[11] 川出説は,被疑者の利益侵害という観点から,余罪取調べの限界を基礎付けようとしているわけであり,基本的には別件逮捕・勾留の新しい考え方とパラレルといえる。すなわち,新しい考え方は,別件逮捕の違法論拠として,令状主義を潜脱するという点を挙げている。そして,捜査官に主観的な意図があるだけでは,結局,被疑者は少なくとも客観的に「別件」の捜査を受けている以上は利益侵害はないと考えているものと思われる。そうだとすれば,別件逮捕が違法になるのは,「客観的」に本件の取調べを受けたとき-と考えていくことができる。これを余罪取調べについても応用したものといえよう。川出は,余罪の取調べが行われることにより,被疑者の身体拘束期間が長期化するという点に被疑者の利益侵害があると位置づけ,その観点から余罪取調べの限界も画そうという考え方であり,結果無価値的といえよう。