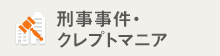審判の対象
第18編 審判の対象
第1 審判対象論
1 論争の背景
(1) 訴因と公訴事実
256条3項,312条1項
(2) 旧法時代
検察官は,「犯罪事実」を起訴状に記載
裁判官は,「事件の同一性」が保たれている限り,職権で真実を探究
審判の対象は,「犯罪事実」の記載が指し示そうとしている事件,すなわち,「公訴事実」
(3) 現行法
旧法以来の「公訴事実」の概念+英米法に由来する「訴因」という概念
「訴因」は,「公訴事実の同一性」が認められる範囲で変更可能
⇒ 裁判所が訴因変更なしに訴因外の事実を認定することは許されない
(4) 突き詰めると
旧法と連続的な職権主義的な理解とするのか,新たな当事者主義的理解か
2 論争の展開
(1) 公訴事実対象説
ア 原型
審判の対象は,伝統的ない意味の公訴事実
訴因は,被告人の防御のため,公訴事実の法律的構成を指す
⇒ 訴因は,不意打ち防止のためにあり,審判対象画定という性格は薄く!
イ 折衷説(団藤)
訴因は,現実的・潜在的審判対象,公訴事実は観念的・潜在的審判対象
(2) 訴因対象説
検察官が犯罪事実を主張し,裁判所はその主張の当否を公平中立に吟味
審判の対象は検察官の主張する具体的事実たる訴因
⇒ 不意打ちだけでなく,訴因は審判対象画定の見地からも重要!![1]
第2 訴因の変更
1 意義
(1) 定義
訴因変更とは,検察官の請求により,起訴状記載の訴因を追加,撤回,変更をすることをいう(312条1項)
(2) 典型例
検察官は,Xが,盗難被害届記載の甲所有の宝石を,被害直後の時間帯に甲宅に近接した路上において所持していたことを示す証拠に基づいて,Xを当該日時ころ甲所有の宝石を窃取したという事実で起訴した。ところが,審理の過程で,捜査段階では黙秘していたXが,起訴状記載の日時頃に,甲宅に近接した路上で,氏名不詳者Yから,当該宝石を盗品であると思いながら買い受けた旨自白し,裁判所はその自白を信用できると考え,他の証拠をも勘案して,宝石窃取の事実ではなく,盗品である宝石買受けの事実について確信の心証を得た
(3) あり得る制度設計(立法政策論)
① 検察官の主張の変更は許さないという立法政策
⇒ 判決は無罪となるが,Xを盗品有償譲受罪で再び起訴することはできる
② 審判対象の同一性が損なわれない限り,裁判所が自らの心証に従って,検察官の主張とは異なる事実を認定することを許容する方式(旧刑訴法)
③ 検察官が審判対象の自己同一性(公訴事実の同一性)が害されない限度で,1回の訴訟手続の過程において,主張する事実の変更を認める方式(現行法)
(4) 訴因変更制度の存在理由
① 訴訟は流動的
② 訴因との間に食い違いが生じる可能性
③ 1回の手続で終わらせる方が合理的
(5) 裁判所の対応
① 検察官が訴因変更をしない場合
⇒ 裁判所は無罪判決をする
∵ 裁判所が審判の請求を受けているのは,窃盗の具体的事実であり,これに拘束されて存否を判断できるにとどまるから
② 検察官が訴因変更をする場合
⇒ 裁判所は自らの心証に合わせた有罪の事実認定ができる
(6) 追加・撤回・変更の意義(検察121)
ア 訴因の追加
訴因の追加とは,予備的若しくは択一的関係に立つ訴因,又は牽連関係若しくは観念的競合の関係に立つ訴因を新たに加えることをいう
* 実務では,当初の訴因を維持しながら予備的訴因を追加するケースが多い
イ 訴因の撤回
訴因の撤回とは,このような関係に立つ訴因中,一部のものを撤回することをいう
ウ (狭義の)訴因の変更
訴因の変更とは,ある訴因を撤回すると同時にこれに替えて新たな訴因を掲げることをいう
* 窃盗+住居侵入の訴因⇒窃盗の訴因(牽連犯で一罪)[4]
(7) 補足意見
講義の中で森下弁護士は,「今後は訴因変更が問題となることはほとんどなくなる」と述べられていた。なるほど,公判前整理手続において,訴因は明確にすることが求められ,この時点で明確ではない訴因は変更を余儀なくされるということになると思われる。公判前整理手続では攻撃対象をはっきりさせられてしまうので,上記(4)で挙げられている①と②の要素がほぼデリートされてしまう。計画審理が徹底されると訴訟から流動的な要素がなくなり訴因との間に予想外の食い違いが生じるということはなくなるわけである。そうだとすれば,立法政策は上記(3)で述べたように,日本では③が採用されているわけであるが,運用上は今後①に近い運用実態になってゆくのではないかと予測される。
第3 訴因変更の要否
1 問題の所在
裁判所の立場から見て,証拠調べの結果,認定しようとする事実とその段階で主張されている訴因との間にずれがある場合に,どの程度のくい違いであれば訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる事実認定をしてよいか
2 従前の議論―審判対象論と訴因変更の要否
(1) 審判対象論との関係
公訴事実対象説⇒法律説(罰条同一説,法律構成説)
訴因対象説⇒事実記載説
(2) 各学説の整理
ア 罰条同一説
罰条同一説とは,訴因とは,社会的事実としての犯罪事実を各罰条にあてはめて,法律的に構成した事実であるから,訴因の同一性は各罰条の構成要件的定型を基準とするという見解をいう
⇒ 審理の過程で,各行為の態様・客体などに差異が生じても,依然として同一罰条に該当すると認められれば,訴因を変更する必要はない
× 作為による殺人で起訴されたが,不作為による殺人であるという認定をしても罰条は同じ(刑法199条)であるから,訴因変更は不要であることになるが,作為でないことを立証してきた被告人にとって,訴因変更なしに不作為による殺人が認定されるのは,不意打ちとなる
イ 法律構成説
法律構成説とは,構成要件そのものが問題ではなく,公訴事実の法律構成の仕方に重要な意味があると解する見解をいう
ウ 事実記載説
事実記載説とは,被告人の防御に実質的に不利益を与えるような,具体的な事実(犯行の態様,日時・場所など)の変動があれば,訴因の同一性は害されるとする見解をいう
⇒ 事実が少しでも変われば,そのたびに訴因変更を求めるのは実際的ではないので,事実の「重要な」,「実質的な」側面にずれが生じているかが基準
(3) 従来の判例の整理
ア 最決昭和40年12月24日刑集19巻9号827頁
法律構成に変化がなくても事実の重要なずれがある場合,訴因変更が必要!
イ 最判昭和28年5月8日刑集7巻5号965頁
法律構成・構成要件や適用罰条が異なることになっても,事実に違いがなければ訴因変更を要しない
* 従来の判例も「事実の差異」に着目している
3 事実記載説における要否の基準
(1) 問題の所在
実質的ないし重要なずれ,差異とは,どのように判断されるべきか
(2) 従来の学説
⇒ 被告人の防御に不利益を与えるか否か[5]
ア 抽象的防御説
抽象的防御説とは,訴因事実と認定事実とのずれを抽象的・一般的な観点から判断するという見解をいう
イ 具体的防御説
具体的防御説とは,防御上の不利益は,実際にとられた被告人側の防御方法等現実の審理の経過を踏まえて,個別的・具体的に判断するという見解をいう
* 二段構えの防御説[6]
ウ 批判
×① 検察官による訴因の設定構成権限及び訴因の第一次的機能は,裁判所に対して,審判範囲を示すという点にある。そうだとすると,訴因変更の要否すなわち検察官の設定した訴因の裁判所の審判に対する拘束力の問題を検討するのに,専ら被告人の防御上の不利益の観点に着目するのは不整合
×② 審判対象の画定という問題の核心を被告人の防御に対する不利益という解釈の余地の広い基準の中に埋没させてしまうことは,訴因変更の要否に関する判断の明確化を阻害してきた
(3) 新しい学説
ア 筋の流れ
訴因の第一次的機能は,裁判所に対し審理判決の対象たる「罪となるべき事実」を画定し識別特定すること
⇒ 訴因記載の拘束力,すなわち,訴因変更の要否も第一次的には,審判対象画定の見地から限界を考察すべき
イ 基準
事実の差異が審判の対象の画定に必要不可欠な事項・部分であるかどうか
∵ 訴因変更が必要かは,訴因の機能である「罪となるべき事実」の画定という観点から判断すべき
ウ 具体的な説明
訴因の記載は,裁判所の審判対象である「罪となるべき事実」の特定・明示に必要不可欠な部分とそれ以外の要素から成る
* 2段階の事実
| 識別に必要な事実 | 識別に必ずしも必要でない事実 |
| この事実の差異は,審判対象としての具体的内容を変動させ,検察官が当初設定構成した罪となるべき事実とは違った事実となる | 証拠上証明される事実との差異が生じたとしても原則として訴因変更は不要であり,訴因と異なる事実認定をすることができる |
| 被告人の防御上の不利益の有無にかかわらず,訴因変更が不可欠
∵ 裁判所は,検察官の訴因設定構成権限を害して審判対象を逸脱した事実認定をしたことになるから |
例えば,被害物件が増大してその価額によっては量刑に影響があり得るものの,罪となるべき事実の画定に必要不可欠な部分に重大な差異が生じているとはいえない |
4 最決平成13年4月11日刑集55巻3号127頁
(1) 事案の説明
罰条:殺人の共同正犯
訴因:「被告人は,Yと共謀の上,・・・被告人が・・・Aを殺害した」
認定:「被告人は,Yと共謀の上,・・・Y又は被告人あるいはその両名において・・・Aを殺害した」
(2) 問題の所在
訴因において殺人の実行行為者が被告人と明示されていたにもかかわらず,訴因変更手続を経ることなく,判決において,「A又は被告人あるいはその両名において」という認定がなされたことの適法性
(3) 判旨
第1審の判示は,殺害の日時・場所・方法が概括的なものであるほか,実行行為者が『X又はY又はXあるいはその両名』という択一的なものであるにとどまるが,その事件がXとYの2名の共謀による犯行であるというのであるから,この程度の判示であっても,殺人罪の構成要件に該当すべき具体的事実を,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにしているものというべきであって,罪となるべき事実の判示として不十分とはいえない
そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべぎ事実の特定に欠けるものとはいえないから,訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見地からは,訴囚変更が必要となるとはいえない。とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴囚変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない
本件では,共謀の成立の点ではXの主張を排斥したものの,実行行為者についてはXの主張を一部容れ,検察官の主張したXのみが実行行為者である旨を認定するに足りないとし,その結果,実行行為者がYのみである可能性を含む択
一的認定をするにとどめたもので,その認定はXに不意打ちを与えるものではなく,また訴因に比べてXにとってより不利益なものとはいえないから,その認定に当たって訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない
(4) 木谷教授の批判(適正化136)
木谷教授は,平成13年判例について,理論的には注目できるとしても,その具体的な適用は不意打ちになっており不当であると批判している。
まず,本件の証拠構造をみると,本件では,A以外にBという共犯者がおり,その共犯者供述の信用性が争われている。すなわち,Bは,PSにおいて,「被告人と殺人の共謀をしましたが,私はVを被告人に引き渡した段階で帰宅してしまいました。したがって,自分は殺害現場には行っておらず,Vを殺したのはAです」と供述しているのであり,検察官はこの共犯者供述に依拠して,Aが,殺人の実行共同正犯であるとの訴因を構成したのである。
このような証拠構造の場合は,弁護人は,Bの証言,具体的には,「BがAにVを引き渡していないこと」を主張して,B証言を突き崩すことができれば,実務上は,Aは殺人の実行共同正犯とされる可能性はなくなるし,共謀共同正犯に関しても,検察官立証の要であるBの証言が信用できないということになれば,共謀の事前防止についても疑問符がついて,結局,共謀共同正犯についても証明不十分となる可能性があると考えられる。
ところが,裁判所は,B証言は信用できないとしつつ,三者択一の事実認定をして,間接事実から総合考慮して事前共謀を認定してしまったということになる。そうすると,被告人の側は,事前共謀に関する検察官の主張を前提としつつ,「B証言が全面的に崩れても,その余の証拠だけで共謀が認定されるという事態を予測して防御せよ」と求めるのは酷であり,結局,被告人に不意打ちがあったと非難している。
そして,木谷教授は,裁判所は,検察官に対して,B証言以外の証拠により,共謀認定の根拠となる間接事実を明確に主張させ,その事実事態及びこれらを総合して共謀を認定できるかどうかについても被告人に防御の機会を与えるべきであったと非難している
5 判例の検討―2段階の基準
(1) 訴因の記載として不可欠な事項
⇒ 審判対象の画定の見地から訴因変更必要
* 裁判所が認定しようとする事実が,検察官が訴因として設定した審判対象の範囲を逸脱しないかを基準に判断する
ア 訴因の機能と訴因変更の要否の基準
法律に直接の定めがない以上,その基準は,訴因変更の趣旨を踏まえつつ,訴因の果たすべき機能から導いてゆく
⇒ 訴因対象説からは,審判の対象という側面における当事者主義を示す裁判所に対し審判の範囲を示す機能の方が重要というべき
イ 審判対象画定の見地から訴因変更が必要とされる場合
判例の立場によれば,審判対象画定の見地からの訴因変更の要否は,訴因の特定の程度に関する識別説の規範により判断すればよいので,訴因変更の要否には明確な線引きが可能
(2) 訴因の記載として不可欠ではないが一般的に防御に重要な事項
⇒ 原則として訴因変更が必要。審理の経過を考慮した例外
ア 判例は防御の利益を軽視したのか
● 本決定は,一般的に被告人の防御に重要な事項について,原則として訴因変更手続が必要であるとしつつ,そこに例外を認めている
⇒ 具体的防御説による抽象的防御説の侵食を許し,防御の利益を軽視!!
× 審判対象の画定という見地も,防御の利益の保護と無関係ではない
○ むしろ,従来よりも防御の利益に手厚い配慮をしたもの
イ 訴因変更が必要な理由と審理の経過を考慮することの是非
○ 審理の経過を考慮に入れるのは正当
∵① 第二段階の訴因変更は,訴因の拘束力に起因するものではなく,訴因固有の機能に基づくものではない
⇒ 第二段階の訴因変更は,一般的な争点明確化=不意打ち防止の要請が訴因の記載にもあてはめる結果,訴因として拘束力がない事項に訴因変更が要求される場面
② 争点についての十分な攻撃防御機会の確保を目的とする以上,その目的が果たされる以上,およそ一律に例外を許さないものではない
* 例えば,傷害の事案で傷害の結果として,「加療3週間を要する左上腕部切創の傷害」と記載されている場合,左上腕部の切創は,傷害という構成要件的結果に該当する具体的事実となるので,罪となるべき事実それ自体ということになる。したがって,訴因の記載として不可欠であるので訴因変更が必要となる。これに対して,加療期間は,傷害の程度に関する犯情事実にすぎず罪となるべき事実それ自体ではないので。訴因変更はいらない
⇒ どの事実が訴因の記載として不可欠であるかは,犯罪ごとの構成要件やそれ以外の成立要件を理解していないと区別できない(読本Ⅰ103)
(1) 定義
縮小認定とは,訴因事実αが事実βを包み込む関係にある場合に,事実βを認定することをいう
(2) 従来の議論
従前の議論では,縮小認定の理論の根拠は,「大」なる訴因に関する防御が尽くされていれば,これに包摂されるより,「小」さな事実を認定しても,その「小」さな訴因は黙示的・予備的に主張されていたともいえるし,原則として被告人の防御の利益を特に害することにはならない
(3) 縮小認定でも不意打ちになる場合(福岡高判平成20年4月22日)
ア 事案
1審の裁判所は,殺人の共同正犯の訴因に対し,殺人の幇助犯の犯罪事実を認定したものである。この点,弁護人は,もし,1審の裁判所が,殺人の幇助犯の成否について弁護人に防御の機会を与えたのであれば,弁護人としては,被告人から,その点を踏まえた供述を得ることができていたもので,その結果,確実に無罪が言い渡されていたはずである,そうであるのに,1審の裁判所が,訴因変更の手続を踏むことなく,殺人の幇助犯の成立を認めたのは,著しい不意打ちであり,防御権の侵害であるといわざるを得ず,訴訟手続の法令違反がある,と主張して控訴したものである
イ 判旨
1審の審理においては,①事前共謀の成否,②事前共謀の解消の有無,③被告人が被害者殺害の実行行為に及んだか否かが争点となり,そのため,検察官及び弁護人の主張からも明らかなとおり,当事者は,被害者殺害までにされたbと被告人との間の会話内容や被告人のbに対する協力内容,さらには被害者の殺害状況,特に被告人が実行したのか否かという点に関して,攻防を繰り広げていたものである。
一般に,共同正犯の訴因に対し,訴因変更の手続を経ることなく幇助犯を認定することは,いわゆる縮小認定として許容されることがある。しかしながら,これまでみたとおり,1審での当事者の攻防は,被告人に関していえば,もっぱら,被害者殺害の場面を含めそれまでの被告人の有形的・物理的関与を巡って行われたと評価することができる。
これに対し,1審の裁判所が認定した犯罪事実は,被告人が,被害者殺害後の事後処理等についてbに協力してもよいと考えており,bも,それに期待していたというもので,黙示の無形的・心理的幇助である。そうだとすれば,両者は質的にかなり異なる。このような場合,被告人の防御の対象も,当然に異なってくる。しかし1審においては,この点について訴因変更の手続がとられていないことはもちろん,明示にも黙示にも争点となっていなかった。そのため,4回の公判期日にわたって行われた被告人に対する質問において,弁護人だけでなく,検察官や裁判所も,共謀が解消した後,なお被害者殺害後の事後処理等の協力の意思があったか否かなどに関して,被告人に対し,まったく質問していない。そうであるのに,1審の裁判所が無形的・心理的幇助犯の成立を認めたのは,被告人の防御が尽くされないままされた不意打ちの認定であるといわざるを得ない。
7 新しい議論
(1) 審判対象画定の見地
まず,審判対象画定の見地から訴因変更が必要となるのかが問題となる。この点,縮小認定をする場合とは,当初の検察官主張事実に対して一部消極の判断をするのであり,検察官の主張の枠外にある別個固有の事実を認定するわけではない。そうだとすれば,縮小認定される犯罪事実は,当初から検察官により,黙示的・予備的に併せ主張されていた犯罪事実と考えることができる。このように考えると,縮小認定とは,訴因の記載とは異なる事実認定の問題ではなく,訴因の記載どおりの認定の一態様
⇒ 一般には,審判対象画定の見地から,検察官の設定構成した当初の訴因の拘束力と訴追の意図を逸脱したものではないから,訴因変更はいらない
(2) 争点明確化すなわち不意打ち防止の見地
抽象的な防御は害されないが,審理の具体的経過にかんがみ,訴因に含まれる別の犯罪事実を争点として顕在化し,具体的な防御の機会を付与すべき場面がないとはいえない(!)
8 訴因逸脱認定の効果
不告不理原則違反(378条3号)か
(1) 従来の議論
公訴事実対象説⇒3号にあたらない
訴因対象説⇒3号にあたる
* 公訴事実対象説からすれば,訴因を逸脱しているとしても,結局,審判の対象(=公訴事実)を逸脱していないのであれば,単に,訴訟手続に違反があったにすぎず,3号にはあたらない
(2) 平成13年決定以降
罪となるべき事実の特定に不可欠な事項に関する場合
⇒ 不告不理原則違反となるので3号にあたる
一般的に防御に重要な事項に関する場合
⇒ 争点を明確化し防御を尽くさせるという趣旨にすぎないので手続違反にすぎないので3号にはあたらない
第4 訴因変更の可否
1 議論の前提
(1) 公訴事実の同一性を欠く場合
⇒ 別訴によるべき
(2) 公訴事実の同一性を欠かない場合
⇒ 当該訴訟手続内で訴因変更により刑罰権を実現すべき
* 別訴はできない(二重起訴の禁止⇒338条3号・339条1項5号,一事不再理効⇒337条1号)
(3) 312条1項の制度趣旨
「公訴事実の同一性」という訴因変更の限界を画すると共に,二重起訴の禁止と一事不再理の効力が及ぶ範囲を画定する点にある
⇒ 「公訴事実の同一性」は,刑事手続による一つの刑罰権の具体的実現に際して,別訴で2つ以上の有罪判決が併存し,二重処罰の実質が生じるのを回避するための道具概念
∵ 刑事手続の目的は,1つの刑罰権の存在を確認するという点にあるので,別訴が併存し2つ以上の有罪判決が重複して生じる可能性があるとすれば,二重処罰となり不都合であることはいうまでもない。そこで,実質的な二重処罰,すなわち,1つの刑罰権の存在を確認するために2つ以上の訴訟が併存しないようにするためには,「そのような可能性を生じる訴因」を別訴で主張すること自体を許さないとすべき
⇒ 併存すれば二重処罰の実質を持つような両立し得ない関係にある訴因の変更により処理を図ることが要請される
2 問題の所在
検察官から訴因変更請求がなされても,「公訴事実の同一性」が害される場合には,裁判所はこれを許さないことができる。そこで,『公訴事実の同一性』とは何を意味するかが問題
3 公訴事実の同一性
『公訴事実の同一性』とは,訴因と訴因とが1回の刑事手続内においてどちらか一方で一度だけ処罰すれば足りる両立し得ない関係にあり,別訴により2つ以上の有罪判決が併存すれば二重処罰の実質を生じるような場合の訴因間の関係をいう
(1) 公訴事実の単一性
ア 定義
両訴因に記載されている犯罪事実が実体法上一罪と扱われる関係にあると認められる場合をいう
イ 典型例
窃盗罪の訴因を同一機会における住居侵入罪・窃盗罪の訴因に変更
[*検討課題 公訴事実の同一性と単一性の区別は必要か]
1 同一性と単一性の区別
「単一性は事件の幅の問題であるのに対して,同一性は事件のずれの問題」
(1) 旧法下での役割
旧法下では,審判の対象は公訴事実であり,裁判所は,起訴状の記載から漏れた部分も含めてその全体について審判する権限と責務(公訴不可分の原則)
⇒ 単一性という概念は,裁判所の審判対象を具体的に確定する役割及び事件の数を数える単位として機能
(2) 新法下での役割
ア 伝統的な理解の放棄
訴因対象説を採る限り,公訴事実という概念を実在的にとらえる必然性は失われて,「公訴事実の同一性」は社会的な事実などの実体を伴う概念ではなく,単なる訴因変更の限界を画する機能概念に変化した
⇒ 審判の対象は訴因であるので,「単一性(=公訴事実の同一性)がある限度で訴訟係属していた」という説明をする余地はなくなった
イ 平野博士の見解
(ア) 単一性は訴因変更の場面でも問題となること
「択一的又は予備的訴因の場合には,空間的にも同一性が問題となるが,初めから1個の犯罪事実の一部が訴因とされた場合には,訴因の変更によって,単一性も時間的に変化する」
⇒ 平野博士は,「単一性=空間的,同一性=時間的」という区別はできないことを明らかにされる
* 時間的前後における事実のずれの問題を扱う「訴因変更」では,単一性もその許容範囲を画する働きをするとされる
(イ) 両概念の区別
「同一性とは,両訴因が両立しえない関係であり,単一性は両立しうる場合の関係である」
⇒ 両立しない訴因が「基本的部分」で重なり合う場合に同一性が認められ,両立する訴因が1個の犯罪(1罪)である場合に単一性が認められるという
(ウ) 評価
平野博士の見解は,公訴事実対象説の下でしか成り立たない概念である「単一性」という概念を,訴因対象説の下で新たな位置づけを与えて再構成したものと解される。すなわち,平野博士の見解では,①「併合罪の関係にある訴因の間では訴因変更は許されない」,②1罪の関係にある訴因の間では訴因変更を許す―という2つの説明を「単一性」という概念の中に新たに織り込んだもの
∵ 公訴事実対象説における「単一性」は審判対象を具体的に確定するという機能を有していた。そうすると,審判の対象が訴因となる場合,訴因は審判対象を確定するという機能を有するということになるところ,その概念は,訴因変更の限界を画する概念として利用可能であるということで,いわば,「単一性」の概念を流用したものと解せられる
2 単一性解消論
(1) 批判論
ア 田宮博士の見解
「単一性は,実体刑法上の罪数の問題であり,訴訟法に固有の問題としては,訴訟の前後の関係たる狭義の同一性のみが残る」
イ 松尾教授の見解
「公訴不可分の原則と表裏一体の関係で生成した単一性の概念は,旧刑訴までの職権主義的な訴訟法学の所産にすぎず,公訴不可分の原則が妥当しなくなった現行法では,単一性概念とも訣別する必要がある」
(2) 批判論の処理
事例
住居侵入の訴因を住居侵入窃盗に変更する場合
⇒ 一罪であることを理由に直ちに訴因の変更が許されるとするのではなく,一罪の訴因と一罪の訴因との間には,「狭義の同一性」があることが要件
* 従来は,単一性が認められると直ちに訴因変更が認められるという関係にあったが,この思考の下では,「一罪性が認められても,狭義の同一性が認められない故に,訴因変更が許容されない」という部分を認めてるという点に積極的意義がある
3 「単一性」概念の再々構成の試み(大澤裕「公訴事実の同一性と単一性」法教270号60頁)
● 実体的な刑罰権の一個性から直接に,一罪の関係にある訴因の間における変更の許容性を導くには無理がある
∵ 旧法下では,裁判所が起訴状記載の事実が一罪の一部にすぎないことを発見した場合に,その全部について判決するための説明に使われたのに対して,審判対象が訴因となり,その設定は検察官に委ねられることになった現行法では,実体的な刑罰権の一個性から一罪の訴訟上の不可分性を主張することは困難
× 刑罰権の一個性に根拠を置きつつ,「一罪に対する別訴は許されない」と説けば,審判対象の設定権限が検察官にあることと矛盾しないというべき
○ 現行法においても,訴因が一罪の関係にある場合(=単一性が認められる場合)について,「公訴事実の同一性」を肯定し,訴因変更を許容すべき理由はあると解すべき
∵① 一罪に対する二個以上の訴因が別々に審判されれば,一罪に対して二個以上の有罪判決がなされる可能性がある。これを回避するためには,「一罪に対しては二個以上の審判そのものを許さない」という命題を承認することである。そして,338条3号の趣旨には,矛盾裁判の回避が含まれるものと解される
⇒ 一罪に対する二個以上の有罪判決という実体法的に見て整合性に欠ける裁判を回避するために,訴訟法上,一罪に対する別訴をそれ自体として許さないのは合理的
② 現行法は,「公訴事実の同一性」を害しない範囲で訴因の変更を許しており,反面,その限度で二重起訴として別訴を排斥している。そうだとすれば,「別訴が許されない範囲で訴因の変更は許容されている」という命題を承認される。そうすると,「一罪について別訴を許さない」とするならば,論理的には,「一罪ならば訴因変更は許容される」という命題を承認することになるはずである
* 単一性の範囲で訴因変更が認められる論拠は,旧法下では実体的な刑罰権の一個性から導かれていたが,現行法下では,「矛盾裁判の回避」という訴訟法上の考慮を反映したものと解すべき[9]
4 同一性・単一性統合論
(1) 問題提起
単一性という概念を再々構成するにしても,狭義の同一性と切り離して論じるかはまた別個の問題となる
(2) 香城説
「公訴事実の同一性が認められる範囲とは,両訴因が科刑上又は実体上一罪となる場合及び両訴因が同一の社会的事実に対する評価としていずれか一方しか成立しない関係にある場合であり,前者が単一性,後者が同一性の問題として説明されてきたものであるが,両訴因が別罪として両立するか否かという同じ判断基準により判別されるとすれば,単一性の場合を同一性の場合と区別して論ずべき必然性はない」
⇒ 単一性解消論とは,「単一性の基準と同一性の基準は質的に異なるから,両
者に通じる統一的な基準はない」という考えを前提としていたのに対して,統合論は,「両訴因が別罪として両立するか」という観点から統一的な説明を加えており,従来の前提を覆している!
* 一罪にある訴因はどのみち,別個独立に処罰され得ないという意味では非両立と説明することも可能
(3) 検討
ア 香城説の問題点
たしかに,香城説の主張は,一つの基準で統一的な説明を加えており,錯綜した議論の簡明化に資する。しかし,「非両立」という概念自体がブラック・ボックス化を招いている。というのも,香城説の主張の中には,①事実として両立しない場合と②法的評価として両立しない場合―が混在している。そこで,①及び②の非両立という概念は,果たして,同じ意味であるかが問われなければならない
イ 検討
この点,上記①の事実として両立しないことの真の意味とは,「基本的事実関係の隣接関係が認められるうえでの非両立」と解する必要がある。というのも,事実関係が非両立であったとしても,日時,場所,犯行態様が異なる場合は,基本的事実関係の同一性を認める余地はない。けだし,もとより,非両立性基準というのは,基本的事実関係の近接性を図る道具概念にすぎないからである。
したがって,論理的には,「基本的事実関係が近接しているならば,事実関係が非両立である」という命題を承認し得ても,「事実関係が両立しないならば,基本的事実関係が近接している」とは言い切れないのは当然のことである。このように見てくると,上記①の「事実として両立しない場合」ということの意味は,一定の限定が論理的に内在しているということになるのであろう
(4) 結論⇒一応区分は維持![10]
ア 単一性の根拠付け
一罪の関係にある訴因の間で,訴因変更が許される理由は,そのような訴因が別訴で同時に有罪とされることを防ぐために,別訴そのものを許さず,訴因の変更などによる一回的処理を図ることの訴訟上の合目的性に求められる[11]
イ 狭義の同一性判断
狭義の同一性判断は,刑罰権と全く無縁のものではなく,別訴で同時に有罪とすることが1個の刑罰権に対する二重処罰の実質を有する訴因については,別訴そのものを許さず,訴因変更による一回的処理を図ることが合理的[12]
4 狭義の同一性の基準
(1) 旧法下の対立
旧法時代には,判断の事実に置くのか,そこに法的評価を加味するかが争われた(基本的事実同一説VS罪質同一説)
* 罪質同一性
公訴事実は,裸の社会的事実ではなく法的評価を経たものであるので,罪名及び罪質に制約される(⇒判例のように基本的事実が同一かを基準にしながらも,それだけであると基準が曖昧になるとして,犯罪構成要件上の制約を加える立場)
× この見解は,審判対象論ともつながっており,訴因対象説によれば事実を基準とするべきであるから,法的な観点から限定を加える見解はその後はなくなっていった
(2) 現行法下の対立
訴因の背後にある事実への帰属を問題とするのか,訴因同士の比較を問題とするかが争われた(基本的事実同一説VS訴因共通説)[13]
(3) 平野博士の「訴因共通説」
ア 基本的な判断枠組み
訴因共通説とは,両訴因の奥に「実体」を観念・措定することなく,「公訴事実の同一性」の有無は,端的に訴因と訴因とを比較して決めるべきとする立場
⇒ 訴因は検察官による具体的事実の主張であるから,主張された事実と事実とを対比して基本的部分が共通であれば同一性が認められる
イ 訴因共通説的理解からの同一性判断
⇒ 検察官と被告人の間の対立利益の比較考量
「訴因は,罪となるべき事実を特定して示したものであり,その要素としては,犯罪の主体としての被告人のほか,犯罪の日時,犯罪の場所,犯罪の方法ないし行為の態様,被害法益の内容,その主体としての被害者,共犯関係などが考えられる。これらのうち,いずれか1個だけの変動にとどまる場合は,かなりの程度まで『同一性』を肯定できる。逆に,2個以上が変動する場合は,各要素間に,一致,類似,近似,包含などの関係を求める必要が増大する。同一性の判断は,これらの要素間の関係を総合的に評価し,検察官と被告人との間の対立利益を比較考量して決定される」(松尾(上)265頁)
(4) 論争の到達点
ア 最決平成15年10月7日の調査官解説
「公訴事実の同一性(広義)の判断方法は,訴因変更,二重起訴の禁止及び一事不再理効を通じて一貫するものである必要があるところ,基本的には訴因を基準として比較対照する方法によるべきものであり,訴因の背後にある社会的事実ないし社会的諸事情は,訴因間の比較対照だけでは,判断に困難が生じる場合などにおいて,必要に応じて考慮されるべきであると考えられる。このように解することは,訴因制度を採用した現行刑訴法において,少なくとも第1次的には訴因が審判の対象であると解されていることとも合致しよう」
イ 酒巻(法教302号68頁)
「訴因変更の可否は,裁判所の事実認定とは別個に処理されるべき法的判断であり,検察官の主張する事実相互の関係が法律上非両立で,いずれか一方で処罰すれば足りるもので,別罪で有罪とすれば二重処罰の実質を生じるような場合であるかにより判定すべきである」
(5) 非両立性基準
ア 非両立性基準の定義
非両立性基準とは,訴因事実βによって構成される犯罪が認定できるときは,訴因事実αで構成される犯罪は論理的に成立しえない関係にあるという基準をいう
イ 非両立性基準の理論的基礎
二重処罰になるような関係にある場合の一回的処理の要請
⇒ 別訴で両者が有罪とされれば実質的に二重処罰となり不当と判断されるような関係,どちらか一方の事実で1回処罰すれば良いと判断される関係が認められる場合
* 単一性と同一性は,二重処罰を防止するという視点で統一的に説明できる
(6) 最高裁の判例
① 基本的事実関係の同一性
判断の基礎とされる「事実」の意味内容はかつての歴史的社会的事実から実質的に変化し,基本的には,訴因として記載された検察官の主張する犯罪事実の具体的記載を比較することによって,そこに表示された事実関係の共通性の程度を総合的に評価して同一性を判断している(法教302号67頁)
② 両立しない関係
両訴因を比較対照しただけでは,日時・場所・行為態様などに相違する部分が多く,「基本的事実関係が同一」とはいいにくい場合に,「二重処罰になりかねないような関係にある訴訟が生じないようにする」という制度趣旨から訴因変更による同時的処理を可能とするのが適切・妥当と認められる場合に用いられる
* 判例は,「非両立性」の基準は,基本的事実関係の同一性に代わるものではなく,むしろ,これを根拠付け補充・補完する趣旨で用いている[14]
(7) 判例の検討
ア 最判昭和29年5月14日刑集8巻5号676頁
(ア) 事案
変更前…10月14日ころの静岡県長岡温泉における背広一着外数点の窃盗
変更後…10月19日ころの都内における背広一着の盗品有償譲受
(イ) 評価
訴因を比較対照するだけでは,事実の構成要素の共通性が乏しいために公訴事実の同一性があるとは判断することができない。もっとも,記載された事実の非両立性という観点からは,実体法上の解釈上,罪の成立が択一関係にある。すなわち,窃盗罪が成立するとすれば,盗品関与罪は不可罰的事後行為となるので,盗品関与罪が成立すれば窃盗罪は成立しない。このような場合は,いずれか一方の罪で1回処罰するとしなければ,二重処罰の実質が生じかねないので,訴因変更を認める場合にあたる
イ 最決昭和53年3月6日刑集32巻2号218頁
(ア) 事案
変更前…Xは,A又はBと共謀の上,運転免許証取得希望者13名から不正の請託を受けて,15万円ないし25万円の供与を受けたという枉法収賄
変更後…Xは,運転免許証取得希望者と共謀の上,A又はBに対して,4万円ないし5万円を供与+饗応接待をしたという贈賄の事実
(イ) 評価
たしかに,訴因を比較対照するだけでは,収賄と贈賄という行為態様の相違から事実の比較による共通性を見つけることはできない。しかし,共通する賄賂に関与した被告人が収賄側か贈賄側かによりどちらか一方の罪だけが成立する(対向関係)という意味で,非両立といえる
ウ 最決昭和63年10月25日刑集42巻8号1100頁
(ア) 事案
変更前…XはAと共謀の上,10月26日午後5時30分頃,栃木県芳賀郡二宮町の被告人方においてAをして自己の左腕部に覚せい剤水溶液を注射させて使用した
変更後…10月26日午後6時30分頃,茨城県下館市所在のスナック店舗内において,覚せい剤水溶液を自己の腕部に注射して使用した
(イ) 評価
たしかに,両訴因を比較対照するだけでは,むしろ,両者は併存するとも考えられるが,検察官の釈明を考慮していずれの事実も尿鑑定の結果に対応する1回の使用行為を起訴したという趣旨であれば,いずれか一方の罪しか成立しない関係と判断できる
エ 法教302号69頁
(ア) 事案
変更前…Xが自動車を運転してAに衝突し業務上過失致死の結果を発生させた
変更後…XがAを死亡させた運転者Yの身代わり犯人となった犯人隠避
(イ) 評価
たしかに,論理的には両立しないが,その主張の間におよそ事実上の共通性が認められない以上,刑罰権の実現に際し両者が別訴で有罪とされると二重処罰の実質を生じるかという意味での両立し得ない関係にあるとはいえない。すなわち,検察官の主張が事実認定の次元で間違っているという問題であり,法律上いずれか一方の罪が択一的に成立するという関係,刑罰権の非両立という関係ではない。したがって,両者の間には公訴事実の同一性がなく訴因変更はできない[15]
5 訴因変更の許否
(1) 問題の所在
裁判所は,「公訴事実の同一性」がある限り,訴因変更請求を必ず許可しなくてはならないか
⇒ 訴因変更請求を認めると,①手続の適正化保障を破ることになる,②被告人に防御上の著しい支障や迅速裁判を受ける権利の侵害など法的地位に実質的に不利益をもたらす場合
(2) 理論的根拠
① 手続の初期には,かなり自由に訴因変更をすることができるが,手続の最終段階では事情が異なる
∵ 公訴提起時の訴因事実はある程度の緩やかさを持っていて,いわば可塑性に富んだ主張といえる。しかし,実体審理が経過するにつれて,次第に事実がより厳密に特定されてゆき,可塑性は減少し訴因変更の幅は減少
⇒ ある程度まで実体が形成された時点では,訴因変更は許されない
② 公判手続の停止だけでは対応できない場合がある(312条4項参照)
* 考慮要素[16]
① 被告人側がした立証の努力や負担
② 検察官の立証活動
③ 訴因変更によって新たに生じると予想される被告人側の負担
6 訴因変更命令
(1) 意義(312条2項)
検察官が訴因変更を請求すべきときに適切に請求しない場合は,裁判所による後見的な介入を認め,訴因変更命令を出すことができる
(2) 訴因変更命令の義務性
ア 原則的処理
裁判所に訴因変更を命じる義務はない
∵ 当事者追行主義
イ 例外的処理
① 訴因を変更すれば有罪であることが証拠上明らかにであること
② その罪が相当重大である場合
⇒ 例外的に検察官に訴因変更手続を促し,又は,命じる義務が生じる
* 殺人の訴因を重過失致死の訴因に変更すれば,有罪となり得た事案
* ただし,検察官が約8年半にわたって,当初の訴因に固執し続け,その結果として被告人側もその訴因に防御を集中していたという事情があるときは,裁判所は釈明を求めるだけで足りることもある
⇒ 手続裁量の問題なので柔軟に判断している!
ウ 裁判員裁判と訴因変更命令の義務性(大型否認18)
「公判前整理手続を実施した裁判員の参加する重大刑事事件の公判審理の過程で,従前と変わらぬ訴因変更や,訴因に関する裁判所による求釈明の運用と訴訟法上の義務がそのまま維持できるかどうかについては,議論のあるところ」
⇒ 「慎重に運用すべき」と,昭和43年判例の射程距離の限定を示唆!
(3) 訴因変更命令の形成力
裁判所が訴因変更命令を発しても検察官がこれに従わない場合は,訴因は変更されることにはならない
∵ 当事者追行主義
[1] これは,寺崎259の叙述によるものであるが,このような視点は極めて示唆に富む点があると言わなくてはならない。というのも,公訴事実対象説からすれば,審判の対象は,公訴事実ということになり訴因ではない。ならば,訴因とは何者かを問うと,「被告人に対して不意打ちを防止するため」の告知機能を有するものということになるのであろう。そうだとすれば,面白いことが分かる。というのも,これまでの刑事訴訟法の学説では,訴因の機能として,「不意打ち防止」の観点を強調する者が多かった。例えば,訴因変更の要否については,抽象的防御と具体的防御の観点を加味して判断すべきであるという主張が見られたわけであるが,それらの主張の前提は,実は,公訴事実対象説を前提にしている憾みがあるということになるのであろう。このように考えてくると,かつて,泉谷さんが,「白取は団藤ぽい」と言っていたことも納得できるように見えてくる。たしかに,白取の訴因に関する叙述を見ると,「防御説」な見地一辺倒といえる。そうすると,白取も,訴因の機能は,被告人の防御に尽きるのであると考えている節がないではないであろう。突き詰めてゆくと,訴因対象説を前提として,訴因が審判対象画定の見地からも意味があるということを認めるのであれば,審判対象画定の機能が訴因にあるということも意識されなくてはならない。その意味で,平成13年の最高裁の決定が理論的な反省を迫ったというのも,刑訴の学者たちは,審判対象画定の見地を訴因の機能から落としており,それは訴因対象説と矛盾するのではないかということに捉えることもできるように思われる。平成13年判例を契機に東大系の学者たちは,盛んにこの点を主張し出している(例えば,訴因の特定に関する覚せい剤の吉田町事件など)わけであるが,理論的には正当といわなくてはならないであろう。
[2] 少しこの議論について考えてみることにしよう。この問題の本質は,「刑事訴訟の審判対象,すなわち,訴訟物は何か」という問題といえる。刑事裁判の訴訟物は,「国家刑罰権の存在」であることには疑いがない。この点が民事訴訟法のように,様々な訴訟物が想定されるものとは異なっている。したがって,刑事訴訟法の解釈では,審判の対象は,民事訴訟法的な請求権と解するのではなく,民事訴訟法でいうのであれば,事実レベルにまで引き落とされているということになるのである。そして,その事実レベルのどの範囲が果たして,審判の対象であるのかというのが議論の本質である。審判の対象となるのは,法的な観点から犯罪事実をあてはめた結果である訴因と考えるのが訴因対象説であるのに対して,何らの犯罪が行われたという社会的事実をとらえて審判の対象というのが,公訴事実対象説ということになる。分かりやすいように民事訴訟法に敷衍して説明しよう。訴因対象説による場合の訴因とは,結局,要件事実と同じである。すなわち,「法律構成要件に対応する具体的事実を並べたもの」が訴因であり,民事訴訟法で置き換えると訴因ということになる。刑事訴訟法では,要件事実が審判の対象とされているという点は少し意識してもよいのかもしれない。これに対して,公訴事実対象説による場合の審判の対象は,民事訴訟で例えると,「その民事的紛争の社会的実態」ということになるのであろう。このように考えてくると,公訴事実対象説による場合,一体,何が審判の対象となるのか裁判官も実際のところよく分からないということになるであろう。そこで,助け舟として出てくるのが訴因で,基本的には訴因のみ判断しておけばよいということになる。このように考えてくると,分かった人もいると思うが,実は,現行法を前提にする限り,訴因対象説でも公訴事実対象説でも,具体的な帰結には差はないのである。すなわち,審判の対象が公訴事実という社会的な事実と解したとしても,訴因外の事情を認定する場合は,不意打ちとなるので,いずれにせよ,訴因変更が必要となるわけであり,旧法下のように突然訴因外の認定をすることは,公訴事実対象説を前提としたとしても許されないわけである。このような事柄の本質をある意味で突いているのが団藤説である。団藤は,審判の対象は,「現実的・顕在的」には訴因であるが,「観念的・潜在的」には公訴事実であるという。これは,ある意味では正しく,ある意味では間違っているということになるであろう。これを民事訴訟法に敷衍して説明しよう。XがYに対して,賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求をしているとしよう。この場合,Xは,返還しない間の不法行為に基づく返還請求もしようとかかる訴訟物を訴えの変更によって追加したという事案を想定する。この場合,団藤の理屈を用いると,「潜在的には,訴訟物を追加する前から,不法行為に基づく返還請求権」も訴訟物になっていたので,これも含めて,潜在的には,審判の対象となっていたと主張するわけである。少し,不思議な主張であることが分かるであろう。結局,民訴と異なり,刑訴の場合は,審判の対象はかつての議論である既判力の範囲と直結し,既判力の範囲が広ければ被告人の人権保障になるという発想がある(なお,再考すると,もし訴因が審判の対象ととらえても,一事不再理効が生じる範囲というのは,実は,一致せず,公訴事実の範囲で一事不再理効が生じると解するのが通説である。そうだとすれば,団藤はドイツ的な学者であるから,「訴訟物=既判力」というドグマを維持したくて仕方なかったのではないかという物の見方もできよう。このドグマを維持するかについては,民事訴訟でも一大論争があるところであるが,少なくとも,民訴の判例はこれを形式的には維持しているのに対して,刑訴の場合は,既判力ではなく,英米学者の田宮が一事不再理という説明がするようになってからは,このようなドグマは実質的に放棄されているといえよう。そうだとすれば,現在の通説からすれば,審判の対象と一事不再理効の範囲は一致しないわけであるから,なおさら,審判の対象を無理して,公訴事実であると説明する必要はないということになるのであろう)。だからこそ,しばらく,前時代の遺物とも思える主張が消えなかったわけである。いってみれば,公訴事実対象説といのは,民事訴訟法における新訴訟物理論の試みと既判力の範囲が広いという意味では,共通するところがあるといえるのであろう(だが,田宮の一事不再理という主張を受けて,この説明は意味を喪失しているのであろう)。結局は,同じ条文構造をとらえて,「どう説明するか」という性格が強く,あまり意味のある議論ではないということになるのが,私見の一応の結論である。なお,いずれが正しいかを考えてみれば,民事訴訟で「訴えの変更が抽象的に予測される範囲まで訴訟物である」とは言わないので,審判の対象は訴因と解することが正しいことはいうまでもない。
[3] 備忘のために論証スタイルを提案しておきたい。まず,訴因変更の要否については,「審判の対象は検察官の主張する具体的事実たる訴因である。そうだとすれば,訴因には,審判対象画定の見地と被告人に対して防御の範囲を示す告知機能があると解される」というのが検討に値しよう。これまで,審判対象画定の見地をどのように審判対象が訴因ということとつながるのか分からなかったわけであるが,このように考えれば,職権主義的というかつての私見の疑問は解消されよう。
[4] 窃盗及び住居侵入の訴因を窃盗のみに広義の訴因の変更をする場合は,理論的には,狭義の訴因の変更になると解される(大澤)。これは,「一罪一訴因の原則」を貫くと,前者は科刑上一罪の関係にあるので訴因は一罪ということになる。また,変更後も一罪であることに変わりはない。したがって,この場合は理論的には,狭義の訴因変更となる。これに対して,実務上の処理としては,科刑上一罪の場合,行為ごとに一つの訴因で構成するとされている。そうだとすれば,設例のようなケースでも,形式的に2つの訴因のうちの1つが撤回されるので,「訴因の撤回」となると考えられる。
[5] 従来の見解は,訴因の第一次的機能は,「防御の対象」を示すという点にあると考えるのが妥当とされている(三井『刑事手続法Ⅱ』199頁・179頁)。その理由として,「旧法から新法への訴訟構造の変革を踏まえれば,訴因説は,訴因を審判の対象と捉える前に,第一義的に訴因=防御の対象であることを自覚すべき」という点が挙げられている(三井の見解は,訴因が審判の対象であるということは承認しているが,それよりも前に,訴因説の真の意義として,「訴因の設定によって被告人側に対して防御対象を事前に告知し,公判審理において,この訴因に防御を集中していれば,その範囲を超えて不利益を与えることはない点」にあると指摘し,従来の「審判対象は何か」という問題提起自体が不適切であり,「防御の対象は何か」という切り口でこの問題を論ずべきであったという)。このような理解からは,訴因変更の要否を考えるのに際しても防御の視点が最も重要な意味を持つということになるのであろう。多数の学者は,現在でも,抽象的防御説や具体的防御説を基準にすると思われるが,その前提は,以上のようなものであると考えられる。
私見は,防御の対象を明確にするためには,もとより審判の範囲が示されている必要があると考える。審判の対象が画定されなければ,被告人に対して,究極の防御の限界が示されないということになるからである。このように考えてくると,審判対象の範囲を明らかにせず,それとは切り離して防御の範囲を問題にするという従来の議論は議論が逆立ちをしているといわざるを得ないであろう。
[6] 三井『刑事手続法Ⅱ』199頁は,訴因変更の要否は,二段構えの防御説に立って,その基準を設定するのが説得的なアプローチであるとしている。すなわち,まず,一般的・抽象的な見地から防御に支障を生じないかを考慮するべきであるとする。これは,原則として訴因と認定とに重要な,実質的な事実の差異がないかがメルクマールとなるという。また,一般的・抽象的視点からは防御に支障をもたらすおそれがない場合でも,現実の事案・訴訟を前提にすると,具体的な防御の観点から訴因変更を必要とすべきケースはあり,第二次的には個別事案に即応した具体的な防御上の不利益の有無を考慮しなければならないとしていた。
[7] 縮小認定の理論についても,これまでの議論は詰め切れていない面があったといえる。というのも,従来の議論は,被告人の防御が侵されるかという見地から問題にしてこなかったのであるから,防御の「大」は「小」を兼ねるというような説明が多かったと考えられる。この点,突き詰めて考えると,民事訴訟法においても,処分権主義の問題として,訴えが提起されていない事項について判決をすることは許されないが,一部認容については,原告の合理的意思や被告の防御が尽くされており不意打ちにならないこと,訴訟経済が理由に挙げられていた。もっとも,民事訴訟法において,一部認容が許されるのは,量的一部認容に限られるとする理解が一般と思われる。逆に言えば,質的一部認容,例えば,訴えの形式を変えてしまうとか,訴訟物自体を変えてしまうようなものは,処分権主義に反するとされてきている。このこととのパラレルで,縮小認定の理論といっても,その射程距離というのは,民事訴訟法における量的一部認容の場合に限られるということになるであろう。それが,審判対象画定の見地から訴因変更が求められる場面と考えられる。というも,例えば,強盗罪が成立しないから,その代わりに詐欺罪を縮小認定することができるかというとこれはできないと考えられる。なぜなら,強盗罪の罪となるべき事実は,構成要件が,①反抗抑圧に足りる暴行・脅迫を加えたこと,②他人の財物を強取したこと―であり,これを構成する事実がそれということになるが,詐欺罪を認定するとなると,①欺罔行為,②相手方が錯誤に陥ったこと,③それに基づく財物の交付行為があったこと―の認定が必要であるから,要するに,強盗罪の「罪となるべき事実」の中には,詐欺罪に対応する事実は含まれていないわけである。したがって,裁判所が詐欺罪の事実を認定するには,審判対象画定の見地から訴因変更が必要となるということになる。
縮小認定が問題となる場面は,一般的には,争点明確化すなわち不意打ち防止の見地から訴因変更が要求されないかが問題とされることが多いとも考えられる。
しかしながら,縮小認定が問題とされるケースでは,異なる見地から縮小認定自体が許されなくなるということが考えられるというべきである。それが時機的限界である。すなわち,裁判所は,強盗罪について暴行罪の認定にとどまるとの心証を形成したとしても,本件の背景,審理の経緯などを考慮すると,暴行罪の成立の有無に関する審理を継続することはせずに無罪とすることが考えられる。その典型的なケースとしては,検察官が,傷害,強盗罪の成立を力説し審理の終盤までその主張を維持しているのに対して,被告人は,一切の暴行を否定し争っていたという場合である。この場合,審理の終盤では,信義則ないし権利の濫用ということで訴因変更自体が許されなくなるものと解される。そうだとすれば,被告人の具体的防御の状況から見れば,縮小認定自体が許されない場面があるということになるわけである。すなわち,平成13年の判例の定式からすれば,むしろ,縮小認定が問題となるケースでは,防御は「大」は「小」を兼ねるので不要と解することが多くなりそうであるが,それとは別の「時機的限界」という視点を入れることで,縮小認定が限界付けられることもあると解される。
[8] 浦和地判平成3年3月25日は,「本件において,検察官は,覚せい剤の共同譲受けの訴因しか掲げていないので,訴因変更手続を経由しないまま,幇助の事実を認定することができるかどうかにつき,法律上問題がないわけではない。なぜなら,訴因に掲げられた共同譲受けの事実と,当裁判所が認定した譲受け幇助罪の事実とは,犯行の日時・場所・方法が厳密には一致せず,また,いわゆる「大は小を兼ねる」関係にもないので,訴因変更の要否に関する講学上の事実記載説及び抽象的防禦説を忠実に貫く限り,幇助の事実を認定するためには,訴因変更手続が必要であるとの見解も成立し得ると思われるからである。
しかし,周知のとおり,最高裁判所の判例は,訴因変更の要否に関し,抽象的防禦説を貫くことなく,具体的防禦説的考慮を相当程度取り入れており,現に,共同正犯の訴因に対し幇助罪を認定するのには,訴因変更手続を要しないとした判例も,相当数集積されている。
そして,本件において,当裁判所が認定した幇助行為は,その日時・場所が譲受け行為のそれに接着しているもので,検察官も,「犯行に至る経緯」としてではあるが,冒頭陳述中でこれを明確に主張しているところ,被告人・弁護人も,被告人が,客観的に,右幇助行為にあたる行為をしたこと自体は,これを争っていない。他方,右行為に及んだ際の被告人の主観的意図(幇助の意思)は,共謀の主張の中に包含されていると認められ,被告人側は,共同譲受けの訴因事実を争う過程において,被告人が当時,幇助の意思すら有していなかったという観点からの反証を尽くしており,従って,本件においては,幇助罪の成否に関し,その客観面についてはもとより主観面についても,立証上の防禦が十分尽くされていると認められ,しかも,右の点は,論告・弁論において,明示的に弁論の対象ともされているのである。右のとおり,共同譲受けの訴因事実の審理の過程において,幇助行為及び幇助の意思の存否に関する十分な主張・立証が尽くされている本件事実関係のもとにおいては,訴因変更手続を経ることなく幇助罪を認定しても,被告人に何らの不意打ちを与えるものではない。
したがって,本件において,幇助の限度で有罪の立証がされている以上,訴因変更の手続を経ていないというだけで,同罪の認定を拒否するわけにはいかない(ちなみに,弁護人は,最終弁論において,検察官が論告においてした幇助罪の主張を明確に意識した上で無罪の弁論をしたが,訴因変更手続を経由せずして幇助罪を認定することが許されないとの主張は全くしておらず,当裁判所の求釈明に対しても,幇助罪が成立しないと考える根拠は,右弁論で述べたとおり,被告人には幇助の意思すらなかったからである旨答弁するに止まっている。もっとも,被告人の行為が,前記認定の程度の幇助罪を構成するに止まるものであることが,捜査段階において明らかにされていたとすれば,果たして,起訴価値があったのであろうかとの疑問は残る。また,かりに起訴されたにしても,単なる幇助罪の訴因であれば,審理がこれ程紛糾することもなく,早期の保釈も当然認められたと思われる。従って,これらの点は,本件の量刑―未決勾留日数の算入を含む―を決する上で,十分考慮される必要がある。)」とする。最終弁論の段階で検察官が,幇助罪の成立を突如主張したものであり,信義則や権利濫用の主張をすることができた事案であった。
[9] なお,法教302号66頁も,「筆者は,両訴因が実体法上一罪の関係にあると認められる場合は,(狭義の同一性を問題にするまでもなく)法312条にいう「公訴事実の同一性」を認めるべき一局面であると考える」とする。
[10] なお,法教302号66頁も,単一性と同一性の区別を残した上で,両者に「統一的に説明する方法があり得るとすれば,それは,・・・1個の刑罰権(実体法)に対し複数の判決が併存する可能性を回避するための訴訟手続上の方策・要請」となるとしているが,結局,統一的な説明が理論的に可能であるので「区別は不要」としている。
[11] 民事訴訟制度の下では,訴訟物が同一であるという場合において原告が敗訴したという場合は,基準時前の事情が異ならない限り,既判力によって後訴は遮断されるということになる。これも特段民法が訴訟上の一回的処理を求めているわけではないが,訴訟法上の立法政策で一回に限られているということになるであろう。だが,民事訴訟においては,いわば同一訴訟物の一回性は事情変更がない限り当たり前のこととされている。つまり,民事訴訟制度の目的達成の観点から,既判力が求められるということになるはずである。これとの均衡からみれば,大澤が「刑法の要請ではなく訴訟法上の立法政策」と力説するほどのことはなく,いわば当たり前のことということもできよう。
[12] 大澤の所論は分かりにくいが,「二重処罰の実質を有する訴因」というのは,二重起訴,もっと突き詰めると「裁判所の矛盾判断の防止」のことを意味するのではないかとも思える。すなわち,実体論理からは,二重処罰が禁止されるので二重処罰に手を貸しかねない判決を禁止するという説明をするわけであるが,現実には,訴訟法的に,二重起訴から生じる弊害を防止するために,裁判所の訴訟経済,裁判所の矛盾判断の防止(≒被告人のダブル・ジェパート),紛争の一回的解決という調和点から狭義の同一性は基礎付けられているのではないかとも考えられる。なお,大澤の「実質」という概念は,ひょっとしたら,本来は,公訴事実の同一性というのは,二重処罰の禁止が妥当される範囲にも認められるものであるが,被告人の人権保障の見地からそれをやや広めに概念構成をすべきとの意味が含まれるのかとも考えたが,そうではなく,要するに,刑罰関心一個説の説明を単に,別の言葉を使って言い換えているにすぎない。そして,そのように解する理由は,結局,大澤が訴因の背後に公訴事実という概念を想定するのを拒否しているために,それと親和性のある刑罰関心一個説を拒否せねばならないということを力説する点にある。私見は,特段,公訴事実という観念を否定する理由はないと解するから,必ずしもこのような説明をする必然性を感じないものであるが,公訴事実の単一性と同一性という概念を統一的な理論的背景での論証に成功しているという点及び訴因対象説と適合的であるという点では,注目に値する。結局,大澤の見解は,「単一性と同一性の区別は一応維持される」,「両者の理論的背景には共通性であり,区別はするがその実益はそれほど大きいわけではない」という点に集約されるのであろう。
[13] この議論の対立には,いずれの観点を重視するかという問題であり,いずれも傾聴に値する見解といえる。まず,訴因共通説の主張は,①犯罪事実の存在は,刑訴の判決によりはじめて明らかになるものといえる。そうすると,その訴因の背後にある実体を観念してしまうということは,その犯罪事実があったということを初めから当然の前提にしてしまうということである。このような理解が,「疑わしくは,被告人の利益に」の原則に適合しているか疑わしい,②背後の事実を想定すると,訴因の吟味を超えて,裁判所が訴因の背後の実体をみることになるので,訴因の構成設定権を検察官に与えるという当事者主義の建前と適合しない,③実際上,裁判所が社会的実体を判断するには困難がつきまとう―という論拠を挙げている。これに対して,背後の実体を想定するべきとの主張は,①「A訴因とB訴因の間」,「B訴因とC訴因との間」には,公訴事実の同一性が認められないが,A・C間には,公訴事実の同一性が認められない場合―という問題設定をする。そして,この見解は,訴因共通説では,順次,A⇒B⇒Cという訴因変更を認めることになると批判する。これは,訴因共通説によると,「公訴事実の同一性」という概念があまりに道具概念化して,際限なく訴因変更が認められる範囲が拡大することを防止しようとする意図に基づいているものと考えられる。そのうえで,白取274は,訴因共通説を「有罪の可能性が生じたらいつまでも訴因変更を認める」ものであり,の果たす機能は,「糾問的」と批判している。たしかに,論理的には,白取274の主張も成り立つが,現実には,訴因を比較対照するだけでは,基本的事実の同一性が認められるかが不明な場合が多いので,必ずしも訴因変更が認められる範囲が拡大するという批判が妥当するかについては違和感が残る。また,背後に実体を想定するというのは,公訴事実対象説と親和性があり今日の訴因対象説と整合するのかという疑問もある。また,訴因変更には時機的な限界があることも近時は意識されており,「有罪の可能性が生じたらいつまでも訴因変更を認める」わけではないと考えられる。さらに,公訴事実の同一性の範囲が拡大することは,一事不再理効の範囲が拡大することも意味するので,直ちに被告人の不利になるという論理にも違和感がある。このように考えてくると,白取274は理由がないというべきであり,原則としては,訴因共通説によるべきと考えられる。
[14] 法教302号67頁は,判例の根底に流れている基本的思考は,基本的事実関係が同一であるかという観点ではなく,むしろ,「二重処罰の実質が生じるのを回避するという非両立性の基準ひいては実体法の解釈として犯罪の成立が択一的関係であること」がメインの判断基準であると主張している。従前,非両立性基準は,基本的事実関係を補完する基準という位置づけが多かったと思われるので,この位置づけには注意しておく必要があろう。
[15] 東京高判昭和40年7月8日の事案である。たしかに,非両立性基準の中に広く,事実上の非両立一般も含まれるとすれば,非両立性基準を満たすということになる。しかし,非両立性基準の理論的基礎は,二重処罰の実質を有するおそれがあるような訴訟が併存するということを防ぐという点にあるので,検察官の主張する事実相互の関係が法律上非両立,すなわち刑罰権の非両立の関係があるかにより判断するべきである。このような視点からすれば,業務上過失致死罪と犯人隠避罪というのは,事実上のレベルでは両立し得ないものと考えられるが,法律上のレベルで両立するものといえる。そうすると,検察官の主張は,いずれか一方,あるいは両方とも間違っているというにすぎないので,事実上両立しないことが直ちに,非両立性基準を満たすということにはならないことに注意が必要であると考えられる。この点,種明かしをすれば,先述したとおり,東大系の学者は,「公訴事実」を観念することを拒否する。したがって,「基本的事実関係の同一性」という判断枠組みの実質は中身のないものであり,訴因を比較対照し,かつ,非両立性基準を用いることこそがメインの基準であると主張している。このように,背後に「公訴事実」を想定しないので,無理が生じた一つの典型例といえるのであろう。伝統的な判例の枠組みからすれば,基本的事実関係が同一であるかを判断するために,非両立性基準を併用的に用いるということになる。上記の例によれば,そもそも,事実的に両立しないからといって,基本的事実関係が同一とは限られないという領域は少なからず残るということになる。したがって,非両立性基準を満たしても基本的事実関係がないという関係にある一事例にすぎないわけであるが,このような説明は,東大系からはすることができない。そこで,非両立の射程距離は,法律上の非両立性に限られるとの限定を付し,事実上の非両立は,事実認定の誤りに過ぎず,したがって,二重処罰の禁止とは関係がないとすることによって論証しようとしているわけである。しかし,仮に,同じ時間にA罪及びB罪を別の場所で犯したということであれば,両方とも有罪にされるというのはおかしいというのが素朴な感情であろうが,東大系は,それはいずれかが間違いであるからと決め付けることによって,二重処罰の問題ではないとするわけである。筋が通っていないわけではないが,それほどすっきりする説明ではないと言わなくてはならないであろう。この二重起訴による主張の現実は,「刑罰関心同一性」の論証をすりかえただけという実質があることを忘れてはならない。そうすると,「国家の刑罰関心が1個か」という観点から判断することになるので,この説明からすれば,両者の刑罰関心が同じとは言いがたいところであろう。たしかに,事実上の両立性がないからといって,国家の刑罰関心が一つしかないとはいえないのに対して,法律上の両立性がない場合は,国家の刑罰関心が一つであると言いやすいところであろう。
[16] 浦和地判平成元年3月22日は,先の浦和地決昭和63年9月28日判時1306号148頁に対する検察官の反論について詳細に再反論を加えている。
「反論(1)について
当裁判所も,公訴事実の同一性の範囲内にある訴因変更請求は,原則としてこれを許可しなければならないとする点で,右反論と基本的に見解を異にするものではない。そうすると,公訴事実の同一性の範囲内にある訴因変更であっても,一定の例外的場合は,許されるべきでないとする決定の見解が,直ちに,当事者主義の訴訟構造に背馳するものでない。もちろん,訴因変更の許否は,できる限り明確な基準に基づいて決せられるのが望ましいが,当裁判所もかかる観点から,不許可とされるべき場合が,「訴因変更が許可されることにより被告人の受ける不利益が,公判手続を停止しただけでは回復することができない重大なものであると認められる場合」に限られるべきであることを,刑訴法312条の法意から導き出している。
反論(2)について
判例は,憲法37条1項の迅速裁判保障条項に反する事態に至った場合には,刑訴法の明文に反しても,一定の段階で審理を打ち切り免訴の裁判により被告人を訴訟手続から解放すべき旨判示している。かかる判例の趣旨は,刑訴法の他の規定の解釈上も,尊重せざるを得ない。このような判例の流れからいうと,究極的には憲法の右規定の趣旨に照らし,訴因変更の許否を決しようとする決定の立場は,容易に首肯される。問題は,刑訴法の明文に反して公訴を打ち切ることが許されるかというような深刻な次元のものではなく,予備的訴因変更請求の可否という,いわば派生的手続に関する刑訴法の規定の解釈であるから,右判例の場合と比べれば,問題の次元は,はるかに低い。
反論(3)について
決定は,訴因変更の許否の判断にあたり,新訴因につき有罪判決の得られる蓋然性の程度をも考慮に容れるべきとする。この見解は,条理上当然である。検察官の訴訟行為は,原則として,究極的に有罪判決を得ることを目的として,有罪判決の得られる蓋然性を前提とする。そうだとすれば,審理の途中において,本来の訴因につき有罪判決を得られる蓋然性が全く失われ訴因変更の余地もないならば,裁判所は,直ちに審理を打ち切り被告人に対し無罪の言渡しをする必要がある。このような場合,検察官が審理の打ち切りに応じない場合でも,裁判所は,蓋然性がないものと判断する限り,検察官の立証を許さないまま審理を終結することもできるはずである。問題は,このような,一定の訴因を前提とした上での立証打切りの可否ではなく,新たな立証のテーマを設定しようとする検察官の訴訟追行行為(予備的訴因変更請求)の許否であるから,ことがらは,右に述べたところと必ずしも全く同一ではない。たしかに,当事者主義を基調とする現行刑訴法は,立証のテーマの設定を検察官の合理的な裁量に委ねており,最高裁判所の判例も,当事者主義的訴訟構造を重視した見解を積み重ねている。しかしながら,判例の見解も,当事者主義の考え方を徹底するものではなく,例えば,一定の要件の存する場合には,裁判所に訴因変更命令義務のあることが肯定されており,右訴因変更命令義務の要件の一つとして,新訴因につき「有罪であることが明らかな場合」が挙げられているのである。このように判例が,一方において,新訴因につき有罪判決の得られる蓋然性が極めて大きい場合に,裁判所に訴因変更命令義務を課している。そうだとすれば,逆に,訴因変更請求の許否にあたっても右蓋然性の程度を考慮に容れ,これが著しく小さい場合には,従前の訴訟の経過等を勘案して,これを許すべきでないとする決定の見解は,判例の趣旨に副うものである。訴訟手続に関する裁判においても,常に有罪判決の得られる蓋然性の程度との関係が考慮されており,この点を考慮することが,訴訟手続に関する裁判としての性格に反するものではない。反論は,決定が,検察官に対する求釈明により,新訴因につき有罪判決の得られる蓋然性を判断したことを,るる論難する。しかし,訴訟の初期の段階であればともかく,争点に関する審理も煮つまった最終段階に至れば,裁判所が,新訴因に関する検察官の立証計画の内容を既存の証拠と併せ検討することにより,新訴因につき有罪判決の得られる蓋然性を容易に判断し得ることがあるのであって,かかる場合に,裁判所が右のような方法で右蓋然性の存否を判断することが許されないはずはない」