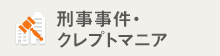伝聞法則―最伝聞
第7 再伝聞
1 定義
再伝聞とは,二重の伝聞であることをいう
2 問題の所在
Aが「被告人であるX,Yと共にB宅を放火する計画でしたが,私は他に用事があったために犯行には参加しませんでした。翌日,Xと会ったのですが,Xは,『昨日,B宅に火をつけてやったぜ。スカっとした』と言っていました」という検面調書を作成した後,死亡した。検察官は,X被告事件において,要証事実を「Xが,B宅に放火したこと」として,本件検面調書の取調べ請求をすることができるか。伝聞証拠の中に含まれる伝聞事項について証拠能力は認められるのかが問題となる
3 考え方(最判昭和32年1月22日刑集11巻1号103頁)
(1) 弁護人の上告趣旨
弁護人は,AのXについての伝聞の供述は,公判期日における供述ではなく,検察官の面前における供述であるから,324条1項を適用することは許されないと主張
(2) 再伝聞に証拠能力を認める論理(平野説)
ア 第1段階
まず,Aの検面調書のうち,Xの供述部分を除く部分については,321条1項2号により証拠能力が認められる
イ 第2段階
この見解は,「検面調書に証拠能力が認められるのは,公判期日における供述に代えられるから」と主張する。すなわち,320条の「公判期日における供述に代えて」という部分から,いったん321条1項2号で伝聞例外として証拠能力が認められれば,それは,「証人が公判廷で供述したのと同じ」効果を認めるという論理を展開する
そして,この論理を用いると,検面調書の一部をなすXの供述部分については,「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述」(324条1項)と同視することができるということになる。そこで,Aの検面調書は,厳密には,「公判供述」ではないが,324条1項を類推適用することになる。そして,324条は,322条・321条1項3号を準用しているから,これらの要件を満たせば,Xの供述部分にも証拠能力が認められるという論理である
(3) 平野説の検討
① 検面調書に含まれるXの供述部分まで「公判期日における供述」と同等の証拠能力があるとはいえない
② 324条1項の典型例と再伝聞のケースとでは,Xの反対尋問の可否が異なる。すなわち,典型例においては,公判廷でAが供述するのであるから,Xはこれに対して反対尋問をすることができるのに対して,公判廷に出頭しない場合には反対尋問をすることができず利益状況が異なる
(4) 学説の展開[1]
① 従来の議論
320条の「公判期日における供述に代えて」と規定していることから,伝聞例外の適用の結果が,公判供述と同視できるか―という形式的な観点から議論がなされていた
× このような文理解釈でそのいずれが正当であるか結論付けることはできず,実質的な考慮が必要というべき
⇒ 平野説を前提にすれば,320条1項からもし,「公判期日における供述に代えて」という文言がデリートされると,324条の類推適用ができないという論理になる。
しかしながら,以下のように今日の議論を前提にすれば,再伝聞であっても,それぞれが321条以下の伝聞例外の要件を満たせば,伝聞供述者の供述に証拠能力が認められるということになる。そうすると,実質的には同一内容の公判廷における供述(伝聞供述)と区別する理由がなくなる。すなわち,伝聞供述者の供述とその中に含まれる伝聞供述(再伝聞)の関係は,「公判期日における供述と原供述」との関係(324条)の関係と利益状況が似てくるものと考えられる。したがって,このような前提の利益状況の類似があって類推適用を可能とするにすぎず,上記のような形式的な文言から類推適用を可能とするわけではないということを自覚しておく必要がある
② 現在の議論
● 再伝聞の証拠能力は否定すべき
∵① 再伝聞は関連性が遠くなり証明力も非常に弱い
② 伝聞例外の機械的適用は,理論的に際限なく続くので調和しない
△ 原供述者の「肯定確認」があれば,証拠能力を認めてよいとする見解
∵ これは,321条1項や322条1項における供述録取書における署名押印が伝聞性を解消する議論とパラレルに理解しようという見解である。鈴木教授は,「伝聞供述の正確性に対する原供述者自身による積極的確認がない以上,たとえ伝聞供述に特信状況が備わっていてもそれだけでは再伝聞証拠に関連性を認めるに十分ではない」とする。そこで,鈴木教授は再伝聞証拠の関連性を認めるには,「原供述者のいわゆる肯定確認のある場合に限って」,324条を類推適用をすることができると解する
× そもそも,署名・押印は供述録取書の録取過程の伝聞性を解消するという意味があるにすぎず,署名・押印があるから要証事実との関係で関連性が認められるという意義が認められているというわけではない。したがって,供述録取書に署名・押印が要求されていることから刑訴法が供述録取書以外の再伝聞についてまで原供述者の肯定確認を要求していると解するのは,論理の飛躍がある
○ 各過程ごとに伝聞例外の要件を満たす場合には伝聞例外を認めるべき
∵① 複数の伝聞例外の要件が確認されることで証拠能力が認められる要件が厳格になる(この立場は,繰り返し伝聞例外を適用しても信用性の情況的保障が担保されるということを前提としているものと思われる)
② 再伝聞であるだけで証拠排除すべきではなく,二重の伝聞であることを踏まえ,その危険性に十分配慮しつつ証拠評価をすべき
第8 当事者が証拠とすることに同意した書面・供述(326条)
1 要件
裁判所がその書面が作成されまたは供述されたときの情況を考慮して相当と認める限り許容
2 同意の意義
● 反対尋問権放棄説
×① 刑訴法326条が被告人の供述調書(322条,反対尋問は問題とならない)や公判期日での証人尋問調書(321条2項,すでに反対尋問をしている)を掲げている趣旨を説明できない
② 実務では,当事者が書面の証拠採用には同意しつつ,証明力を争うために原供述者の証人尋問請求をすることがあるが,反対尋問権を放棄していればこのような尋問請求はできないはず
○ 証拠能力付与説
⇒ 同意は,書面や供述に証拠能力を付与する積極的な訴訟行為であると考えられる
* 326条1項が証拠能力に関する処分権限を当事者に与えたものと見る
第9 証明力を争うための証拠(弾劾証拠)(寺崎347)
1 実質証拠と補助証拠
実質証拠とは,要証事実の存否の証明に持ちいられる証拠をいう。補助証拠とは,実質証拠の信用性・証明力を争うためにのみ用いられる証拠をいう
⇒ 補助証拠のうち,供述証拠の証明力を争うための証拠を弾劾証拠という
2 証明力を争う証拠の意義
(1) 自己矛盾供述
ア 定義
自己矛盾供述とは,公判廷外の供述と公判供述とで,その内容が矛盾する供述をいう
イ 立証趣旨
証人Xの公判廷での供述には信用性がないこと
ウ 弾劾証拠
公判で供述する以前になされた公判廷外での供述
エ 考え方
この場合は,供述内容の真実性が要証事実とされているわけではないので,もともと伝聞法則の適用はないということになる
⇒ 328条の「証拠」にあたることに争いなし!
(2) 他の者がした異なる供述
ア 定義
他の者がした異なる供述とは,公判廷外の他の者の供述と公判供述とで,その内容が矛盾する供述をいう
イ 立証趣旨
証人Xの公判廷での供述には信用性がないこと
ウ 弾劾証拠
他の者Zが異なる供述をしている事実
エ 考え方
たしかに,Zの供述はその供述内容の真実性を要証事実としているわけではないが,実質的にはXの供述が弾劾されるというためには,Zの供述が真実であるということが前提とされている。そうすると,Zの供述を328条の「証拠」とすることは伝聞法則に実質的に反すると解すべき
⇒ 328条の「証拠」にあたらない(通説)
(3) 補助事実の弾劾
ア 定義
証人の信用性に関する補助事実を証明するために公判廷外の供述を用いることをいう
イ 立証趣旨
供述者の資質や事件に対する偏見の存在など
ウ 弾劾証拠
公判廷外の(他人の)供述
エ 考え方
原則は,供述者の資質や事件に対する偏見の存在は補助事実にすぎないので,もとより厳格な証明がいらないから関連性が問題となるにすぎない。
しかしながら,基本的に補助事実の証明は,同時に実質的に間接事実の立証ともなると考えられる。すなわち,補助事実の証明は犯罪事実の認定と密接不可分の関係にある。したがって,厳格な証明が要求されるか,言い換えれば,伝聞法則の適用があるかは個別具体的にみていかざるを得ない
⇒ 基本的には,補助事実の証明が間接事実の証明を兼ねないのは,「証人の能力・性格などを証明して公判供述を弾劾する」という場合となるが,現実的にこのような弾劾の仕方は稀!
* 一見,補助事実の弾劾と見える場合は間接事実の立証となっていないかを検討し,これを肯定するのであれば厳格な証明が要求され,328条の「証拠」としては許容されない
3 許容される証拠の範囲―学説の状況
(1) 非限定説
立証趣旨を法廷での供述の証明力を争うことに限定する限り,自己矛盾供述に限らず,すべての伝聞証拠を利用できるとする見解をいう
(2) 限定説
限定説は,自己矛盾供述についてしか証拠能力を認めないとする見解をいう
(3) 純粋補助事実は328条の証拠に含まれるとする見解
ア 大澤説
∴ 328条は,証人及び被告人の性格・能力・利害関係・偏見などの信用性のみに関する純粋な補助事実の弾劾については「伝聞例外」を規定したもの
× 同一条文に性格の異なる証拠の利用方法を読み込むことは不自然(演習305を見ると,大澤本人もムリがあると認めているようである)
イ 渡辺咲子説
∴ 純粋な補助事実について厳格な証明ではなく自由な証明で足りるのであり,純粋な補助事実については法328条を持ち出すまでもなく許容される
∵① 純粋補助事実の証拠は,犯罪事実の存否についての認定に関して供述の証明力の判断に影響を与えるだけであり間接的である
② 純粋補助事実については確実な書類(診断書や民事裁判の答弁書)があることが多いのに,作成者を証人尋問するか321条以下の規定によらなくては証明力を争う証拠として提出できないことには疑問がある
× 補助事実には厳格な証明を要するというのが通説(白取298)
(4) 調査官解説
「条文の文言のみを見れば,むしろ非限定説の方が素直な解釈であるといえるが,限定説の論拠に現れているように,その点については立法過程で特にGHQとの関係において問題となる経緯があったようであり,文言にあまり拘泥するのは相当でないように思われる。また,限定説のように自己矛盾供述に限るとすれば,供述証拠を非伝聞的にのみ用いることになるから伝聞法則との関係で何らの問題も生じない・・・。以上のような点からすると,少なくとも現在においては限定説を採るのが相当といういことになると思われる」
「(大澤説や渡辺説を指して)そもそも,間接事実と純粋補助事実を比較した場合に,後者の方が犯罪事実に関する心証形成に対する影響力が格段に低いといいきれるかどうかという点について,かなり疑問があるように思われる」
「自由な証明説は,限定説と理論的に抵触するものではない上に,主に刑事裁判官の経験者が,審理の円滑性,柔軟性等をも根拠にして強く唱えている説であり,前記のとおり,実務の運用の大勢が限定説に立ちつつ,その運用で特に不都合が生じているとの議論が生じていない背景には,一部において,自由な証明説を採り入れた運用がなされていることがあるのではないかとも考えられ,一定の意義があるように思われる」
* 私見の分析[2]
4 判例(最決平成18年11月7日刑集60巻9号561頁)
(1) 事案
1審で証人Aが証言した後,弁護人が消防指令補K作成の聞き込み状況書を328条で証拠採用を求めたというもの。これは,KがAから火災発見時の状況を聞き取りしたものであり,署名・押印はなかった
(2) 判旨
「刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。
そうすると,刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を充たすものに限る),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる」
(3) 意義
① 328条で許容される証拠の範囲について限定説を採用した[3]
② 自己矛盾供述が供述録取書に含まれている場合には,その供述録取書が刑訴法の定める要件(供述者の署名若しくは押印)を満たす必要がある
5 供述録取書における供述者の署名押印について
(1) 問題の所在
18年判例で問題となった書証は,他人の供述を聞き取って記述した書面である以上,あくまでも供述録取書にあたるところ,供述者の署名押印を欠いているのであるから,限定説からすれば,供述者の署名押印を欠く供述録取書を証拠として許容することができるかが問題となる
(2) 考え方の整理
ア 限定説を前提とする見解
(ア) 伝聞証拠の構造
供述録取書の供述過程は,①供述者が供述録取者に対して供述をする過程と②供述録取者がこれを書面化して伝える書面による供述過程―の2つの供述過程に分かれる
⇒ ①,②の伝聞過程はいずれも,反対尋問にさらされておらず二重の伝聞!
(イ) 署名押印の趣旨
署名押印の趣旨は,第2供述過程の伝聞性を考慮し,供述録取書の記述内容を供述者自身に認証させることによって,その真実性・正確性を確保し,この点についての被告人からの反対尋問を不要なものとして,その伝聞性を問題のないものにする趣旨
(ウ) 限定説によるあてはめ
限定説とは,自己矛盾供述に限って伝聞法則による制限を外すという考え方であるところ,限定説によって伝聞性がなくなるのは,あくまで上記①の伝聞過程のみである。そうすると,上記②の伝聞性は残る
⇒ 上記②との関係から,供述者の署名押印が備わっていない限り,結局供述録取書全体について伝聞法則による制限が外れず,法328条によっても証拠として許容されないと解するのが論理的な帰結
イ 非限定説を前提とする見解
非限定説に立った場合には,供述者の署名押印は不要となる見解となりやすい。その理由は,非限定説を前提とすれば,Aが「信号は赤であった」と証言したところ,Bが「信号は青でした」との検面調書があるとする。そうすると,非限定説によれば,Aの証言の信用性を減殺するのにBの証言を用いることができるということになり,これはBの供述の信用性を前提とするものといえる。ところが,本来は,Bの供述の信用性があるというためには反対尋問が必要であると考えられるところ,非限定説は反対尋問がなくても328条の証拠として許容できるという趣旨である。そうすると,最も核心ともいうべきBの証言の信用性について反対尋問がいらないのに,それよりも重要性が劣り形式的な要件ともいえる第2供述過程にこだわるのは疑問があるからである。したがって,非限定説を採る場合には,供述者(B)の署名押印も不要である
6 従前の供述に限られるか
(1) 限られるとする見解(通説,大澤)
∵ 公判中心主義や当事者対等の原則
(2) 限られないとする見解
∵① 刑訴法328条には,321条1項と異なり「前の」供述とはされていない
② 証明力を争う証拠(補助事実)には伝聞法則の適用はなく,反対尋問の機会の保障は不要であるから,自己矛盾供述がなされた時期を問題にする必要はない
(3) 判例(最判昭和43年10月25日刑集22巻11号961頁)
積極説による
* 公判前整理手続導入を受けて
連日的開廷がなされれば,公判外で証人を取調べることの時間的制約が厳しくなる。さらに,公判前整理手続の導入により,そうした供述による弾劾は,公判前整理手続において証拠調べ請求することができなかったことの「やむを得ない事由」のあったことが必要となるが,公判廷で検察官が尋問する機会がありながら,自己の尋問が功を奏しないからといって,「やむを得ない事由」があると認められるかは疑わしいとする見解がある(津村政孝「判批」刑事法ジャーナル102頁)。このように考えれば,裁判員裁判においては,実質的に積極説によることはできないという運用になると考えられる。今後は,従前の供述であっても裁判員裁判において,公判廷で供述が行われたにもかかわらず,検察官が弁護側証人を事前に取調べで公判前整理手続で取調べ請求をしておくという運用自体が公判中心主義や当事者対等の原則からいって問題ではないかということが根源的に問われよう
7 回復証拠と増強証拠―回復証拠の使用に限られるとする見解
∵① 伝聞証拠で証明力を増強することを認めると,伝聞証拠を実質証拠に用いることになる
② 回復証拠としての使用は,弾劾証拠の証明力を減殺するにすぎない
③ 証明力を争うといっても,伝聞証拠を弾劾証拠として用いる場合と弾劾した証明力を回復するための回復証拠として用いる限度で,伝聞法則の趣旨との抵触を避けることができるにすぎない
8 裁判員裁判との関係(大型否認34)
裁判員裁判においては,刑訴法328条による書証の請求は避けるべき
∵ 裁判員が,実質証拠と弾劾証拠の差を理解すること不可
(1) 328条の典型例
328条における書証の証拠請求の典型例は,当事者が証人尋問において,当該承認の捜査段階における矛盾した供述を用いて,証人の供述の信用性を弾劾しようと試みるもの
(2) 今後の弾劾の仕方
弾劾の目的を達するために,当事者は,当該供述調書などの内容を証人に的確にぶつけるなどして,尋問の中でその目的を達成する必要!!
⇒ 尋問技術の向上が大きな課題!!
* 尋問において的確に供述の変遷を明らかにするべき
(3) 裁判員裁判における328条の適用例
研修所の文献は,今後は,供述者が公判廷において言を左右にして,自己矛盾供述の存在自体をあいまいにするなど極めて限定されたものとなるとする
(4) 判例(名古屋高裁金沢支判平成20年6月5日判タ1275号342頁)
名古屋高判は,弾劾証拠が316条の32第1項の「やむを得ない事由」にあたるとした原審を誤りとし,弾劾証拠の取調べの必要性を厳格に吟味するもの
「公判前整理手続を実施した事件における弾劾証拠の採否に当たっては,同法316条の2第1項の要請から証拠としての「必要性」についても厳格な吟味を要する。具体的には,①その供述者の立場,②その弾劾の対象となる供述者のした供述の重要性,③弾劫の対象が供述者の供述全体の信用性にかかわるものか供述中の特定の事項の信用性にかかわるものか,④公判準備又は公判期日における供述と,別の機会にした供述の矛盾の程度,⑤別の機会にした供述が複数あって,それらの相互の間にも矛盾がある場合などにおいてはその供述のなされた時期や変遷の経緯,⑥その公判期日等において,供述者の別の機会にした供述とのくい違いに関し十分な尋間がなされているか否か,⑦供述者が,別の機会にした供述とのくい違いについて十分な説明をしたか否か-等の諸点について,考慮することになる」と指摘する。
そのうえで,名古屋高判は,自己矛盾の供述について十分な尋問をしていない場合に328条の弾劾証拠を認めると信用性判断が難しくなりすぎるとし,原則,「公判期日等における反対尋問や補充尋問が十分になされることなく請求された場合には,それを許容すべきでない」とする。もっとも,名古屋高判は,本件で弾劾証拠の取調べを請求したのは弁護人であるところ,弁護人は,検察官と異なり十分な証人テストをあらかじめすることが困難なことが多く,事前準備には限界があるとして,弁護人が,「公判期日等の審理の際に十分な反対尋問等ができないことも考慮すべきで,公判期日等における反対尋問等がなされていないことのみで,弾劾証拠をすべて排斥するのも相当ではない」と指摘しており,弁護人請求の弾劾証拠の取調べが認められる余地を一定程度残しているものと評価され,片面的デュープロセスにも通ずる考え方と思われる
[1] 再伝聞については,この証拠能力を否定する見解がいなかる利益を考慮しているかを理解することが重要である。まず,①再伝聞証拠は関連性が遠くなり,証明力が非常に弱いことを根拠とする見解がある(白取388)。しかしながら,伝聞例外は,証拠能力の要件であり証明力が弱いから証拠能力が認められないというのは逆立ちした議論であると考えられる。したがって,この点は決定的な理由付けとはならない。
次に,②伝聞例外の機械的適用は,理論的には際限なく続くので,伝聞禁止の原則とは調和しないとする見解がある。この見解を突き詰めると,再伝聞証拠であっても,証拠として用いるべき必要性が高い場合は容易に想定できるから,再伝聞の場合に信用性の情況的保障というのがあり得るのかという問題意識といえよう。
たしかに,法は伝聞例外の要件を満たしていれば,信用性の情況的保障があることを前提としているわけであるが,これは,典型的な伝聞の場合のみであり,再伝聞やそれ以上の多重伝聞の場合に繰り返し伝聞例外の規定を適用すれば,信用性の情況的保障がなされているかについては疑問が生じるところである(要するに,要件を満たしても,多重伝聞の場合は信用性の情況的保障が確保されないという事態が想定することができる。信用性の情況的保障がないまま事実認定の証拠に用いれば,実体的真実発見の見地からも相当ではない事態も生じるであろう)。
このような観点から,介在者が検察官の場合は再伝聞が認められるとする見解もある(田宮391,田口421)。すなわち,伝聞例外規定が2度適用されているが,適用される伝聞例外の規定が異なる場合は,その要件を満たすことで,信用性の情況的保障が確保されていると解するわけである。
私見は,再伝聞証拠については,証拠能力を認めるべきものと解する。そもそも,伝聞法則は典型的には捜査機関作成の書類が無制限に公判廷に流れ込むことを防止することを意図したものと解することができる。また,それを裏付けるように伝聞供述に関する規定は1か条しかない。したがって,伝聞供述に関する点は解釈に委ねられている面が大きいというべきである。してみると,たしかに,本件の場合は,検面調書に録取されているのであるから,321条1項2号を適用する他はない。しかしながら,その先の伝聞供述の部分については,柔軟に解するべきものと解する。すなわち,伝聞供述は,他に適当な採証の手段がなく,証拠とすべき必要性が高い場合が多い。そこで,伝聞法則を厳格に適用するのは相当ではないということになる。したがって,少なくとも各伝聞過程において,その要件を満たし信用性の情況的保障があれば,証拠能力を認め後は証明力評価に委ねられるべきと思われる。この点,Aの検面調書は供述録取書であるところ,原供述者であるXの署名・押印に代わる肯定・確認,すなわち,Xが自分は確かにXの供述部分の通りのことをAに述べたことを認めるXの肯定・確認を公判で求めるべきとの見解もある(田口422,松尾下68,田宮391,結論において寺崎350)。これは,伝聞供述という特殊性に照らして,信用性の情況的保障の要件を具体化して定立したものものと解することもできるであろう。私見もこれに賛同したい。このように見てくると,判例のように機械的に複数の伝聞例外規定を適用すれば,信用性の情況的保障がなされることを前提とするのは悪しき概念法学といわなくてはならず,相当性を欠いている。伝聞供述の再伝聞については,解釈によって信用性の情況的保障の要件を定立すべきアプローチが正しいものがあるとみるべきであろう。
[2] 補足説明を加える。この論点を理解するには,実質的な伝聞法則の趣旨の射程距離がどこまで及んでいるかを具体的に思考することが重要であり,限定説と非限定説の対立もこの視点から考えなければ意味がない。まずは,条文から考えてみると,328条には「供述の証明力を争うためには」とある。そうすると,概念法学的な帰結は,弾劾との立証趣旨が明確にされていれば,特に328条で許容される証拠に限界はないということになるはずである。
したがって,ドイツ的な概念法学から導かれる結論は非限定説が正しいといわねばならない。現実に戦後すぐにおいて日本の刑訴法が大陸法の影響を強く受けていた時期は非限定説が主流であったように思われる。
しかしながら,非限定説はもはや今日では採用することができない解釈といわねばならない。なぜなら,日本の刑訴法はその後,英米法の影響を強く受けるに至ったからである。すなわち,実質的に伝聞法則の趣旨を潜脱する目的で328条の証拠として許容されることはできないとの解釈が主流になっていったからである。この問題意識からすれば,「伝聞法則の趣旨が実質的に潜脱されるか」という視点が最も重要ということになる。上記の学説の対立は,非限定説は論外といわねばならないが,それ以外は結局は,「伝聞法則の趣旨が実質的に潜脱されるか否か」のあてはめが異なっているにすぎない。
まず,この論点の対立には「厳格な証明」が要求される範囲の問題と関連している。この点,通説は補助事実についても厳格な証明が要求されるとするが,渡辺咲子は補助事実には厳格な証明はいらないとしている。たしかに,厳格な証明が必要なのは,構成要件該当事実を軸として刑罰権の存否・範囲にかかわる事実をいうのであるから,証拠の信用性に関わる補助事実はこれにあたらないと解することも可能である。その限りでは,私見は渡辺の見解に首肯できるものがあると考える。
以上を前提に考える。まず,限定説は,自己矛盾供述しか328条で許容しないとする。この見解は,補助事実についても厳格な証明が必要とする見解を前提としている。そうすると,補助事実についても伝聞法則の適用があるということになるのであるから,328条で「補助事実の弾劾」を広く認めるのであれば,伝聞法則の趣旨が没却されると非難するわけである。そして,かかる批判を受けないものは,伝聞法則の適用がない自己矛盾供述に限られると論じるわけである。
次に,渡辺説について考えると,渡辺は,厳格な証明は「補助事実」には及ばないと考えている。そうすると,そもそも補助事実には伝聞法則は適用がないということになるから,限定説と比較すれば伝聞法則の射程距離が短い分,その潜脱が問題となるということも理論的には少なくなる。それを踏まえて,「証人及び被告人の性格,能力,利害関係,偏見などの信用性のみに関する純粋な補助事実の弾劾については,厳格な証明はいらないので伝聞法則の適用はない。それゆえ,自己矛盾供述に加え,補助事実の弾劾については伝聞法則の趣旨を潜脱しないので,328条の証拠として許容される」と論じるのである。
最後に,大澤説であるが,この見解は「結論においては,渡辺説が妥当であると考えるが,学説上の通説である補助事実に厳格な証明が必要であるとする一線を譲ることはできない」という思考態度を前提に,それと矛盾しない理論を展開するものと解される。しかしながら,補助事実について厳格な証明が必要であると力説しておきながら,直ちに補助事実を証明する場合一般について伝聞例外を328条で認めることはその実質において一貫性を欠いており,大澤説は採用の限りではない。もっとも,判断の実質は,大澤説と渡辺説はあまり大きく変わるものではない。
このように考えてくると,限定説VS大澤・渡辺説という構図と理解したいと思うかもしれない。しかしながら,これらは結論が分かれることはほとんどないのである。重要なのは,なぜこのように筋が分かれるかを理解するという点にある。
これらの見解は,「伝聞法則の趣旨を実質的に潜脱する供述証拠は328条の証拠として許容されない」という思考態度が根底にある。そうだとすれば,渡辺説を前提としても,間接事実には厳格な証明を要することには争いがない。そうすると,補助事実の弾劾が要証事実とされていても,実質的に犯罪事実の存在の間接事実が要証事実となっていることがあると考えられる。現実にも,大澤が指摘するような,証人の能力・性格などを証明して公判供述を弾劾する例はほとんどないとされている。すなわち,大澤や渡辺の見解を前提としても,伝聞法則の趣旨を実質的に潜脱するかを見てゆくと,たいていはその潜脱が認められてしまうという関係にあると解される。そうすると,補助事実は自由な証明で足りると仮定すると,理論的には328条の証拠を自己矛盾供述に限定する必要性はないというべきことになる。しかし,伝聞法則の趣旨を潜脱を許さないという視点から吟味を重ねると結局,渡辺説からも許容できるのは,自己矛盾供述以外はないということになるであろう(この場合は,実質的な要証事実が間接事実の存在に向けられているという認定が必要となる)。それゆえ,限定説と渡辺説の間には結論には差異が生じるということはないのである。寺崎348は明示しないが,私見に同旨のようであり首肯するに足りるものである。
[3] 調査官解説は,「本判決は,判文自体から非限定説を排斥していることは明らかであり,また,証拠請求者によって扱いを異にする旨を判示しておらず,むしろ,本件事案が被告人側からの証拠請求であったことからして,片面的構成説も排斥したものであることが明らかである。しかし,『刑訴法328条により許容される証拠』がどのようなものかという形で限定を付する判示をしているため,純粋補助事実を特別に扱う説の中で実務家の中の有力説といえる自由な証明説については採否が留保された形となっている」と指摘している。