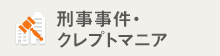違法収集証拠排除法則
第26編 違法収集証拠の排除
第1 問題の所在
1 違法に収集された非供述証拠の証拠能力
(1) 自白の場合との差異
① 条文の存否
供述の側面では自白法則(319条)があるが,物的証拠には条文がない
② 証拠価値の変化
捜索・差押え許可状なしに被疑者のアパートを捜索し,覚せい剤を押収したとしても,その覚せい剤は小麦粉に変わるわけではない
(2) 最判昭和24年12月13日裁判集刑事15号349頁
「押収物は,押収手続が違法であっても,物それ自体の性質,形状に変異を来すはずがないから,証拠たる価値に変わりはない。それゆえ,裁判所の自由心証によって,これを罪証に供すると否とはその専権に属する」
2 学説の展開―違法収集証拠排除論
(1) アメリカにおける排除法則の展開
ア 初期(1914年)
違法に押収した物を証拠に使うと修正4条(日本国憲法35条に相当)の保障が没却される
* この事件は連邦事件にしか適用がなかった(⇒適用は限定的)
イ 中期(1961年―排除法則の絶頂期)
論拠は,修正4条に違反するという点から,①違法捜査の防圧という抑止効と②裁判所は違法に加担しないという司法の廉潔性―にシフトする
⇒ 田宮博士の留学時期であり,田宮博士はこの時期の連邦最高裁の判例の影響を強く受けている
オ 後期(1970年―排除法則の試練)
70年代に入り,アメリカでは犯罪が急増し社会が保守化し,リベラリズムの退潮を受けて,排除法則は厳しい非難の的とされ,その適用の範囲がしぼむ
* 特に,具体的なデータを用いて抑止効果はないという論証が試みられた
⇒ アメリカは絶対的排除法則が採用されていたが,「不回避的発見の例外」や「善意の例外」が登場し,排除法則は徐々に骨抜きにされる試練の時代を迎える
(2) 日本における学説の展開
⇒ 田宮博士の影響が大きいので中期のアメリカの学説が輸入される!
① 適正手続の確保
② 司法の廉潔性の保持
③ 違法捜査の抑止[1]
第2 違法収集証拠排除法則
1 意義
違法収集証拠排除法則とは,証拠を収集する過程で違法な行為があった場合は,その証拠に証拠能力を認めない原則をいう
2 大阪覚せい剤事件判決(最判昭和53年9月7日刑集32巻6号1672頁)
「違法に収集された証拠物の証拠能力については,憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので,この問題は,刑訴法の解釈に委ねられているものと解するのが相当であるところ,刑訴法は,『刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする』(同法一条)ものであるから,違法に収集された証拠物の証拠能力に関しても,かかる見地からの検討を要するものと考えられる。
ところで,刑罰法令を適正に適用実現し,公の秩序を維持することは,刑事訴訟の重要な任務であり,そのためには事案の真相をできる限り明らかにすることが必要であることはいうまでもないところ,証拠物は押収手続が違法であつても,物それ自体の性質・形状に変異をきたすことはなく,その存在・形状等に関する価値に変りのないことなど証拠物の証拠としての性格にかんがみると,その押収手続に違法があるとして直ちにその証拠能力を否定することは,事案の真相の究明に資するゆえんではなく,相当でないというべきである。
しかし,他面において,事案の真相の究明も,個人の基本的人権の保障を全うしつつ,適正な手続のもとでされなければならないものであり,ことに憲法35条が,憲法33条の場合及び令状による場合を除き,住所の不可侵,捜索及び押収を受けることのない権利を保障し,これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること,また,憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると,証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定されるものと解すべき」
3 違法排除の法的根拠
(1) 最高裁の立場
排除法則は訴訟法レベルの原則という見解
⇒ 判例は,刑訴法1条の解釈によったのではなく,その趣旨に照らして法全体の精神から政策定立的解釈を試みたもの(田宮402)
(2) 憲法上の排除を認める見解
適正手続に関する憲法上の保障を根拠に挙げる見解
⇒ 判例は,「刑訴法の解釈に委ねられている」とするので,憲法上の保障を認める見解には立っていないと評価されており,この点は確立した最高裁の判例とされる(争点194)[2]
(3) 判例の読み方と機能
① 大阪覚せい剤事件(覚せい剤事案で事案の重大性が認められず,しかも,被侵害利益が人身の自由ではなくプライバシー侵害にとどまっていることに留意せよ)では,憲法上の証拠排除が問題とならない事案にすぎず,憲法上の排除が問題となるケースは事案によってはあり得る(大澤)
② 将来の違法捜査抑止の見地と司法の廉潔性の2点に根拠を求めていると理解するのが一般(司法の廉潔性は判例は言及していないが,ただ,裁判所が判例で排除法則を採用するにあたり最も用いやすい理由である。また,証拠排除の基準として「違法の重大性」が要求されているが,これは司法の廉潔性から根拠付けられやすい。将来の違法捜査の抑止の観点からいえば,違法が重大という場合のみ抑止の必要性があるとはいえないからである)。
4 証拠排除の基準
(1) 判例
①令状主義の精神を没却する重大な違法があり,②将来の違法な捜査を抑止する見地からして違法収集証拠の許容が相当でないときに,証拠能力否定
(2) 相対的排除(二段階の基準)
①証拠収集手続の違法・適法⇒②違法の重大性と抑止効から見た排除相当性
(3) 相対的排除に対する批判とその検討
ア 排除の根拠から見た相対的排除
違法であるが証拠排除しないでは,違法のやり得となる
イ 相対的排除の機能
証拠排除は決定的な証拠の利用を禁じ,明らかな犯罪者の無罪放免を帰結するという重大なコストを払うことになる。とすると,違法捜査の抑止や司法の廉潔性から,「違法,即排除」を導くことには疑問がある。抑止効からすれば,当該捜査官を処罰したり民事賠償という方法もある。また,司法の廉潔性からも,最終的には司法の信頼確保を目的とするから,明らかな犯罪者を放免すると,かえって国民の信頼を損ないかねない。さらに,裁判所が効果の重大性から,絶対的排除法則によると,安易に適法としてしまうおそれがある
(4) 視点
①違法収集証拠を用いることにより,被疑者・被告人の人権を侵害し,刑事司法システムの公正さや正義を疑わせるおそれの程度と②その証拠を排除することにより,真実発見の利益を放棄し,刑事司法システムの運用コストを増大させる程度との比較考量
(5) 違法の重大性と抑止効から見た排除相当性との関係
ア 重畳的か並列的か
⇒ 重畳的と見るのが素直
* 並列的な要件とみる見解の核心
重畳説は,「違法は重大ではないが,排除相当性がある」として証拠排除ができる余地が生じるのは妥当でない[3]
イ 判断の実際
違法が重大である場合は,排除相当性が認められることが多いので,事実上,違法が重大であるかが証拠排除されるか否かの分水嶺となる
ウ 重畳説から違法は重大であるが排除相当性はないというケース
二度と繰り返されることがないような稀な違法は排除されない(教室設例)
*法教328号71頁杉田発言
「違法収集証拠排除法則が争われてきたのは,もっぱら覚せい剤取締法違反の事例に限られてきたところ,仮に,これが被害者が死亡するような非常に重大な事案であって,争われている証拠が有罪・無罪を決する意義を有する場合は,警察官がミスをしたのみで重要な証拠を排除して凶悪犯人を無罪放免にしてよいかという非常に重い問いを付きけられ得る。この点については,利益衡量的な見地から,例外的とはいえ違法は重大でも排除不相当という結論に至る可能性がある」
第3 排除法則の展開
1 先行手続の違法
⇒ 証拠収集手続に先行する手続に違法がある場合
(1) 最判昭和61年4月25日刑集40巻3号215頁
判例は,先行する捜査手続における違法性が後行の証拠収集手続の適法性に「同一目的・直接利用」の関係がある場合は影響を及ぼすと言う
* 両手続を一体としてみて,全体について違法性を判断するわけではない
⇒ 先行する手続の違法の有無・程度を間接的に考慮する手法を採る[4]
(2) 最判平成15年2月14日刑集57巻2号121頁
「本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を潜脱し,没却するような重大なものである」。「このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは将来における違法捜査抑制の見地からも相当でない・・・から,その証拠能力を否定すべき」
(3) 同一目的か密接関連性か
ア 61年判例
61年判例は,先行手続と証拠収集手続の間に同一目的・直接利用の関係がある場合には,先行手続の違法が証拠収集手続に承継される。そして,違法の重大性の要件は,先行手続の違法を承継した証拠収集手続について判断される。
これに対して,15年判例は,証拠収集手続における先行手続の違法の承継という点は問題とされず,むしろ,違法の重大性の要件は逮捕という先行手続について判断されている。そして,証拠の許容性については,先行手続と密接な関連性があるかにより判断されている。
イ 川出説の問題提起
(ア) 論旨
最終的に獲得された証拠の証拠能力が問題なのであるから,先行手続と証拠収集手続との間の違法の承継と言う判断を介在させることなく,端的に先行の違法行為と因果関係を有する証拠がどのような場合にその証拠能力を否定されるのかを検討すればよい
(イ) 杉田判事の評価
違法の承継という観念で判断すると,選考の違法な手続から後行の証拠収集手続まで因果の仮定の逐一について,それが違法であることを指摘せざるを得ない。
杉田判事は,同一目的・直接利用という概念を用いると平成7年判例は説明に窮すると指摘する。すなわち,平成7年決定では,車の中を被告人の承諾なく警察官が調べたという事案である。そして,杉田判事は,この先行手続の違法は他の最高裁判例と比較すれば軽微であるという。しかるに,違法の承継の論理を用いると,車の検索の後の現行犯逮捕自体も違法となり最高裁もそのように指摘している。しかしながら,現行犯逮捕が違法であれば本来ならその場で釈放しなければならない。とすれば,違法状態を利用した任意採尿が本当に重大な違法といえないのか疑問が生じる,と指摘する。
⇒ 本判決で示された密接関連性の判断手法を用いれば,そのような無用の判断を経る必要はなくなるので基本的には妥当な方向を示すという
ウ 検討
違法の承継という考え方をとっても,証拠収集手続において考慮される違法性の実質を突き詰めてみると,先行手続の違法の程度と先行手続と証拠収集手続の因果性の程度―が考慮されている。このような視座からみると,「同一目的・直接利用」とは一定の因果性が認められるための基準とも考えられる。また,61年判例では,「同一目的・直接利用」が認められる場合でも,さらに,採尿が自由な意思により行われているという事情も考慮されたうえで,承継される違法性の程度が判断されている。これは,自由な意思というのは,因果性の程度の要素であるから,61年判例はこれも含めて判断している。
そうだとすれば,15年判例については,先行手続について重大な違法があるかを判断し,それと密接な関連性がある証拠であるかを判断する枠組みであったとしても,先行手続の違法の程度と因果性の程度を考慮するということになるので,実質的には両者の判断枠組みは共通しているものと考えられる
⇒ 両者の枠組みとしての違いを強調するのは意味がない
* 杉田判事は,因果性の濃淡の考慮要素として,同一目的,直接利用が挙げられるが,これは必要条件ではないとする。平成15年判例は,狭い意味での同一目的という要素はない。しかしながら,直接利用の関係にあったことは明らかで,逮捕状態を利用していることや時間的な接着性をあわせれば十分密接性を認められると指摘する
2 違法の重大性の判断
(1) 「令状主義の精神を没却するような重大な違法」
⇒ 実質的に強制処分とみるべきものが令状なしで行われたケースが典型!
* 任意同行後に採尿したが任意同行に違法があるというケースが典型
明示的な拒絶があるのに有形力を用いての滞留の強制(実質的逮捕と評価すべきような場合に採尿が行われたもの)
* 現行犯逮捕や緊急逮捕が可能というのであれば,違法の本質は手続的瑕疵ということになるので,逮捕される事情がない場合と比較すると違法は限定的となる
(2) 平成15年判例
この事案では通常逮捕に際し,逮捕状を呈示しなかった瑕疵が,判例の基準に当たるとは考えられない。
⇒ 事後的な警察官の態度の考慮
* 客観的な違法というのは,令状の提示をしなかったり緊急執行の手続を踏まなかったという手続的な瑕疵にすぎない。そうすると,「逮捕はできるけれども,手続を誤ったにすぎない」ので,違法の重大性は否定されやすい事案であった。ここでは,事後的な警察官の態度の考慮がなされているが,本来では,事後的な事情から客観的な違法性が上昇するということはないはずである。しかしながら,違法の糊塗を防ぐ行為をしているので警察官の法無視の態度や本件行為の違法性を認識していたということを推認するものと考えられる。そうすると,そのような有意性のある違法の場合は違法が重大と判断することができる
(3) 違法の有意性は「重大な違法」の必要条件か
たしかに,多くの判例では,「違法の有意性がない」ということを一つの論拠として違法の重大性の要件が否定されている。しかしながら,それらの判例をみると,所持品検査で被侵害利益がプライバシー侵害にとどまるものなど,客観的な違法性の程度が重大とはいえないものが中心とされている。そうだとすれば,客観的な違法性の程度が重大ではない場合に,「違法の有意性がない」というワーディングはあまり意味がないといえる。これに対して,平成15年判例は,客観的な違法が重大ではないのに,「違法の有意性」を挙げて証拠能力を否定している。そうすると,判例は,違法が客観的には重大ではなくても,捜査官の有意性を判断すれば,違法が重大であるといえることを前提とした判断をしているものと考えられる。したがって,重大な違法に違法の有意性は必要条件ではないと解すべき
*イメージ[5]
客観的な違法が重大⇒違法は重大
客観的な違法が軽微+捜査官に有意性あり⇒違法は重大[6]
*法教328号73頁杉田発言
「警察官といえども人間であるから,ミスをすることもあるが,単純ミスであればそのように処理をすればよかった。しかしながら,本件での警察官は,逮捕状の呈示,緊急執行をしていないばかりか,その後も逮捕状への虚偽記入,捜査報告書の虚偽記載を行い,公判でも偽証を続けているから,事実認定の問題としても,この警察官は逮捕状さえ取っていれば,それを呈示したり緊急執行をしなくても,そのような違法は大したことない,令状主義をないがしろにするような姿勢で今回の逮捕手続に臨んだと推認せざるを得ない」と指摘する
* 平成15年判例については,事後の隠蔽行為を違法な逮捕手続を行った捜査官の意図や令状主義を履践することに対する認識・態度を推認させる資料,すなわち遡及的情況証拠と理解すべき
3 排除法則の例外の有無
(1) 問題の所在
アメリカでは,排除法則の例外として,①不回避的発見の例外と②善意の例外という理論がある。これは,日本においても妥当する理論といえるかが問題
(2) 考え方
まず,不回避的発見の例外とは,たまたま一部の捜査官が違法捜査をなしたが,捜査官がその捜査をしなくてもいずれ他の捜査官が適正捜査を進めてその証拠に達したはずであるという場合には証拠は排除されないという考え方(家庭的因果関係の付け加え)である。また,善意の例外とは,違法捜査をした捜査官がその手続の合法性を信じていた場合は証拠を排除されないという考え方をいう。
しかしながら,日本においては,このような排除法則の例外は認められないと考えられる。アメリカにおいては,違法収集証拠排除法則の理論的根拠について,抑止効が正面に据えられている。そうすると,上記①及び②に該当する場合は,いずれも証拠を排除しても違法捜査の抑止的効果はないので排除法則の例外が認められるという理論的根拠に基づいている。これに対して,すでに述べたように,日本における排除法則は,司法の廉潔性が正面に据えられるに至っており,最高裁の判決のあてはめをみても,その判断は違法の重大性の要件の判断の精緻化に収斂する傾向を示している。したがって,日本の刑訴法の解釈としては,司法の廉潔性を害しないかという視点から筋を進めるべきであって,抑止効がないから排除法則の例外が認められる議論は失当であるといわざるを得ない。アメリカの排除法則は,その根拠を抑止効に求めたために,その後,不幸な展開を辿ったということを忘れてはならないというべきであろう。この点,「違法の程度が軽微でかつ偶発的な場合には,このような例外を認める余地もあろう」とする見解(田口)もあるが,客観的法益侵害の程度が軽微で,かつ,有意性がないというのであれば,もとより重大な違法がないとすれば足りるのであって,排除法則を骨抜きにするこれらの例外を認める余地があるとする田口の所論は首肯することができない。
4 私人による違法収集証拠
(1) アメリカの議論
繰り返すが,アメリカの排除法則は抑止効が論拠である。そうすると,私人が違法に収集した証拠を訴追機関が利用したとしても,将来の違法捜査抑止という観点からは関係がない。したがって,抑止効を論拠に据えると,私人による違法収集証拠は排除する必要はないという帰結になる。
(2) 考え方
そもそも,日本では,排除法則の論拠は司法の廉潔性にある。したがって,違法が重大といえるのであれば,証拠排除をすることができると解するのが相当である。具体的には,①客観的法益侵害の程度が大きい場合は,捜査機関の捜査との密接関連性を考慮するまでもなく証拠排除するべきであろう。また,②客観的法益侵害の程度が大きくない場合であっても,捜査機関が私人に依頼をしたというように,捜査機関の有意性と密接な関連性が認められるという場合には,証拠排除すべきものと考える(私見)[7]。白取説は、違法の程度がどの程度にいたれば証拠排除されるかについては、判例のいう「重大な違法」を超える違法があれば証拠排除すべきではないか、と考えるとすると、証拠排除について「しぼり」をかけている。なお、医師に関する最決平成17年7月19日刑集59巻6号600頁は、「所論は,担当医師が被告人から尿を採取して薬物検査をした行為は被告人の承諾なく強行された医療行為であって,このような行為をする医療上の必要もない上,同医師が被告人の尿中から覚せい剤反応が出たことを警察官に通報した行為は,医師の守秘義務に違反しており,しかも,警察官が同医師の上記行為を利用して被告人の尿を押収したものであるから,令状主義の精神に反する重大な違法があり,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。
しかしながら,上記の事実関係の下では,同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったものであって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同医師のした上記行為は,医療行為として違法であるとはいえない。
また,医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。
以上によると,警察官が被告人の尿を入手した過程に違法はないことが明らかであるから,同医師のした上記各行為が違法であることを前提に被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力を否定する所論は,前提を欠き,これらの証拠の証拠能力を肯定した原判断は,正当として是認することができる。」と判示している。調査官報告では、「医師による被告人の尿の採取過程や警察官への通報にはいずれも違法はなく,結局,警察官が被告人の尿を押収した点も違法はないことに帰することになったから,本決定は,様々な議論のある私人(捜査機関以外)の違法収集証拠排除の論点については検討するまでもなく,被告人の尿の鑑定書等が違法収集証拠であるとの所論は,前提を欠くとして,被告人の尿鑑定書等の証拠能力等を認めた原判断を是認したものと考えられる。
そして,その結論に至る過程で,警察官による被告人の尿の入手過程の違法性,つまり,医師の医療行為としての適法性や守秘義務違反の成否についての判断が示されたが,その中でも,取り分け,担当医師による警察官への通報行為と医師の守秘義務違反の成否の論点については,先例がなく,患者の治療の過程で当該患者自身の犯罪情報を得た場合における警察通報の適否に関する医療現場の行動指針を示すものとしても大きな意義を有する上,その余の論点も含めると,下級審の裁判実務にも参考となるところも少なくなく,本決定は,判例として重要な意義を有すると考えられる。」と解説されている。
5 毒樹の果実(違法収集証拠として排除される証拠に基づいて得られた証拠)
(1) アメリカの議論
ア 定義
毒樹の果実論とは,違法な手続によって獲得された証拠そのものの証拠能力を否定するだけではなく,その証拠から2次的・派生的に得られた証拠もまた排斥するというアメリカの理論をいう
イ 例外理論[8]
① 稀釈化の法理
稀釈化の法理とは,被告人が任意に行動して,最初の違法な手続による汚染状態が薄まった場合には証拠は排除されないとする理論をいう
② 独立入手源の法理
独立入手源の法理とは,違法な手続とは無関係な,独立した源泉から収集された証拠は排除されないという理論をいう
*毒樹の果実の例外の整理
| 条件関係がなし | 条件関係は認められる場合 | ||
| 被疑者の意思が介在して遡及禁止の場合 | 別途進行中の別の手続で発見できる,仮定的条件の付け加えの場合 | ||
| 独立入手源の例外 | 稀釈化の理論 | 不回避的発見の法理[9] | |
(2) 日本の議論
ア 毒樹の果実論の理論的根拠
● 毒樹の果実論の理論的根拠は,「排除されるべき第1次証拠に基づいて獲得された」という点にあるとする見解
○ 「派生証拠まで排除しなければ,排除法則の意味がなくなる」という点に
据えるべき(杉田判事)
⇒ 派生証拠まで排除しなければ排除法則の趣旨が没却されるような社会的事実関係にあるか否かが重視されるべき
* 杉田判事は,一連の社会的事実関係における証拠は派生証拠となり得るが,新たに発生した犯罪に関する証拠であり,社会的事実として別のものといい得るのであれば,派生証拠として排除の対象から政策的に外すべきとする
イ 平成15年判例の登場
「証拠能力のない証拠と関連性を有する証拠」,「関連性は密接なものではない」
* 証拠能力は,違法性と因果性の掛け算で決まる(大澤)
ウ 伊藤裁判官の補足意見(最判昭和58年7月12日刑集37巻6号791頁)
(ア) 事案
Xは,本件現住建造物等放火罪を理由とする逮捕,勾留に先き立って,住居侵入罪を理由として逮捕されている。この逮捕は,裁判官が適法に発付した逮捕状によって行われたものであるが,その真の目的が,当時いまだ逮捕状を請求するに足りる資料のなかった本件現住建造物等放火事件について被告人を取り調べることにあり,住居侵入事件については,逮捕の必要性のなかったことが認められる。したがって,住居侵入罪の逮捕は,憲法の保障する令状主義を潜脱して強制捜査を行つた,いわゆる違法な別件逮捕にあたる。これによって収集された自白は,これを違法収集証拠として裁判の資料から排除するのが,適正手続の要請に合致し,また将来において同種の違法捜査が行われることを抑止し,司法の廉潔さを保持するという目的からみて相当であると考えられる。問題は,その後に行われた本件たる現住建造物等放火罪を理由とする逮捕,勾留中における,捜査官に対してされた同罪に関する被告人の自白が毒樹の果実として証拠能力を否定すべきかである
(イ) 判旨
「違法収集証拠(第一次的証拠)そのものではなく,これに基づいて発展した捜査段階において更に収集された第二次的証拠が,いわゆる『毒樹の実』として,いかなる限度で第一次的証拠と同様に排除されるかについては,それが単に違法に収集された第一次的証拠となんらかの関連をもつ証拠であるということのみをもって一律に排除すべきではなく,第一次的証拠の収集方法の違法の程度,収集された第二次的証拠の重要さの程度,第一次的証拠と第二次的証拠との関連性の程度等を考慮して総合的に判断すべきものである。
第一次的証拠の収集者自身及びこれと一体とみられる捜査機関による第二次的収集証拠の場合には,特段の事情のない限り,第一次的証拠収集の違法は第二次的証拠収集の違法につながるというべきであり,第二次的証拠を第一次的証拠と同様,捜査官に有利な証拠として利用することを禁止するのは,将来における同種の違法捜査の抑止と司法の廉潔性の保持という目的に合致するものであって,刑事司法における実体的真実の発見の重要性を考慮にいれるとしても,なお妥当な措置であると思われる」
「しかしながら,本件勾留質問は,裁判官が,捜査に対する司法的抑制の見地から,捜査機関とは別個の独立した職責に基づいて,受動的に聴取を行ったものである。また,これに対する被告人の陳述も任意にされたと認められる。そうすると,その手続自体が適法であることはもとより,この手続に捜査官が支配力を及ぼしたとみるべき余地はない。このことに照らすと,第一次的証拠との関連性も希薄であって,この勾留質問調書を証拠として許容することによって,将来本件と同種の違法捜査の抑止が無力になるとか,司法の廉潔性が害されるとかいう非難は生じないと思われる。
また,消防機関は,捜査機関とは独立した機関であり,その行う質問調査は,効果的な火災の予防や警戒体制を確立するなど消防活動に必要な資料を得るために火災の原因,損害の程度を明らかにする独自の行政調査である。そうすると,消防機関による質問調査が,捜査機関によって違法に収集された第一次的証拠を資料として発付された逮捕状による被疑者の身体拘束中に,当該被疑者に対して行われても,そこに捜査と一体視しうるほどの密接な関連性を認めて,その質問に対する任意の供述の証拠能力を否定すべきものとする必然性はない」
エ 証拠能力の判断枠組み
第1次証拠が排除されても当然に第2次証拠の排除が帰結されるわけではないが,第2次証拠を排除しなければ,司法の廉潔性や抑止効の観点から証拠排除の目的を達成することができない場合には2次的証拠の証拠能力も否定
* 判断の基準
① 第1次証拠の違法の程度
② 第2次証拠が第1次証拠の違法性にどの程度の影響を受けているか
オ 因果性の程度のあてはめ(平成15年判例)
① 司法審査による令状発付の介在
② 適法な窃盗事件についての捜索差押令状とあわせて執行
* 大澤は,①については令状発付自体に疑問があるのでこの点の議論は残されているという。なお,杉田判事は,違法に収集された疎明資料に基づいて令状が発付されたとしても,『実質的な審査』ができていないから,関連性は稀釈されていないと指摘する[10]
* なお,「先行手続の違法がある場合の証拠の証拠能力の問題」と「毒樹の果実」の判断手法は,基本的には同一の枠組みである(大澤)
6 捜査の違法と量刑
(1) 問題の所在
排除法則はオールオアナッシングで効果が峻烈すぎる。重大な違法があっても,無罪とするのは疑問がある場合もあるし,逆に重大な違法といえなくても,何の効果が生じないのもおかしい
(2) 木谷明説(杉田判事も同調,反対,指宿説)
量刑の段階でその違法捜査を受けたこと自体を被告人に有利な情状として考慮するとして評価
(3) 理論的根拠
ア 原田説
犯行後被告人が受けた社会的制裁などと同様,違法捜査によって被告人が受けた苦痛を,刑罰という苦痛や害悪の先取りとして精算する趣旨
イ 杉田説
捜査過程に違法があったとしても,違法収集証拠として証拠排除されないというのであれば,あとは国賠にお任せというのではいけない。現に手続的正義に反する事態を国家機関が引き起こしているのであるから,それは刑事上の実体的正義を実現する最終段階で考慮し,何らかの精算をすべき[11]
⇒ 杉田判事は,この理論を用いて,取調べ中に警官が被告人に暴行を加えた事案について,量刑上,有利に斟酌している(大阪地判平成18年9月20日判時1955号172頁)。このような対処は,取調べに対する有効な規律の一つにもなるのではないかと考えるところであり,私見も賛成するものである。
*浦和地判平成元年12月21日判タ723号257頁
刑罰権を実現する過程で被疑者に課せられる種々の不利益(未決勾留や取調べ等)は,それが適法なものである限り,被疑者において当然これを受忍しなければならないが,被疑者に受忍を求め得るのは,あくまで刑罰権を実現する上で必要不可欠なものとして法が許容した限度に止まると解すべきである。
したがって,かかる不利益が,本来法の予定する以上に著しい苦痛を被疑者に与えるものであったときは,被疑者がかかる苦痛を受けた事実は,広義の「犯行後の状況」の一つとして,ある程度量刑に反映されるべきものと考える。
かかる見解に対しては,刑罰の量は,犯罪の違法性及びこれに対する被告人の有責性の程度等により決せられるべく,捜査の違法を量刑に反映させるのは不当であるとの反論も考えられる。しかしながら,法定の手続に従い,被告人(被疑者)に対し本来受忍を求め得る限度での苦痛しか与えずに科される刑罰の量と,法定の手続を逸脱し,被告人(被疑者)に対し右の限度を超える著しい苦痛を与えた上で科される刑罰の量に一切差があってはならないというような見解は,社会の常識ないし正義感情に反し,到底採用し難いところである(ちなみに,違法捜査の場合ではないが,例えば,公訴の提起自体により被告人が公職を失ったり,社会的地位を失墜した場合のように,刑事手続の遂行により,被告人・被疑者が通常の場合と比べ著しい不利益を受けるときに,かかる不利益を量刑上ある程度考慮に容れ得ることは,一般に当然のことと考えられている。)
*大阪地判平成18年9月20日判時1955号172頁
捜査段階における被告人の取調べ中,警察官が被告人に対し有形力を行使した事実は当者事間で争いがないところであり,もしこの有形力行使が違法な暴行であると判断されるのであれば,その違法の重大さ・深刻さからしても,これが被告人の量刑判断に影響を及ぼすことは避け難いところであると思われる。
けだし,現在の刑事裁判実務では,刑事訴追の過程で被告人がいかなる苦痛を被ったかということも広い意味での「犯行後の状況」として量刑上考慮されるべき一事情になり得るものと解されているところであるが,捜査過程で捜査官の側が被告人に対し違法を働いたという事情もその一種として位置付けられるのであって,量刑への影響の程度が基本的に行為責任の幅の中に止まる限りは,これを量刑の際の一事情として考慮することを否定すべき理由はないように思われる。ことに,捜査官による違法捜査によって被告人が肉体的・精神的苦痛を被ったという場合は,本来であれば,実体的にも手続的にも刑事上の正義を追求し体現しなければならない刑事訴追の過程において,国家機関の一員たる捜査官が自ら手続的正義に反する振る舞いに出て,これが被告人に対し現実の苦痛を与えたというのであるから,衡平の見地からも,この点は量刑事情として軽視すべからざるものと考えざるを得ないのであって,その手続的正義に反する度合い,すなわち捜査官が犯した違法の程度・深刻さや,これによって被った被告人の肉体的・精神的苦痛の程度等を総合的に考慮するとともに,他方で,この違法や苦痛を事後的にせよ消却・鎮静化させる実効的措置が既に存在し又は今後施され得る現実的可能性があるか否かの点も相関的に併せ考えた上,実体的正義実現の最終段階である量刑判断に適宜それを考慮・反映させるべきであると考える。
*大型否認27
司法研修所の文献は,裁判員裁判においては,「有罪無罪又は量刑の判断に必要不可欠な事実に限られるべき」であるから,証拠構造から有罪無罪や量刑に関係しない場合は,もはや「刑事裁判において解明すべき事実に当た」らないとの見解を示す。そうだとすれば,違法収集証拠が有罪無罪の分水嶺となるのは,その証拠構造からみて,薬物事犯くらいなものであるから,違法収集証拠排除法則が薬物事犯以外の刑事裁判から葬り去られる可能性を示唆するものということができよう。
もっとも,司法研修所の文献の見解を参考にしても,「違法捜査は量刑を減じる情状となる」という命題を承認することができれば,捜査の過程に違法があったか否かを取り調べる必要性が生じることになる。そうだとすれば,違法か否かを判断することを迫られる可能性が残るとする余地が出てくる。しかしながら,司法研修所の文献は,裁判員裁判を迅速に終わらせるためには,当該証拠を厳選すべきとの立場から,国家賠償で解決すれば足りるとの見解に直結させており,論理に飛躍があるように思われる。もとより,その裁判をするための準備手続に違法があったのに,その裁判で違法があったか否かを取り上げる必要はないというのは,上記の杉田説にかんがみると問題があるといわざるを得ない。
[1] 抑止効説は,もともと国家による違憲行為の抑止を内容とする憲法原理として,出発したものであるが,違法抑止という機能面に注目される余り,いつの間にか憲法上の保障という見解はなくなり,「判例の作り出す予防ルール」にグレード・ダウンさせられることになる。
[2] このように,憲法上の問題とされなかったのは,上告理由の中で違法収集証拠を証拠採用とするのは憲法違反という主張を排斥するためと言われている。だが,憲法上の証拠排除が認められる余地が事案によってはあるということになれば,憲法違反の上告理由が成り立つ場合もあるであろう
[3] この並列的な要件とみる見解は,多彩な証拠排除を可能とするので一見魅力的に写るが,理論的背景まで読むと相当ではない。もとより,絶対的排除法則論の影響を受ける田宮博士も支持していない。なぜなら,アメリカにおける排除法則の退潮の原因は,「抑止効に効果はない」という反証にあった。そうすると,もし抑止効に重点を置いた判例の読み方をすると,その実証の困難性のゆえにかえって排除相当性が認められることはほとんどなく,結果,証拠排除が認められる余地がなくなると言うことになりかねないのである。したがって,今日の学説が排除法則の論拠として,「司法の廉潔性」を正面に据え,それとつながる「違法の重大性」の要件を重視する流れにあるのも,アメリカが「抑止効」を論拠の正面に据えたために,排除法則の退潮を招いたことの反省に立っているということもできるであろう。
[4] 先行する違法捜査と後の手続とが「同一目的に向けられ」,先行する違法手続によってもたらされた状態を「直接利用して」後行の手続がなされたときに初めて,先行手続における違法の有無・程度を十分考慮して後行の手続の適法・違法を判断する。しかも,違法の有無・程度は,すでに述べた排除法則の2つの基準を考慮して判断する。したがって,先行手続に違法があっても,その影響を受ける後行の手続はかなり限られたものになると考えられる
[5] 大澤の所論は興味深い示唆を示している。というのも,従来は,「重大な違法」と「排除相当性」の関係を「かつ」で結ぶのか「OR」で結ぶのかという議論がなされていた。この点に関し,寺崎364は,「OR」で結ぶのが妥当であるとしており,その論拠として,平成15年判例との整合性を挙げている。すなわち,寺崎は,平成15年判例は,「重大な違法」がないケースでありながら,「排除相当性」があるケースと位置付けていると分かる。これに対して,大澤の所論は,実質的には,「重大な違法」のみが要件となり,「排除相当性」は実質的な要件ではないという田宮博士の所論を前提としつつ,「重大な違法」の中でルールを準則化していこうという試みと位置付けられる。そして,重大な違法があるというためには,①客観的法益侵害の程度が大きいこと,②客観的法益侵害の程度は大きくないが捜査官に有意性があること―というように整理をする。これは,寺崎が,「OR」説に立ちながら,①重大な違法がある場合,②重大な違法はないが排除相当性がある場合―という整理とほぼパラレルということができる。私見は,アメリカの排除法則の失敗にかんがみ,排除相当性を要件として実質的に意味づけを行うことには躊躇を感じざるをえない。したがって,私見は大澤の所論を支持する。
[6] 杉田判事は,重大な違法かは客観的に決まるべきであり,捜査官の意図は関係ないとする見解に対して,「刑法における結果無価値と行為無価値の対立にも関連する問題であって・・・訴訟法の分野においてのみ,行為者の主観的事情を度外視して違法評価をしなければならないという立論は成り立たない」と指摘する。
[7] この点の白取346の叙述は,おおむね私見と同旨をいうものと思われる。白取は,私人による違法収集証拠は原則として証拠排除されないという。白取は,田宮博士の影響を受けるので,排除法則の主要な論拠に抑止効を据える。それゆえ,このような帰結になるのであろう。もっとも,白取は,①捜査機関が私人に証拠収集を依頼するなど捜査の一環として私人が関与した場合,②違法の程度が著しく手続の公正という点で容認しえないときは,例外的に証拠排除されるとするのが通説という。これは,概ね,大澤の所論を前提に敷衍する私見と同旨であるということが分かるであろう。なお,白取346は,私人による違法収集証拠については,「判例のいう『重大違法』を超える違法」が必要というが,排除法則の論拠を司法の廉潔性に据える私見からは賛成できない。そもそも,司法の廉潔性は客観法というべきであるから,その証拠を用いると国民の司法に対する信頼が損なわれるか―という視点から判断すべきものである。したがって,私人と捜査機関という主体の違いから,客観法のあてはめが異なるとは考えられない。特に,私人の場合にのみ,「『超』重大な違法」と要件を加重する論拠はない。
[8] 考えるに,稀釈化の法理と独立入手源の法理は,先行する違法手続と2次証拠との間の因果性の濃淡を問題としているものと考えられる。そうだとすれば,排除法則の論拠とは一応関係がないということができるので,この2つの理論については,日本においても参考にすることができるといえるであろう。ただし,アメリカでは,絶対的排除法則であるから,その例外理論の必要性が大きいのに対して,日本では,もともと相対的排除法則が採られているから,例外理論の必要性は高くない。したがって,あてはめをする場合でも,固く判断をするのではなく,その程度を意識して因果性の程度がどれくらいあるのかということを刑法における因果関係論なども参考にしながら,具体的に確定して判断していくことが求められよう。
なお,毒樹の果実の理論の例外理論として,不回避的発見の理論を挙げる者もいる(寺崎366)が,これは,むしろ,排除法則自体の例外とみるべきで,毒樹の果実の例外と位置付けることは相当ではない。しかも,不回避的発見の理論的根拠は,抑止効という論拠が妥当しないという点に求められている。そうすると,司法の廉潔性を論拠に据える限り,不回避的発見の法理を受け容れることは許されない。
[9] 割り切るのは難しいが,条件関係の判断で仮定的条件を付け加えるのは許されないというのが刑法理論である。ところが,刑訴法では,仮定的条件を付け加えて,「『もし』違法手続で収集しなくても,別途進行する手続で発見されていた」という論法で因果性を弱めようというわけである。しかしながら,これは理論的に誤っていると言わざるをえない。その証拠を発見する原動力を考えれば,違法な先行手続の寄与度が100パーセントなのであって,仮定的に「こうなるかも知れない」といっても因果性が弱まるわけではない。したがって,アメリカの不回避的発見の法理というのは,客観的な因果性の濃淡を問題にしているというよりかは,抑止効の観点から捜査官に悪意がないということを過度に重視する主観的な因果性を問題にしているといえるであろう。したがって,司法の廉潔性を根拠に据える限り,やはり,いかなる視座から考えても不回避的発見の法理には疑問がある。この点に関して,杉田判事は,やはり因果性がなくなるというほどではないが多少は弱くなるという趣旨のあてはめをしている。すなわち,たしかに,窃盗の捜索差押許可状が存在していたとしても,それだけで覚せい剤を差し押さえることは許されない。それゆえ,差押えの部分については,覚せい剤取締法違反の令状によって得たものといわざるを得ず,違法との因果関係は存在する。しかしながら,少なくとも,「被告人宅を捜索し覚せい剤を発見するところ」までは,窃盗罪の令状でフォローされる。そうすると,違法がなくても覚せい剤は発見され得たということになる。したがって,その密接性はかなりの程度薄められる,とのあてはめを展開する。
[10] この点,司法審査が媒介されていることは重視しない方がよい。たしかに,覚せい剤の差押えは令状によって行われているが,その疎明資料として尿の鑑定書が使われている。そうすると,令状の疎明資料がすべて違法に獲得された者である場合には,令状は本来発付されなかったということになるから,むしろ,先行手続との因果性の程度は濃いという判断がされる。そうすると,司法審査を経たとしてもそれが因果性を弱める要素にはならないわけである。また,違法の重大性の判断には,捜査官の有意性も考慮されるところ,さすがに,令状請求をしたのが当の警察官であるという事情があれば,なおさら因果性を弱めるということにはならないと思われる。他方,本件では,窃盗事件についての令状による捜索も現に行われており,その捜索だけからでも発見されていた可能性が高いので,この観点から先行手続との因果性は薄いといい得る。これは,「被告人が任意に行動した」わけではないから,稀釈化の法理の応用とはいえないが,これを独立入手源の法理の応用と見るかは別にして,因果性が弱まっていることは間違いがないであろう。
[11] 杉田説は少し難しい点があると思われるが,要するに,捜査官が違法なことをしてしまったわけであるが,排除法則や自白法則をすべり落ちて証拠能力があるとしても,国家が手続的面において卑劣なことをしたのであれば,最終段階ではその違法を精算すべきとの考え方である。手続的な不正義について手続の段階では,精算することができなかったが,およそ国家機関が卑劣なことをした以上精算がいらないはずはない。そこで,実体的正義実現の最終段階である量刑判断でやるしかない,という理屈を立てているように思われる。いわば,刑訴の問題を刑法に持ち込んで解決しようという試みともいえよう。