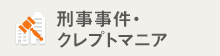検察側の罪人
検察側の罪人という映画をみた。
冒頭、検事の最上は「自分の信じる正義に固着する検事は罪人になる」との定式を述べる。
この映画は、3人の犯罪者又は容疑者がそれぞれ証拠関係が符合せず、神の目からみたとき全員が有罪であるのに、証拠関係でみたとき無罪になる、というようなストーリーの映画だ。
この映画をみたとき、犯罪心理学のケースでみたジャスティス事件を思い出した。最上もまた検事でありながら、アメリカの裁判官が評決の際に用いる小槌を集めるのが趣味であったことをそれを示唆させる。ジャスティス事件では、さすまたであったが、少年が、母親が、不倫男性と性交渉をしている際、それを見て暴行を加えていると勘違いし、あるいは、不潔な行為と考え、父母ともに殺害したという事件だ。その後も男性は、主に、性的産業に従事する女性に対して「評決」を下していったシリアルキラーである。今回でいえば、最上検事がシリアルキラーといったところであろうか。
ストーリーは、都内で発生した殺人事件。犯人は不明。
事件を担当する検察官は、東京地検刑事部のエリート検事・最上(木村)と、刑事部に配属されてきた駆け出しの検事・沖野(二宮)だ。木村は複数いる被疑者の中から、意図的に、一人の男に狙いを定め、執拗に追い詰めていく。
実は、その男・松倉は、過去に時効を迎えてしまった未解決殺人事件の重要参考人であった人物だ。最上を師と仰ぐ二宮は、被疑者に自白させるべく取り調べに力を入れるのだが、松倉は犯行を否認し続け、一向に手応えが得られない。
やがて沖野は、最上の捜査方針に疑問を持ち始める。「最上さんは、松倉を、犯人に仕立て上げようとしているのではないか?」というものであった。
検察事務官が劇中指摘するが、「検事の価値観は犯罪者とばかり接しているから、ねじ曲がっている」という指摘が出る。たまに弁護士においても、価値観がゆがんでいるがゆえ、社会通念上の健全な正義から大幅に逸脱している者がいる。仮に自分が正義に固着しているとすれば危険なことだということが分かる。重要な指摘として胸に刻むべきであろう。事件単位の原則がありながら、別件逮捕を強行し、結果、殺人での再逮捕はできなかった。真犯人は別にいることが分かったが、木村は、松倉を公判で死刑にしたいとねじ曲がった正義感を有していた。そして、真犯人には、自ら「評決」を加える。
以前、修習のころ、検事が嬉々として暴力団の出世の構造を語ってくれたことがあった。これではどちらがヤクザか分かるまい。もちろん検事が法務省等に出向することもあり、永遠に捜査担当検事ではないことが多い。しかし、犯罪心理学の観点からみても、その正義感なるものがあるとすれば、それを長きに適正に保つことは難しいように思う。だが、そうした問題提起が垣間見れたところは良かったと思われる。また、劇中で、「相手は国選ですからね」と国選を馬鹿にしているような言動を見逃せない。日本も少なくとも裁判員のような事件では、裁判所や法務省に所属する刑事専門の弁護士を韓国のように例えば「弁務検事」「弁務専門官」のように制度化すべきではないか、との感想を持った。