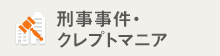前科及び類似事実に関する推認は認められるのか
最近、前科及び類似事実に関する重要判例があります。
まず、前科証拠を犯人の同一性を証明するために用いる場合において、、最判平成24年9月7日刑集66巻9号907頁は、前科にかかる犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、これが起訴にかかる犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用することができる」としました。
これは、他人宅に窃盗に入って欲する金品を得られないときに腹立ち放火したという事案で、同種前科で証拠能力を認めた原審を破棄し、原審の認定は、「実質的根拠に乏しい人格評価による認定というほかない」と説示しました。
「前科も一つの事実であり,前科証拠は,一般的には犯罪事実について,様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有している。反面,前科,特に同種前科については,被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価につながりやすく,そのために事実認定を誤らせるおそれがあり,また,これを回避し,同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため,当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど,その取調べに付随して争点が拡散するおそれもある。したがって,前科証拠は,単に証拠としての価値があるかどうか,言い換えれば自然的関連性があるかどうかのみによって証拠能力の有無が決せられるものではなく,前科証拠によって証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。本件のように,前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって,初めて証拠として採用できるものというべきである。
前刑放火は,原判決の指摘するとおり,11件全てが窃盗を試みて欲するような金品が得られなかったことに対する鬱憤を解消するためになされたものであること,うち10件は侵入した室内において,残り1件は侵入しようとした居室に向けてなされたものであるが,いずれも灯油を撒布して行われたものであることなどが認められる。本件放火の態様は,室内で石油ストーブの灯油をカーペットに撒布して火を放ったという犯行である。
原判決は,これらの事実に加え,被告人が本件放火の最大でも5時間20分という時間内に上記の放火現場に侵入し,500円硬貨2枚とカップ麺1個を窃取したことを認めていることからすれば,上記の各前科と同様の状況に置かれた被告人が,同様の動機のもとに放火の意思を生じ,上記のとおりの手段,方法で犯行に及んだものと推認することができるので,関連性を認めるに十分であるという。しかしながら,窃盗の目的で住居に侵入し,期待したほどの財物が窃取できなかったために放火に及ぶということが,放火の動機として特に際だった特徴を有するものとはいえないし,また,侵入した居室内に石油ストーブの灯油を撒いて火を放つという態様もさほど特殊なものとはいえず,これらの類似点が持つ,本件放火の犯行が被告人によるものであると推認させる力は,さほど強いものとは考えられない。
原判決は,上記のとおり,窃盗から放火の犯行に至る契機の点及び放火の態様の点について,前刑放火における行動傾向が固着化していると判示している。固着化しているという認定がいかなる事態を指しているのか必ずしも明らかではないが,単に前刑放火と本件放火との間に強い類似性があるというにとどまらず,他に選択の余地がないほどに強固に習慣化していること,あるいは被告人の性格の中に根付いていることを指したものではないかと解され,その結果前刑放火と本件放火がともに被告人によるものと推認できると述べるもののようである。
しかし,単に反復累行しているという事実をもってそのように認定することができないことは明らかであり,以下に述べる事実に照らしても,被告人がこのような強固な犯罪傾向を有していると認めることはできず,実証的根拠の乏しい人格評価による認定というほかない。
すなわち,前刑放火は,間に服役期間を挟み,いずれも本件放火の17年前の犯行であって,被告人がその間前刑当時と同様の犯罪傾向を有していたと推認することには疑問があるといわなければならない。加えて,被告人は,本件放火の前後の約1か月間に合計31件の窃盗(未遂を含む。以下同じ。)に及んだ旨上申している。上申の内容はいずれも具体的であるが,これらの窃盗については,公訴も提起されていない上,その中には被告人が十分な金品を得ていないとみられるものが多数あるにもかかわらず,これらの窃盗と接着した時間,場所で放火があったという事実はうかがわれず,本件についてのみ被告人の放火の犯罪傾向が発現したと解することは困難である。
(2) 上記のとおり,被告人は,本件放火に近接した時点に,その現場で窃盗に及び,十分な金品を得るに至らなかったという点において,前刑放火の際と類似した状況にあり,また,放火の態様にも類似性はあるが,本件前科証拠を本件放火の犯人が被告人であることの立証に用いることは,帰するところ,前刑放火の事実から被告人に対して放火を行う犯罪性向があるという人格的評価を加え,これをもとに被告人が本件放火に及んだという合理性に乏しい推論をすることに等しく,このような立証は許されないものというほかはない。
したがって,本件放火の犯罪事実を立証するための本件前科証拠の取調べ請求を全て却下した第1審裁判所の措置は正当であり,これについて判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に当たるとした原判断には刑訴法379条の解釈適用を誤った違法がある。この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
また、最判平成25年2月20日刑集67巻2号1頁は、同じく同種前科及び類似事実の証拠能力が問題になったものである。事案は、原審のいう、「いわゆる色情盗という特殊な性癖」が前科及び類似事実に認められるかが争点となったものです。決定は、行動傾向は、前科に係る犯罪事実に照らしても曖昧なものであり、「特異な犯罪性向」ということは困難であるとしたうえで、そもそも、このような犯罪性向を犯人が被告人であることの間接事実とすることは、被告人に対して実証的根拠の乏しい人格的評価を加え、これをもとに犯人が被告人であるという合理的根拠に乏しい推論をすることにほかならず許されない、としています。
前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いようとする場合は,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,その特徴が証明の対象である犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって,初めて証拠として採用できるところ(最高裁平成23年(あ)第670号同24年9月7日第二小法廷判決・裁判所時報第1563号6頁参照),このことは,前科以外の被告人の他の犯罪事実の証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いようとする場合にも同様に当てはまると解すべきである。
そうすると,前科に係る犯罪事実や被告人の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることは,これらの犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,その特徴が証明対象の犯罪事実と相当程度類似していない限りは,被告人に対してこれらの犯罪事実と同種の犯罪を行う犯罪性向があるという実証的根拠に乏しい人格評価を加え,これをもとに犯人が被告人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されないというべきである。
これを本件についてみるに,原判決指摘アの色情盗という性癖はさほど特殊なものとはいえないし,同イの,あらかじめ下見をするなどして侵入先の情報を得る,女性用の物の入手を主な目的とする,留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入するという手口及び態様も,同様にさほど特殊なものではなく,これらは,単独ではもちろん,総合しても顕著な特徴とはいえないから,犯人が被告人であることの間接事実とすることは許されないというべきである。また,原判決指摘ウの「特異な犯罪傾向」については,原判決のいう「女性用の物を窃取した際に,被告人本人にも十分に説明できないような,女性に対する複雑な感情を抱いて,室内に火を放ったり石油を撒いたりする」という行動傾向は,前科に係る犯罪事実等に照らしても曖昧なものであり,「特異な犯罪傾向」ということは困難である上,そもそも,このような犯罪性向を犯人が被告人であることの間接事実とすることは,被告人に対して実証的根拠の乏しい人格的評価を加え,これをもとに犯人が被告人であるという合理性に乏しい推論をすることにほかならず(前掲最高裁平成24年9月7日判決参照),許されないというべきである。
(3) したがって,原判決が,上記前科に係る犯罪事実並びに第1審判決判示第1ないし第9及び第19の各事実にみられる上記アないしウの特徴が第1審判決判示第10ないし第15,第18及び第20の各事実に一致することを上記各事実の犯人が被告人であることの間接事実の一つとしたことは違法であり,原判決には法令違反がある。