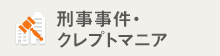被疑者勾留
被疑者勾留は分からないという方が多いと思います。今では当たり前では昔では信じられませんが、被疑者勾留は、検察官の起訴・不起訴を決めるための手持ち期間とされています。したがって、やむを得ないという勾留延長の要件も緩やかになる理論的視座にあるのではないかと考えていますが、あくまでも人身の自由という憲法上最も保障される権利を侵害するものですから厳格な運用が望まれます。なお、被疑者勾留には保釈の制度はありません。起訴後に保釈の制度があるのみとなっています。
第5編 被疑者の勾留
第1 被疑者の勾留(207条1項)
1 意義
(1) 定義
勾留とは,被疑者・被告人の身体を拘束する裁判及びその執行をいう
(2) 勾留の目的
① 被疑者・被告人の逃亡を防止し,被告人が公判廷に確実に出頭するよう身体を確保する(60条1項1号3号)
② 罪証隠滅を防止する(60条1項2号)
③ 有罪判決が宣告されたときに刑の執行をするために身体を確保
(3) 被疑者勾留の特徴
Ⅰ 職権勾留が許されず,検察官の請求による
Ⅱ 逮捕前置主義があてはまる
Ⅲ 勾留期間は最大25日
Ⅳ 保釈がない
(4) 207条1項の意味
もともと60条では,被告人の審理を担当する裁判所に勾留の権限があるので,207条1項はこれを前提にしたうえでの規定である。そして,207条1項は,204条ないし206条の規定によって勾留の請求を受けた裁判官は,刑訴法や刑訴規則が裁判所又は裁判長に認めている権限と同一の権限を有する。言い換えると,207条1項は,受訴裁判所又はその裁判長のする勾留に関する60条以下の総則の規定が準用されることを定めている(検察39)
2 要件
① 勾留理由(60条1項)
Ⅰ 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
Ⅱ ⅰ住居不定,ⅱ罪証隠滅のおそれ,ⅲ逃亡のおそれ―があること
* Ⅱの要件は,『勾留の必要性』を類型化し勾留理由として要件化したもの
* 定まった住居の有無は実質的に考察すべきで客観的には定まった住居があってもそれが捜査機関が認知できない場合は要件に該当する
* 罪証隠滅のおそれは,自白の有無,関係参考人に不当な影響を与えるおそれがあるかを犯行内容や態様から考えること
* 逃亡のおそれは,裁判所の勾留,勾引の手続自体を困難にするのも含む
② 勾留の必要性があること
Ex.年齢,健康状態,家庭事情など
③ 勾留請求手続の適法性
Ⅰ 勾留請求の犯罪事実と逮捕事実の同一性があること
Ⅱ 時間的制約が遵守されていること(203条ないし205条)
Ⅲ 逮捕手続が適法であること(適法な逮捕の前置 207条)
3 手続
(1) 勾留の請求
ア 請求権者
検察官のみ(204条,205条,211条,216条)
イ 勾留請求書の添付資料
やむを得ない事情によって,制限時間に従うことができなかったときはこれを認めるべき資料を添付(規則148条)
(2) 勾留質問(61条)
勾留の請求が適法な場合,裁判官は理由の有無を審査
⇒ 裁判官が被疑者に対し被疑事実を告げ,これに対する被疑者の陳述を聴いた後でなければ被疑者を勾留することはできない(手続的制約の一種)
* 捜査機関の影響を遮断する必要あり
(3) 勾留の裁判
ア 勾留請求を却下すべき場合
(ア) 却下の要件
① 勾留の理由がないと認められる場合
② 勾留請求の遅延がやむを得ない事由に基づく正当なものと認められず(206条2項)
⇒ 勾留状を発付せず,被疑者の釈放を命じる
(イ) 検察官からの準抗告
429条1項2号+原裁判の執行停止の申立て(検察42)
イ 上記以外の場合
裁判官は,速やかに勾留状を発付
4 勾留の期間
(1) 最初の10日間
検察官は,勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならない(208条1項)
* 勾留裁判官がこの10日間の期間を自由に短縮することは許されない(検察41)
(2) 延長の10日間
やむを得ない事由がある場合は,勾留期間の延長を請求することができる
⇒ 通じて10日間を超えることは許されない(208条2項)
* 逮捕の3日間も含めると身体拘束は合計23日が通常MAX!!
* なお,208の2(5日間の再延長)
* 「やむを得ない事由」[1]
やむを得ない事由とは,10日間の勾留期間内に公訴を提起することができる程度に,捜査を遂げることができなかったのが相当であり,勾留期間を延長すればその期間内に捜査を遂げる見込みがあることをいう(最判昭和37年7月3日民集16巻7号1408号参照)
* 余罪捜査を理由とする勾留延長が許されるか
「1個の勾留を利用して,余罪の取調べをすることは,差し支えないと考えられ,捜査機関としても,同時審判の可能な事件については,できるだけ同一勾留期間中に取調べを終え,一括起訴をすることが,むしろ望ましいことである。
しかし,それは,勾留の基礎となっている事件について,勾留の理由と必要がある限りにおいてであって,勾留期間延長の理由の有無についても,当該勾留の基礎となっている犯罪事実について考えるべきであるから,単に余罪捜査のためだけの理由による勾留延長が許されないことはいうまでもない。
したがって,原則として,検察官においてその余罪を調べなければ,当該勾留の基礎となっている被疑事実の起訴・不起訴の決定ができないというような場合のみ,勾留の延長は許されるものと解する」(令状事務114頁)
第2 勾留からの解放(白取189,田宮88)
1 勾留からの解放の意義
『人質司法』+黙秘権侵害
⇒ 現行法を前提に,弁護人は被疑者の身体拘束を解くための活動が必要
* 被疑者段階での保釈が認められていないので,弁護人は以下の制度を積極活用すべき(だが,あまり活用されていない)
2 勾留理由開示
(1) 意義
勾留された被疑者は,自分がいかなる理由で勾留されたのかを公開の法廷で明らかにしてもらう権利を有する(82条ないし86条,207条1項)ので,これに対応する制度をいう(憲法34条,法82条)
(2) 制度趣旨
英米のヘイビアス・コーパス(イギリスの人身保護法)を背景に不当拘禁からの救済を認める趣旨
(3) 弁護人の使命
現実には,勾留理由開示が勾留取消しに結びつくのは稀であるが,適正手続の観点に加えて,被疑者を精神的に励ますことになる重要な弁護活動である
*被疑者は338件(2003年)で利用数は少ない
3 勾留の取消し
① 勾留の理由・必要がなくなったとき(87条1項,207条)
② 拘禁が不当に長くなったとき(91条1項,207条)
4 勾留の執行停止
裁判所は,職権で勾留の執行停止を命じることができる(95条,207条)
* 弁護人は裁判官に職権の発動を促す
5 準抗告
(1) 弁護人の使命
勾留決定が出されて拘束されてしまった被疑者を救済するために,弁護人は,勾留を認容した裁判に対して準抗告を行う(429条1項2号)
(2) 犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告ができるか
● 否定すべき(通説)
∵ 429条2項は,420条3項を準用している
× 起訴後については,犯罪の嫌疑は公判手続で明らかにされるものであるが,起訴前の被疑者にはあてはまらない
○ 肯定すべき
∵ 429条2項・420条3項の『勾留』とは,起訴後第1回公判期日後の勾留をいうと解すべき(田宮87,白取191)
* 嫌疑がないことを理由に準抗告を認めないのが実務であるが,弁護人の準抗告に対して,裁判所は職権で嫌疑があることを判断することがあるので,弁護人は上記の理論を展開して準抗告すべき
第3 逮捕前置主義
1 意義
(1) 定義
逮捕前置主義とは,被疑者を勾留するには,その前に被疑者を逮捕しなければならないという原則をいう
(2) 制度趣旨
① 刑訴法207条1項が逮捕に引続く勾留請求を前提にしている
② 逮捕の際と勾留の際の2度にわたって身体拘束の要否を裁判官が判断することで司法的抑制の効果がある
③ 逮捕の際には,身体拘束の要件を満たしていても,その後,要件が欠けるかも知れない。そこで,初めから勾留を認めると10日間は裁判官による審査の機会が保障されないので,まずは逮捕による短期の拘束を先行させようとしたもの(大澤は,②を否定し①と③が論拠という[2])
* ③は,比較的長期間の身体拘束処分たる勾留に先立って,短時間の拘束処分である逮捕手続を設けることで,勾留に至らない釈放の可能性を認め,人身の自由剥奪という重大な基本権制約について慎重を求める趣旨(法教291号95頁)
2 逮捕手続と勾留事実の同一性[3]
(1) A罪⇒B罪の場合に同一性の要件を満たすか
● 許される
∵Ⅰ 人単位説
Ⅱ B事実による逮捕を経て勾留となると身体拘束時間が長くなる
×Ⅰ 事件単位説
Ⅱ 逮捕前置主義の③の趣旨[4]
Ⅲ 逮捕手続の先行により勾留されない可能性もあるから,人単位説と比較して身体拘束時間が長くなることはB事実に基づく逮捕手続を省略する理由にならず
○ 許される
*事件単位説のイメージ *人単位説のイメージ
 |
 |
||||
|
|||||
|
*人単位説は,勾留は一つしか認めないので,別罪の考慮を認めてしまうので上記の理想モデルとは異なり現実は以下のようになってしまう
*人単位説の正体
 |
* 人単位説によると,勾留がいずれの罪によって行われているのか裁判官や弁護人の立場からも分かりにくい
⇒ 裁判官の令状審査との関係でも考える必要がある!!
∵① 勾留は,特定の犯罪事実により行われる
② 令状審査を経ていない事実が考慮されてしまい,現行法と整合しない
(2) A罪⇒A+B罪の場合に同一性の要件を満たすか
○ 例外的に違法ではない(法教291号95頁)
∵① 逮捕前置主義の趣旨が逮捕段階での釈放の可能性を見込んだ慎重な身体拘束の審査であるとすれば,A事実について勾留できる以上,被疑者の身体拘束が継続されることは動かない
② 勾留段階で身体拘束の根拠が認められるB事実が付加されても,被疑者に格別の不利益があるわけではない
③ A事実について逮捕前置の要請が満たされており,B事実の逮捕手続が省略される分だけ,拘束時間については被疑者に有利に作用する
3 違法な逮捕と勾留
(1) 違法な逮捕に引き続く勾留の適法性
ア 逮捕手続の瑕疵と勾留請求の効力
● 逮捕手続の違法は勾留手続の瑕疵とはならない
×① 逮捕前置の制度趣旨は,短時間の身体拘束の後,勾留請求段階での身体拘束継続の理由と必要性を速やかに勾留裁判官の慎重な審査に付すため
② 制度上も逮捕手続に対する準抗告は認められていない(逮捕に対する独立した不服申立て手段の欠如)
③ 将来における違法逮捕抑止
○ 逮捕手続きの瑕疵の審査をすべて勾留請求の場面で行うことを予定
イ 勾留請求の却下の違法性の程度
● 違法事由があればすべて却下すべき
×① 法は,勾留請求に先行する手続の違法について,身体拘束時間制限不遵守という重大な違法がある場合について明文を置いている(206条参照)
② 検察官の勾留請求自体を無効とすべきは,明文ある場合に限られない
○ 明文のある身体拘束時間制限超過に匹敵するような重大な違法が認められる場合には,勾留裁判官は重大な違法手続に基づく勾留請求を却下すべき
(2) 勾留請求が却下されるべき逮捕の違法
ア 令状審査という一種の実体要件に瑕疵がある場合
典型例
① 逮捕状に裁判官の押印が欠けている場合[5]
② 逮捕状請求書に規則148条1項8号該当事実の記載が欠如している
③ 任意同行が無令状の実質逮捕と評価される場合
⇒ 重大な違法の典型例は,令状裁判官の審査を経ず,身体拘束の実体要件である犯罪の嫌疑がない身体拘束が行われていた場合
*法教291号96頁は,実質逮捕時点からの拘束時間が法定の制限内であっても令状主義の精神を没却する重大な違法がある以上,却下すべきとする
イ 手続要件に瑕疵があるにとどまる場合
典型例
① 緊急逮捕の要件があるのに誤って準現行犯逮捕した場合
② 適法な緊急逮捕手続を採ることなく,実質逮捕にあたる任意同行の場合
③ 緊急逮捕後の逮捕状請求手続が遅延した場合
● 法定の時間制限内の勾留請求があれば,違法の重大性は認められず
∵ 法形式の選択の誤りや逮捕手続の実行方法の軽微な過誤にすぎない
× 現に法定の手続が踏まれていない以上,それ自体重大な違法というべき
⇒ 裁判官が違法宣言を行い違法捜査に対するコントロールを及ぼすという政策的観点からは一度勾留請求を却下する方が適切
[1] 「やむを得ない事由」については,過去に捜査機関が十分な捜査をしているか及びこれからどのような捜査を行う必要があるかという観点から判断されているものと考えられる。具体的には,勾留担当裁判官は,「関係書類追送書」や「取調べ状況報告書」を一件記録からみて判断することになっている。前者は,一種の書類の目録であり,例えば,ある非現住建造物放火未遂事件の場合は,19種類の書類が作成されていた。具体的には,実況見分調書,被疑者の供述調書,「僕がやったこと」と題する書面などである。また,取調べ状況報告書は,被疑者の各供述調書の前に綴られているものであり,内容は取調べ時間の記載,休憩時間,取調べ場所,担当者,調書作成の有無,参考事項として上申書を作成した旨の記載-などから構成されているものである。この書類にも被疑者の署名・押印がなされている。取調べ時間については,例えば,「13時40分から17時05分まで」,「15時20分から17時35分まで」,「13時55分から17時00分まで」というような記載となっている。この事件は少年事件であったために無理な取調べはなされていないとうかがわれるものであるが,やはり大人が被疑者の事件では,取調べ時間も朝から昼を挟んで夕方までというものもみられた。要件の判断に関しては,裁判官は一件記録をみて判断をしているが,勾留延長を認めるのに適当でない事件については,検事に電話で問い合わせをするということもある。
しかしながら,一件記録の中に身体拘束の必要性が高いということを示すためか,「被疑者少年は,養護学校に通う者であるという特殊性を前面に,被害者に憐憫の情を訴え,被害を取り下げさせ立件を困難にさせるおそれがある」というのであるが,被疑者の知的障害の程度が大きいというわけでもなく,そのような所為に及ぶ危険性が高いともいえず,抽象的な危険性にすぎないのであって,ともすれば,不当な偏見に基づいているといわざるを得ない記述が捜査報告書に散見されるのは遺憾である。
[2] 大澤の論拠は,付加して行う勾留請求の論点に関連して,「A罪で逮捕⇒A罪+B罪」で勾留請求ができるかについて,逮捕前置主義の②の制度趣旨を位置付けてしまうと,B罪については逮捕が先行していないので,B罪を付加することはできないという論理的な帰結になる。そこで,制度趣旨は③を中心に把握すべきとする。
[3] なお,筆者と大澤の見解が一致しないためにここの部分は位置づけが少しおかしくなっている。というのも,私は,「逮捕事実と勾留事実の同一性」や「違法な逮捕と勾留」については,勾留の要件の一つとして,「勾留請求手続の適法性」という要件を設けて(検察実務講義14参照),その中で論じているが,大澤は逮捕前置主義という要件の中で検討するように思われる。整理の混乱を避けるために,大澤のレジュメどおりに整理することにする。
[4] B事実についての被疑者の弁解聴取や捜査状況により,B事実の嫌疑が薄弱化することも考えられる。したがって,まず逮捕手続を先行させ慎重を期することが法の趣旨に合致する
[5] これは,捜査機関からの逮捕状請求があったものの,要件を満たさないので,裁判官が逮捕状請求書を押印のない状態で捜査機関に返還したところ,捜査機関がこれを悪用して被疑者を逮捕したというケースである。