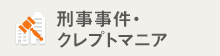逮捕・勾留の諸問題
第6編 逮捕・勾留の諸問題
第1 逮捕・勾留と余罪
1 問題の所在
(1) 1人の被疑者に対する複数の犯罪の嫌疑と逮捕・勾留
ア 原則的処理
逮捕・勾留という身体拘束処分の効力は,裁判官の審査を経て,手続的に明示顕在化された被疑事実(事件)についてのみ及ぶ
イ 別個の被疑事実が存在する場合
競合する別事件についても裁判官の審査が行われ,手続的に明示されない限り,その事実に関しては身体拘束処分の効力は生じない
⇒ 人を基準にして既に実行されている身体拘束処分の効力を競合する他の被疑事実の間に相互に流用することはできない!!
* その人の余罪被疑事実を潜在的な状態のまま考慮勘案してそれを被疑者の身体拘束に関する判断において不利益方向に用いることは許されない(法教291号98頁)
(2) 事件単位説と人単位説
ア 事件単位説
(ア) 定義
事件単位説とは,逮捕や勾留の効力は,逮捕状・勾留状に記載された被疑事実のみに及ぶと主張する見解をいう
(イ) 二重勾留の容認
例えば,死体遺棄の疑いで逮捕・勾留された被疑者甲について,その身体拘束期間中に殺人の疑いで逮捕・勾留の手続が執られて,甲は死体遺棄の罪と殺人の罪で二重に勾留されているといった事態
イ 人単位説
人単位説とは,二重勾留容認を批判し,勾留は被疑者を単位にして考えるべきであるとする見解をいう
ウ 検討
● 人単位説
∵① すでに拘束されている人に複数の勾留をするのは意味がない
② 事件単位で複数の拘束処分がなされると身体拘束期間が長期化する
○ 事件単位説
∵① この問題の核心は,1人の被疑者の身体拘束に際し,事実として現に競合している被疑事実に関して,裁判官は手続的に明示されてはじめて考慮できるか潜在的なまま考慮することができるか
② 人身の自由という重大な基本的利益を制約する場合について,裁判官の審査・令状主義を採用する現行法からは,個々の被疑事実が明示されてはじめて身体拘束処分に際し考慮できるとすべき
2 事件単位の原則
(1) 定義
事件単位の原則とは,事件単位説の主張,すなわち,逮捕・勾留の効力は,逮捕状・勾留状に記載された被疑事実のみに及ぶとする原則をいう(寺崎143)
(2) 事件単位の原則の帰結
事例 A事実で勾留中の被疑者について,B事実の嫌疑が生じている場合に,B事実で逮捕・勾留の手続を執ることなくB事実を考慮勘案して勾留期間の延長(208条2項),接見・授受の制限(81条)をすることの可否
∴ 許されない
⇒ B事実について身体拘束を継続し捜査を続行する必要性があれば,新たにB事実により逮捕・勾留の手続を執らなければならない
(3) 事件単位の原則と取調べの法的規律
ア 酒巻説(法教291号98頁)
事件単位の原則とは,身体拘束処分についての令状審査という原理から導かれる原理である。そして,逮捕・勾留制度の直接の目的は,被疑者の逃亡と罪証隠滅の防止である。そうだとすれば,被疑者の取調べは逮捕・勾留制度の目的ではない。したがって,事件単位の原則は被疑者の取調べには適用されないと解すべきとするが疑問である[1]
イ 木谷説[2]
第2 再逮捕・再勾留
1 再逮捕・再勾留の許容性
(1) 定義
再逮捕・再勾留の原則とは,刑法上1個の罪を構成する被疑事実については,1回しか逮捕・勾留が許されないとする原則をいう
(2) 論拠
身体拘束期間の制限
⇒ 法が身体拘束期間を厳格に制限して,人身の自由とこれを剥奪制約する捜査目的達成の必要性とのバランシングを図る趣旨
* 再逮捕・再勾留の原則が認められないとすれば,常に捜査目的達成の必要性という利益が人身の自由の利益の前に優先されるおそれ
(3) 前提―法律の根拠
再逮捕 ⇒ 199条3項,規則142条1項
再勾留 ⇒ 格別の規定なし
2 例外としての再逮捕・再勾留
(1) 再逮捕の許容性
○ 合理的な理由のある場合は,再逮捕は認められる
∵① 199条3項は,逮捕と釈放の繰り返しによる不当な自由侵害が生じるのを防ぐ趣旨
② 同時に199条3項は,再逮捕を許容するように見える規定であり,合理的な理由のある場合は,同一被疑事実に基づく再度の逮捕状請求・発付を想定している
(2) 嫌疑復活型
ア 典型例
いったん逮捕された被疑者を釈放した後,事情の変更が生じて身体拘束の理由・必要性が新たに発生した場合
⇒ 当初の逮捕後の捜査の結果,嫌疑が薄弱化したため釈放されたが,その後有力な新証拠が発見されて身体拘束の理由が生じた場合
イ 基本的視座
逮捕後の段階で嫌疑が減退したのであれば,直ちに被疑者は釈放されるべきであり,他方,事情変更により減退した嫌疑が復活したという場合には,再度の身体拘束により対処するという基本的視座
ウ 合理性の要件の具体化
Ⅰ 事案の重大性
Ⅱ 再拘束して捜査を続行する特段の必要性
Ⅲ 再逮捕の理由または必要性を新たに生じさせた事情変更の内容
Ⅳ 先行する身体拘束期間の長短とその間の捜査状況
* 身体拘束期間をすべて使い尽くした後の再逮捕
⇒ 特段の合理的根拠及び高度の必要性が必要と解すべき
(3) 先行手続違法型
ア 問題の所在
① 原因が捜査機関側の違法手続
② 特段の事情の変更もない
イ 基本的視座[3]
① 当該具体的事案の性質
② 再逮捕による手続のやり直しを認めない結果として被疑者が釈放されることの捜査に及ぼす影響の程度
③ 当初の逮捕手続の瑕疵の性質・手続違背の程度
* 以上を慎重に勘案して,再逮捕の適否を判断すべき(法教291号97頁)
ウ 再逮捕の許容性
違法の程度が極めて重大で,当該被疑者に対する身体拘束処分の続行がおよそ相当でないと認められるような場合には再逮捕を許容すべきではない(法教291号102頁)
第3 一罪一逮捕一勾留の原則
1 意義
(1) 定義
一罪一逮捕一勾留の原則とは,同一の被疑事実に基づいて,同じ被疑者を再び逮捕・勾留することはできないとする原則をいう
(2) 制度趣旨
① これを許すと,逮捕・勾留に関する時間の制限が無意味になるから[4]
② 刑罰権の個数とこれを実現するための刑事手続の個数は一致すべきものであり,身体拘束処分の個数も実体法上の罪数によって決定されるという[5]
⇒ 検察官は,実体法上一罪の関係にある犯罪事実については,これに対応する1回の身体拘束処分を利用して捜査を遂げ同時に処理すべき義務を負う!!
2 包括一罪・科刑上一罪と一罪一逮捕一勾留の原則
(1) 単位事実説と実体法上一罪説
(2) 実体法上一罪説と一罪一逮捕一勾留の原則の例外
ア 事例
① 実体法上,常習罪として評価・処罰される事実(常習累犯窃盗)には複数の可罰的行為が含まれる
② 科刑上一罪にも同様の場合がある(包括一罪と評価し得る一連の業務上横領行為など)
イ 視点
常習一罪や科刑上一罪には,もともと複数の具体的犯罪事実が含まれるのであるから,一罪一勾留の原則を徹底することが困難である。これに対して,明確な基準がないのに再度勾留を生じる可能性があるとすれば,対象者に及ぼす不利益は著しい
⇒ 調和の観点
ウ 一罪の一部をなす事実が,先行する身体拘束の終了後に行われた場合
○ 事実上のみならず,原理的に同時処理がおよそ不可能な犯罪事実についてまで,この原則を及ぼすことは不合理
∵ 一罪一勾留の原則の根底に検察官の同時処理義務を想定
エ 一罪の一部をなす事実が,先行する身体拘束の時点で未発覚であった場合
● 同時処理は可能と解する見解
∵ 当該犯罪事実は,原理的・観念的には当初の身体拘束処分によって,同時処理が可能であったはず
⇒ 対象者の再度の拘束の可能性は少なくなる
○ 同一の被疑事実については,特段の事情変更があれば再逮捕可能
⇒ 個別具体的事案において,当初の身体拘束時点において一罪の一部を構成する犯罪事実が捜査機関に判明しなかった点についてはやむを得ないと認められる合理的な理由があり,それが事情変更によって判明した場合
* 一罪一勾留の観点から同時処理の義務が認められるので,再逮捕の問題となるが,再逮捕・再勾留の禁止の原則の例外の検討で肯定の余地あり!!
第4 別件逮捕・勾留
1 意義[6]
別件逮捕・勾留とは,被疑事実Aで被疑者を逮捕・勾留するだけの要件が備わっていない場合に,Aについての取調べをすることを主たる目的として,他の被疑事実Bについて被疑者を逮捕・勾留する捜査方法をいう
*イメージ
![]() 主眼 名目
主眼 名目
被疑事実A=本件 被疑事実B⇒令状=別件
2 別件逮捕・勾留の適法性
(1) 問題の所在
捜査官は,本件の存在を隠匿し別件による身体拘束処分を道具として利用しようとする点
⇒ 外形上利用された別件による身体拘束処分それ自体が違法ならないか
* 本件と別件との罪の軽重は必ずしも決定的な要素ではない[7]
(2) 別件基準説と本件基準説[8]
ア 別件基準説
別件基準説とは,逮捕・勾留の要件が別件について具備されているかを問題とする見解をいう
⇒ 別件について要件が具備されている限り適法
イ 本件基準説
(ア) 定義
本件基準説とは,本件取調べの目的で別件に名を借りて行われる逮捕・勾留は,実質的に本件についての逮捕・勾留であるから,たとえ別件について要件が具備されていても,本件について令状主義を潜脱する点で違法とする見解をいう
⇒ 隠れた本件による身体拘束の実質を持つ脱法行為ととらえ違法とする
(イ) 違法論拠
① 逮捕・勾留が自白獲得の手段とされている
② 別件による身体拘束期間満了後に本件で逮捕・勾留することがあらかじめ見込まれている点で身体拘束の時間制限を定める刑訴法の規定を潜脱
③ 別件逮捕・勾留が専ら本件捜査の目的に向けられているのに,本件について裁判官が司法審査を行い得ないまま令状が発せられ,被疑者が実質的には本件について逮捕・勾留の理由となった犯罪事実を明示する令状によることなく身体拘束されることになるから令状主義に反する
(3) 判例
ア 帝銀事件(最大判昭和30年4月6日刑集9巻4号663頁)
判例は,捜査機関がはじめから本件の取調べに利用する目的・意図をもって,ことさらに別件で逮捕した事情がない限り,別件について逮捕の要件を満たしていれば適法とする
イ 狭山事件(最決昭和52年8月9日刑集31巻5号821頁)
判例は,別件による逮捕・勾留がその要件を具備する適法なものであったとの結論を導くに際して,当該逮捕・勾留が「専ら,いまだ証拠の揃っていない『本件』について被告人を取り調べる目的で,証拠の揃っている『別件』の逮捕・勾留に名を借り,その身体の拘束を利用して,『本件』について逮捕・勾留して取り調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである,とすることはできない」と判示する
* 上記の場合は違法になることを示唆するもの
3 検討
(1) 別件についての逮捕・勾留の要件を具備しない場合
ア 従来の考え方
従来の本件基準説が前提としている『逮捕の必要性』(199条2項ただし書き)という要件については,①犯罪の嫌疑があること,②逃亡・罪証隠滅のおそれがあること―という理解を前提にしている。したがって,従来の本件基準説からは,『別件』についての逮捕の必要性の要件が具備されやすいといえる[9]
イ 新しい考え方
新しい考え方では,逮捕・勾留の期間の制度趣旨を起訴・不起訴に向けての捜査を行うという点にあると位置付ける。とすれば,起訴・不起訴に向けての捜査を行う必要がない場合は,逮捕・勾留をすることができないと考えていく。これは,「起訴・不起訴に向けての捜査をすること」を『逮捕又は勾留の必要性』の要件と位置付ける見解といえる
⇒ 新しい考え方からは,『別件』についての逮捕の必要性は具備されにくい[10]
(2) 実質的に本件の逮捕・勾留と見られる場合
ア 事件単位の原則に反するか
(ア) 形式的観察―別件基準説の立場から
そもそも,事件単位の原則からすれば,別件以外は考慮できないと解すべき
しかるに,別件以外を考慮する本件基準説は,事件単位の原則に反する
(イ) 実質的観察―本件基準説の立場から
身体拘束は,令状主義に基づく裁判官のコントロールを受けるところ,実質的にコントロールを受ける被疑事実は何か―という視点から実質的に事件単位の原則を適用すべき。したがって,本件基準説の方が事件単位の原則に適合的
*事件単位の原則との関係では優劣はつかない
イ 実質的判断の方法
(ア) 従来の本件基準説の立場から
別件を口実にして本件を取り調べる捜査機関の意図を根拠とする
(イ) 新しい考え方の立場から
* 検察サイドの見解(古江頼隆「演習」法教339号148頁参照)
検察官出身の古江は,本件基準説の違法論拠を次のように批判している。
まず,違法論拠①についてであるが,逮捕・勾留が自白獲得の手段とされているというのである。しかしながら,自白獲得の手段とされている逮捕は,通常の逮捕であったとしても違法となると考えられるが,逮捕・勾留中の取調べは通説からも認められているはずであるから,自白獲得を手段として何がおかしいのかという趣旨の批判を加えており,論拠①を失当としている。この点,私見は,自白獲得を目的として逮捕したのであれば,三井説のいうように違法としてよいのではないかと考えるので首肯できない。
次に,本件によう逮捕・勾留が予定されているとはいえ,いまだこれが行われていない段階で期間の潜脱というのは無理があるので,論拠②も失当であるという。たしかに,この点は首肯すべきものがある。証拠能力が争われる段階に入れば「将来の逮捕が予定されている」のではなく,「二重に逮捕された実態」が存在するのであるから,その点を問題視すべきというのは問題意識としては検察サイドと共通なのである。しかしながら,主観を問題にしないと当初の逮捕を違法にすることができないというジレンマがあるわけである。逆にいえば,この点は手痛い指摘なのである。
そこで,検察サイドは本件基準説において,理由があるのは論拠③の令状主義潜脱のみであるところ,なぜ主観的な意図・目的があるだけで令状主義に反するのかと反論している。つまり,そのような主観があっても現実には別件の捜査が実施されたのであれば,何も違法にする必要はない,という反論をしている。刑法の世界では,あれだけ行為無価値に固執しながら刑訴の世界になると「結果無価値に欠ける」とは,都合がよいものである。この点について考えると,判例が刑訴においても行為無価値的な枠組みを採るのは,違法収集証拠排除法則の判断の仕方から明らかである。逆にいえば,私見は,川出説や中谷説を前提としても,捜査側に過度の主観的違法要素があれば,従来の本件基準説も理論的に両立する可能性があると考える。
このような理論的視座から,検察サイドは,令状請求時の裁判官の主観的な意図・目的が重要というわけではなく,身体拘束中の捜査の客観的な実態に注目すべきものと論じる。そして,このような観点を踏まえつつ,たしかに,捜査官が主として本件の捜査に利用する目的・意図を有しており,現実に逮捕・勾留したのと同様の状態が客観的に作出されれば,令状主義が潜脱されるということは古江ですら認めている。しかしながら,他方で古江は,別件逮捕といい得るほどの客観的な実態(本件の取調べをしているか)がない限りは,被疑者には特段の不利益(法益侵害)はないと結論付けている。たしかに,人単位説で考えれば分かるが被疑者からすればどの罪名で逮捕されても身体を拘束されるという点は変わらないわけであるから,余罪の取調べをされない限りは,新たな法益侵害があるとまではいえないと考えることも可能である。
このような見解は,「別件による身体拘束期間を本件の捜査に利用したという身体拘束中の捜査の実態」は令状主義を潜脱するものであり,これのみが違法論拠であると把握しているものと考えられる(東京地決平成12年11月13日判タ1067号283頁が同旨)。たしかに,違法論拠①②が失当であるとすれば,この説明は理論的な流れとしては秀逸なものがある[11]。
* 川出説を中心とする従来の本件基準説に対するオーソドックスな批判
×① 従来の本件基準説からすると,殺人で取り調べる意図で逮捕状を請求したが,被疑者を逮捕した後,軽微な窃盗のみを取り調べて,殺人については取調べを一切しなかったとしても逮捕が違法となり非常識というべき[12]
② そもそも逮捕状発付の段階で裁判官が捜査官の主観を見抜いて逮捕状請求を却下することは社会的実態としてほとんどなく[13],専ら自白の任意性や採取過程の適法性が争点となることが多い。そうすると,従来の本件基準説の実態は,「別件での逮捕・勾留中に本件の取調べが行われた事実」を問題視しているにもかかわらず,時を遡らせて,逮捕状請求が違法であったとするフィクションにすぎない
⇒ 従来の本件基準説の利点は,「取調べの事前抑制ができること」にある
ところが,現実には,余罪取調べが行われた点を根拠に遡及的に逮捕を違法にする,というパラドックスを抱えている
○ 捜査官の主観を基準とせず,「捜査のために利用するという客観的事情」があるかを規範に定めるべき(逮捕・勾留中の捜査状況)
⇒ 諸般の事情を総合検討することにより,当初,捜査機関によって秘匿され,裁判官に示されることなく伏在していた潜在的被疑事実(本件)こそが,当初の身体拘束処分やその継続の実質的理由とされているのであり,別件による逮捕・勾留は外形として利用されたものであるということができれば,その身体拘束自体が令状主義を実質的に潜脱する違法な処分であったと評価
考慮要素
Ⅰ 本罪と余罪の罪質・態様の相違・軽重
Ⅱ 捜査の重点の置き方の相違
Ⅲ 関連性の有無・程度
Ⅳ 余罪の取調べ方法・程度
Ⅴ 余罪の客観的証拠の収集程度
Ⅵ 取調官の意図←この要素は決定的ではなく補助的な位置付けになる!!
(3) 第3の道(寺崎148)
別件基準説に立って,理由と必要性を具備した当初の身体拘束処分それ自体は適法としたうえで,その身体拘束期間中の余罪取調べの限界を検討すれば足りる
∵① 本件基準説には致命的な欠陥がある(Ⅰ逮捕状発付の段階での見極めは事実上無理,Ⅱ別件について逮捕・勾留の要件が揃っているのに,背後の意図を見抜くのは捜査の初期では無理,Ⅲ別件自体それなりに重大であるのに,他に本件があれば別件の逮捕・勾留自体も許されなくなってしまう)
② 新しい考え方も相当でない(まだら模様の取調べをされるとお手上げ状態となりプラクティスに向いてない)
× 身体拘束処分の外形的利用という脱法行為であり,かつ,令状主義の核心部分である裁判官の審査を不当に潜脱し,裁判官を錯誤に陥らせている点に照らすと,外形的道具として濫用されており,令状主義の重大な違反を理論的根拠として援用可能な当初の身体拘束処分それ自体を標的にして,これに対する違法判断を試みるべき(法教290号85頁)
* 検討[14]
(4) 強盗殺人の余罪
ア 最初,窃盗で逮捕して,窃盗・強盗殺人で勾留請求し,強盗殺人で起訴という場合
イ 別件逮捕ではないかと争われるおそれ
明らかな軽微な窃盗で逮捕して身柄拘束し,その間,証拠を集めて強盗殺人で起訴されたと判断されるおそれがある。
別件逮捕は,実務と学説はかけ離れているので実務を知る必要。別件逮捕
は,罪名が軽重や関連性の有無では決定されない。実務的には,別件基準説であるので,窃盗について逮捕の理由があり必要性・相当性が認められれば,逮捕が違法といわれる筋合いはないという(検察)。全然かみ合わない。
逮捕の理由や必要性・相当性がない場合と考えればよい。余罪取調べもその観点から考えると早い(検察)。余罪取調べについても,逮捕事実についての必要性や相当性が欠けているから余罪の取調べができるのであって,別件に逮捕の必要性があれば本件のことばかり聞いていられるはずはないという。
検察は,重い罪で一括して処理すると別件逮捕をするおそれがあるので,マスコミ用語の再逮捕する。よくあるのは,死体遺棄で指名手配されているが,殺人では証拠がそろっていないので,固い死体遺棄で逮捕する。
ウ 付加して勾留請求をする場合は別件逮捕になるおそれがあるので,勾留事実を付け加えることは実務上許されているが重い方を付加しないように気をつけているという。
検察官としては,強盗殺人ではなく,「強盗」程度であれば,軽い窃盗と同時処理するという判断をする(検察)。強盗といっても重い罪とまではいえないので。もっとも,窃盗について不起訴の見通しであれば,窃盗で逮捕していても釈放して,マスコミ用語で再逮捕する。窃盗は10日で処理して,その後強盗で再逮捕して同じく10日で処理するのが基本であるという(検察)。逮捕の時点では殺人の証拠がない場合は死体遺棄であるが,これも10日で処理することが多い。その後,再逮捕。逮捕前置主義に反することはできないので,これを意識しつつ柔軟に処理する
4 第二次逮捕・勾留の適法性[15]
* 第二次逮捕・勾留のイメージ
①別件による逮捕・勾留 ⇒ ②本件による逮捕・勾留 ⇒ ③公訴提起
![]()
![]() 自白 疎明資料
自白 疎明資料
(証拠能力なし)
A説 疎明資料による連続を重視する見解
∵ 結局,自白の証拠能力がなくなるので本件による逮捕・勾留の要件を満たさなくなるので,2次逮捕はできなくなる
× 独立源の別証拠があればよいということになりかねない(否定されるのは,疎明資料が欠けるという理由に基づくから)
B説 身体拘束の蒸し返し(再逮捕再勾留)
⇒ B説は疎明資料は関係ないということになる
[1] 法教291号99頁は,「事件単位の原則によって取調べの対象範囲を身体拘束被疑事実に限定するためには,取調べを直接の目的とした身体拘束処分を論理的前提としなければならない」とする。たしかに,取調受忍義務を否定する場合は,取調べには何らの公法上の義務が課されたものではないと解することになる。そうすると,逮捕・勾留は強制処分であるが,取調べは被疑者が自由な意思によって応じているのにすぎないということになるので,事件単位の原則を適用するのは難しいということになる。しかしながら,この見解によると取調べに対する法的規律が困難になり糾問的な取調べに対する規律ができない。また,酒巻説は少なくとも出頭・滞留義務という意味では取調受忍義務を肯定しているはずであり,かかる義務は身体拘束中の被疑者に生じるものであり,これは逮捕・勾留の直接の効果といわねばならない。したがって,取調受忍義務を生じさせるものである以上,取調べをするということも逮捕・勾留の目的ないし効果と解して差し支えないものと考えられる。そうだとすれば,取調べは任意処分というべきではなく,出頭滞留義務が課されていると解する限り強制処分と解すべきであり,取調受忍義務を課した取調べには,事件単位の原則が適用されると解するのが相当である。酒巻説について疑問に思うのは,取調受忍義務の肯否如何という問いでは,取調受忍義務について松尾説を採用していると思われるのに,余罪取調べの限界を論じるにあたっては,松尾説がどこかに行ってしまい,代わって取調受忍義務を否定する平野説に前提がすり替えられているように思われる。その後,筆者は質問できたので,附言するのに,大澤は,取調受忍義務について松尾説を採用するとまでは断言していないとする。もっとも,松尾説を採ると,身体拘束の直接の法的な効果として,出頭滞留義務という公法上の義務を被疑者が負担することになるということは否定することができない。そうすると,逮捕・勾留の効果として,出頭滞留義務には事件単位の原則が適用されるというのが論理的な帰結である,とのことである。酒巻や大澤はこのような見解を素直に受け容れているわけではなく松尾説を「少数説」と形容する。そのうえで,取調受忍義務との関係では,平野説を前提にしているものと考えられる。
[2] 浦和地判平成2年10月12日判タ743号69頁は,「当裁判所は,右余罪の取調べにより事件単位の原則が潜脱され,形骸化することを防止するため,これが適法とされるのは,原則として右取調べを受けるか否かについての被疑者の自由が実質的に保障されている場合に限ると解するものである(例外として,逮捕・勾留の基礎となる別件と余罪との間に密接な関係があって,余罪に関する取調べが別件に関する取調べにもなる場合は別論である。)。
刑事訴訟法198条1項の解釈として,逮捕・勾留中の被疑者には取調べ受忍義務があり,取調べに応ずるか否かについての自由はないと解するのが一般であるが,法が,逮捕・勾留に関し事件単位の原則を採用した趣旨からすれば,被疑者が取調べ受忍義務を負担するのは,あくまで当該逮捕・勾留の基礎とされた事実についての場合に限られるというのが,その論理的帰結でなければならない。もしそうでなく,一旦何らかの事実により身体を拘束された者は,他のいかなる事実についても取調べ受忍義務を負うと解するときは,捜査機関は,別件の身体拘束を利用して,他のいかなる事実についても逮捕・勾留の基礎となる事実と同様の方法で,被疑者を取り調べ得ることとなり,令状主義なかんずく事件単位の原則は容易に潜脱され,被疑者の防禦権の保障は,画餅に帰する。
したがって,捜査機関が,別件により身体拘束中の被疑者に対し余罪の取調べをしようとするときは,被疑者が自ら余罪の取調べを積極的に希望している等,余罪についての取調べを拒否しないことが明白である場合(本来の余罪の取調べは,このような場合に被疑者の利益のために認められた筈のものであり,現実に行われている余罪の取調べの大部分も,かような形態のものである。)を除いては,取調べの主題である余罪の内容を明らかにした上で,その取調べに応ずる法律上の義務がなく,いつでも退去する自由がある旨を被疑者に告知しなければならないのであり,被疑者がこれに応ずる意思を表明したため取調べを開始した場合においても,被疑者が退去の希望を述べたときは,直ちに取調べを中止して帰房させなければならない」と指摘している。
そのうえで,本件については,「被告人の取調べにあたった吉川警察署の警察官及び浦和地方検察庁のQ検事は,余罪取調べに関する前記のような限界を全く意に介することなく,別件逮捕・勾留中においても,本件たる放火の事実について,別件の不法残留に関する取調べの場合と同様,被告人に取調べ受忍義務があることを当然の前提として取調べを行ったことが明らかであって,当然のことながら,被告人に対し,前記のような意味において,本件たる放火の事実については取調べを受ける義務がない旨告知したことはなく,被告人自身も,かかる義務がないということを知る由もなかったと認められる(のみならず,右取調べの方法は,犯行を否認する被告人に対し,目撃者がいるといって自白を迫り,被告人が一旦マッチを投げて放火したと供述するや,その方法では火事にならないから他の方法だろうと執拗に供述を迫るなど,取調べ受忍義務がある場合として考えてみても,明らかに,妥当を欠くものであったと認められる。)。従って,本件第一次逮捕・勾留中になされた本件放火に関する取調べは,明らかに許される余罪取調べの限界を逸脱した違法なものであり,これによって作成された被告人の自白調書は,証拠能力を欠き,また,その後の第二次逮捕・勾留は,右証拠能力のない自白調書を資料として請求された逮捕状,勾留状に基づく身体拘束であって,違法であり,したがってまた,その間に作成された自白調書も証拠能力を欠くと解すべき」とする。
[3] 再逮捕を考えるにあたって重要な視点は,捜査の具体的必要性と被疑者の人身の自由の利益のバランシングを図るという点にある。たしかに,先行する手続に違法がある場合には事情変更はないが,手続的瑕疵の存在は捜査の具体的必要性を減殺させるものではないと考えられる。そうすると,その手続的瑕疵の具体的中身が被疑者の人身の自由の利益に対してどの程度の不当な制約を与えるものであるのかという視点が重要になると思われる。例えば,逮捕の要件がないにもかかわらず,実質逮捕をしたという場合は令状主義を没却する重大な違法があるというべきであるし,これは被疑者の人身の自由という利益に対して重大な制約を加えたものと考えることができる。そうすると,捜査の必要性がいくら高度であっても,深刻な人身の自由に対する制約が行われたのであるから,このバランスを考えると,再逮捕は認めないという利益調整のあり方も考えられる。再逮捕の許容性で示される規範は以上の趣旨で理解することができると考えられる。これに対して,緊急逮捕をすべきところを準現行犯逮捕をしてしまったという場合はどうであろうか。この場合は,単に適用する法条を誤ったというにすぎないのであり,いずれにせよ被疑者は身体拘束処分を受けざるを得なかったというのであれば,そこで侵害ないし制約される被疑者の人身の自由の利益の制約も通常逮捕のそれと異ならないということができる。これと比較して捜査の必要性,具体的には罪証隠滅と逃亡のおそれがあるというのであれば,なお再逮捕が許容されてもよいように思われるという視座から理解すべきもののように思われる。なお,適法な逮捕手続のやり直しが行われるという場合は,現実に被疑者が受ける可能性がある利益に対する制約というのは,逮捕が繰り返されることによりその分,若干ではあるが身体拘束期間が延びてしまうという点にある。この点,松尾説は,勾留裁判官が一度逮捕手続の違法を宣言し勾留請求を却下した後は,「被疑者の拘束期間についての再逮捕留置時間や再請求後の勾留期間の短縮を検討する方法」で利益調整を図るべきとするが傾聴に値する見解のように思われる。
[4] 法は,人身の自由剥奪という重大な基本権制約について,厳格な時間制限を設定して捜査の必要性との合理的調和を図っている。したがって,ひとつの被疑事実を根拠として複数回の身体拘束処分を無制約に繰り返すことができるとすれば,このような法の趣旨は没却されてしまうからである(法教291号99頁)
[5] 実体法上一罪については,刑罰権の個数は1個であり,これを実現するための刑事手続の一環である逮捕・勾留も,これに対応して1個1回だけ許される帰結になる(法教291号99頁)
[6] 捜査官が逮捕に足りる疎明資料を揃えることができないために行われる見込み捜査は,被疑者を取り調べて自白させるという手法が典型的である。そして,そのために利用されるツールは,①別件逮捕・勾留と②任意同行・取調べ―である。これまでの誤判事例を振り返ると,多かれ少なかれ①か②のいずれかの捜査手法が介在していることが多い。したがって,例えば,高輪グリーン・マンション事件やロザール事件なども根底にある問題は見込み捜査であるという点で,別件逮捕・勾留と軸足を同じにする問題であるということを押さえておく必要がある。興味深いのは,法教290号83頁が「別件被疑事実に基づく『強制処分』を外形として利用するか,『任意捜査』の外形を利用するかの手法の違いはあるが,いずれも『実質』において人身の自由に関する令状主義を潜脱するものと評される」と指摘していることである。酒巻は,所持品検査については3分説を支持しつつ,任意同行については2分説を採用しているところであるが,任意同行と別件逮捕・勾留の問題の平仄を合わせようとする意図を看取することができる。
[7] 例えば,忠別川事件(旭川地判昭和48年2月3日刑月5巻2号166頁)は,傷害致死被疑事件(本件)で捜査中に探知した殺人未遂被疑事件(別件)で逮捕した事例である(寺崎144)。
[8] 従来,別件基準説と本件基準説は2項対立的に対極的な考え方と位置付けられてきた。しかしながら,今日では,むしろ,両者は連続的な考え方と位置付けられるようになっていると思われる。すなわち,基本的な思考の手順としては,①まず,別件について逮捕の必要性を具備しているかを新しい別件基準説の立場から判断すべきである。この時点の判断によって従来,本件基準説が違法としてきた別件逮捕のほとんどは必要性が否定されるということになると考えられる(「別件基準説を前提とする実体喪失説」と呼ばれる中谷説)。②もっとも,別件について逮捕の必要性の要件を具備すると思われるケースの中でも,別件逮捕・勾留となる余地を否定しないのが新しい考え方の流れである。したがって,この場合は本件基準説を前提に本件として取り調べる実体がないかを検討するものといえる(これは,「本件基準説を前提とする実体喪失説」と呼ばれる川出説である)。もっとも,理論的に考えると,新しい考え方の下では,別件基準の①の手順の段階でたいていは違法とされてしまうと考えられるので,川出説が問題とするような別件逮捕・勾留は想定されにくいということになる。すなわち,新しい考え方の下では,「別件逮捕・勾留」の議論の射程距離は著しく縮減するものと理解すべきものであろう。なお,私見は,川出説が主張するようなカテゴリーを認めることは論理的にはあり得るとはいえ,別件について逮捕の必要性が満たされるとする場合は,余罪取調べの限界の問題にシフトした方がわかりやすいと考える(寺崎148)。結局,両者が連続しているといっても,判断の中身は表裏を構成するので,川出説的な②の手順の中でより厳格な判断をするという考え方を採れば別論,そうでない限り,①⇒②という流れの判断を重ねる意味はほとんどないであろう。結局,①限りでの判断にとどまるという意味で中谷説が正当ということができよう(なお,念のため附言するが,川出説は中谷説のような判断を前置することは想定しておらず,②の判断を行った後,余罪取調べの限界について独自の規範を定立しシフトしていくようである。だが,大澤も上記で述べた理解を採用しているとみられ,川出説とイコールではない)。
[9] 本件基準説が支持を失いつつあるのは,別件についての逮捕・勾留の要件が本当に認められているのかという根本的なところに関する理解がファジイだからである。別件基準説を採用しつつ,逮捕の必要性や勾留の必要性の要件を精緻化していくことにより,蛸島事件のようなケースのほとんどは,別件についての逮捕ないし勾留の必要性が否定されることになると考えられる。
[10] この見解は利益調整的な思考であるということも注意されていいように思われる。すなわち,この見解によれば,検察官は,起訴・不起訴の判断に必要な捜査を遂げた場合には,速やかに起訴するか否かの処分が求められ,当初適法な逮捕が途中から違法になるということを可能にする。そうすると,二次逮捕・勾留が行われた場合に,一次逮捕・勾留のうち,4日間は本件の身体拘束期間と評価されるので,二次逮捕・勾留の段階で,4日分を差し引いて勾留を認めるという判断を可能にするわけである。たしかに,従来の本件基準説は,途中から捜査が違法になるということを想定していないという点で不当であり,しかも,二次逮捕・勾留が再逮捕・再勾留にあたるということで例外要件を満たさない限り許されないという過激な効果が生じるとの比較からは利益調整的な思考をしているということが分かる。
[11] 別件逮捕・勾留の要件の立て方としては,①あるべき理論は何かという視点と,②判例を分析したらどうなるのか―という2つの観点からの筋がある。しかるところ,中谷判事や川出教授の見解はどちらかといえば,判例を分析すればこのようなことになるという実証的なものと評価される。また,このようにあるべきであるという理念の根底にあるのは,木谷判決のように事件単位の原則を入れて取調べを規律しようという試みということができるであろう。
[12] この疑問は要するに,客観的にみて別件の起訴・不起訴に向けた捜査のために身体拘束処分が利用されているという実態があるのに,別件逮捕・勾留の意図が捜査官にあるという主観的な理由で逮捕・勾留が違法になるとするのは妥当ではないとする見解といえる。新しい別件基準説は,主観から客観へ判断枠組みを変更しようとするものといえる。
[13] 法教290号84頁は,「刑事実務上それが顕在化して適法性が争いになるのは,本件重大事犯が起訴され裁判となってからであるのがほとんど」と指摘する。
[14] 私見は,寺崎148のような『別件逮捕否定説』ともいうべき立場にも傾聴に値するものがあると考えるものである。そもそも,別件逮捕・勾留が違法とするべき理由は,余罪取調べを行うという点にある。したがって,正面から問題とするべき点を見据えてこの点のみを検討すれば足りるとする理解は素直なものといえる。では,なぜ,それ以外の学者たちは,別件逮捕・勾留を検討したがるのであろうか。それには,2つの立場からの思惑が潜んでいる。まず,通説は,取調受忍義務を否定している。したがって,取調べは任意ということになり,したがって,任意処分に限界はないという帰結になってしまう。そうすると,余罪取調べを規律する余地がなくなり不当ということになる。そこで,余罪取調べという実態に着目して遡って逮捕が違法という逆立ちした理屈をつけるわけである。通説の立場からすれば,余罪取調べには限界はないということになるので,別件逮捕・勾留論で勝負をかけるしかないわけである。これに対して,検察サイドの見解としては,取調受忍義務が認められるのは当たり前と解すべきであるが,不思議なことに取調べは任意というべきである。したがって,余罪取調べの限界はないということになる。そうすると,やはり別件逮捕・勾留を問題とするべきということになる。例えば,渡辺咲子は,「別件勾留要件消滅説」というのを採るが,要するに,逮捕勾留の目的は,取調べをするためである(!)ところ,別件についての取調べの必要性がなくなれば,勾留要件も消滅するという理屈を立てている。渡辺も取調べが任意処分と解するので,限界が問題となる余地はない。したがって,論理的にはもっとも素直というべき第三の道は各立場の思惑により採用が難しい見解とされてきているわけである。
しかしながら,いずれの見解にも理論的には無理があるというべきである。まず,取調受忍義務は,取調室への出頭・滞留義務という意味において承認せざるを得ない。このように解しても,取調べを受けなければならない義務はないと解すべきであるから,黙秘権の保障と矛盾するところはないというべきである。そうだとすれば,取調べは取調受忍義務という義務を被疑者に課して行われるものであるから,強制処分と解するのが相当である。したがって,事件単位の原則による規律を受けると解すべきであり,取調受忍義務を課して取調べをすることができるのは,事件単位の原則から,別件に限られると解するのが最も実効的な取調べに対する規律としての意味を持つものと考えられる。寺崎148は,学者及び検察サイドのいずれからも厳しく非難された浦和地判平成2年10月12日判時1376号24頁とほぼ同趣旨の結論を採るものと解され,プラクティスには最も適しているといえよう。私見は,別件逮捕が問題とならないとするには令状主義の潜脱という実質にかんがみ,なお躊躇を覚えるものであるが,基本的な理解は寺崎148と前記浦和地判と同旨である。この点,百選19事件の解説は,「本件の取調べが任意に行われる限り,この立場においても,その実施を制約する契機は見い出しがたい」とする。たしかに,被疑者が任意に承諾して余罪の取調べに応じるのであれば,この指摘は正当である。しかしながら,本当にその承諾は任意であるのかということを実質的に判断されるという点が重要な問題である。特に,余罪について任意に取調べるということであれば,その実質的な強制的雰囲気にかんがみ,任意取調べに応じる合理的な理由がない限り,承諾は実質的にみて,ないものと解される。木谷判決はそのために取調受忍義務がないことを伝えるなどの方策を要求するものである。佐藤は,この視点を欠落させ,承諾があることを前提にその限界はないというが,私見はその点についてなお疑問があると解するものであるが,この点を措くとしても,木谷判決の真意を正解しないで,解説している点がそもそも不当というべきである。なお,この点に関する東大系の学者たちの主張には注意すべき点がある。すなわち,彼らは,取調受忍義務は松尾説が妥当であると主張しているにもかかわらず,別件逮捕の問題となると取調受忍義務はないことを前提に議論をしだすのである。大澤はこの矛盾について,「自分は松尾説が妥当であると考えるが,松尾説を採っているわけではない」という。たしかに,それならば矛盾はないが,松尾説を推し進めると,理論的には寺崎148のようになることは確認されてしかるべきものと考える。
[15] 論理的なつながりがあるとはいえないが,寺崎148のように別件逮捕否定説に立つと,余罪取調べの限界という問題しかないということになるので,A説しか採る余地がないように思われる。これに対して,実体喪失説によると,形式的には,先行する勾留が別件のものと評価されるので,再逮捕再勾留の問題となるが,実質的な判断によれば,身体拘束期間の制限を潜脱になるという実質面からも第二次逮捕・勾留を否定することができる。したがって,実体喪失説が実体を失った後,形式的にどのような状態になるかについては特に詰める必要がないというのが大澤の理解のようである。再度勾留という実質があることが問題なのである。