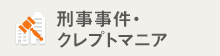おとり捜査
第11編 おとり捜査(白取114,寺崎58)
第1 意義
1 定義
おとり捜査とは,捜査機関又はその協力者である私人がおとりになって人に犯罪を行うように働きかけ,その犯罪に着手するのを待って検挙する捜査方法をいう
2 効用
おとり捜査は,薬物の密売など,国民生活に対する弊害が大きい重大な罪でありながら,秘密裏かつ組織的に行われるので,通常の捜査方法では検挙が困難な犯罪に有効(児童ポルノ違反,薬物事犯,売春,贈収賄,鉄砲の不法所持)
3 意識しなければならない視点
① なぜ,おとり捜査は許されないのか(違法性の実質)
② おとり捜査は将来捜査であり,「捜査」ではないのではないか
第2 判例の展開
1 最決平成16年7月12日刑集58巻5号333頁
「少なくとも,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは,刑訴法197 条1 項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべき」
2 従前の判例との関係
(1) 最決昭和28 年3月5 日(刑集7 巻3 号482 頁)
「他人の誘惑により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に,わが刑事法上その誘惑者が場合によつては・・・教唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別,その他人である誘惑者が一私人でなく,捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は責任性若し
くは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものとすることのできないこと多言を要しない」
(2) おとり捜査を全面的に適法としたものか
ア 捜査の違法と法的効果
⇒ 捜査の違法と法的効果は別個の問題
* 28年判例は,おとり捜査に対する法的効果として,被告人が無罪,公訴棄却,免訴とならないことを示したのみ
イ 具体的事案との関係
28 年判例は,おとりの働きかけにより「犯意を生じた者」ではなく,既に犯意を有していた者であったから,同決定の「犯意を生じた者」に関する判示は,すべて傍論と解する余地
⇒ 判例は,被告人が犯意を誘発された場合を含め実体法上無罪とならないことを明らかにしただけ!![1]
* 従来の判例が,訴訟法的救済措置を講じる可能性まで否定するか疑問
第3 おとり捜査の許容性(任意捜査としてのおとり捜査)
1 違法性の実質[2]
① 国家が自ら犯罪を作り出したうえで処罰することの矛盾ないし不公正
② 刑事実体法で保護された法益の侵害ないし危殆化(佐藤説で有力![3])
③ 捜査対象者の人格の自律性の侵害[4]
2 自己撞着性(上記②)と人格的自律(上記③)からの法益侵害の検討
⇒ 犯意誘発型と機会提供型は,共犯の教唆犯と幇助犯と概ねパラレル
(1) 自己撞着性の視点
ア 犯意誘発型[5]
国家の法益侵害に対する因果性が強いという点で国家が犯罪を創出し法益を侵害したという側面が強く,他方,人格的自律の制約の程度も大きく違法重大
イ 機会提供型
おとり捜査が行われなくても,別の機会に同種犯罪が行われた蓋然性のある場合であるから,創出という面が薄く国家の法益侵害に対する役割の程度は小さいし,すでに犯意は生じているから人格的自律への制約に乏しい
(2) 働き掛け行為の強さ自体
⇒ 因果性の強弱に影響を与える要素!!
ア 働きかけが執拗の場合
機会提供型に属するといえても,対象者の意思決定の自由を侵害し,ひいては,国家が犯罪を創出したに等しいといえ自己撞着性も認められる
イ 働きかけが通常の程度
人格的自律に対する制約や自己撞着性とは評価できず適法
2 おとり捜査は任意捜査か
(1) 強制処分であるか
①② ⇒ 捜査対象者に対する直接的な権利・利益の制約は問題でない
③ ⇒ おとりの働きかけは対象者の意思決定の自由そのものを奪うものではないことを前提とするから,そこで制約される権利・利益は,「意思決定に当たってむやみに国家の干渉を受けない自由」にとどまる(このような利益の観念自体に争いあり)
* 51年判例に照らす限り,一般に有形力の行使を伴わずに行われ,相手方の重要な権利や自由の侵害も通常は認められない[6]
⇒ 強制処分とはいえない
(2) 任意捜査としての問題点
① 重大な権利・利益の制約の有無
② 将来の犯罪の摘発と捜査[7]
(3) 任意捜査としての適法性
ア 従来の有力な考え方
「機会提供型」と「犯意誘発型」を区別する二分説
イ 近時の考え方
おとり捜査の必要性と客観的態様の相当性に注目する考え方
∵ 二分説が捜査対象者の主観に着目していた点を反省し,おとり捜査の適法性はその必要性と客観的な態様の相当性によって判断すべき
* 16年判例も,捜査機関側の働きかけの態様にも言及したうえ,おとり捜査
の適法性を認めるから,この見解によるものと見えなくはない
ウ 大澤説
(ア) 51年判例の任意捜査の相当性基準をあてはめる見解
おとり捜査も任意捜査であるとすれば,その適法性の判断枠組みは,他の任意捜査と共通であることが合理的[8]
⇒ おとり捜査も,当該捜査手段を用いる必要性とそれによって制約される権利・利益とを比較衡量し,具体的状況の下で相当と認められることが必要!!
(イ) 本決定が示す事情は,比較衡量の結果,相当性が認められる場合示す
* 判例があげる3つの事情
① 直接の被害者がいない薬物犯罪であること
② 通常の捜査方法のみでは,当該犯罪の摘発が困難であること
③ 機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象とすること
* 大澤の理解[9]
Ⅰ 判示の事情は,いずれもおとり捜査の必要性を基礎づける
Ⅱ ②は補充性を基礎付け[10]
* 大澤は,判例が①と区別して②を挙げたことについて,「①から導かれる一般的なおとり捜査の(抽象的な)必要性に加えて,②にあたる具体的事情(具体的必要性)をも要求する趣旨」と指摘する[11]
Ⅲ ③の事情も,おとり捜査一般に当てはまる,その捜査手法としての特殊性から必要とされる事情といえる
* ③は将来の犯罪に向けられたおとり捜査において,犯罪発生の蓋然性を基礎づける事情。犯罪発生の蓋然性がなければ,捜査の必要性なし[12]
Ⅳ 同時に『直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において』の部分は,おとり捜査により侵害・危殆化される法益が特定の個人のものではないという意味において,制約される権利・利益の限定性を基礎付ける
Ⅴ 『機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うこと』は,法益の侵害・危殆化がいずれは発生するはずのものであるという意味において,あるいは対象者の意思決定への干渉の度合いが小さいという意味において,制約される権利・利益の限定性をも基礎づける
* 大澤は,②・③の事情が欠けた場合のおとり捜査が適法とされることは考えにくいとし,16年判例は事例判例であるが,その先例性は高いという
(ウ) 相当性の枠組みの考慮要素の整理
① 将来捜査との関係
対象者が犯罪に常習的・組織的に関わり,具体的犯罪の嫌疑があること[13]
* 「被疑者に事前に客観的嫌疑があること」を最初に認定すべき
② 捜査の必要性
Ⅰ 対象犯罪が社会に大きな害悪をもたらす重大なもの
Ⅱ 対象犯罪が密行性・組織性があること
Ⅲ 具体的事情のレベルでおとり捜査の方法によるしかないこと
Ⅳ 被害者がいない犯罪であること
③ 手段の相当性
Ⅰ 犯罪性向のない一般通常人をすら犯行に陥れかねないような巧妙,積極的なものでないこと
Ⅱ 脅迫や強要など違法な手段を伴わないこと
Ⅲ 対象者が真摯に犯罪を中止しようとしたにもかかわらず,執拗に働きかけて翻意させていないこと
3 おとり捜査の法的効果
① 違法なおとり捜査で証拠が収集された場合
⇒ 違法収集証拠排除法則の適用場面
② 違法なおとり捜査での起訴
⇒ 無罪にはできないのが判例なので,形式裁判で手続を打ち切るべき
● 免訴説(団藤説)
∵ 実体的訴訟条件が欠ける
○ 公訴棄却説(田宮,指宿,白取117)
∵① 捜査の廉潔性が失われ,デュー・プロセスに違反する
② おとり捜査も適正手続の問題の一環と考えれば公訴棄却が妥当
* 犯意誘発型で違法性が極度に高く,国家は犯罪を行ったに等しい「間接正犯型」では,公訴棄却というドラスティックな処理をすべき(調査官)
[1] もともと,二分説は,アメリカの判例理論である「わなの理論」を参考にしたものであり,この理論は,「実体法的な処罰が可能か」というレベルの議論であったために,昭和20年代の判例の上告趣意も「実体的に無罪とすべき」という主張が多かったわけである
[2] 大澤は,おとり捜査の違法性の実質を2つの観点から理解していると解される。まず,①おとり捜査が行われることにより,人権を侵害される被害者が生じるという場合は,国家の基本権保護義務との関係で自己撞着性を生じるので許されないという視点である。また,②対象者には,「国家の干渉を受けることなく独自に意思決定をする自由」があるととらえて,そのような観点からおとり捜査の限界を基礎付けよう―という観点である。このように考えてくると,実に興味深い現象が生じていることがわかる。というのも,従来はおとり捜査の問題点は,Ⅰ国家の行為無価値に着目した自己撞着性,Ⅱ対象者に「わな」を仕掛けてトリックを用いて犯罪へ導くという不公正さ―が挙げられていた。ところが,大澤の見解によると,Ⅰがまさに①に対応し,Ⅱは②に対応しているということが分かる。このように,国家の行為無価値に着目するのではなく,なるべく結果無価値的に法益に対する制約という視点を考慮しバランスをとっていこうという思考態度がうかがわれる。たしかに,調査官解説は,Ⅱについて,「『捜査の公正』とは,・・・人をだましてわなにかけるのはよくない,という素朴な道義」の問題にすぎず,違法性の実質を基礎付けるものではないとする(なお,調査官はそのうえで,基本的には自己撞着性から説明する見解が正当とする)。
[3] おとり捜査の違法の実質は,これまでは,直接には誰の法益も侵害しないという前提にたって,国家の行為無価値に違法性の所在を求めようとしてきた。そこで,挙げられてきた違法性の実質が「不公正」である。しかし,佐藤説は,不公正とは別の視座,すなわち,「国家が犯罪を作り出し,その結果として,刑法により保護される法益を侵害する点」にあるとした。この見解は,三井説が処分の直接の対象者との関係で『人格的自律』という利益を問題にするのに対して,国民一般との関係で,自己撞着性で指摘される問題点を利益制約の視点からとらえている。この見解からすれば,例えば,殺人や傷害については,対象者に殺されたり殴られたりする人の生命・身体という法益が,国家の作為ないし不作為によって侵害されるという関係にある。突き詰めてゆくと,ドイツ憲法の基本権保護義務論にもつながる考え方といえよう。
[4] 人格的自律に着目すれば,おとりが働きかける際に,強制・脅迫などの手段を用いない限り,対象者の意思の自由はむしろ確保されているのではないか-との疑問が生じる。たしかに,被疑者は,おとりの身分について錯誤に陥っているが,「犯罪が禁止されていること」は十分理解しているのであるから,意思決定の自由が侵害されたとはいえないという見解もある(佐藤隆之「おとり捜査の適法性」ジュリ1367号133頁)。
[5] 注目されてよいように思われるのは,この2分説は,「犯意が生じているか」という点に着目し区分しているという理解が一般的であるが,調査官は,この2つの区分を「合理的嫌疑の存在の有無」で区別しているという点である。たしかに,合理的嫌疑がすでに存在しているということは,何らかの特定の犯罪がすでになされて,それに伴い捜査が始まっているということを意味するのであろうから,犯意誘発型となる可能性はないということになろう。すなわち,合理的嫌疑の有無という捜査官側のある程度客観的な事情に着目して両者を区分しているということである。しかしながら,この二分説の区別は,そうだとすれば,「嫌疑が具体的か否か」という視点しか提供していないということになるのであり,したがって,適法・違法を区分するメルクマールというよりかは,裁判所の判断の結果を整理する概念という性格が強いといえるであろう。
[6] たしかに,おとりの対象となっている被疑者の意思のいかんを問わず行われるが,他方で,被疑者の身体の自由やプライバシーの利益を制約するわけではなく,重要な権利・利益の侵害という要素は認められない。むしろ,おとり捜査の違法性は,国家の自己撞着性や第三者の法益侵害から違法性が基礎付けられるものであるから,被疑者との関係では強制処分に該当するとまではいえないと考えられる。
[7] 白取114は,「おとり捜査には,犯罪発生前の『捜査』という側面は否定できない。薬物の売買のように反復する犯罪の検挙の場合,過去の犯罪捜査のために『おとり』を用意するという構成がとれなくもないが,その場合でも,将来発生する予定の1個の犯罪に着目すれば,それとの関係では『将来の犯罪捜査』である。学説が薬物取引など『反復型』の犯罪以外のおとり捜査に慎重なのはこのため」と説明している。この指摘に対して,大澤裕「おとり捜査の許容性」平成16年重判190頁は,「伝統的な考え方そのものを疑問とし,行政警察活動と司法警察活動の区別は,目的の違いであって,犯罪発生の前後と結びつく必然性はなく,犯罪の訴追・処罰に向けられた活動である限り,将来の犯罪についても刑訴法197 条1 項本文の任意捜査を行うことは妨げられないとする考え方も有力に説かれている(酒巻)。
おとり捜査の場合,伝統的な考え方を前提にしても,例えば,現に薬物所持の嫌疑がある被疑者について,その隠匿場所等の捜査が容易でないため,おとりが薬物購入の申込みを行い,被疑者が薬物を持参したところを検挙するという方法をとることは,既に発生し継続している所持事犯の捜査の一環と見ることができる(三井)。また,被疑者に対し既に行われた犯罪の嫌疑が存在する場合には,「その犯罪の捜査と併行して将来の犯罪への対応を見込んでいたとしても,そのことから直ちに違法な捜査ということはできない」(池田・後掲40)との指摘もある」と白取114に反論を加えている。
[8] 大澤の51年判例を出発点とする見解に対して,調査官は,「おとり捜査については,同じ任意捜査の範疇に属するといっても,国家が犯罪を創出するという点に違法性の実質があり,対象者の利益(行動の自由,プライバシー)との関係で適否が問題となるものではないから,昭和51年判例に準拠する判断手法がおとり捜査に直ちに妥当するか」は,疑問であるとする。たしかに,51年判例は,対象者の行動の自由という利益との関係での利益の比例性が問題となっているわけであり,自己撞着性の論理により違法性を基礎付けようとすれば比例原則の枠組みは直ちに持ち込めないのは首肯できる。しかし,大澤は,一応は,人格的自律が問題となるとするし,51年判例が任意捜査一般の規範と理解するのであれば,比例原則を持ち込むという判断も間違いとは言い切れないであろう。
[9] 大澤の理解について,佐藤隆之「おとり捜査の適法性」ジュリ1367号135頁に基づいて補足的に説明しておこう。まず,判旨が挙げた3つの事情というのは,すべて『捜査の必要性』の事情であると考えられている。したがって,捜査が適法というには,『捜査の相当性』も認められる必要があるが,この点,判旨①の事情が相当性の事情も兼ねていると理解されている。たしかに,おとり捜査によって侵される法益侵害を考えると,「大麻の散逸・濫用によって,使用者の心身が蝕まれる危険」ということになる。しかしながら,判例の事案ではほぼ確実に大麻が捜査機関の手に帰する過程にあったとされている。したがって,直接被害者がいる殺人のようなケースと比較すれば法益侵害は観念できるとしても,それは間接的であり,しかも,それが現実化する危険も少なかったと考えられる。このような事情に照らすと,判旨①が同時に捜査の相当性も基礎付けるものであるから,あえて,相当性に関する事情を判例は挙げなかったものと理解できる。
各事情に関して,コメントを付すことにする。まず,判旨①については,「直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査」とされている。たしかに,これらの事情があれば捜査が一般的に困難であるということはいえる。しかしながら,判旨①に対しては,最決平成8年10月18日判例集未登載の大野正夫・尾崎行信裁判官の反対意見が鋭い反論を加えている。すなわち,反対意見は,判旨①でおとり捜査が許容されるというのであれば,抽象的な必要性があれば一般的におとり捜査が認められるということについて批判を加えている。このような観点からは,一般的な必要性に加えて当該事案に即したおとり捜査の具体的な必要性があるということが必要と考えられる。判旨②は,このような観点から理解することができるわけである。
次に,判旨③は,捜査という概念からくる要件である。すなわち,そもそも具体的な嫌疑が発生していなければ捜査をすることはできないはずである。したがって,おとり捜査においては,対象者が特定の犯罪を行う具体的な蓋然性があるということが,嫌疑の内容となると思われる。本件の事案では,被告人Xが捜査協力者Aに対して大麻樹脂の有償譲渡を電話で持ちかけているという事情がある。そうすると,Xは,すでに大麻樹脂の有償譲渡を企図して買手を求めていたと推論できる。そうすると,大麻を持っているから譲渡ができるのであるから,ここに,Xに対する大麻樹脂の所持ないし有償譲渡の嫌疑が生じているといえる。したがって,判旨③の要件を満たすわけである。
[10] おとり捜査は任意捜査であるが,本決定は,補充性ともいうべき特別の必要性が認められる場合にその適法性を認めた。このような特別の必要性の要請は,司法の廉潔性に反すると見るか,刑事実体法によって保護された法益を侵害・危殆化すると見るかは別として,おとり捜査には他の捜査手法にない特別の弊害が伴う点から基礎づけられる
[11] 実際,本決定は,②の事情の存在を認めるに当たり,「麻薬取締官において,捜査協力者からの情報によっても,被告人の住居や大麻樹脂の隠匿場所等を把握することができず,他の捜査手法によって証拠を収集し,被告人を検挙することが困難な状況にあ〔った〕」として,具体的事件の事情に立ち入った判断を示している
[12] この意味からすれば,将来捜査の対象を無条件に拡大するということに対して,制限的に臨もうという態度が見られるわけであり,白取説の批判も無駄ではなかったといえよう。
[13] 調査官解説は,「合理的嫌疑の存在」という要素が最も重要なものと指摘する。というのも,合理的嫌疑すら存在しないという場合には,国家機関が犯罪を創出し国民の法益を侵害したという自己撞着性を抱えてしまうし,合理的嫌疑があれば,当該対象者を犯人として逮捕したり同種犯罪の反復を予防する必要性が生じ,それ故に,人格的自律に制約を加えることも正当化されるからと解される。