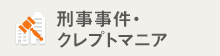犯罪被害者
第16編 犯罪被害者
第1 「事件」の当事者と「手続」の当事者
1 被害者の権利(理論的に考えられるもの)
① 社会的援助を受ける権利
② 二次的被害から保護される権利
③ 被害者として刑事司法情報にアクセスする権利
④ 刑事手続に参加する権利
2 歴史的な流れ
2000年5月「被害者保護二法」成立
2007年6月「被害者参加制度」と「損害賠償命令制度」
第2 被害者参加制度
1 定義
被害者参加制度とは,一定の犯罪の被害者などが,裁判所の許可を得て,被害者参加人として,検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちつつ,一定の要件の下で,公判期日に出席するとともに,被告人質問などの一定の訴訟活動を自ら直接行う制度をいう
2 制度趣旨
① 犯罪被害者がその尊厳にふさわしい処遇を受ける必要
② 被害者は事件の推移や結果の重大な関心を持つ
③ 被害者は刑事裁判に関与し被害からの立ち直りに資する
3 参加することによりすることができること(効果)
(1) 全体について
① 公判期日に出席することができる
② 被告事件についての刑訴法上の検察官の権限の行使に関し,意見を述べ,説明を受けることができる
(2) 証人尋問の段階
⇒ 情状についての証言の証明力を争うための尋問をすることができる
(3) 被告人質問の段階
⇒ 意見を陳述するために必要な場合に質問をすることができる
(4) 論告・求刑の段階
⇒ 訴因の範囲内で,事実又は法律の適用について意見を陳述することができる
* 全体について[1]
4 被害者参加制度の理論的問題点
(1) 被害者参加と当事者主義
ア まず,被害者参加人が訴訟法上,どのような地位を取得するかという問題がある。この点について,被害者参加人には,公判請求権や訴因設定権,証拠調べ請求権,上訴権などが認められていないので,当事者それ自体の地位とは異なる。もっとも,被害者参加人は,証人尋問や被告人質問の訴訟活動を自ら直接行うことが認められているから,一定の制限が加えられた訴訟法上の当事者的地位が与えられたものと位置付けることができる。したがって,被害者参加人がまったく当事者と異なるとして,当事者主義に反しないと結論することはできない。
イ そもそも,当事者主義,弾劾主義の必須の構成要素は,おおむね,検察官が訴因を設定し,その訴因の範囲内で検察官が犯罪事実の主張・立証を行い,被告人は弁護人の助力を受けて挑戦的,徹底的に防御活動を行い,その結果,検察官の主張たる訴因が合理的な疑いを超えて証明されている場合にはじめて有罪認定がされるという内容であると考えられる。
まず,被害者参加人が証人の尋問をする場合に,これが犯罪事実の主張・立証に関わってくる場合については,それによって被告人の防御の範囲が拡大させられるということになるし,訴因から逸脱するということも考えられる。したがって,被害者に犯罪事実に関する証人尋問を認めれば当事者主義や弾劾主義に反するというべきである。ところが,被害者参加人がすることができる証人尋問は情状に関する事項に限定されている。
他方,被告人質問については,情状に関する事項に限定されているわけではないが,拡大されるのは,「意見の陳述をするために必要がある場合」に限定されるということになっている。そうだとすれば,被告人質問との関係では,当事者主義や弾劾主義との間で若干の緊張関係があると評価することも可能と思われる。すなわち,上記の「必要がある場合」とは,被害者参加人が意見の陳述を行うに当たり,どのような態様にするかを被告人に対して質問をしてその状況を見定めるための必要性である。そうすると,この質問の事項は多岐に渡る可能性が高いというべきであろう。この点,尋問が定められた範囲を超える場合は,裁判長が尋問を制限することができるとされているが,そもそも,本件被告人質問との関係では,「尋問が定められた範囲を超える」と評価することが困難であるケースが多いと考えられる。突き詰めると,被害者の意見陳述は,もっぱら情状に関することが多いと予測されるが,それは訴因の範囲を超えるものであることがほとんどであろう。もっぱら,被告人の悪性格の立証に情熱を燃やされるという決してあり得ない事態を想定すると一層不都合性は大きくなろう。そうすると,これについての適切な運用がなされないという事態が生じれば,結局のところ,被告人質問について,罪体に踏み込んだ質問も含んだ質問がなされ被告人側の防御の範囲が拡大する側面を否定することはできないであろう。したがって,証人尋問については問題はないが,被告人質問は問題が大きいというべきである。
(2) 被害者参加と無罪推定原則
ア 被害者参加制度が無罪推定の原則に反するという見解がある。これは,どのような見解というと,被告人の有罪判決が確定するまでは被害者も確定していないのに,確定しない被害者を事件の当事者として訴訟参加を認めるのは,無罪推定原則に反するというのである。
イ この見解についてはおよそ荒唐無稽な主張といって切り捨てることは正しくない。すなわち,この見解が憂慮しているのは,特に犯人性が争われている事件において,被害者が登場して,被告人に対して被害感情をぶちまけるという事態になったときに,被告人としては自己が犯人であることを前提として,種々の質問を受けるということになるので,前提が誤っている誤導質問しかなされず,これを法律上の制度により認めることになると,ひいては事実認定をも誤り,刑訴法の目的とする真実発見を妨げることになるばかりか,無辜を処罰する人権侵害をもたらす結果になるというのが論旨であろうと考えられる。現実の誤判事件の多くも誤導が前提で非難を受けて裁判所がそれに影響を受けて有罪認定につながったと疑われる事案も散見されるわけである。このような問題意識を無罪推定原則に反映させて,被害者参加制度を論難しているものにすぎず,ジュリブック19が理論的な観点から反論を試みているのは論旨の問題意識を正解していないと考えられる。
ウ ジュリブック19の論旨には疑問な点が種々,見受けられる。すなわち,論者の見解は,無罪推定原則というのは,おそらく訴訟法上,検察官が立証責任を負担するという立証責任の原則に昇華してしまって,もとより被告人が有罪判決を受けるまでは無罪であるという状態を保障するという点については,無意味であるという立場を理論的な前提にしていると考えられる。
しかしながら,ならば黙秘権が保障されている理由を合理的に説明することはできないはずである。そもそも,無罪推定の原則というのは,刑事裁判において被告人が有罪と認定されるまでは無罪と推定されるという原則のことである。そうすると,そこから検察官が立証責任を負担するという原則が導けるとしても,それはあくまでも派生原則にすぎないのであって,無罪推定の原則と検察官挙証責任の原則は別の原則であると考えるのがむしろ一般的な立場ではないかと思われる。そうだとすれば,検察官挙証責任がこれからも検察官にありこの点については何ら変更されるものではないと反論してみたところで,有効な反論とはなっていないというべきである。ある事件について被害者がいるということは否定できないとしても,その事件の犯人が被告人ではないと争っている場合は,少なくとも被告事件の被害者ではないという立論は十分可能なものであろう。ジュリブックの見解は,大方の自白事件を典型例として想定しているが,当事者主義や弾劾主義の下では,正常なのはむしろ否認事件なのでありその多くは犯人性を争っているわけであるから,典型例の想定に誤りがあるということではなかろうかと思われる。
そうだとすれば,少なくとも犯人性の否認事件に限定しては,被害者参加制度を導入して,特に問題の大きい被告人質問をすることは,無罪推定の原則という刑訴法上の原則に反するものというべきである。したがって,私見は,犯人性否認事件については無罪推定原則に反するかどうかは別として,被告人質問をすることは許されるべきではなく,これを認めれば,裁判所の被害者参加許否についての合理的裁量を逸脱したと評価すべきものと考える。
この点についてジュリブック93も,「被告人が無罪を主張している事件であっても・・・直ちに被告事件の手続への参加を許さないとすることは,適当ではない」とするが,犯罪の証明に支障が生じるおそれや被告人の防御に不利益を生じるおそれがあると判断され「相当でない」と判断される可能性が一定程度は考えられるという見解を前提としていると思われ,基本的な方向性は妥当であろう。
(3) 裁判が復讐の場となり報復の連鎖が復活するか
ア たしかに,裁判が復讐の場ということになれば,そもそも私刑を禁止して,裁判権を国家が独占した意味がなくなるのであって,国家の役割を否定するに等しい立法であるという批判は十分成り立つというべきであろう。ジュリブック20は,「法廷が復讐の場となったとの批判はない」というが,それはことさらに被害者を批判するという論文が少ないだけであり,特に少年事件において被害者が感情的に泣きわめくなどして肝心の少年が話さなくなったなどの報道もみられるところであって,社会的な実態がないというのは誤った事実認識であるといわざるを得ないであろう。
イ したがって,かかる批判については常に念頭においた運用がなされる必要がある。この点について,犯罪被害者の訴訟参加はすべて検察官を経由して行われることとされている。そうだとすれば,被害者参加人は検察官と十分なコミュニケーションの下に参加してくることが予測される。そうすると,ある程度は適切な参加のあり方について一定の理解があるということが予測されよう。しかも過度に感情的な尋問や質問がなされて法律上の趣旨に沿わない場合には裁判所が尋問や質問を制限することができる。以上のようにみてくると,裁判が復讐の場となる可能性はないとはいえず,上記の制度を適切に運用することが重要といわなくてはならない。特に,被害者が感情的な質問をしてそれがきっかけで真相の解明が妨げられたり人権が侵害されるということがあれば,検察官の責任は重大であるといえるであろう。
第3 損害賠償命令制度
1 定義
損害賠償命令制度とは,一定の犯罪の被害者などが被告事件の係属する刑事裁判所に対して,被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができることとして,当該裁判所は,被告事件について有罪の言渡しをした後,最初の審理期日において,被告事件の訴訟記録を取調べたうえで,原則として4回以内の期日において審理を行い,決定によりその申立てについての裁判をする制度をいう
2 制度趣旨
現在の損害賠償制度が犯罪被害者のために十分に機能しているとはいえず,刑事手続の成果を利用することにより被害者の労力を軽減し,簡易迅速に損害賠償を受けられることにする
3 制度の特色
① 刑事手続の成果の利用
② 被害者の労力・負担の軽減
③ 手続の簡易迅速性
4 制度の概要
(1) 損害賠償命令の申立ての要件
① 申立てが認められている一定の事件であること(17条1項)
* 財産犯は適用外
② 被害者又は一般承継人であること
③ 訴因を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求であること
④ 弁論の終結までに申立てがあること
(2) 損害賠償命令事件の審理と裁判
① 口頭弁論をしないことも可能(23条1項)
② 有罪判決の言渡し後に原則,損害賠償命令の申立てにかかる期日開く
* 通常は刑事裁判の判決後すぐに行う
③ 裁判官は刑事裁判における心証を損害賠償命令事件の審理に事実上引継ぐ
④ 証拠調べは職権で行うので,弁論主義の例外
(3) 異議の申立てとその後の裁判
2週間以内に異議可能(27条1項)
⇒ 事物管轄に応じて地裁・簡裁に訴えの提起ありとみなし(28条1項)
(4) 損害賠償命令事件の終了
① 4回で終わらない場合(32条1項)
(被告人が犯罪事実への関与を否定し,改めて証拠を提出して争う場合や損害額の認定に複雑な争点がある場合)
② 当事者の意思に基づき通常の民事訴訟手続への移行がなされたことに伴い手続が終了する場合(32条2項)
* 地裁ないし簡裁に訴え提起ありとみなし(32条4項)
5 制度に対する理論的な批判
(1) 刑事裁判が長期化するおそれがある
一応は,損害賠償命令制度は,刑事裁判が終了してから損害賠償命令の申立てにかかる審理を行うものとされている。したがって,制度的に刑事裁判の長期化については一定の配慮がなされている。もっとも,損害賠償命令制度については,裁判官が刑事裁判からの心証の引継ぎをすることを前提としているので,被告人としてはこれを意識した防御活動をすることが求められることになるという側面は否定できず,刑事裁判が長期化するというおそれは完全に否定することはできないが,事実上のものにとどまると思われる。
(2) 損害賠償命令の申立てが刑事裁判の判決前になされることにより,それを担当する裁判官に対して予断を与えるおそれがあるという指摘
たしかに,損害賠償命令制度の申立てにおいて訴状が提出され縷々被害者が主張するということになれば,それを予断というかは別として,検察官以外の者の主張が裁判に上程されるということになりかねない。したがって,何らの制度的手当てが必要であるところ,法は,損害賠償命令の申立てについて請求を基礎付ける具体的事実の記載を禁止している。そうすると,被害者の具体的な主張が刑事裁判に上程されることはなく,予断が生じるということにもならないと思われる。
(3) 損害賠償命令事件の審理における被告人の防御権が十分に保障されないという指摘
この問題が損害賠償命令制度の核心的な問題点であると考えられる。これは,法律上,理論的な問題点というよりかは,社会的実態としてそうならざるを得ないのではないかという指摘であり,被告人の防御権の保障の見地から何らの制度的手当てがなされても良かったと思われるのであるが,結局,何の手当てもなされなかったお。そうすると,どういうことが起こるかといえば,①刑事事件の弁護人は民事事件の代理人となるわけではなく,被告人は改めて代理人を選任する必要があるということになるのだが,資力がない被告人が早期に代理人を選任することができるかといえば疑問であろう。そうすると,弁護士の代理人なしで行う必要が出てくるが,民事事件の裁判のために刑事施設に収容されている被告人は常に出頭することができるというわけではないというのが実務上の運用である。したがって,代理人なしであるばかりか,自らの出頭もかなわず,結果,欠席判決がなされるおそれがあるということになる可能性は否定することはできないと思われる。
理論的には2つの方向性からの問題解決の方向があると思われるが,1つは,刑事弁護人が事実上民事事件の代理人もボランティアで活動してあげるという点であるが,弁護人に善意の奉仕を強制することを前提にしか成り立たない制度はもとより問題がある。そこで,民事事件とはいえ公的なディフェンスを得られるように,現在の国選弁護制度を民事事件の損害賠償命令制度に限ってという限定付きで拡大させるということも立法論としてはあり得ると思われる。これは,法テラスによる扶助を利用することで代えられる可能性もあろう。
他方,それが実現しない間はなるべく本人の民事事件の審理についての出頭を可能にするように刑事施設の収容のあり方を見直し,後は裁判官の適宜の釈明に委ねるという方向性の解決に委ねるしかないという状況にあるのではないかと思われる。ただし,被害者が刑事裁判の裁判官に対してアクセスしてくる中で裁判官が現実的にどれだけ民事事件の被告となった受刑者に釈明権を行使できるのか,かかる制度の簡易迅速の理念に照らしても問題が残されているように思われる。そうしてみると,代理人がいない間は民事裁判体で釈明権を適切に行使させつつ,審理を行わせるという方向性もあり得るように思われるが,移行権は申立人にのみ認められ,被告人には認められていない。したがって,この解決策も現行法上では難しいわけであるが,被告人が命令に対して異議を述べることはできることとの均衡から,立法論としては検討されてよいように思われる。
ただ,このような問題点は現実には民事訴訟にも起こりえることではあるので,それとの均衡をどのように考えるかも問題であるということはできるが,そもそも資力が不足している者に対して,実効的な訴訟を提起するということがこれまでもあり得たのであろうかという社会実態にかんがみるときは,民事訴訟においても手当てがないから刑事手続においても手当てなしで構わないと結論付けるのは早計のようにも思われないこともない。結局のところ,これは残された課題というべきであり,損害賠償命令の申立てがなされた段階でついて回る問題といわざるを得ない。
第4 犯罪被害者の被害者特定事項の保護
1 被害者特定事項
被害者特定事項とは,例えば,被告事件の被害者の氏名及び住所など,その者が当該事件の被害者であることを特定させることになる事項をいう
2 公判手続における被害者特定事項の秘匿(290条の2第1項1号2号3号3項)
(1) 要件
① 強制わいせつ,強姦,児童福祉法違反などの性犯罪
② 被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合
この類型としては,迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件,精神病院の入院患者が被害者である殺人事件,ラブホテルで出張風俗嬢が殺害された場合などが挙げられる
③ 被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者などの身体・財産に害を加えて又はこれらの者を畏怖・困惑させる行為がなされるおそれがあると認められた場合
この類型としては,暴力団構成員による事件で,被害者特定事項が明らかにされることによって,被害者に対して当該暴力団の関係者から,報復や嫌がらせを受けるおそれがあるような事件
(2) 効果
起訴状の朗読,証拠書類の朗読などの訴訟手続を被害者到底事項を明らかにしない方法により行われる
3 証拠開示の際における被害者特定事項の秘匿の要請
弁護人に対して,被害者特定事項が被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる制度をいう
* 後藤貞人弁護士のコメント(弁護人の仕事はどこまでなのか)
「弁護人は被害者のことなど考えなくてよいに決まっています。弁護人が被害者のことを考えるのは,被害者に対する弁償などを誠意をもってきちんとしないと被疑者・被告人の刑が必要以上に重くなるからです。それは,プロフェッションとして考えなくてはならないことです。
しかしながら,弁護人が被害者のことを考えてはなりません。例えば,残忍な人殺しの被告人に対して,『死刑が相当や』というのか。そんなの,われわれの仕事ではない。それはもうはっきりしている」
「ただ,被害者の苦しみを理解しなくてはならないことは当たり前です。だから,私は死者が出ている事件では法廷に赤いネクタイはしていかない。被害者の遺族が傍聴席にいるとき,私は法廷では絶対に笑いません。それは,人としての常識です。また,被害者や遺族に手厚い救済措置が講じられるべきだとも思います。しかしながら,そのことと,刑事の弁護人にあたって被害者のことを考える必要はないということとは全然違うのです」
[1] (1)の①や②はこれまでも事実上,行われてきたことと考えられるので大きな影響力を持つものではない。また,たしかに,これまで被害者は論告・求刑をすることはできなかったわけであるが,従前も292条の2で意見の陳述をすることができた。これまでは,事実や法令の適用については被害者は意見を述べることができなかったわけであるが,事実上は,特定の刑罰に処すよう求めたりする意見を述べる被害者が見られたところであるし,他方,被害者参加制度の下における意見といっても検察官求刑とさして変わらないことに照らすと,「被害者が求刑ができる」と騒ぐほどのインパクトはないものと解されよう。結局,被害者参加制度で目新しいのは,被害者が証人尋問や被告人質問に関して尋問ないし質問をすることができるようになったという点であると考えられる。たしかに,証人尋問をすることや被告人質問をすることはこれまであり得なかったわけであるから,そこに被害者が入ってくるということになると,現実にあり得るのであればインパクトがあるといえよう。もっとも,現実の被害者が本当に証人尋問や被告人質問をするかは問題であり,現実には先述した意見陳述で,被害者が一方的に被害の状況について陳述して,特定の刑罰に処するように求めるということになると思われるが,これは,これまでも292条の2の問題として事実上,行われてきたことである。そうすると,被害者参加制度は,とりあえずは実務に大きな影響を与えない一方で,理論的には多数の問題点を抱える制度であると位置付けることができよう。新制度の弁論として意見を述べるという場合は,証拠に基づいて意見を述べる必要があるので,訴因から逸脱するような意見を述べることはできないのに対して,従前の292条の2については,必ずしもそれに限られないので,生の被害感情であるから,厳密に訴因との関係で厳密に考える必要はないと思われる