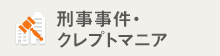伝聞法則
第24編 伝聞証拠の意義(寺崎315,白取365)
第1 伝聞法則
1 意義
伝聞証拠とは,公判廷外でなされた供述(原供述)を内容とする書面・証言で,原供述の内容たる事実を証明するものをいう。伝聞法則とは,固有の誤謬が介在する危険を勘案して,正確な事実の認定に資することを目的に,公判期日外における原供述を内容とする供述や原供述を記録した書面などの証拠能力を認めない準則をいう
2 刑訴法320条1項と伝聞法則
(1) 条文
「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし,又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」
* 供述とは,証人尋問によるテストを必要とするような供述証拠固有の問題を含む形で用いられる場合をいう
(2) Xによる放火の目撃者Aの供述を証拠とする方法
① Aを証人として公判廷で尋問する
② Aの供述を記載した書面を証拠として取り調べる
③ Aの供述を聞いたBを証人として公判廷で尋問する
*イメージ
![]() 公判廷外 公判廷
公判廷外 公判廷
① Aが放火事件の犯人について「Xが放火
するのを見たと供述する
|
|||
②
③ ![]()
B「Aが『Xが放火するのを
見た』と言っていました」
3 伝聞法則の根拠
(1) 問題の所在
伝聞法則によって証拠から排除されるべき伝聞証拠とは何か。伝聞証拠の定義は法律の文言から直接導かれるわけではない。そこで,伝聞証拠排除の法理の根拠に遡った目的論的な検討により,伝聞証拠の定義を明らかにする必要
(2) 伝聞法則が考慮している利益
⇒ 供述過程の危険(供述証拠一般にある危険)
人が自己の体験事実についてなす供述は,知覚⇒記憶⇒叙述という心理過程のいずれの段階にも誤りの入り込み事実認定が誤導される危険[1]
* 典型例との比較
| 表①[2] | 表②及び③[3] |
| Ⅰ 真実を述べる旨の宣誓と偽証罪による処罰の予告
Ⅱ 不利益を受ける相手方当事者による反対尋問によるチェック Ⅲ 裁判所による供述態度の観察 * 上記3つの方法で供述の信用性を吟味・確認・担保できる |
公判廷外でなされた原供述が書面によって,又は,それを知覚した証人(伝聞証人)の証言によって法廷に検出される場合には,表①の典型例の場合にあり得るⅠないしⅢの信用性のテストを経ることができない |
(4) 伝聞法則の理論的根拠
法が伝聞証拠を排除するのは,公判廷外でなされた供述が,それが記載した書面あるいはそれを知覚した証人の証言によって公判廷外に持ち込まれる場合に,原供述の信用性をテストできない。そうすると,そのような供述証拠を用いて,原供述の内容である事実を証明する証拠とすれば,その推論が誤導されるおそれがある。そこで,このような原供述を事実認定の基礎から除いて,事実認定の正確性を担保!
⇒ 原供述の内容たる事実を証明する証拠として,このような書面・証言(伝聞証拠)を用いることは許されないものとした
*「原供述の内容たる事実を証明する証拠として」という部分
この点は,供述証拠に一般的に潜む知覚,記憶,叙述の各過程に誤りが入り込むおそれがあることが問題となるのは,「ある事実の存在を要証事実として,体験者のする供述から,その事実の存在を論理的に推論する」という場合に限られている。すなわち,体験者のする供述から,供述の内容である事実の存在を推論しない場合には,知覚・記憶・叙述の各過程に誤りが入り込むことによって推論が誤導される危険は理論的にはないということになる
⇒ このような理論的基礎の下では,伝聞証拠排除の法理の射程距離というのは,「原供述の内容たる事実を証明する証拠として伝聞書面・伝聞証言を用いる場合」に限られる!!
(5) まとめ
ア 伝聞法則の位置づけ
伝聞法則は,刑事訴訟制度の目的である正確・的確な事実認定のための準則
⇒ 刑事被告人の基本的人権である証人審問権とは異なる制度であり,両者の訴訟活動に等しく係わる(争点180)
イ 伝聞法則の射程距離
公判廷外でなされた供述(原供述)を内容とする書面・証言が伝聞証拠として排除されるのは,原供述が証人尋問によるテストを必要とするような供述証拠固有の問題を含む形で用いられた場合
ウ 書類と伝聞供述
現行法の規定は,「公判期日における供述に代えて」書面を証拠とすることを原則として禁止している(320条1項)する一方で,伝聞供述に関する規定は,324条しかないことに照らすと,現行法の目的は,主に「捜査段階で作成される供述録取書その他の捜査書類が公判に無制約に流入することを防止するため
⇒ 裁判員裁判との関係で捜査書類が無制約に流入しない方がよい
⇒ 伝聞供述については,必ずしも,法の主たる関心が向けられておらず解釈に委ねられていると解する余地がある(法教306号65頁)
4 被告人の証人審問権(憲法37条2項)との関係(争点180)
(1) 両者は別個独立の無関係の事柄であるとの見解(判例)
∵① 憲法は法廷に出てきた証人に対する反対尋問を保障しているにすぎず,証人になり得る者に対する審問権まで保障したものではない
② 伝聞法則は,法廷に出てこない証人の供述証拠に関する証拠法上の準則
⇒ 判例の理解からすれば,伝聞法則と憲法37条2項は直接結びつかない![4]
![]() *判例からの証人審問権と伝聞法則との関係
*判例からの証人審問権と伝聞法則との関係
![]() 法廷に出てきた証人との関係 法廷に出てこない証人との関係
法廷に出てきた証人との関係 法廷に出てこない証人との関係
『被告人側の反対尋問権』 正確・的確な事実認定
憲法37条2項 刑訴法320条1項
(2) 通説
ア 問題の所在
証人審問権と伝聞法則は完全にイコールの制度ではなく,『被告人側の反対尋問権の保障』という部分でシンクロするにすぎない。そこで,両者の関係をどのように説明をするかが問題
イ 通説
伝聞法則とは,供述証拠に対する反対尋問権の保障を中核的理由とする制度
⇒ 通説の特徴は,「被告人側の反対尋問権の保障」というシンクロする部分があることから,憲法の証人審問権と伝聞法則を密接不可分のものと同視
∵① 証人という概念は,「供述証拠を供する者」と実質的に把握すべきであり,形式的に公判廷に出てきていない証人に対しても憲法37条2項が問題
② 被告人側の反対尋問権は,憲法37条2項の証人審問権の具体化であるのに対して,伝聞法則は,供述証拠に対する反対尋問権を保障する関係
ウ 通説の注意点
① 伝聞法則は,反対尋問の欠如のみによって説明される準則ではないので,例えば,伝聞法則を「反対尋問を経ていない供述証拠」と定義することは制度の趣旨及び条文の文言から離れすぎるという意味で適切ではない
② 証人審問権と伝聞法則との関係がどれほど密接であるかは,学説によってニュアンスの違いがある
*通説からの証人審問権と伝聞法則との関係
![]() 証人審問権
証人審問権
(反対尋問権を被告人側について憲法レベルで保障)
証人審問権と伝聞
被告人側の供述証拠に対する反対尋問権の保障 法則は密接な関係!
(この部分のみ証人審問権と伝聞法則がシンクロ)
伝聞法則(被告人及び検察官のいずれの
反対尋問にも配慮することを中核とするが,
事実認定の正確・的確も目的の一つ)[5]
(3) 新しい学説
⇒ 憲法の証人審問権条項に独自の積極的意味を見出すべき
ア 伝聞法則と共通する意味
証人審問権の伝聞法則と共通する供述証拠の信用性を吟味して正確・的確な事実認定に資するという機能
イ 伝聞法則と共通しない意味
証人を「審問」する機会を持つプロセス自体の権利性に着目する
⇒① 訴追側の原供述者喚問義務
② 公判期日外供述許容要件としての個別的特信情況
* 最判平成7年6月20日刑集49巻6号741頁
この判例は,憲法の「証人審問権」に言及しつつ,伝聞証拠である検面調書の証拠能力に制約をかけている。これは,被告人の基本的人権である証人の審問(証人と対決し供述内容の信用性を吟味・段階する反対尋問を行うこと)が実効不能となった事由によっては,憲法37条2項を根拠に伝聞証拠の証拠能力を否定する可能性を示したものと考える余地がある
第2 伝聞と非伝聞
1 伝聞概念の相対性
(1) 伝聞法則の相対性
伝聞法則の適用があるかどうかは,立証趣旨ないし要証事実との関係で決定される。したがって,同一の書面及び供述が立証趣旨のいかんによって,伝聞証拠となったりならなかったりする
⇒ 書面ないし又聞きされた「供述内容の真実性」を証明する証拠として用いる場合には適用はある。これに対して,書面の存在自体や書面に記載されているような内容の供述の存在自体,及び又聞きされたような内容の供述の存在自体を要証事実とする場合は適用なし(検察109)
(2) 具体例①
「Aが,『・・・』と言っているのを聞いた」という証人Bの公判証言
ア 「Aが一定の内容の発言を行ったこと自体」を要証事実とする場合
Aの供述内容の正確性は問題でなく,Aが『・・・』と供述したこと自体は,証人Bの体験事実であり,Bに対する証人尋問で正確性の吟味可能
⇒ 『・・・』という言葉は,供述証拠固有問題はなく,伝聞法則の適用なし
イ 「Aが発言した内容通りの事実が存在したこと」を要証事実とする場合
Aの供述内容から事実を推論することになるので,知覚・記憶・叙述に誤謬があることで推論が誤導されるおそれがある。そこで,Aの供述の正確性の吟味が必要となるので,伝聞法則の適用があり原則Bの証言は排除される
(3) 具体例②
「Aが,『Xは放火犯人だ』というのを聞いた」という証人Bの証言
ア 「人の名誉を毀損した」(刑法230条1項)ことを立証するために,「Aが,『Xは放火犯人』と発言したこと」を要証事実とする場合
要証事実との関係では,Aの発言内容が真実であるかは問題ではなく,要証事実はA発言の存在自体であり,犯行目撃者であるBがそのようなA発言を聞いたとおりに証言しているかが問題でありBに対する証人尋問で吟味できる
イ Xが「放火し」(刑法108条)たことを立証するために,「Xと放火犯人との同一性」を要証事実とする場合
まさに,Aについて供述証拠固有の問題があるので,伝聞法則の適用あり
2 言葉の非供述的用法
(1) 供述がなされたこと自体が犯罪事実を構成する場合
⇒ 具体例②参照
(2) 証人の自己矛盾供述による信用性の弾劾
ア 事例
Xの公判期日外の発言をそれと矛盾するXの公判証言の信用性を弾劾するために用いる場合
イ 要証事実
検察官は,「Xの証人としての信用性が低い」という補助事実を立証するために,「Xが公判廷外で公判証言と矛盾する発言をしていること」
ウ 検討
まず,伝聞法則の適用があるのは厳格な証明を要する事実(罪となるべき事実)の立証に限られているのが原則であるが,補助事実については伝聞法則の適用はいらないのではないかとの疑問も生じる。この点について,最決平成18年11月7日は,「刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨」とする。そうだとすれば,補助事実を要証事実とする場合であっても,自己矛盾供述については,伝聞法則の適用が論理的にはあり得るということになる。
もっとも,この場合,Xが公判廷外で矛盾する発言自体が問題となっているので,その発言の内容から事実を推認するわけではないので,供述証拠に固有の問題は存在しない
(3) 供述の受け手の反応を推論する場合(言葉を発言内容の真実性とは関係のない事実を推認する情況証拠として用いる場合)
ア 典型例
発言や書面がその聞き手・読者に与えた効果・影響(犯行の動機・目的・何らの認識を生じさせたこと)を立証しようとする場合は,要証事実は発言内容の真実性ではない。例えば,傷害事件で殴られたAが,加害者Bに対して,「お前はばかだ」という言葉について,「BがAに対して,傷害の動機を有していたこと」を要証事実とする場合(Bが「ばかであること」を要証事実とするわけではないので,供述内容の真実性は問題とならない)
* 一般的に動機は,犯意を明確にして,ひいては罪となるべき事実自体も明確にする機能がある(検察68)
イ 具体例
(ア) 事例
Xは,Yから客観的に饗応行為を受けたが,それが饗応行為にあたることの認識,すなわち,故意がなかったと反論した。これに対して,検察官は,「XがYについて近い将来の選挙において,Yが立候補することを認識していたこと」を要証事実として,その旨が記載した新聞紙の取調べを請求
(イ) 検討
たしかに,新聞の記事は供述証拠としての側面もあるため,その記事内容の真実性が要証事実となる場合は,伝聞法則の適用がある。しかし,本件で要証事実とされているのは,「近く国会が解散されること」や「Yが立候補すること」ではなく,その記事を見たXの認識が要証事実とされている。これは,記事内容の真実性とは関係のない事実を推認するものであるから,非伝聞である(大阪高判昭和30年7月15日高刑裁特2巻15号782頁)
(4) 供述内容と無関係な精神状態を推論する場合
ア 事例
Xに「責任能力があったこと」が争点となっている場合に,「私は神である」というXの発言について,「Xの精神が異常であったこと」を要証事実
イ 検討
供述内容の真偽とは関わりなく,供述者の精神状態を推論するので非伝聞
(5) 事実と一致する供述から事実の認識を推論する場合
ア 事例
Xが交通事故について自動車運転過失致傷罪(211条2項)の過失の有無,具体的には,検察官が「ブレーキが故障している自動車を運転しない」という客観的注意義務があることを主張し,その客観的注意義務発生の前提となる予見可能性について,「Xが運転前にブレーキの不具合に気付いていたこと」を要証事実として,Xが運転前に述べた「この車はブレーキの具合がよくない」という発言の伝聞証言
イ 検討
この場合,自動車のブレーキが故障していたという事実を要証事実とするわけではなく,あくまで,Xの認識を問題にしているにすぎないので,供述内容の真実性が問題となっているわけではないので非伝聞
3 現在の心理状態の供述
(1) 問題の所在
ア 事例
Yが何者かに殺害された殺人事件について,Xが殺人犯人として起訴され,その犯人性が争点となっている場合について,検察官が,「Yが発言の時点において,Xに対して恐怖感を抱いていたという事実」を要証事実として,証人Wを取調請求をして,Wは,「Yさんは,『Xは恐ろしい。何をするかわからんから怖い』と言っていました」と証言した
イ 検討
(ア) 「供述内容と無関係な精神状態を推論する場合」にあたらないか
∴ あたらない
∵ 発言の内容をなしている感情・心理状態の真実性が要証事実とされる
⇒ 伝聞証拠
(イ) 典型的な伝聞証拠と何が違うか
| 典型的な伝聞証拠と異なる点 | 伝聞証拠と同じ点 |
| 発言時点におけるYの感情・心理状態の表明,表出であると見る限り,過去の事象の知覚とその記憶保持の要素が欠けている | Aが発言の際に用いた言葉の正確性,及びAが本心から自己の心理・感情を正直に述べていたかどうか(誠実性)について誤謬の介在する危険あり |
*イメージ
⇒ 知覚・記憶の過程を遡及しないでも要証事実を推認できる!!
![]() 裁判官
裁判官

 |
精神状態の供述○
![]() 通常の場合
通常の場合
 |
通常の場合
 |
通常の場合
(2) 伝聞説と非伝聞説の争い
伝聞法則は,正確な事実の認定に資することで真実発見に資する証拠法則
ア 利益考量の視点
公判期日における証人尋問で供述内容の真実性を吟味する要請の程度と,当該公判期日外供述の事実認定にとっての重要性・証拠としての価値の比較
⇒ 実質的に判断されるべき問題!
イ 白取370の利益考量
叙述における誤りの危険とそれに対する吟味の必要性のウェイトを重く見る
「知覚―記憶というプロセスはたどらないものの,Aがこのような発言を発するにいたる感情の経緯を確認し,A本人の真意を確かめるため尋問する必要はある。人はこのような言葉を,冗談として言うこともあるからである」
⇒ 伝聞証拠と解する見解
ウ 法教305号82頁,争点184の利益考量
① 反対尋問による吟味が「強く」要請されるのは,知覚と記憶
② 叙述の真摯性は,非伝聞の典型例である「供述内容と無関係な精神状態を推論する場合」で,例えば,精神異常を推認する場合にも問題となる。そうだとすれば,叙述の真摯性は,反対尋問などによる吟味が「不可欠」とまで言えず,一般的な関連性の問題で処理すれば足りる
③ 叙述の真摯性は,発言に接した証人を尋問し,発言がなされた際の状況を問いただすことによって確認できる場合が多い
④ ある時点における人の心理状態については,それが他人から見えない以上,当人の当時の発言が最良証拠
⇒ 非伝聞とすべき
(3) 非伝聞説と伝聞例外説の争い
ア 伝聞例外説の批判の論拠
① 伝聞証拠の定義からすれば,供述内容の真実性が問題となっているのに,なぜ,伝聞証拠とならないのか
② 母法であるアメリカでは,伝聞証拠にあたるとしたうえで伝聞例外で整理
③ 非伝聞説は,「供述内容と無関係な精神状態を推論する場合」でも叙述の真摯性は問題とされていないことを論拠とするが,そもそも,その場合は,発言内容の真偽に関わりなく推論するのに対して,精神状態の供述は,発言内容の真実性が問題となる局面であるから,非伝聞とパラレルとは暴論である
④ 典型的供述過程の一部が欠落することを非伝聞とする理由とすれば,感情を記載した供述書は常に非伝聞となるのか
イ 伝聞例外説の主張
○ 精神状態の供述は,「伝聞証拠」だが,伝聞例外を柔軟に認めていくべき!
ウ 明文なき伝聞例外を認める論拠
① 現行法は,書証の規制を主たる目標としているから,伝聞の口頭供述は解釈に委ねられている(書面は要件を緩めないのが原則であるが,精神状態の供述は典型的供述代用書面と違うので例外的に要件を緩和してもよい)
② 伝聞供述は,供述の性質に応じて例外要件を認めることができる
③ 324条2項・321条1項3号のうち,「供述不能」の要件がデリートされる
⇒ 供述時点における信用性の情況的保障が認められる場合には,「伝聞例外」として証拠能力を認めるべき[6]
*学説の整理
| 非伝聞説 | 伝聞例外説 | 白取説 | |
| 心理状態を述べる発言を内容とする公判供述 | 非伝聞
⇒叙述の真摯性が要件 ∴証拠能力あり |
伝聞例外
⇒信用性の情況的保障が要件 ∴証拠能力あり |
伝聞例外
⇒324条2項・321条1項3号全部 ∴証拠能力なし |
| 捜査段階で作成された供述調書や供述書[7] | 同上
∴証拠能力あり |
伝聞例外
⇒321条1項3号全部 ∴証拠能力なし |
伝聞例外
⇒321条1項3号全部 ∴証拠能力なし |
4 最判昭和30年12月9日刑集9巻13号2699頁(寺崎322,白取371)
(1) 事実関係
Aは,何者かによって強姦致死の被害に遭い,Xが犯人であるとして起訴され,公判ではXと犯人との同一性が最大の争点となっていた。検察官は,「XがAと情を通じたいとの野心を持っていたこと」を要証事実として,第三者Wの取調請求をして,Wは,「Aが,Xのことを『あの人はすかんわ,いやらしいことばかりするんだ』と言っていました」と供述した
(2) 検討[8]
ア 被告人の犯人性を推論する場合
伝聞証拠といえる
イ 同意の存否を推論する場合
非伝聞(精神状態の供述)
⇒ Aの供述の誠実性や適切さを吟味すれば足りる
* このような供述の誠実性や言葉の適切さは,Wへの反対尋問で吟味可能
5 共謀成立過程の供述
(1) 白鳥事件(最判昭和38年10月17日刑集17巻10号1795頁)
ア 証拠
① Aの検面調書
「Xは,電産社宅で行われた幹部教育の席上,『白鳥はもう殺してもいい奴だな』と言いました」
*立証趣旨:Xがそのような内容の発言をしたこと自体
* 現在ではこのような証拠関係のものは少ないと解される。最近は科学的捜査が発達しているので別の証拠もあると思われる。裁判官もこう言っていたというだけでは,もう少し何かあるはずだろうと述べる
② Bの公判供述
「Xは,『白鳥に対する攻撃は,拳銃をもって行うが,相手が警察官であるだけに慎重に計画をし,まず白鳥の行動を出勤退庁の時間とか乗り物だとかを調査し慎重に計画を立てチャンスを狙う』と言っていました」と供述
*立証趣旨:Xがそのような内容の発言をしたこと自体
③ Cの公判供述
「Xは,『共産党を名乗って,堂々と白鳥を襲撃しようか』と言っていました」と供述
*立証趣旨:Xがそのような内容の発言をしたこと自体
* この事案では,被告人Xは完全黙秘を貫き,実行正犯やその他の共謀共同正犯はすべて逃亡中であったために,第三者によるXの発言内容についての伝聞供述などが証拠関係において重要な地位を占めているという事情がある
イ 考え方
(ア) 共謀共同正犯のうち,主観説による場合
検察官の要証事実は,「犯意の合致があったこと」ということになる。そうすると,上記の各証拠からは,「Xが白鳥刑事を殺害その他危害を加える何らかの犯意を有していたこと」が要証事実となる[9]。これは,Xの精神状態の供述といえるので,非伝聞となる
(イ) 共謀共同正犯のうち,客観説による場合
共同意思主体説を前提とすると,意思の連絡という側面が重視され,「謀議に参加したこと」が共謀共同正犯の客観的要件となる。そこで,検察官の要証事実は,「謀議に参加したこと」に該当する事実である「当該発言をしたこと自体」ということになる。この点は,重要な役割説を前提とする客観説であっても,そのような発言をしていることから,重要な役割を果たしているということが基礎付けられる。したがって,重要な役割説を前提とする客観説でも,検察官の要証事実は,「当該発言をしたこと自体」になると考えられる。そうすると,これは,「謀議に参加したこと」という客観的な謀議行為に該当する「発言したこと自体」が犯行の内容として要証事実とされていることになるので,発言の非供述的使用であるから,伝聞ではないということになる[10]
⇒ 共謀共同正犯で客観説を採る者は,再伝聞の論点で伝聞過程が一つなくなることもあるので特に注意を要する
(ウ) 判例に対する評価
判例は,発言自体を要証事実ととらえているが,この点については,疑問の余地がある(争点184[11])。もっとも,ここでのポイントは,共謀共同正犯理論の理解の仕方によって理解に差が生じているにすぎず,伝聞法則の適用がないという結論自体は同じである。この点,客観説を前提とすると,上記発言は,「謀議に参加したこと」に該当する行為にすぎなくなるので,伝聞法則を適用する余地はないということになるが,他方,精神状態の供述と解する場合については,白取説を採れば伝聞法則の適用があり,伝聞例外説を採れば,少なくともAの検面調書について証拠能力を認めるのは疑問となると思われる。
(エ) 調査官解説の指摘
Ⅰ 証拠
Dの公判供述「Eが『白鳥刑事を射殺したのは,自分である』と言っていました」
*立証趣旨:Eの発言自体
*最高裁の要証事実:EがSを射殺したこと
Ⅱ 検討
判例は,「Eが白鳥刑事を射殺したこと」は,その発言内容の真実性が問題となるので伝聞証拠であるとして,これを「発言自体」が要証事実とした原審の判断を誤りであると指摘している。この点,原審は,「発言自体」を要証事実とする限りは,DがE発言を直接知覚しているので伝聞証拠ではない。そして,「Eがこのような発言をしたこと」自体から,Sが白鳥刑事を殺したという主要事実を推認しようという論理である。調査官解説は,このような立証方法は,「要するに,発言したという事実からその発言内容の真実性を推認することを許すことにほかならず,伝聞法則を採用している我が刑訴の禁止するところ」と指摘している。つまり,伝聞法則の適用を潜脱する意図で不自然な要証事実を設定することは許されない趣旨をいうものと解される。内容の真実性が絶対に問題になるからである
* 実務ではこのようなものが尋問中にさらっと出てしまうことが多い。この場合は,弁護人は証拠能力がないということで異議を述べるべきである。問題は,弁護人も時機を失して異議を述べないことも少なくない。異議を述べなかったので,326条の黙示の同意があったと扱われることが多い。裁判長としてはどのように対処するべきかが問題となるが,同意をするかどうかの意見を求める方が妥当であると思われる。特に争点となっている重要な事項となることが多いと思われる。止めて,「弁護人,今の証言でよろしいですか」と聴くことになると思われるが,気付かないことが多いが当事者が注意すべきであろう。
6 犯行計画メモ(争点185,法教306号65頁)
(1) 設例1
ア 事例
被告人Xは,単独で銀行強盗を実行した旨の事実で起訴されたが,身に覚えがないと犯人性を争っている。被告人の自宅から押収された日記帳があり,強盗事件発生の数日前の日記に,実行された銀行強盗の経過に附合する詳細な犯行計画・逃走経路が記載されていた場合,この日記の記載内容を証拠として用いることができるか
イ 要証事実の検討
(ア) メモの記載内容と客観事実との一致
「Xの自宅から発見されたメモの記載内容と客観的に発生した銀行強盗事件の内容が一致している事実」を要証事実として,そのメモの記載者,すなわち,Xの犯行であることを推認する場合[12]
⇒ 記載内容の非供述的使用であると見ることができる
* 日記の記載の証拠物としての使用の側面
(イ) 犯行の計画性・意図・動機の証明に用いる場合[13]
記載当時の心理状態・意図・計画を述べる言葉であるから,非伝聞
* 伝聞例外説(少数説)もある
⇒ 322条の可能性を考えないとすると,まず,知覚・記憶という過程は欠落するものの,メモ内容の真実性が前提となるので,伝聞証拠になる。もっとも,書面であるが,典型的供述代用書面との距離を問題にして,記載当時の供述者の心理・意図・計画を表出したものであるから,信用性の情況的保障が認められれば伝聞例外として証拠能力を認める見解
(2) 設例2
ア 事例
銀行強盗の日時,場所,役割分担(X,Y,Zの3名と思われる人物が符合で表示され,外の見張りと逃走車両準備役,店内で猟銃を構えて脅す役,金を奪い取る役との記載がある),逃走経路などが詳細に記載された犯行計画メモが発見・押収されているとする。このメモの作成者は誰かは不明である。このメモの記載を証拠として用いることはできるか
イ 要証事実①
Xが犯行に加担したことを否認している場合において,犯行計画メモの存在と立証趣旨として,メモに記載された事項と実際に実行された犯行態様が一致する旨を証明することにより,メモ中にXと思われる人物の役割分担の記載があることから,Xの犯行への関与を推認するという場合[14]
⇒ メモ記載と犯行態様の一致(他のメモ記載事実が実現されているので,それ以外の部分も真実であろうという推論から,Xの犯人性を推認)という事柄を要証事実とした非供述的使用であるので,証拠物としての使用となる
ウ 要証事実②
メモ作成者がX,Y,Zとは,別のAであり,Aが3名から聞かされた犯行計画の内容を記載したものであることが判明したとする。この場合に,メモを共犯者3名による共謀の事実を証明する証拠として用いようとする場合
⇒ 典型的な伝聞証拠となる。記載された犯行計画の内容の真実性を証明する場合に用いる場合であって,かつ,メモ作成者Aの知覚・記憶・叙述のすべてについてその正確性が問題となり得る「供述」となる[15]
(3) 設例3
ア 事例
共謀者のひとりであるXが3名で犯行を共謀する過程でメモを作成し,YとZもその内容を確認している場合に,その存在と記載内容を共謀の事実の証明に用いるとき
イ 要証事実
犯行計画メモが共犯者間で回覧・確認されるなどして,まさに謀議の形成手段として用いられたということが示されたならば(例えば,書面上にX,Y,Z全員が回覧・確認したことを示す署名がある場合),要証事実は,「共謀者相互間の意思連絡・謀議を構成する犯罪事実そのもの」と把握(客観説が前提)
⇒ 共謀関与者間の口頭による発言自体が意思連絡・謀議行為そのものと見ることができる(要するに,「人の名誉を毀損した」(刑法230条1項)ことを立証するために,「Aが,『Xは放火犯人』と発言したこと」を要証事実とする場合と同じということである)
⇒ 非伝聞[16]
(4) 設例4
ア 事例
共謀者のひとりであるXが,YとZと3者で合意した謀議の結果を後日記載したメモである場合
イ 要証事実①
X作成のメモを,その記載内容である謀議の存在・事前共謀の証明に用いる場合(主観説が前提)
⇒ Xが共謀内容として知覚した事項を記憶し叙述した書面をその内容の真実性の証明に用いる典型的な伝聞証拠
ウ 要証事実②
謀議に関与しその後犯行計画メモを作成したXが,「メモ作成当時(×謀議当時)その記載内容と同一の計画・意図を有していたという事実」が要証事実
⇒ 精神状態の供述として非伝聞
* ただ,この使い方の場合は,基本的にXが共謀の事実を否認し,Xの共謀の有無が争点となっている場合が典型的であろう
* 法教306号66頁は,「さらに,Xの精神状態から他の共謀関与者の意図や共謀成立の事実を推認することが可能な場合があり得る」とする[17]
(5) 実務家の見解
ア 山室説
山室説は,共同意思主体説に立ち,作成者自身の意図と他の共謀関与者の意図という区別をせず,共謀加担者全員の1個の意図・計画を表示したものととらえ,非伝聞とする見解
「本件メモについて,Xの意図・計画を表すという面と,その余の共謀加担者であるYの意図・計画を表すという面とに分けて考えているからであるが,このような区別自体がおかしいのではないかと思われる。すなわち,本件メモは,Xの意図とかYの意図というように区別することのできない共謀加担者全員の1個の意図を表したもの,換言すれば,メモ作成者自身の意図と一体をなす共謀加担者全員の1個の意図・計画を表したほうが実態に即している」としたうえで,例えば,Xのメモで,Yの意図を要証事実とする場合であっても,「本件メモは非伝聞になる」と主張する。山室説は,共同意思主体説を前提にする限り,正解であるが,個人責任の原則を蹂躙するものであり,そもそも,共謀共同正犯理論の段階で相当性を欠いている[18]
イ 一般的な裁判官の見解(三好)
共謀参加者全員が謀議の過程で共通の意図を形成し,そのうちのXが形成された計画・意図の内容を記載したという場合であることを別途,他の証拠によって立証することができる場合,そのメモは,作成者との関係でその意図・計画の表明であることから,共謀参加者全員が共通の意図を形成したという事実を介することにより,他の関与者の意図や共謀成立の事実を推認できる[19]
*三好説のイメージ
Yの犯罪についての意図
 |
Xの犯罪についての意図 共謀関与者全員が共通の犯罪意思形成
X作成の犯行計画メモ X,Y,Zの謀議会議の議事録
7 判例の検討
(1) 大阪高判昭和47年3月16日判時1046号146頁
ア 事例
Xがほか10数人と共謀の上,被害者を襲撃して傷害を負わせたといういわゆる内ゲバ事件において,事件後,過激派の事務所から押収された作成者不詳のメモが扱われた事案。このメモには,犯行現場付近の建造物や周辺地域との地理的関係などを示した図面,犯行手順や犯行後の逃走方法,犯行現場付近から他へ連絡するために必要な事項が記載されていた[20]
イ 判旨
伝聞証拠か否かは,要証事実の如何によって異なってくるものであるところ,本件メモ紙の要証事実は,その記載に相応する事前共謀の存在及び被告人の本件への関与の事実と解されるから,本件メモ紙は,要証事実との関連から伝聞証拠というべきであるが,およそ供述とは心理的過程を経た特定の事項に関する言語的表現であり,それには表意者の知覚,記憶の心理的過程を経た過去の体験的事実の場合と,右のような知覚,記憶の過程を伴わない,表現,叙述のみが問題となるところの,表意者の表現時における精神的状態に関する供述(計画意図,動機等)の場合とがあって,本件の事前共謀に関するメモは,その時点における本件犯行に関する計画という形で有していた一定の意図を具体化した精神的状態に関する供述と考えられる。
精神的状態に関する供述については,その伝聞証拠としての正確性のテストとして,その性質上必ずしも反対尋問の方法による必要はなく,その表現,叙述に真摯性が認められる限り,伝聞法則の適用例外として,その証拠能力を認めるのが相当である。そして,本件記載の真摯性は十分認められるから,本件メモ紙は,伝聞法則の適用を受けない
ウ 検討
(ア) 前提となる事実
判決では,「メモ紙は本件犯行の事前共謀にあたってその内容を明らかにするために,共謀に参加した者のうち,右メモ紙に記載した者が複数の人数でなされる計画の内容を明らかにし,具体化するために記載された」という事実が認定されている。
(イ) 要証事実
まず,考えられるのが,本判決が指摘する「事前共謀の存在の事実」が要証事実となる場合である。これは,突き詰めると,「あらかじめ,過激派のアジトにおいて,Xと他の10数人との間で,被害者を襲撃することを中核とする犯意の合致があったこと」になると考えられる。しかしながら,そうすると,本件の場合はメモを作成した人物が不詳である。例えば,共謀者であるYがメモを記載したと仮定すれば,先述のとおり,「Yの精神状態の供述」とはいえても,そこから,Xの精神状態を推認することには飛躍がある[21]。したがって,この事案を上記の設例4のケースと同様と考えると,「作成者Yの作成時の心理状態・意図の記載としてそれが証明されるだけでは,事前共謀の存在を直ちに証明することはできない」(法教306号66頁)と解される。
もっとも,仮に,「共謀計画の表出」ではなく,設例3のように,これが「謀議の過程において共謀者間で回覧・確認されつつ作成されたもの」という事実が他の証拠から認定することができれば,このメモは,謀議の形成手段・意思連絡として,そのメモの存在と記載内容自体を要証事実とする非伝聞ととらえることもできる。
なお,本件の場合は,メモの記載と客観的な犯罪の実行が合致しているのであるから,その合致している事実を要証事実とすることが考えられる。そして,このメモが過激派の事務所から発見されたものである以上,過激派のメンバーによって犯行が行われたという事実を推認することができると考えられる
(2) 東京高判昭和58年1月27日判時1097号146頁
ア 事例
集団による計画的な恐喝事件において,犯行前に行われた会議において被害者に対する要求内容として謝罪と慰謝料の支払いが確認されたことを会議出席者Kから聞いた共犯者が書き留めた,「確認点―謝罪と慰謝料」とのメモの証拠能力が問われた事案
イ 判旨
判決は,作成者との関係で,メモが心理状態の記載として非伝聞となる旨を述べたうえ,「この点は個人の単独犯行についてはもとより,数人共謀の共犯事案についても,その共謀に関する犯行計画を記載したメモについては同様に考えることができる」とした。
そして,「この場合においては,それが最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致するところとして確認されたものであることが前提とならなければならない」と述べている(なお,問題のメモについては,上記の確認がなされていなくても,弁護人の異議はない旨の証拠意見により,反対尋問権が放棄されたがゆえに証拠能力を有すると結論付けられている)。
ウ 検討
(ア) 要証事実①
まず,設例3のように,メモの存在と記載内容自体を要証事実とすることが考えられる。しかしながら,本件では,メモを手段として共謀者間で新たな意思連絡や確認が行われた事案ではない。したがって,上記のように要証事実をとらえて,非伝聞と考えることはできないものと考えられる。
(イ) 要証事実②
次に,設例2のように,「会議における事前共謀の事実」を要証事実と見る場合,典型的な伝聞証拠ということになる。
(ウ) 要証事実③
もし以上のようなものでないとすれば,本件事案は,設例4の場合と同様に,メモ作成者について心理状態の記載として証拠能力が認められると考えたうえで,共謀関与者全員が,メモ作成者と共通の意図を有していたという事実が別途認められ前提とされるのであれば,これを介して,共謀の存在を推認できる場合であったと思われる
8 借用書
(1) 伝聞証拠にあたるか
借用書をその記載内容の真実性,すなわち,記載された額の金銭の貸借又は授受の事実を証明するための証拠として用いる場合
⇒ 作成者の「供述」にあたり伝聞証拠
(2) 証拠能力を付与するための思考
ア 伝聞例外の検討
⇒ 323条2号又は3号で証拠能力は認められないか
∴ 321条1項3号によるべき
∵ 個別的に作成される借用書は,2号書面にはあたらない。また,3号との関係でも,2号と同程度に作成過程と内容の正確性・真実性について信頼性の高い書面であることを要するという支配的見解に立てば3号にもあたらず
イ 要証事実を設定を変える方法
(ア) 立証趣旨=借用書の書面の存在?
⇒ 形式的には,書面としての存在が要証事実となるが,それを間接事実として記載内容の真実性,すなわち金銭貸借や授受の事実を推認するというのであれば,伝聞法則を潜脱することになり許されない[22]
(イ) 潜脱的立証にならない場合
⇒ 証拠物としての側面を有する固有の証拠価値を利用する!!
* 例えば,Xが借用書を作成したと法廷で証言し,「自分が借金する際に作成し交付した借用書はその書面である」と供述した場合
⇒ 酒巻は,当該借用書の存在を要証事実と考えて,これを証拠として採用し,Xの証言と併せて,Xが書面に記載された金額の貸借を受けたとの事実を認定する場合は伝聞法則の潜脱にあたらないという
∵ 書面の存在自体から記載内容の真実性を推認しているのではなく,その書面の存在自体のもっている証拠物としての価値と公判供述を併せて資料としているから伝聞法則の潜脱にはあたらない
* 何を真の要証事実と理解し,そのうえで書面の存在自体からいかなる推認を行うかが議論の本質
⇒ 書面の存在自体から記載内容の真実性を推認すると違法が前提!
9 レシート
(1) 伝聞証拠にあたるか
ア レジスターの場合
∴ あたる
∵ 商品名,販売価格などについて定員の入力印字に頼っているレジスターの場合は,その点に対する店員の知覚・記憶・叙述の過程がある
イ ポス・システムの場合
● 非供述証拠とする見解(山室)
∵ ポスでは印字発行されるレシートの作成は,ほとんどが機械的過程であり,人の判断が介在する余地は極めて乏しい
○ 供述証拠とする見解(酒巻)
∵ バーコードからの読み取り捜査を行う部分と客の交付した金銭を受領してその預かり金額を打ち込む部分に人の介在があり,そこに過誤に危険が皆無ではないとみれば,伝聞法則の適用はあるが,323条2号又は3号で許容するという筋道も有り得る
(2) 伝聞例外の検討
323条2号か3号
第25編 伝聞例外
第1 総則
1 伝聞証拠排除の趣旨
① 公判廷で宣誓をして偽証罪の制裁があること
② 供述態度・表情などを観察する裁判官の面前での供述
③ 知覚,記憶,叙述の過程で生じ得る誤りの反対尋問による吟味
* ①から③が確保されて供述の信用性は類型的に担保される
2 伝聞例外の要件
① 証拠として取り調べる必要性があること
② 特信情況(公判廷における供述に代わるほど信用できる外部的な情況)
* 証拠の必要性も特信情況もともに強弱があるので,2つの要素の強弱の組み合わせで伝聞例外の許容性が決まる
第2 被告人以外の者の供述代用書面―一般的なもの
1 供述書と供述録取書
ア 321条1項の書面
(ア) 供述書
供述書とは,供述者自ら供述を記載して作成した書面をいう
例えば,被害届,上申書,答申書,捜査報告書,日記,手紙,メモなど
* 筆跡や供述内容などで作成者を特定し得るので,供述者の署名押印不要
(イ) 供述録取書
供述録取書とは,第三者が供述者が聞いた供述内容を記録した書面をいう
例えば,証人尋問調書,供述調書
イ 供述録取書と署名・押印
(ア) 論理的帰結
原供述者の供述を録取者が聞き取って記録し書面で法廷に報告するものであるから,二重の伝聞
(イ) 署名・押印の意味
録取の正確性を保障する趣旨で原供述者の署名又は押印があれば,録取者が介在することによる伝聞性は解消する[23]
2 基本類型―3号書面
(1) 要件
① 供述者が死亡,精神もしくは身体の故障,所在不明又は国外にいるため公判準備または公判期日において供述することができない(供述不能)
② その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができない(証拠の不可欠性)
③ その供述が特に信用すべき情況のもとにされた(特信性)
(2) 制度趣旨
国家機関であり,かつ,法律家である裁判官又は検察官が作成したものではないため,厳格な要件の下に証拠能力が認められる(検察110)
(3) 供述不能の意義
ア 限定列挙か例示か(1号,2号にも共通)
(ア) 判例
各号で掲げられた死亡等の事由は例示であり,それに準じる事由で供述の再現が不能となる場合あり
(イ) 供述不能にあたる場合
Ⅰ 証人が証言拒絶権を行使した場合
Ⅱ 記憶喪失の場合(最決昭和29年7月29日刑集8巻7号1217頁)
イ 当てはめ
(ア) 伝聞証拠を許容する必要が認められる程度の供述不能である必要
∵ 供述不能事由は例外的に伝聞証拠を用いる必要性を基礎付けるものであるから,死亡以外の要件は一定程度継続している必要がある。また,一時的な心身の故障や所在不明は含まれず,期日を変更する方法により供述者の喚問をできる限り図らなければならない
(イ) 供述不能に至った経緯が不当ではないこと[24]
* 判例(東京高判昭和63年11月10日判時1324号144頁)
「当該の供述拒否が立証者側の証人との通謀或いは承認に対する教唆などにより作為的に行われたことを疑わせる事情がない以上,証拠能力を付与するに妨げないというべきである・・・所論がいうような被告人に対する敵意によるものと窺われる状況はなく,また,検察官側が作為的に同人に宣誓等を拒否させたものとも認められない」
* 判例(最判平成7年6月20日刑集49巻6号741頁)
手続的正義の観点からの公正さ
(4) 不可欠性と特信性
ア 不可欠性
不可欠性の要件とは,他の適法な証拠では代替できない場合でなければならないことをいう。
イ 特信性
(ア) 定義
3号書面の特信性とは,絶対的特信情況,すなわち,その供述の特信情況は絶対的な判断が求められる
(イ) 当てはめ
特信情況のもとで供述がなされ,供述内容の信用性を担保する外部的な状況の存在が必要[25]
3 応用類型―1号(裁判官面前調書・裁面調書)
(1) 視点
被告人以外の者の供述代用書面のうち供述録取書については,録取者が誰であるかということについて信用性に差が生じ得る。そこで,録取者による信用性の担保があることを考慮し,基本となる3号よりも緩和した要件で伝聞例外を認めるものが1号と2号である
(2) 1号書面の例
① 検察官請求による証人尋問(刑訴法226条以下)の調書
② 被告人の請求による証拠保全のための証人尋問(刑訴法179条)の調書
③ 他事件の公判調書
(3) 要件
⇒ 必要性の要件しかない!
① 供述不能
①’前の供述と異なった供述をした場合
(4) 制度趣旨
裁判官に対する供述=高度の信用性の情況的保障が存在
Ⅰ 公平中立な裁判官
Ⅱ 原則として宣誓(偽証罪の制裁)
Ⅲ 当事者が立ち会った場合は反対尋問もできる
Ⅳ 裁判官が公平な立場から信用性のチェック
* 伝聞証拠排除の趣旨とよく比較すること
* 321条2項前段の書面
当該事件の公判期日・公判準備における供述を録取した書面は,321条2項前段によるので,321条1項1号による必要はない
4 応用類型―2号書面(検察官面前調書・検面調書)
(1) 前段
ア 要件
供述不能のみ
イ 2号前段の合憲性
(ア) 問題の所在
2号では,3号よりも要件が緩和されているのは,検察官が法律家であるうえに,法の正当な適用を請求するという客観義務を負う立場にあるからである。しかし,検察官は被告人と対立する当事者の一方であるので,裁判官と同じ第三者立場にあるわけではなく,信用性の担保が劣っている。そこで,前段において,供述不能という要件のみで伝聞証拠を許容するのは問題ではないか
(イ) 学説の批判[26]
① 違憲とする見解[27]
② 合憲限定解釈を施す見解
Ⅰ 「信用性の情況」を解釈上補えば合憲(平野)
ウ 特信性を要求する下級審裁判例
大阪高判昭和42年9月28日高刑集20巻5号611頁
大阪高判昭和52年3月9日判時869号111頁
(2) 後段
ア 要件
① 公判準備もしくは公判期日において前の供述と相反するか実質的に異なった供述(相反性)
* 相反性
相反性とは,要証事実について異なる認定をもたらす供述をいう
* 従来は相反性については検察官が対照表を示して文書で請求し,次回期日までに検討あるいは30分間休廷して判断するということになる。この点,今後は対照表を作るヒマがない裁判員裁判においては検察官は対照表を作るヒマはないので検察官は今後はこの点がネックになる。そこで,弁護人の側としては,「いやいや変わっていない」,「もともとその程度の証人であったんだ」と主張することで2号書面の採用を阻止すれば無罪方向に働くことになると思われる。
* 最決昭和32年9月30日刑集11巻9号2403頁
判例は,検面調書の方が詳細である場合も実質的に異なる供述に当たるとする(反対,大澤)が,証人尋問を簡単に打ち切り検面調書で補うという単なる手抜き事項については証拠能力を認めるのは不当である(争点187)
② 公判準備もしくは公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の事情(相対的特信性)
イ 合憲性
3号は,絶対的特信情況,2号は,相対的特信情況
* 3号後段の場合には,供述者は公判廷におり調書の内容も尋問可能であることに注意すべき[28]⇒反対尋問権の保障が不完全ながらあるので違憲とはいいにくい!
ウ 特信情況
(ア) 供述がなされた情況についての判断
(イ) 供述内容の信用性(証明力)の比較ではない
● 古い考え方
相対的特信情況は,証明力の比較によるしか方法がないというべきであるから,証明力の問題でありその判断は裁判官の自由心証に委ねられるべき
○ 現在の考え方
証拠能力の問題であり,したがって,外部的付随事情という意味に解する
(ウ) 供述内容を考慮するのは,供述の情況について判断する資料としてのみ
* 特信情況は,証拠能力の判断であるから,当該供述の外部的付随的事情に基づいて判断をする。具体的には,比較を前提とする相対的特信情況であり,証言の信用性を減殺する事情の有無が決め手となることが多い
エ 後段の要件の立証
2号後段の特信情況は相対的特信情況であるから,前の供述が信用できる情況だけではなく,公判における供述が信用できない情況というのも問題となる。このうち,前の供述,すなわち,検察官の面前の方が,信用性の情況的保障で優れていることを立証することは難しいことが多い。そこで,現実には,公判供述の方が信用できない情況があるという方がカギとなることが少なくない。例えば,証人と被告人との関係や傍聴席の状況,被告人側からの働きかけの有無,証人による被告人の弁解の知悉―が挙げられる[29]
* 証人の証言が後退した場合において,いきなり2号書面の請求はいけないのだろうかが問題となる。この点,記憶喚起や誘導尋問をする必要があるのかが問われるが,公判中心主義の視点からはその方が望ましいであろうということである。模擬裁判をやると,あっさり2号書面に頼る人がいるが,それは相当ではなく,そこで誘導尋問で証人が言い直してくれればかえって公判廷における証言の方が信用が高まると考えられる。
* 裁判員裁判の場合は2号書面については,まず裁判員6条は1項が裁判員も含んだ合議で行うという規定であり,2項は構成裁判官の判断となっているのであり,また68条3項の場合は裁判員に「意見を聴くことができる」とされている。そうすると,2号書面の採否にあたっては,構成裁判官だけで判断をすることができるが,基本的には相反性や特信性について説明し,その判断を聴くべきではないかと思われる。だが,裁判官は裁判員は1票を持っていないので無視してもよい的なニュアンスをいうであろう。この点について,特信性については裁判官しか判断できないとしても,その検面の証明力の判断は裁判員の判断を要することになるので,その判断は実質的に重なってくるものと思われる。そうすると,翻って,前倒し的に2号書面として中間評議として意見を聴いておいた方がよいと思われる。
オ 考慮要素あるいは典型例
(ア) 供述の表現
Ⅰ 検面調書の供述は事理にかなっているが,公判の供述は曖昧
Ⅱ 検面調書では,自分にも不利益な贈賄の経緯を断定的に自認しているのに対して,公判では,被告人の面前だからか断定的ではない表現の場合
Ⅲ 公判供述では,違法取引について覚えがないというだけであるのに対して,検面供述では,公判供述に比べて供述が自然であり,自己の非を認めている場合
(イ) 公判での供述態度
Ⅰ 公判供述では,他の被告人の供述と矛盾しないように努めているため,不自然とみえる陳述訂正が随所に見られるに対して,検面供述にはこの種の作為の形跡がない
Ⅱ 恐喝の被害者の公判供述が滞りがちであるのに対して,検面調書では滞ったり,矛盾した形跡が認められない場合
(ウ) 供述の変遷
検面調書と公判供述を比較すると,時間が経つにつれて,次第に事実を否認するようになっているなど
(エ) 一定の身分関係
Ⅰ 被告人の弟分が公判廷で,検面調書と異なった供述をした場合は,特別の事情がない限り,特信情況が存在する
Ⅱ 父親が母親を殺害した事件において,公判準備期日における子の証人供述が犯行現場で,しかも父の面前で行われたのに対して,検面供述は,犯行直後に検察官が証人をいたわりつつ,子の母に対する愛情に訴えて供述を求めたという場合
[補論 田中康郎「公判手続の実務と刑事訴訟法」法教280号11頁のまとめ]
第1 被告人以外の者の検面調書に関する証拠調べの運用
1 書面の活用と迅速な裁判
検察官が,立証趣旨を犯行目撃状況として,犯行目撃者の検面調書の取調べを請求した場合には,裁判所はこれに対する決定をする必要
⇒ 実務上は,同意書面の活用によって,書面と証人尋問との賢明な使い分け* 訴訟の迅速かつ効率的な運用に資する
2 弁護人が書面に同意しない場合
検察官は,犯罪事実を立証するために,その書証に代えて原供述者である目撃者を,その書証と同一の立証趣旨で証人尋問請求
⇒ 証人尋問に流れていく
3 証人が期待する証言をしない場合(通常は,2号書面の取調請求は,「相反供述」(後段)の場合がほとんど)
検察官としては,321条1項2号後段で取調べ請求をすることを念頭に,目撃証人が公判廷で証言する場合には,必ず,検面調書の特信性に関わる事項,例えば,調書を読み聞かせていること,供述者の署名押印の確認に関する尋問を行っておく
⇒ 裁判所は,検面調書の閲覧を求めて,相反性と特信性を判断することもあるが,基本的には,検察官が尋問の過程で立証されることが多い。
4 321条1項2号での取調請求がなされた場合
弁護人は,要件を満たすものかを検討し,例えば,「特信性」の要件が欠けると思料する場合は,「異議がある」と述べる
⇒ 裁判所は,弁護人の意見を参考として許否の判断をする。裁判所は,一般的には,特信情況があるかの判断について検面調書の閲覧を求めないことが多いように思われるが,もとより検察官に検面調書の提示を命じる(規則192条)こともできる
* 証拠能力を判断するために認められた権限で,心証形成は許されず
5 目撃証言の検面調書についての視座
(1) 有罪か無罪かの分水嶺となる
本件の検面調書は,犯行目撃状況を内容とするところ,目撃者は出廷しても期待している供述はしないわけであるから,この場合,検面調書が2号後段で取調べられるかが判決の結論にも重大な影響を与える
(2) 運用のあり方
ア 従来の運用
従来の運用では,検察官は,公判供述が期待したそれと異なる場合は,直ちに証人尋問を終了し,検面調書末尾の供述者の署名押印を確かめ,取調べ当時は記憶に基づいて正直に供述したかどうかを尋ねて,その旨の証言が得られれば,裁判所もそのまま2号後段として証拠採用するのが通常であった。
イ あるべき運用
しかしながら,裁判所としては,できる限り公判における証人尋問を通じて直接心証を形成するのが原則である。そこで,裁判所は,安易に2号後段で証拠採用することをすべきではなく,①検察官に,弾劾尋問(規則199条の3第2項)や誘導尋問(同条3項3号から6号)を活用し,あらゆる角度から必要な尋問をさせるべきである。そのうえで,裁判所は,相反性の要件との関係では,公判廷における供述と調書の内容とは表現方法が似ているが同一趣旨であるか,経験事実かそれとも推測事実であるかという点を証言の事項ごとに明確に特定し,検面調書との実質的相違点を具体的に把握しなければならない。
また,特信性の要件との関係では,公判廷における供述が,①真実を述べることを困難にさせる情況でなされたか,②検面調書に信憑性がある事情からフォーカスをあてて,尋問をすることが求められる。この点,検面調書については,一般の場合と異なる特別の信用性の情況があるということは稀であるから,むしろ,裁判所は,公判廷における供述の際の情況に信用性が欠けている故に,相対的に検察官の面前における供述の際の情況に信用性があるとされる場合が多いということに留意しなければならない
ウ 弁護人・裁判所が証人に尋問すべき事項
裁判所は,証人に対して,①検察庁で事情を聴かれて調書を取られた事実があるか,②その際どのような供述をしたのか,③それは記憶が新鮮なうちに記憶どおり述べたものであるのか,④当時と今では供述が相反していると理解してよいか,⑤相反供述の理由は何か―などを尋問し,具体的に確認していくことが必要である。裁判所としては,「被告人が目の前におり証言しにくい」ということが理由にあると考える場合は,法304条の2や規則202条の措置を採り,適切に措置を講じなければならない
エ 実践的プラクティスと口頭主義
このように,検察官や裁判所が必要な尋問を行い,弁護人も反対尋問を展開すると,なぜ,公判供述と検面供述が異なるのかという点に掘り進んでゆくということになるので,当然,検面供述の内容も証人尋問の内容に取り込まれてゆくということになる。そうすると,裁判所が検面調書に接するのは,検面調書作成のプロセスに怪しい点がないかという点と同時にその内容に接することになる。このようなプラクティスにおいて,裁判所は公平な吟味をすることが可能となるのである
第3 被告人以外の者の供述代用書面―特殊なもの
1 検証調書[30]
(1) 伝聞例外が認められる趣旨[31]
① 客観的・意識的な観察・記録⇒一般的な正確性
② 複雑・微細な内容⇒書面による記録・報告の必要性
(2) 裁判所・裁判官による検証調書(321条2項後段)
ア 検証の具体例
Ⅰ 公判裁判所の採証活動(128条以下)
Ⅱ 受命裁判官・受託裁判官による検証(142条,125条)
Ⅲ 証拠保全としての裁判官による検証(179条)
イ 要件
無条件に許容
ウ 制度趣旨
① 主体の公平中立性
② 当事者の立会い(142条,113条)⇒ 高度の信用性の情況的保障
* 検証の過程で被告人側にも吟味の機会があるという点が大きい
(3) 捜査機関による検証調書(321条3項)
ア 要件
供述者が公判期日において承認として尋問を受け,調書が真正に作成されたものであることを供述すること
イ 制度趣旨
① 主体の一方当事者性
② 被疑者・弁護人に立会いの機会が保障されておらず吟味の機会なし(222条6項参照)
ウ 「真正に作成されたものであることを証言する」ことの意義
単に,書面の作成名義が真正である旨を証言するという意味ではなく,検証者が,検証した結果を正確に記載したものである旨を証言することをいうと解される(検察112)
⇒ 内容の真実性についても実質的な尋問を受けて答えるということになるので,正確であるということも反対尋問にさらされる
2 実況見分調書
(1) 定義
実況見分調書とは,捜査機関が任意処分として行う実況見分の結果を記載した調書をいう[32]
(2) 321条3項の書面に含まれるか
● 3項の書面に含まれない(平野)
∵ 検証は裁判官の令状に基づく強制処分として行われることで観察・記録も意識的かつ正確に行われるが,実況見分の場合はそのような担保がない
× 令状というのは,被処分者の権利利益に対して配慮したものであり,検証の正確性を担保するという趣旨があるわけではない
○ 3項の書面に含まれる(判例)
∵① 検証との差は強制処分であるか否かという違いしかない
② 検証活動の性質に相違はない
③ 格別の不都合もない(弁護人は,3項でも尋問できるので)
* 白取379は,弁護士の作成する実況見分調書は3項で取調請求ができないというのであれば,当事者対等の観点から妥当ではないので,これを積極に解するのであれば,判例は合理的であるという
(3) 実況見分調書から認定できること
立会人がイの地点を特定した事実は認定できるが,イの地点で奪われた事実については認定することができない。
現場供述と現場指示。現場指示であればよい。結構,これは微妙であり,同じ表現であっても要証事実との関係で違ってくる。被害地点を明らかにする限度であれば現場指示になる。
3 立会人の指示説明の証拠上の扱い
(1) 指示説明の定義
指示説明とは,目撃者や被疑者などを立会人として,その指示説明を求めて検証を行う場合の手掛かりとなるものをいう
(2) 原則的処理
ア 考え方
検証の結果と一体のものとして,321条3項により証拠能力肯定
⇒ 立会人の署名又は押印や尋問をしなくても指示説明を採証することできる
∵① 指示説明の記載部分は,検証者が検証をする動機又は手段にすぎない[33]
② 立会人の指示説明は,その内容が証拠となるのではない[34]
* 例えば,「私はこの地点でいきなり殴られました」というのは,現場指示とも現場供述とも理解できるが,何を立証するのかという関係で整理する
イ 最決昭和36年5月26日刑集15巻5号893頁[35]
(ア) 事案
「立会人の説明によれば,甲地点において,車両が横滑りをしていた。その時,被害者は乙地点にいた。甲地点と乙地点を測定すると・・・であった」
(イ) 判旨
「捜査機関は,任意処分として検証(実況見分)を行うに当たり必要があると認めるときは,被疑者,被害者その他の者を立ち会わせ,これらの立会人をして実況見分の目的物その他必要な状態を任意に指示,説明させることができ,そうしてその指示,説明を該実況見分調書に記載することができる」
「立会人の指示,説明を求めるのは,要するに,実況見分の一つの手段であるに過ぎず,被疑者及び被疑者以外の者を取り調べ,その供述を求めるのとは性質を異にし,従って,右立会人の指示,説明を実況見分調書に記載するのは結局実況見分の結果を記載するに外ならず,被疑者及び被疑者以外の者の供述としてこれを録取するのとは異なる」
「従って,立会人の指示説明として被疑者又は被疑者以外の者の供述を聴きこれを記載した実況見分調書には右供述をした立会人の署名押印を必要としない」
⇒ 現場指示というためには,見分の動機・手段となるべき要素が必要!
(3) 例外的処理(被害・犯行再現実況見分調書)
ア 最決平成17年9月27日刑集59巻7号753頁[36]
痴漢事件の犯行状況及び被害状況を再現し記録した写真撮影報告書と実況見分調書についての再現された犯行状況,被害状況を撮影した写真に付された再現者による説明文
「本件両書証は,捜査官が,被害者や被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして,これらの者に被害・犯行状況について再現させた結果を記録したものと認められ,立証趣旨が『被害再現状況』,『犯行再現状況』とされていても,実質においては,再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。
このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については,刑訴法326 条の同意が得られない場合には,同法321 条3 項所定の要件を満たす必要があることはもとより,再現者の供述の録取部分及び写真については,再現者が被告人以外の者である場合には同法321 条1 項2 号ないし3 号所定の,被告人である場合には同法322 条1 項所定の要件を満たす必要があるというべきである。もっとも,写真については,撮影,現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される」
イ 判例の評価
判例は,現場供述や現場指示という区分を用いてはいないが,検察官のいう立証趣旨にはとらわれず,実質的にみて再現者の供述部分自体が伝聞証拠であることを認め,この供述が伝聞例外の要件を満たしていないとするもの
ウ 判例の種明かし
この判例は,要証事実については裁判所は検察官の立証趣旨にはとらわれないとする趣旨の判示をしている。しかしながら,実務上は,当事者が指定した立証趣旨に裁判所は忠実にそこを超えないように取り扱っているのが通常とされている。したがって,この見地からすれば,平成17年判例は現在の実務とは異なる方向性を志向していると考えられないこともない。
しかしながら,本件事案についてみると,このケースでは,「犯行再現状況」そのものを立証する必要性が非常に乏しいと考えられる。なぜなら,被害の状況が単純でしかも被害者が被害状況を詳細に証言しているからである。このような場合において,「証拠の標目」に犯行再現状況報告書が含まれていることからすれば,最高裁は,「要証事実が被害状況」となっていると判断せざるを得なかったものと考えられる(前掲法教86頁[井上発言])
* 調査官解説
「本決定は.実質的な要証事実を判断基準にしているが,証拠能力との関係では常に実質的な要証事実を吟味することが必要であるとしているわけではなく,当事者が設定した立証趣旨を前提とするとおよそ証拠としては無意味となるような例外的な場合に,実質的な要証事実を考慮する必要があるという趣旨」
エ 検討
(ア) 実況見分調書とは似て非なるもの
被害・犯行再現状況報告書とは,捜査官が,被害者や被疑者に,被害・犯行状況を動作等で再現させ,その結果を写真撮影するなどした結果を,その際の被害者や被疑者の説明内容を含めて記載し,写真を添付するなどして作成する実況見分調書をいう。被疑者の再現した被害者との位置関係や体勢を立証するのであれば,実況見分調書の性格を有しているが,それと同時に犯行状況を立証する趣旨としても用いるのであれば,それは自白としての性格を有している
Ⅰ 被害状況の再現
被害状況の再現は,被害者の供述に他ならないので,被害者の供述を録取した書面やビデオと同じ性格
⇒ 第三者の場合には,法321条1項3号の要件を満たすとは考えがたいので,その者の証人尋問が必要となる
Ⅱ 犯行状況の再現
被告人が自ら犯行の状況を再現した場合には,被告人の供述を録取した書面やビデオなどと同様に考えていく
⇒ 被疑者の場合も法322条1項の要件である署名・押印を欠く場合が多い
* 検察官は不同意がある場合は撤回することが多いのであり,その場合は規則199条の10ないし12で証人に対して示して利用するということが考えられるのが,規則49条で公判調書に添付するということになる。犯行再現状況調書についてはほとんど実務ではこのように利用されているのが実態であると思われる。
(イ) 犯行再現状況報告書の2つの類型
① 供述調書の延長とみられるもの
まず,検察官としては被疑者について言葉では説明しにくいことを動作で説明させるために再現実況見分を行うということが考えられる。例えば,両手で首を絞めて殺したという内容であっても,首のどの辺りにどの指が当たっていたのか,お互いの姿勢はどのようなものであるか-など殺意に関連する状況などを取り調べるために行われる
⇒ 供述の延長であるから任意である必要があり,法的にも相当性が欠けるような再現をさせてはならない(法教326号81頁[長沼発言])
② 実況見分的なもの
次に,供述したとおりに実際にできるかどうかを吟味したり,確認したりするために行うということが考えられる。例えば,放火事件で,このようなやり方で火をつけたと供述しているときに,本当にそのような方法で火をつけることができるかを実験する場合が挙げられる
(ウ) 犯行再現状況報告書の考えられる立証趣旨(前掲法教82頁[井上発言])
① 再現したとおりの犯行の事実があったことを立証する
② 物の置かれていた位置や被疑者被害者相互の位置関係を立証する
③ 供述したとおりの方法で実際に行えるということを明らかにして,犯行の客観的な可能性や再現者の供述内容が信用できることを立証する
④ 取調段階でなされた自白調書の任意性があることを立証する(弾劾証拠)
(エ) 再現者の署名・押印は不可欠の要件か
● 不可欠の要件ではない(渡辺修「犯行再現写真の証拠能力」)
∵ 被疑者は,供述と動作で同じメッセージを捜査機関に伝達し,いわば二重に同様の内容を捜査機関に伝えており,署名・押印に代わる信用性保証があり
× 信用性判断と証拠能力判断を混同している
○ 不可欠の要件(長沼)
∵① 供述内容+動作=供述の信用性高まる≠署名・押印不要
② 見分した警察官の録取過程の伝聞の危険を問題にしているのが署名・押印の要件であるから,2通りの方法で報告したからといって伝聞の危険(再現者の報告どおりの内容の録取があるか)の担保とならない
(6) 平成17年判例を意識した実践的プラクティスの検討
ア 検察官の証拠調べ請求
検察官は,犯行再現状況報告書について,立証趣旨を「犯行再現の状況及び犯行の状況」として証拠調べ請求
⇒ 弁護人は,「不同意」!!
イ 検察官は立証趣旨を限定
検察官は,犯行再現状況報告書につき,立証趣旨を「犯行再現状況」に限定
⇒ 立証趣旨の一部の撤回をすると多くの弁護人は同意をすることになる。
これに対しても弁護人が同意をしない場合は,通常の実況見分調書と同様に,作成者の証人尋問で作成の真正を立証し,321条3項書面として取調求める
* この時点で検察官の狙いが被告人の現場供述の立証にある場合は,犯行再現状況報告書の利用は基本的には諦めることになる
* 前掲・法教86頁[井上発言]は,平成17年判例のケースでは,「第1審段階においてその立証趣旨をきちんと明らかにした上で,然るべき証拠の採否をしていれば,この最高裁判例は生まれなかった」と指摘している。これは,1審判決が「犯行再現状況」というファジイな立証趣旨を明確化しないために,事実の認定に用いる直接証拠としての位置づけが与えられるのか,あるいは,本件では被告人は痴漢の事実を公判供述で否認しているから,その信用性についての弾劾証拠という位置付けであるかを明確にしなかったのが原因であるとしている。そして,通常,証拠の標目に掲げられるのは「犯罪事実の立証に供した証拠」,要するに,直接証拠を掲げるところ,1審は証拠の標目に犯行再現状況報告書を掲げたために,これに基づいて犯罪事実を認定しているものと最高裁に受け止められたものと考えられる
ウ 立証趣旨として「犯行状況」の立証を行いたい場合
検察官は,被告人質問により立証
⇒ この場合は,被告人質問の際に,「再現実況見分調書中の写真」を利用したい場合(規則199条の10及び12参照)は,検察官は,写真について弁護人の同意を得るか,321条3項で取調請求するか,あるいは証拠物として写真そのものを請求する
* ただし,検察官としても「写真」にこだわるのは,再現実験のケースが典型的であり,それ以外については被告人の供述で賄えることが多い
エ 被告人の公判における否認供述を弾劾する趣旨の場合
被告人供述に対する弾劾の趣旨ならば,刑訴法301条の趣旨からして,乙号証として証拠調べを請求するのが首尾一貫している。本件の写真撮影報告書は,実質的には自白調書にすぎないものであるから,甲号証として検察官が取調請求をしたのは301条に反する(寺崎説)
オ イレギュラーながら,事実認定の証拠としたい場合
321条3項+321条1項2号3号or322条1項の要件が必要
∵ 当該証拠の形式と実質の両面から要件をみており,特に,供述調書としての性格を重視すれば,321条3項を要件とするのはおかしいという議論もあり得る(寺崎嘉博「本件判批」ジュリ1345号104頁)。しかしながら,単なる供述録取書面ではなく,写真と供述記載が完全にセットとなっている。したがって,再現状況を記録化した検証調書の性質も併せて持っているので,判例の見解は相当である(前掲法教87頁[井上発言])
⇒ 2つの条項が重畳的に適用されるということになるので,以下の手続必要
① 実況見分調書の作成者である警察官について3項所定の手続
② 録取部分についてはそれぞれの条項に従った要件の充足の判断
* 寺崎説の趣旨に徴すると,最高裁は,実況見分調書の自白調書としての利用を(要件が重過ぎるので)実質的に禁じたものとみるべきで,被害状況であれば被害者を証人として,犯行状況ならば被告人質問で行え-という誘導をしているとみられる
オ 写真部分の利用について
(ア) 原則的処理
321条3項
(イ) 例外的処理
写真の内容が,「動作による供述を記録したというような性質」の場合
⇒ 供述録取部分の供述書としての性格はあり
* 署名押印は不要
∵ 記録の歪みが存在しないことを保証するための署名・押印は不要
⇒ 被写体が写真という形で検出される過程には伝聞過程に潜む危険なし
* 簡単にいえば,供述調書と同じである。あれ以前は,普通の実況見分調書と同様に採用されていたのが17年の判例前の扱い。不同意になったら,321条3項で取調請求をしていた。今回は,写真だけである。説明調書の方は,撤回する。
3 鑑定書
(1) 伝聞例外が認められる趣旨
① 法律家による・意識的な観察・判断⇒一般的な正確性
② 法律的で複雑な内容⇒書面による記録・報告の必要性
(2) 鑑定人作成の鑑定書(321条4項)
ア 鑑定の具体例
Ⅰ 公判裁判所が命じた鑑定(165条)
Ⅱ 証拠保全として裁判官が命じた鑑定(179条)
イ 要件
321条3項と同じ
ウ 信用性の情況のレベル
① 鑑定人には,宣誓・虚偽鑑定に対する刑罰の制裁あり
② 当事者の立会権の保障(170条)
(3) 鑑定受託者の鑑定書(321条4項により証拠能力認められるか)
● 321条1項3号によるべき
∵① 鑑定受託者は宣誓をしない(166条参照)
② 当事者に立会権がない(170条参照)
○ 321条4項の準用を認めるべき
∵① 鑑定の性質として違いはなく,321条4項の伝聞例外の趣旨が妥当する
② 宣誓はしないが,正確な鑑定が期待できる
③ 捜査機関は,証拠保全としての鑑定処分を裁判所に請求することはできないとされている(179条1項)。したがって,鑑定受託者が作成したものも鑑定人の鑑定書に準じて取り扱う必要がある(要件に差異があると捜査側が不利になる)⇒必要性!!
(4) 医師の診断書(321条4項により証拠能力認められるか)
● 判例(最判昭和32年7月25日刑集11巻7号2025頁)は,準用を認めている(大澤)
∵① 法律家の意識的な観察・判断の結果を記載した書面として類型的に信用性が高い(刑法160条による処罰の制裁もある)
② 記憶に基づく口頭の報告よりも書面による報告に親しむ
③ いずれにせよ,4項によれば診断者を尋問することになる
○ 321条4項によることは許されない
∵① 医師の診断書は,病状などの「結果」が記載されているものであり,321条4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」とはいえない
② 診断書の内容は比較的簡単であるので医師の記憶に基づいて供述させれば済むことであるので,文言解釈を弛緩させてまで診断書に証拠能力を認める必要はない
(5) 医師がカルテを見ながら証言した場合
医師がカルテを見ながら証言した場合,カルテを独立した証拠と見るのかが問題となる。この点について,カルテを独立した証拠とみながら証言をした場合は,カルテと証言が一体となっているといえるので,規則49条,規則199条の12第2項,規則199条の10第2項で公判調書に添付するという方法を採るということも考えられよう。
なお,この点カルテを朗読したものであれば伝聞法則の適用を受けるとの見解もあり得ると思われるが,カルテはメモとしての性格が強いので,医師に見ながらやってもらうということもできる。また,カルテはその内容が勝負となっているので,カルテを実質証拠として扱うことが多いので,医師がカルテを見ながら証言したとしてもカルテ自体を323条2号あるいは4項で証拠調べすることができるので,あまり問題とならないと思われる。
* カルテはすぐ現場で書くものであり備忘録としての性格が強い。また,診断書は結論を示したものなので一応性格は異なる。
第4 被告人の供述代用書面(刑訴法322条)
1 322条の伝聞例外の特殊性
① 被告人の反対尋問権の利益を考える必要はない
* 法322条は,憲法37条2項の保障とシンクロする部分はない
② 検察官の反対尋問の利益と裁判所による供述観察の利益のみを考えれば足りる
* 322条は,「非伝聞」なのか[37]
2 要件
(1) 前段
① 被告人に不利益な事実の承認を内容とする場合
② 任意性に疑いがないこと(322条1項ただし書き)
* 要件の論拠
Ⅰ 被告人に不利益な場合は,検察官の反対尋問の利益も考慮する必要ない
Ⅱ 検察官は,被告人が自己の主張と両立しない自己に不利益な供述を前にしているのであれば,その供述の証拠調べを請求する権利があるはず[38]
(2) 後段
① 被告人に不利益な事実以外の供述を内容とする場合
② 特に信用すべき情況のもとでなされたものであること
* 要件の論拠
検察官の反対尋問の利益を考慮する必要があるので,特信情況が必要
第5 特に信用すべき書面(法323条)
1 制度趣旨
いずれも書面自体に高度の信用性(信用性の情況的保障)が認められるうえ,証拠として使用する必要性が高い書面であることから,法はこれらの書面に無条件で証拠能力を認めたもの
2 3号の解釈
(1) 「特に信用すべき情況」の意義
● 323条1号2号に準じて,高度の信用性があることをいう(池田371[39])
∵① 特信情況を書面自体で明らかにする合理的な理由はない
② 323条3号書面は,供述者の供述不能が要件ではないから,作成者の公判廷における証言その他の方法によって特信情況の強さが立証されれば,「特に信用すべき情況」といえる
③ 判断の資料を書面自体に限定してしまうと,実質的に価値の高い証拠が排除されてしまう
○ 323条1号2号に準じて,書面自体に高度の類型化された信用性があることをいう
∵① 伝聞証拠の許容性は厳格に解するべき
② 323条1号2号所定の書面は,類型的に信用性の高い書面に限られているから,3号のみ個別的に高い信用性がある場合を含むのはバランスを欠くというべき
(2) 典型例
① カルテの写し(カルテ原本は2号)
② 税務署に対する法人税の確定申告書
③ 真実を記載したと認められる裏帳簿
④ 備忘のためにカレンダーの裏面に記載した勝馬投票類似の申込みに関するメモ[40]
第6 伝聞証人(324条)
1 条文の仕組み
① 被告人の供述が内容⇒322条を準用
② 被告人以外の者の供述が内容⇒321条1項3号を準用
2 324条の適用の有無
被告人の供述をその内容たる事実の立証に用いる場合のみ
3 取調官証言の問題
(1) 問題の所在
捜査官が公判廷に出頭し,「被告人は取調べ中に被疑事実を認めたが,署名・押印を拒んだ」旨の供述をした場合には,324条・322条を適用できるか
(2) 考え方
● 許されない(白取387)[41]
∵① 供述録取書に採ることが法律上予定されており必要性がない
② 捜査官という反対当事者の供述であるのに322条の準用は疑問
×① 署名押印を拒否されたら供述録取書に採れないので必要性あり
② 取調官に対する反対尋問が難しいことは証明力の問題で処理
○ 当然できる(条解727)
取調官が捜査段階で聴取した被告人の供述について証言する場合は典型例
∵ 禁止する条文がない
[1] 自己が直接体験した事実について述べる人の供述というのは,その事実の存在を推認させる力を持っている。例えば,Aが「Xが放火するのを見た」という供述は,その自己の体験事実であるXの放火という事実を推認させる力がある。しかしながら,そのような人の供述というのは,知覚・記憶・叙述という供述過程を経て行われるのであり,その各段階において誤りが入り込む可能性がある。そうすると,誤りが入り込んで,そのような供述から事実の推認が誤導される可能性がある。まず,知覚は見間違いや本当にその時の状況に照らして見えているのかということが問題となる。記憶は思い違いをしていないかということ,叙述は言い間違いということである。そして,誤りが入り込むと事実への推認が誤導される。
[2] 表の①については,本文に掲げられる方法により供述の信用性を吟味し担保するということが可能となる。これに対して,公判廷外でなされた供述が書面や伝聞供述という形で公判廷に提出される場合はどうであろうか。この点,Aが言った供述という部分の信用性,すなわち,Aの知覚,記憶,叙述について証人尋問の過程を通じて信用性を吟味・確認をすることができないと考えられる。そこで,このような信用性のテストに欠ける公判廷外の供述を事実認定の基礎から除くために,表②及び③の類型については,証拠能力を否定することにした。これが伝聞法則の根拠である。
[3] Aの供述プロセスについてAに対する尋問手続を通じてテストすることができないので,Aの供述を内容とする書面及び証言は,Aの供述内容どおりの事実の存在を推認する証拠として用いることは許されないものとしたというものである。
[4] このような理解に立つと,反対尋問の機会のない書面や伝聞証言を例外として許容するかは,「もっぱら,正確・的確な事実認定のための立法政策上の問題」と位置付けられるということになる。したがって,公判期日外の供述を証拠として許容することに関して証人審問権違反という問題は生じる余地はないと考えられる。
[5] このように考えてくると,刑訴法320条1項が憲法37条2項の規定を具体化したと説明するには躊躇も生じてくるところであろう。そもそも,両者は基本的には別の制度であるものの,適用領域が一部でシンクロするので十把一絡に扱われてきたという側面を否定することができないと思われる。そうすると,今後は,伝聞法則の内容と憲法37条2項との関係を検討するよりも,むしろ,当該事案との関係で,伝聞例外の要件を満たす場合であったとしても,証拠能力を認めることが,憲法37条2項との関係で問題を生じる場合があるという点を探究していく方が適切といえるのかもしれない
[6] 結局,伝聞例外説は,精神状態の供述についての利益考量は,非伝聞説と大きく異ならない。すなわち,伝聞例外の要件のうち,「供述不能」の要件をデリートしてしまう論拠は,知覚・記憶の過程が欠落している点に求められている。そして,問題は,「叙述の真摯性」について,非伝聞説は,一般的な証拠の関連性の問題として,証拠能力の要件とするが,伝聞例外説は,324条2項・321条1項3号の「信用性の情況的保障」の中で考慮するという枠組みとなる
[7] なお,この論理を突き詰めると,供述調書などでも,そもそも,供述ではなくなるから,伝聞例外の要件を満たさなくても非伝聞として員面調書の証拠能力が肯定されるということになるが,これは通常の感覚からすれば,非常識であるということは自覚しておく必要がある。伝聞例外説の問題意識もここにあるといえる。
[8] 昭和30年判例について,補足して説明しておきたい。
1 原審の判断
まず,原審は,W供述について,「Aが同女に対する被告人Xの野心に基づく異常な言動に対し,嫌悪の感情を有する旨告白した事実に関するものであり,これを目して伝聞証拠にあたらない」としている。たしかに,XがAを姦淫した事実自体に争いはなく,ただ,和姦の承諾があったかについて争点が形成されているのであれば,検察官が「AがXに対して嫌悪の感情を有していた事実」を要証事実として,承諾がなかったことを推論することは十分考えられる。そして,この場合は,いわゆる精神状態の供述として非伝聞として処理されることになると解される。しかしながら,本件では,Aは死亡させられており犯人性が最大の争点となっている。したがって,上記のように要証事実をとらえる余地はないと考えられるので,原審の判断に誤解があることは疑いがない。
2 本件の要証事実
上記Wの証言の実質的な要証事実はどのように設定されるかが問題となる。
(1) 酒巻・法教305号84頁について
酒巻は,「要証事実としては,Xに犯行の動機があったこと,すなわち,XがかねてからAと情を通じたいとの野心を持っていたこと」とする。この説明は,ミス・リードな点があるので注意が必要である。
(2) 昭和30年判例の読み方
検察官の要証事実は,「XがAをつけた事実があること」,「XがAにいやらしいことばかりしたという事実があること」に設定されており,その間接事実から,「Xに犯行動機があること,すなわち,XがかねてからAと情を通じたいとの野心を持っていたこと」を推論し,さらに,動機があったという事実から,Xと犯人との同一性を推認するものと考えられる。したがって,このように考えると,W証言は,Aの知覚・記憶・叙述したXの過去の言動の存在をも立証して,犯行の動機を推認するために用いられているのであるから,伝聞証拠となると考えられる(白取371も,「Aの発言中,後段の『いやらしいことをした』ことを立証し,これにより犯行の動機を立証しよう」とするものととらえている)。
なお,調査官解説は,まず,①XがAに変な言動をされた⇒②AがXに変な言動をされて嫌悪の情を持った⇒③WはAから「AがXに変な言動をされて嫌悪の情を持った」との体験を聞いた―と整理している。たしかに,「嫌悪の情を持った」原因は,「変な言動をされた」という点にあるから,Xに犯行動機があるというためには,「Xが変な言動をした」という事実を経由する必要がある(仮に,AがXに対して嫌悪の情を持っていたとしても,その事実から,「X」にAを強姦したいという動機があったと推論するのは飛躍がある)。そうすると,Aの発言のうち,「Xが変な言動をした」という部分は,供述内容の真実性が問題となると考えられるので,伝聞法則の適用があるということになる。
[9] なお,法教305号85頁は,「発言内容たる被告人の発言当時の心理状態・意図を要証事実」とするとしている。この点,心理状態というのは漠然としていると思われるが,犯意というのは,部分的犯罪共同説における重なり合いが認められる程度の何らかの犯罪を犯す意図をいうので,故意とは異なるものである以上,このような表現となっていると考えられる。
[10] 調査官解説は,「被告人村上の行動調査指示等に関する発言は,いわば「謀議」そのものであり,実行共同正犯における実行行為の分担にも比すべきもので,右発言をしたこと自体が犯罪行為の内容として要証事実とされているものと解され,したがって,これをその面前で直接知覚した高安の供述も,伝聞のとがめを受けない」としており,共謀共同正犯の客観説の立場に立っていることを当然の前提にしているものと考えられる。
[11] 平野博士は,「この場合は発言自体が要証事実ではない。被告人が白鳥殺害の意図を持っていったことが要証事実である」から,判旨は正確ではないと批判する。
[12] まず,このような要証事実の設定が,白鳥事件最高裁決定に照らして許されるのかということが問題となる。白鳥事件で最高裁が許されないとした推論の過程は,要証事実は,「Eが白鳥刑事を射殺したこと」であるにもかかわらず,Eの発言自体を要証事実ととらえて,その発言からEの犯人性を推論するので,供述内容の真実性が問題とはならない―という推論過程をたどってはいけないとする趣旨である。そうすると,本件の場合においても,要証事実が,「Xが銀行強盗をしたこと」であるにもかかわらず,メモの存在自体を要証事実ととらえて,そのメモの存在自体から犯人性を推論するというのであれば,たしかに,供述内容の真実性は問題とならないので,非伝聞ということになるが,これは,白鳥事件最高裁決定の趣旨に反するというべきであり,このような要証事実の設定は法320条1項に反し許されない。これに対して,本問の要証事実は,「Xの自宅にあるメモ内容と客観的な事実の合致という事実」が要証事実とされているわけで,メモの存在自体が要証事実とされているわけではない。そうすると,言い換えれば,「メモに記載された犯行計画通りの犯行が実行された事実」が要証事実となる。したがって,「メモの内容が真実であるか」が問題なのではなく,「メモ内容が実現された事実」が問題とされているので,メモの内容の真実性は問題とならないと考えられる。このような要証事実の設定は,白鳥事件最高裁決定のケースとは,要証事実が異なるので許されると考えられる。ただし,この推論過程をたどると,推認できるのは,「メモの記載者が犯人であること」という間接事実にすぎず,現実にメモを記載したのが,本当にXであるかについての認定は,別途問題となるのであろう。
[13] 現実には,設例1のケースでは,「犯行の計画性・意図・動機」が要証事実となることは少ないであろう。というのも,このような心理状態の立証は,典型的には,「共謀」や「故意」の認定のためである。しかるに,本件は,単独犯であるから,共謀が問題となるわけではないし,単純な強盗事件の場合故意も問題となることは少ないであろう。もっとも,量刑面で犯意の強さが考慮されるので,これらの事情が要証事実とされることはあるが,本件では,Xと犯人の同一性が争点となっているから,これらの事情が争点となる可能性は乏しい。あり得るのは,「Xがメモ内容のような心理状態にあったこと」を要証事実として,そのような動機があるから,犯人であると推論するケースである。ただ,このような要証事実よりは,むしろ,メモの内容と客観的事実の符合を要証事実とする方が直裁ともいえよう。
[14] 少し詰めて考えてみると,この犯行態様からすれば,XYZは,全員が現場でそれぞれの役割を実行しているので,共謀の有無というよりは,「実行犯人とXとの結び付き」が問題とされている。そうすると,メモ記載内容と客観的事実が一致するという事実から,Xが犯行に関与していることを推論し,その犯人性を推認するということになると考えられる。この点に関しては,例えば,「Xが店内で猟銃を構えて脅したこと」を推認しようという場合に,まさに,メモに記載されている事実があったか否かが問題となるから,その記載内容の真実性が問題となると疑問が生じるかもしれない。考えてみると,その疑問は正しいであろう。というのも,あくまで,「Xの犯人性」,すなわち,Xと実行正犯との結びつきを推論する限度でしか,証拠物として使用することはできない。すなわち,それを超えて,「Xが店内で猟銃を構えて脅したこと」というメモ記載内容の事実を要証事実とする場合は,これは,伝聞証拠とせざるを得ないのではないかと考える。ただ,本件の場合は,見張りも含めて全員が共同正犯となるのであろうから,XYZがそれぞれどの役割を果たしたかは,国家刑罰権の確認という観点からは大した問題ではないので,Xが犯人性を否認し,Xと実行犯人との結び付きが最大の争点となっている本件では,検察官の立証趣旨が,「Xが店内で猟銃を構えて脅したこと」という量刑事情に影響を与える事実にあると考えるのは困難である。このことは,メモの作成者が不明であるので,供述証拠と解すると,関連性の証明が難しいことからも明らかである。
[15] まず,本件の場合,要証事実は,「共謀の事実」とされているが,すでに詳論したように,共謀共同正犯には主観説と客観説の対立がある。犯行計画メモに関する判例が出された昭和50年代は,未だ,客観説な理解がなされていた時期であるから,これがこの期に出された判例にも影響を与えているということに留意しておかないと訳が分からなくなってしまう点に注意すべきである。そのうえで,現在の判例・実務の立場からすれば,共謀とは犯意の合致をいうのであるから,ここで要証事実とされているのは,「X,Y,Zが○○日の○○時ころ,○○において,銀行強盗の日時,場所,役割分担,逃走経路を検討する会議をしたという(間接)事実」から,「銀行から金を脅し取るということを中核とする犯意の合致があった」ことを推認するという構造となる。次に,本件メモを記載したのが第三者Aであるという点にも留意が必要である。共謀共同正犯は,「順次共謀」と言うこともあり得るので,このようなメモをAが作成しているということは,Aも共謀共同正犯として帰責されるということも十分考えられる。したがって,何が要証事実とされているのかということをよく確認しておかないと混乱を招くことになるという点には注意が必要である。
そして,本件は,X,Y,Zを有罪に持ち込みためのものでありAは共謀共同正犯とはされていないので,純粋な第三者として位置付ける。そうすると,Aが「Xが『今度,X,Y,Zで強盗をする』と言っていました」ということとイコールになる。ただ,詰めておかないといけないのは,ここでは,伝聞過程が2つあるので再伝聞になるのではないかという問題意識である。つまり,上記のような伝聞供述に敷衍して考えると,もともとは,XのAに対する供述内容の真実性が問題とされていることになるが,それがメモに記載されていることにより,今度は,メモの記載内容の真実性も問題となるから,伝聞過程は二重ということになるので,再伝聞ということになるのが原則であるということは確認しておいて欲しい。この点に関して,法教306号65頁は,Aの供述プロセスを問題にし,Xの供述プロセスを問題にしていない。これは,詰めて考えると,酒巻は,要証事実は,「Xの発言自体」と考えているのではないかとの推論が成り立つ。このように考えれば,Xの伝聞過程は問題とならないからである。そうすると,Xがそのような発言をしたこと自体から,Xの犯意を推論するということになる。しかしながら,このような要証事実の設定は,白鳥事件決定の許さないところである。そうすると翻って,酒巻は,主観説を当然の前提にして,「Xにメモ内容記載のような銀行強盗をする犯意があること」を要証事実ととらえているのではないかと思われる。そうすると,Xの伝聞過程は精神状態の供述となり問題とする必要がなくなるからである。酒巻の叙述は,上記の趣旨をいう限りにおいて正当として首肯するに足りるものである。
それでは,次に,刑法の通説的見解である客観説を前提にすると本問はどうなるのであろうか。客観説の理論的基礎には,①共同意思主体説と②重要な役割説がある。この点,通説は重要な役割説であるが,かつての判例は共同意思主体説に拠っていたので,客観説からの検討は,これを理論的基礎に据えて行おう。このような共同意思主体説からは,共謀の成立過程が極めて重視される。すなわち,帰責の理論的根拠は謀議に参加したことに求めるからである。そうすると,共同意思主体説を前提とすると,要件は,①謀議に参加したこと,②故意があること―ということになると考えられる。なお,共謀共同正犯では,主観説を前提とする以上,犯意の別に故意を想定する意味はないが,客観説による場合,理論的には主観説よりも故意が問題となる場面が想定される可能性はあり得ることになる。もっとも,帰責の根拠が主観説によると,犯意の合致であるのに対して,客観説によると,謀議に参加したことに求められるから,当然,客観的な謀議に参加する過程を検証し,明らかにしていくことが求められることになる。以上を前提に検討を加えると,「メモを共犯者3名による共謀の事実」とは,敷衍すれば,「X,Y,Zが銀行から金を奪い取るための謀議を行い,X,Y,Zがこれに参加したという事実」ということになると解される。これを,AがXから聞いたのであるから,Aが「Xが『X,Y,Zと銀行強盗をする謀議を○月○日に行った』と言っていました」ということとイコールとなる。そして,この場合の要証事実は,「X,Y,Zと銀行強盗をする謀議が○月○日に行ったという事実」となるので,Xの発言内容の真実性を問題とせざるを得ない。したがって,Xの伝聞過程を省略する余地はないということになる。そして,AがXから聞いた事実をメモに記載しているので,メモの記載内容の真実性も問題となるので,この証拠は再伝聞証拠とならざるを得ない。たしかに,本件の要証事実を「Xが銀行強盗する故意があったこと」という主観面を問題にすれば精神状態の供述となり非伝聞とすることもできる。しかしながら,共同意思主体説の帰責の根幹は「謀議に参加したという事実」にあるのであるから,共謀の有無が争点とされているケースにおいて,その点をさて置き,故意の有無が要証事実となるというのでは伝聞法則の潜脱となると考えられる。したがって,後者のように要証事実を設定することはできないというべきである。
なお,共謀共同正犯における帰責の根幹を重要な役割を演じたという客観的な事実に求めるという見解による場合,「メモを共犯者3名による共謀の事実を証明する証拠として用いる」というだけでは,具体的にXがどのような重要な役割を果たしたのか明らかではないので,具体的に,「Xが金を奪い取る役割を演じたという事実」の立証が必要となる。したがって,謀議が開催されたであるとか,犯意の合致を推認させる事実を要証事実としても,それは幇助ないし共謀共同正犯の事実を基礎付けるにすぎず,共謀共同正犯として帰責するための決定的な要証事実ではなり得ないことには,注意が必要であろう。そうすると,重要な役割説からは,X,Y,Zがどのような役割を果たしたのかを明らかにしていく必要がある。したがって,メモに,「Xは金を奪い取る」という記載があれば,むしろ,この点を要証事実としていくことになり,その事実から重要な役割を推認するという過程をたどることになると解される。そうだとすれば,Xの伝聞過程を精神状態の供述として説明する余地はないから,再伝聞とならざるを得ない。
[16] ここで要証事実として想定されているのは,実のところはよくわからないわけである。すなわち,古い判例のケースを想定しているわけであるが,今日では,共同意思主体説を前提としているわけではないので,「犯行を共謀する過程」というものを詳細に立証する必要性の重要さは失われてきている。もし,メモが謀議,すなわち,共謀のための会議において,議事録のように作られて,全員がこれを確認し署名したという場合,「謀議に参加したこと」が要件事実となる共同意思主体説からは,犯罪事実のいち物証という位置付けになると考えられる。となれば,非伝聞であることは明らかである。
これに対して,現在の判例・実務を前提とすると,X,Y,Zで犯意の合致があったことが要件事実となる。そうすると,考えられる要証事実は複数ある。まず,「○月○日に謀議が行われたという間接事実」を要証事実として,そこから犯意の合致を推認する構造である。そうすると,客観説と異なり,主観説の場合,「謀議に参加したこと」が要件事実となるわけではないし,Y,Zの署名もなされていないとすると,言葉自体が犯罪事実となる場合とパラレルに扱うことはできない。そうすると,基本的には,本当に,「○月○日に謀議が行われたか」という記載内容の真実性が問題とされざるを得ない。したがって,上記間接事実を要証事実に据える限り,伝聞証拠と言わざるを得ないと考える。次に,想定される要証事実としては,ストレートに,Xが共謀の有無を争っている場合に,「Xの犯意の成立」を要証事実とする場合である。これを要証事実とすれば,メモが謀議が行われている時点で作成されたものである限り,精神状態の供述として,非伝聞とすることができる。もっとも,謀議が終了した時点で事後的に思い出してメモを作成したという場合は,「事後的にメモを作成した時点に犯意が存在したこと」を要証事実とする他はないと思われる。もし後者の場合は,意思の連絡の要素の証明がないことになるから,犯意の合致を証明することは困難が伴うであろう。ただ,極めて問題となるのは,本件のメモの記載はXが書き留めたものにすぎないという点である。そうすると,少なくとも「Xの犯意の成立」は要証事実とすることができるが,果たして,その事実から,「X,Y,Z間に犯意の合致があった」と推論できるかは一つの問題と思われる。少なくとも,Zが共謀を否認して共謀の有無が争点となっている場合に,メモにZの役割が記載されていれば格別,そうでない限り,Xが作成したメモから,Xの精神状態を認定し,そこから,いわばZの精神状態を推論するという論理で,XとZとの犯意の合致があったと推論できるかは疑問が残る。そうだとすれば,やはり,前者のように,まず,間接事実を認定し,そこから犯意の合致を推論する方が適切と考えられる。
[17] もっとも,本当にそうであるかはなお疑問の余地がある。たしかに,共同意思主体説を前提とするのであれば,「共同の意思」という個人を超越した意思を観念するから,Xに強盗の犯意があるということは,個人を超越した「強盗の意思」ということがあるということになる。そうすると,Xに犯意があるから,「共同の意思」があり,共同の意思にはYが参加している。それゆえ,Xに犯意ならYに犯意という推論も成り立つのかもしれない。しかしながら,主観説を前提とする限り,Xにメモ作成時の犯意があっても,意思の連絡する機会というのは謀議時を問題にしなければ意味がない。そうすると,推論過程としては,①メモ作成時のXの犯意⇒②謀議時のXの犯意⇒③Yの犯意―となるのかもしれないが,なぜ,Xに犯意があればYに犯意があるといえるのか疑問がある。むしろ,メモの記載からは,直接に「謀議行為があったという間接事実」から,Yの犯意を推論する方が自然であるから,私見は,Xの精神状態の供述からYの犯意の成立ないし合致を推論するという構成は疑問と考える。
[18] 藤木英雄『新版刑法演習講座』(1970年,立花書房)196頁は,共同意思主体説に固有な批判は,共同意思主体を負うべき刑事責任を構成メンバーに転嫁するもので,団体責任を認めるもので個人責任の原則に反する,との批判があると紹介し,「単に,共同意思主体に加わったということからその共同意思主体のしわざに全体について責任を負うべきだ,というだけでは十分な説明にはならない」と指摘し,「他人の行為について刑罰をうけても致し方ない当該の行為者に特有の責任を根拠づける事情があってはじめて共同正犯の責任を負う,とするのが,個人責任の原則から出発した刑法理論の守るべき筋」と言わなくてはならないと厳しく指摘する
[19] この三好説のイメージをみる限り,作成者以外の共謀者の犯意の成立ないし合致を作成者の精神状態の供述から推認することは端的にできないということを象徴的に表している。なぜなら,「共謀関与者全員が共通の犯罪意思形成をした」という事実を他の証拠から認定できるのであれば,その事実から,直接,作成者以外の共謀者の犯行の意図を直接推認できるからである。結局,Yの犯意の成立を証明したいのであれば,Xの精神状態を要証事実とすることにほとんど意味がないことを示しているといえよう。なお,山室説においても,前提として,「謀議行為」があり共同意思が形成されているということが他の証拠によって認定される必要があるのは同じであるから,三好説の主張と山室説はそれほど大きく異なるわけではないと思われる。
[20] 具体的には,犯行現場であるN自動車教習所とその周辺の建造物や周辺地域との地理的関係について相当詳細かつ正確な記載がなされている。また,表面に記載されている文言のうちの記載内容は,いずれも本件犯行の手順や逃走方法に関するもので,しかも他の証拠によって認められる本件犯行の態様とほぼ一致しているのみならず,前記メモの図面と対応して犯行現場から他へ連絡をするために必要な記載もある。これらは,雑然と記載されている反面,その内容は詳細かつ明確で本件犯行を容易に実行するのに役立つものであったとされる。
[21] 寺崎323は,「誰が作成したのか不明のメモ,または,謀議に参加した者から聞いた内容を書き留めたメモを(起訴された被告人の)精神状態の供述と称することはできない」としている。『新・刑事手続3』269も,「犯行計画を記載したメモの内容自体に着目すると,作成者の犯意等の心の状態あるいは共謀参画自体を示すものであるから,その意味で伝聞法則の適用はないとの見解は支持できる。しかしながら,そのためには,(犯行襲撃メモの作成者が不明であることが問題であるので)①作成者が犯行計画を話し合った際の会合に出席した者であること,②メモの記載内容が共犯者全員で確認されたものであることが,立証される必要がある」とする。そのうえで,「作成者が出席者の中に含まれているかさえ不明の場合や,出席者から会合の内容を聞いた者が,単にその内容をメモしたにすぎない場合(むろん,このメモを後に共犯者たる出席者全員で確認したときは別である)には,その要件が満たされていない」と指摘している。
[22] 借用書が証拠として用いられるのは,詐欺事件での代金の詐取の事実の立証ということが多い。もしそうだとすれば,「領収書が発行された事実」を要証事実に設定したところで,目標とする被告人による代金詐取の事実の立証には直接の関係はないということになる。そうすると,領収書の存在を立証するのは,それを間接事実として,「領収書の記載内容に符合する金銭受領の事実を推論する資料」として用いるということになる。結局,この推論プロセスでは,作成者の供述内容の真実性が前提とされ推論をしていくということになるから,伝聞法則の潜脱となる。
[23] 自分の供述どおりであるということを確認していれば,供述録取の伝聞過程は無視して差し支えないとする趣旨である。これは,供述者が自ら記載したのと同じ取扱をするということである。
[24] 作為によって供述不能の状態が作り出された場合に伝聞証拠を許容することができるかは問題である。なぜなら,訴追側がことさらに供述不能の状態を作り出すということは,被告人の反対尋問権を失わせるのに等しいというべきだからである。そこで,法的構成は2つ考えられる。第1は,作為がなかったら供述が可能であるのであるから供述不能要件を満たさない,第2は,証人審問権を侵害する態様は許されない―というものである。いずれにせよ,このような場合は,伝聞証拠を許容することは許されないというべきである。
[25] これは,供述自体の信用性を問題にするのではない。もし,そのような判断をしてしまうと証明力の判断に証拠能力の判断を先行させる意味がないので,外部的な状況を問題にするのである。
[26] 考えるに,刑訴法320条の目的は,裁判所の正確な事実認定を担保し,他方,被告人の証人審問権を保障するという点にあるので,憲法37条2項の規定を直接具体化したものと解することはできない。したがって,伝聞法則は,刑訴法の解釈の問題ということになるので,そこでとられる立法政策が相当性を欠くとしても,直ちに憲法37条2項に反するとするのは早計と言わなくてはならない。しかしながら,判例に反し通説は,憲法37条2項は,実質的な証人審問権を保障したものであるから,例えば,被告人がAの証人喚問を繰り返し要求し,それが不可能とする事情もないにもかかわらず,漫然と検面調書が証拠採用されるという事態となれば,そのような裁判所の訴訟指揮が伝聞法則の問題とは別に憲法37条2項に反する事態というのは想定できると思われる。そうだとすれば,私見は,平野説のように,憲法37条2項と321条1項を直結させるという解釈には首肯できないものであるが,伝聞法則とは別に321条1項2号書面を許容するには,憲法37条2項から直接規律される限界があると解するので結論においては,大きく平野説と異なるものではないと思われる。おそらく,最決平成7年6月20日が伝聞例外の解釈とは別に,手続的正義の観点を持ち出したのもこのような理論的視座によるものと思われる。
[27] 違憲説は,刑訴法321条1項が被告人の憲法上の証人審問権を具体化すると解する見解を前提としている点に注意が必要である。この見解は,合理性に欠ける要件の下で伝聞例外を認めるとなると違憲ということになるわけである。
[28] 田宮382も,判例は,「やや安易にすぎるように思われるが,この場合は,原供述者が証人として出廷しており反対尋問を履践することができるので,この程度でも許容されるのである。換言すれば,(検面調書の記載されている)前の供述内容についての反対尋問が絶対的条件であることを忘れてはならない」と指摘する。大澤も,供述者が公判廷にいるので調書に記載された前の供述について証人に尋問をすることはできる。たしかに,供述後直ちに反対尋問が行われたわけではないから,反対尋問としての機能が十分であるとはいえないが,前の供述について尋問の機会があるのでそのことを条件とする限り,前段のように違憲とまでいう必要はないというべきである,という。
[29] 大澤は,受験生はすぐに,2号は相対的特信情況というが,それが特信情況の判断にどのような意味を持っているのかということを理解しておかなくてはならない。すなわち,特信情況の判断には,単に前に供述が信用できないというだけではなく,公判廷の供述が信用できない情況にあるということが重要であるということをしっかり押さえておかなくてはならない,という
[30] もともと検証調書は,捜査官の供述としての性格があるということを理解しておかなければお話しにならない。検証調書は伝聞証拠にあたるということをもう一度確認しておく必要がある。
[31] このように,基本的には一般的な正確性や書面による記録・報告の必要性という利益を考慮して伝聞例外の要件が緩められているわけであるが,主体によって信用性の情況的保障が異なってくるので,主体ごとに規定されているわけである。
[32] 相手方の承諾がある場合や公道上の事件・事故は特定個人の権利利益を制約するわけではないので,強制処分による必要がないので,実況見分という方法によることが多い。
[33] なお,犯罪捜査規範105条では,「実況見分調書は,客観的に記載するように努め,被疑者,被害者その他の関係者に対して説明を求めた場合においても,その指示説明の範囲を超えて記載することのないように注意しなければならない」と規定されており,指示説明の範囲を超えて,被疑者の供述を録取することは,実況原文調書の有害的記載事項と位置付けられている。この場合は,別途,供述録取書を作成し,被疑者に署名・押印を求めるということになると思われる。
[34] なお,この場合は,内容の真実性が争いとなる場合は,検察官は,別途立会人を証人として取調請求をすることになる。
[35] この点,調書の立会人の指示説明をその内容どおりの甲地点において車両が横滑りをした事実及びその時点において被害者が乙時点にいたという事実の証明に用いることは許されない。この場合は,二重の伝聞,すなわち,立会人の伝聞過程とそれを録取した捜査官の伝聞過程がある。したがって,たとえ調書が捜査官の供述として321条3項により伝聞例外となるとしても,立会人の供述の信用性が残ることになるので,それがテストされていない限り,伝聞法則の適用を免れることはできない。しかしながら,立会人の指示説明が書かれるのは,指示内容どおりの事実が存在した事実を証明するためではなく,捜査機関が甲地点と乙地点をなぜ特定したかを示す趣旨として用いられている。そうすると,立会人が発言した事実のみが問題となる。すなわち,本当に甲地点で車両がスリップしたのかや被害者が乙時点にいたということは別の証拠により証明することが求められる。そうすると,別証拠により,①甲地点でスリップし被害者は乙地点にいたという事実が認定され,②その距離がどの程度離れているかが検証調書を用いて認定するということになる。
[36] 補足すると,この判例で問題とされている犯行被害再現状況報告書という類のものは,近時,証拠として公判廷に現れることが多かったものである。これは,捜査官サイドの狙いとしても,このような犯行被害再現状況報告書では,そのような再現の対象となる過去の事実の存在が要証事実とされていることが多いものと解される。すなわち,従来の実況見分調書は,犯罪捜査規範に照らしても,指示説明を超える「現場供述」は有害的記載事項と位置付けられている。これは,要証事実が客観的な位置関係などに設定されることが多く,「現場供述」を記載すると供述録取書としての性格が出てきて,裁判所が異なる要証事実を設定する可能性を危惧しているものと理解できる。そうすると,犯行被害再現状況報告書は,もともと,過去の事実の存在を要証事実とすることが意図されているものと考えられるから,一応は問題を分けて考えることができると思われる。この判例のケースでは,実況見分調書との類似性から321条3項で証拠能力が取得できないかが試みられたケースであり,判例はこれを否定したということになるものと思われる。したがって,今後は,この種の犯行被害再現状況報告書は,供述録取書とパラレルに扱われることが多くなると予測される。
[37] そもそも,法322条については,伝聞不適用の規定であるとする見解もある。この見解は,伝聞法則とは,「反対尋問を経ていない供述証拠」と定義する見解が前提となる。そうすると,被告人の供述については,被告人の反対尋問権を保障する必要がないのであるから,反対尋問を経ていないことを問題視する必要はないということになると考えられる。しかしながら,伝聞法則の趣旨は,反対尋問権の保障に尽きるものではなく,裁判所の供述態度の観察という利益も考慮されている。そうだとすれば,322条も伝聞法則の適用があるので,伝聞例外の規定と位置付けるのが相当と考えられる。そのうえで,322条1項前段では,検察官の反対尋問の利益も問題とならないので,直接主義的な観点が問題になるだけと考えられる。また,322条1項後段では,直接主義的な観点に加えて,検察官の反対尋問の利益が問題となるので,信用性の情況的保障があるかの検討が必要となるというイメージである。
[38] 従来,「被告人に不利益な事実の承認を内容とする場合」になぜ伝聞例外が認められるのかについては,「人は嘘をついてまで不利益な事実を暴露しないという経験則がある」とする見解が有力であった。しかしながら,このような経験則が本当に存在するかは過去の誤判事件を振り返れば疑問であることは言うまでもない。そこで,近時は,当事者主義の立場から説明する見解が有力となっている。これは,被告人が自己の有利な主張を展開するのに対して,検察官は,被告人を有罪に持ち込むために,以前に被告人が自己に不利な供述をしているのであれば,その取調請求をすることが認められてよいという,いわば訴訟の展開のルールの一種という観点から論証しようとする見解といえよう。
[39] なお,この池田説の立場からも,日記,手紙,メモが一律に3号の特信文書に当たるというわけではないことには注意が必要である。例えば,日記帳については,「航海日誌に準じる程度の実質を備えているものは,証拠能力を認めることができるが,一般の日記は,類型的にそのような高度の信用性は認め難い」としている。そのうえで,「その作成経過,形式,内容等から高度の信用性が認められる場合」には3号書面として許容されるとしている。他方,メモについては,「①作成者が自ら経験した内容を,②その印象が鮮明なうちに作成したもので,③記述の正確性を推認する事情が存在する場合」―には3号の特信文書として証拠能力が許容されるのだとする。このような条件がそろえば,類型的にみて,高度の信用性があるという判断があるものと考えられる。
[40] この判例は,特信情況の判断資料を書面自体に限定せず,作成者の証言などから,作成状況や書面の成立過程をも考慮して特信情況を判断しているものと考えられるので,池田説に親和性があると思われる。
[41] なお,白取388は,取調べにおいて「署名押印」を拒否することが黙秘権の行使であるから,取調官証言を許すのは黙秘権行使を無視するものという。しかしながら,黙秘権というのは,基本的には自己に不利益な供述をしないという点が中核であるから,伝聞過程を解消する趣旨の「署名押印」が黙秘権の行使の一環というのは,弁護の立場から事実上はその通りであるが,理論的には首肯できない。